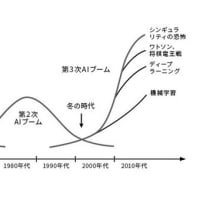12の人工石は天然と比べても物理的な性質はほぼ違いがない
京セラの人工宝石事業が好調だ。2025年3月期の売上高は20年3月期に比べて25%増える見通しだ。同社は人工宝石の国内最大手で、エメラルドやルビーなど電子商取引(EC)では約1500種を扱う豊富さが強みだ。
環境や社会の持続可能性に配慮したエシカルな商品を好む40代以上の消費者に刺さっているほか、時計などの装飾品向けの需要も広がっている。
人工宝石のブランド名は「クレサンベール」(緑の三日月)。エメラルドをはじめ、アレキサンドライト、オパール、パパラチアなど12の人工宝石を使ったネックレスや指輪、ブレスレットを販売する。
ECの場合、約1500種で価格は3万〜40万円。催事では100万円を超える商品も展開する。売上高は非開示だが、近年は堅調に推移している。
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=160&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ae5a385deec556d53bdccf3e22345dfd 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=320&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=971b00fdeeca9b750029faf59b6550f0 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=160&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ae5a385deec556d53bdccf3e22345dfd 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=320&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=971b00fdeeca9b750029faf59b6550f0 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=160&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ae5a385deec556d53bdccf3e22345dfd 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=320&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=971b00fdeeca9b750029faf59b6550f0 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=160&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ae5a385deec556d53bdccf3e22345dfd 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=320&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=971b00fdeeca9b750029faf59b6550f0 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=160&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ae5a385deec556d53bdccf3e22345dfd 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5955006003022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=320&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=971b00fdeeca9b750029faf59b6550f0 2x" media="(min-width: 0px)" />

</picture>
エメラルドの人工石は1975年に開発に成功した
京セラの人工宝石事業は、創業者の稲盛和夫氏が米国出張した際、天然のエメラルドは傷が多いにもかかわらず高い価格で販売されていることを知り、より良いものを自社で作れないかと考えたのがきっかけだ。
1959年に創業した京セラはセラミックの結晶技術を応用できるとみて、京都伏見事業所(京都市)で70年に開発に着手し、75年にエメラルドの生産に成功した。
製造はノウハウの塊だ。たとえばエメラルドの場合、酸化ベリリウムなどの同一成分を含む原鉱石を厳選して仕入れ、1400度以上で溶かす。長期間にわたって温度を下げていくとエメラルドの結晶が育つ。
職人が手作業で磨き上げ、最終製品に仕上げる。不純物を取り除き、育てた結晶から実際に宝石として使うのは重量で3%ほどだ。全体では半年から1年もかかる。
販売好調の背景にはエシカル消費の広がりがある。天然石は地下深くで人力で採掘する過酷な労働環境とされ、水質汚染もリスクもつきまとう。
京セラは人工石の生産の過程をサイトなどで公開し、こうした心配をなくしている。宝飾企画課責任者の河田聡氏は「当社は手掛けてないが人工ダイヤモンドの広がりも受け、エメラルドなどにも関心が高まっている」と語る。
品質も評価される。不純物を極力なくし、天然と比べても物理的な性質はほぼ違いがない。天然石や一部の人工石は一般に無数の小さい傷が見られるが、京セラの人工石はほとんど傷がないのが特徴だ。

販売を始めた当初は天然であることが宝石の価値基準で、人工石に関心が集まらない時期もあったというが、時代の変化とともにモデルチェンジを繰り返しながらラインアップを充実させたことで、受け入れられる環境が整った。
新たな需要も広がっている。近年は自社商品だけでなく時計やオーディオの装飾向けに、工場で育てた結晶を原石として提供してほしいというニーズが高まっている。
宝飾品営業2課責任者の藤本大輝氏は「天然石とは異なり、工場生産により品質を担保し安定供給できることが強みだ」と話す。
ただ消費環境は楽観視できない。矢野経済研究所(東京・中野)によると、25年の国内宝飾品の市場規模は前年比4%減の1兆514億円の見通しだ。
直近は為替の円安や原材料の上昇に伴う値上げで単価が上がったうえ、訪日外国人(インバウンド)の増加で需要が伸びていたが、長引く物価高騰で富裕層の需要が落ち着くとみて、市場は停滞局面を迎えるとみている。
国内市場が伸び悩むなか、海外の開拓が課題となる。これまではOEM(相手先ブランドによる生産)が中心だったが、法人向けの展示会などに出展して自社製品の売り込みを強めていく考えだ。交流サイト(SNS)も有効活用し、若い世代にも実際に手に取ってもらいやすい戦略を練る。
(京都支社 角田康祐)

 </picture>
</picture>