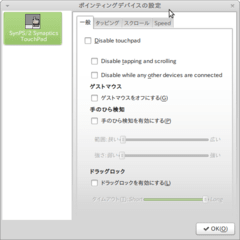なんか、家族の個人個人がパソコンなりタブレットやスマホを持つようになり、データの一元管理がしたくなったのでNASを作ろうと計画しています。
パソコンは以前、WindowsXPが動いていたやつを利用します。
OSはOpenMediaVaultを選びました。
インストールは他のホームページを参考にしていただくとして、問題はPCに接続されているHDDが1台だけだと何かと不都合であるということです。
このOpenMediaVaultはインストール時にはハードディスクのすべての領域をOSとしてインストールしてしまいます。
確かに仕事等で使えのであればOS用のHDDとデータ用のHDDは別にするのでしょうが、個人で使用するNASにはたかだか2GBのOS領域のためだけにHDDをまるまる一台さくなどはできません。それに最近のHDDの容量はデカイですからね。
そこで、1台のHDDでOS領域とデータ領域をシェアする方法を書きます。
まずはUbuntuなどのイメージファイルをダウンロードしたものをCDに焼いておきます。
それからOpenMediaVaultをインストールします。(この場合、クリーンインストールしますのでHDDに入っていたデータは全て消えます)

それからCDに焼いたUbuntuをLiveCDとして起動し、GPartedを起動しパーテーションの領域の変更をします。

そのまま、このソフトで空きとなった領域に新しいパーテーションを作成します。
再び、OpenMediaVaultを起動すれば、WEB画面からデータ領域を指定し、使用することができます。
パソコンは以前、WindowsXPが動いていたやつを利用します。
OSはOpenMediaVaultを選びました。
インストールは他のホームページを参考にしていただくとして、問題はPCに接続されているHDDが1台だけだと何かと不都合であるということです。
このOpenMediaVaultはインストール時にはハードディスクのすべての領域をOSとしてインストールしてしまいます。
確かに仕事等で使えのであればOS用のHDDとデータ用のHDDは別にするのでしょうが、個人で使用するNASにはたかだか2GBのOS領域のためだけにHDDをまるまる一台さくなどはできません。それに最近のHDDの容量はデカイですからね。
そこで、1台のHDDでOS領域とデータ領域をシェアする方法を書きます。
まずはUbuntuなどのイメージファイルをダウンロードしたものをCDに焼いておきます。
それからOpenMediaVaultをインストールします。(この場合、クリーンインストールしますのでHDDに入っていたデータは全て消えます)

それからCDに焼いたUbuntuをLiveCDとして起動し、GPartedを起動しパーテーションの領域の変更をします。

そのまま、このソフトで空きとなった領域に新しいパーテーションを作成します。
再び、OpenMediaVaultを起動すれば、WEB画面からデータ領域を指定し、使用することができます。