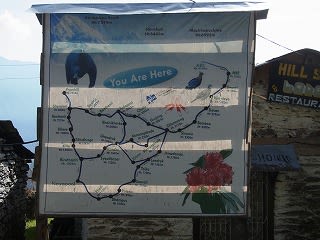麦畑に青々とした緑が広がっていました。
良く見ればマメ科植物が混植されています。
根瘤菌の窒素固定を利用する知恵です。
農業技術を指導する人がいるのかもしれません。


ここの麦畑の脇にホトケノザを見ました。
自信がなかったので、帰国して図鑑をめくると、「ホトケノザは東アジア、ヨーロッパ、北アフリカに広く分布する越年草」と記されています。
間違いなさそうです。

更にもう一つ、ナズナを発見しました。
これも帰国後に調べると、ウィキペディアに「アブラナ科ナズナ属の越年草で、ムギ栽培の伝来と共に日本に渡来した史前帰化植物と考えられる」そうです。
へ~! そうだったんだ。知らなかった!

そしてハコベが現れます。
これも、日本の野草(山と渓谷社)に「世界中どこにでも見られる越年草」と記されていました。
そうだったんですね!

そして最後はハハコグサです。
これもウィキペディアに「中国、朝鮮、日本、台湾などに広く分布し、インド、ネパール、タイ等の熱帯地方でも、標高の高い地域で見られる」そうです。

私はネパールに来て初めて、日本の身近な植物を、今まで、どれ程いい加減に見てたかに気付かされました。
そういえば昔、文化人類学者の今西錦司さんが「裏山にきちんと登れたら、ヒマラヤも登れるようになる」みたいなことを言っていた気がしますが、私は植物学の裏山をきちんと登る前に、ヒマラヤに来てしまったようです。
ヒマラヤの麦畑で、いいお勉強をさせてもらいました。
これから何をすべきか、今頃気付かされた気がします。
そして、「気付かないよりはまし」だろうと、自分で自分を慰めます。
周囲を見渡すと、キュムヌ・コーラの対岸にチョムロンへと続く道が見えていました。

更に、段々畑の中を下って、

更に、サクラソウの咲き乱れる道を下って行くと、

キュムヌ・コーラを跨ぐ吊り橋が見えてきました。

※ 他の記事へは index をご利用頂くと便利です。