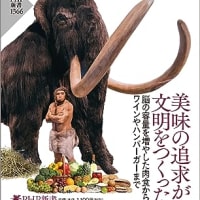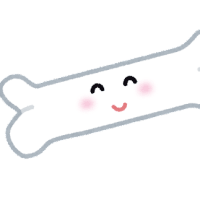家畜化症候群
雑草の栽培化と同じように、家畜化にともなって動物に大きな変化が生じる。つまり、家畜化にともなって、「体格の縮小」「垂れ耳や白い斑点の出現」「鼻先(吻(ふん))の短縮」「尾の巻き上がり」「脳容量の減少」などの特有の変化が現れるのだ。このような変化を「家畜化症候群」と呼ぶ。
家畜化症候群に関しては、1959年からシベリアで始まった実験が有名だ。
ドミトリ・ベリャーエフという研究者は、野生のギンギツネを集め、その中から人に対する敵対心や警戒心が少ないものを選び出し交配を行った。その後も、生まれた子供たちの中で、さらに敵対心や警戒心が少ないものを選び出し、交配するという作業を続けたのだ。
その結果、ギンギツネに衝撃的な変化が現れた。
驚いたことに、通常は人間を見ると唸り声をあげるギンギツネが、10世代くらい後には、人に対して尾を振りながら近づいてきて手をなめるなど、まるで犬のような行動を取るようになってきたのだ。
また、性格だけを基準に選別を繰り返していただけなのに、家畜化症候群に特有の外見の変化が生じた。つまり、体格が小さくなり、耳が垂れ、毛皮に白い斑紋が現れ、吻が小さくなり、尾がカールした。さらに、野生では単独行動をするギンギツネが、群れをつくるようになった。今ではこのギンギツネの子孫たちは、「ナレギツネ」という名称でペットとして売られている。
それでは、どうして家畜化にともなって、このような広範囲の変化が生じるのだろうか。
実はこの問題は、進化論の創始者チャールズ・ダーウィンをも悩ませた。生存に有利(この場合は人間にとって有利)な形質が進化の過程で選択されるというダーウィンの説では、役に立ちそうにない垂れ耳や白斑などの出現を説明することができないからだ。
現在の有力な説として「神経堤(てい)細胞」の関与を家畜化症候群の原因とするものがある。
神経堤細胞は、受精卵が発生を始めて少ししてから一時的に出現する細胞で、体内のあちこちに移動して様々な細胞に変化する。その中には、末梢神経の細胞や、ストレスホルモンを分泌する副腎の細胞、顔の骨や軟骨を作る細胞、メラニン色素を作る細胞などがある。もし、神経堤細胞に何らかの変化が生じると、これらの細胞のすべてに影響が及ぶと考えられる。つまり、末梢神経や副腎の細胞の変化によって人になつきやすい性格になり、骨や軟骨を作る細胞の変化によって吻が小さくなるとともに耳が垂れ、メラニン色素を作る細胞の変化によって白斑が生じるということだ。
実際に、オオカミと、オオカミから家畜化したイヌの遺伝子の違いを調べた研究では、神経堤細胞で働く遺伝子に違いがあることが明らかになっている。