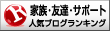新型コロナウィルスの影響は、教会の活動にも及んでいます。
現在、私たちの教会でも日曜午前の礼拝のみに限定しています。日曜午後のプログラムや平日の祈り会を中止にしています。小規模教会なりの活動縮小です。
それにしても、影響がさまざまな分野に及んでいます。注意深く、落ち着いて日常生活を送りながら、速やかな終息を祈るばかりです。
さて、礼拝説教のあらすじ(旧約聖書からの講解説教)も掲載しておきます。しばらく掲載していなかったので、今回は、2019年11月の分です。
2019年11月 Ⅰサムエル記10-12章
説教題:『彼は黙っていた』
旧約聖書では神について「怒るのに遅く」と表現される(出エジプト記34:6他)。そして、人についても、(箴言16:32)「怒りを遅くする者は勇士にまさり…」と教えている。人が自分の感情を適切に扱うのは賢明である。油注ぎを受けたサウルは、イスラエル王国の最初の王として民の前に立つ時が来た。しかし、心理的な重圧のためか、サウルは姿を隠した(10:22)。一方、サムエルは、王権を樹立する手配を進めていた(10:25; 8:10-)。重大な転換期である。民への説明、文書への記録、文書の保管が丁寧に実施された。サウルは(10:24)「主がお選びになったこの人を見なさい」と紹介された。新たに立てられた若い王の姿に民の反応は様々だった。多くの人々は歓迎したが、「こいつがどうしてわれわれを救えるのか」と軽蔑した者たちもいた(10:27)。聖書は、その時のサウルについて、『彼は黙っていた』と伝える。しかも、アンモン人との戦いに勝利し、王としての実績を示した後も、王を軽蔑した者たちへの処罰の要求をたしなめた(11:12,13)。即位した当初のサウルは、このように思慮分別をもって状況に対処していた。私たちにも「怒るのに遅く」という品性が備わり、神を証しする者となりますように。
説教題:『私を訴えなさい』
教職者の倫理について考えたい。新約聖書では教会の指導者の適性を教えて、「不正な利を求めず」(テトス1:7他)と挙げている。サムエルは、サウルを王に立てたところで自らの役目の一つを終えた。すでにサウルは王としての務めを果たし始めている(12:2)。これまでのサムエルは士師として民をさばいてきたが、王の統治への移行とともに権限を手放す。サムエルはその務めから退くにあたり、民に『私を訴えなさい』と呼びかけて、自身に不正があったかを問う(12:3)。こうした呼びかけのことばは、民のさばきを行う職にある者の危険をよく自覚していたことを意味する。神から委ねられた権威と務めを乱用して、利得を求めてしまう危険を意識していなければ、その職を退くにあたり、これほどまでに自分からはっきりと問うことはなかっただろう。サムエルの問いに対して、民は(12:4)「あなたは私たちを虐げたことも、踏みにじったことも、人の手から何かを取ったこともありません」と答えた。さらに、サムエルは、この自分と民との間のやり取りに証人を立てて、揺るぎない事実として念押しをしている(12:5,6)。後になって民の心が変化したとしても、批判の起こる余地を残さなかった。こうして当時の法的な手順を踏んだ場面に、厳粛で公正な審査、相互の責任においての決定の重みを考えさせられる。