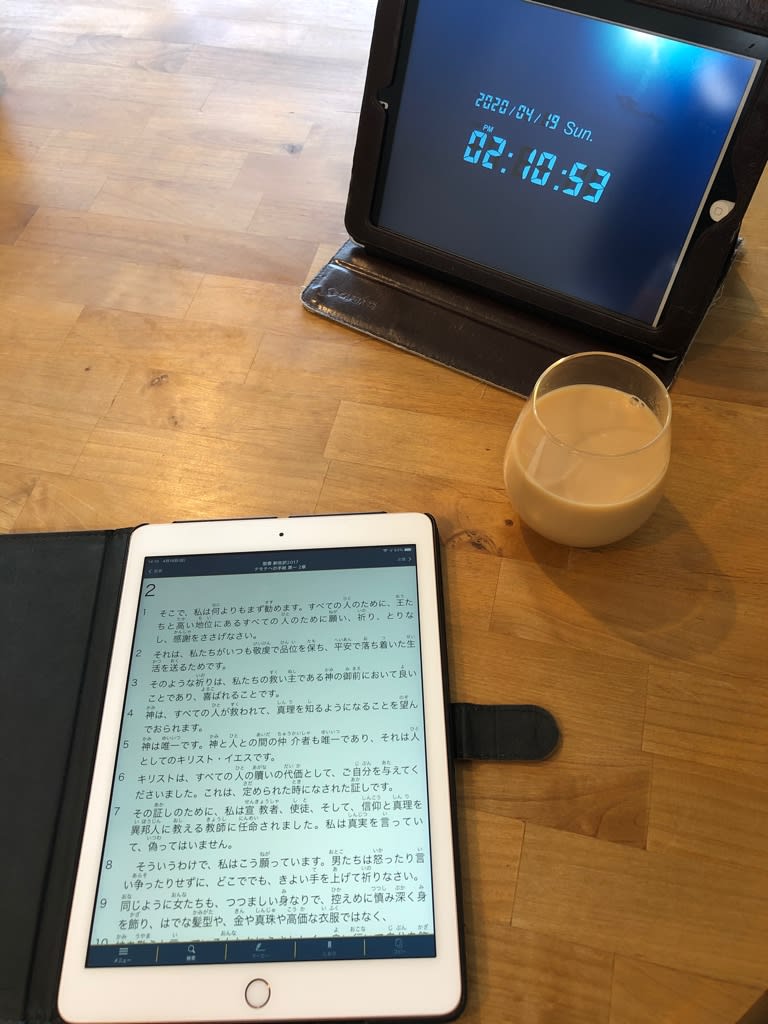新緑の季節を迎えています。ウォーキングの途中に撮影。

ステイホームを心がけつつ、心身の健康管理も大切にしています。
さて、教会の話題です。3月末から、教会はすべての行事を中止して、その代わりに教会員に文書を送っています。
今回は、その文書に掲載したメッセージをご紹介します。新約聖書 ヤコブの手紙5章7-11節からです。
7 ですから、兄弟たち。主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを、初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。8 あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。9 兄弟たち。さばかれることがないように、互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい。さばきを行う方が戸口のところに立っておられます。10 兄弟たち。苦難と忍耐については、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。11 見なさい。耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなたがたはヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は慈愛に富み、あわれみに満ちておられます。
題:『耐え忍びなさい』
①「耐え忍びなさい」(5:7,8)
ヤコブは、試練に苦しむキリスト者たちに「耐え忍びなさい」と言います。これは「我慢が足りない!」と厳しく責めているわけではありません。この手紙でくり返し「(私の愛する)兄弟たち」と呼びかけていることからも、むしろ対等な立場、同じ目線に立って、力づけるためのことばをかけています。励ましのことばです。
この「耐え忍ぶ」には、「待っている間、落ち着いている」という含みがあります。ヤコブはすべての苦しみの終わりを示して、「主が来られる時まで耐え忍びなさい」と言い、その時をじっと待つように諭しています。永遠に待ち続けるのではなく、主の再臨という期限があって、必ずその時が来ます。
農夫の仕事は、天候に左右されます。先の雨は種まきに、後の雨は作物の実りに欠かせません。農夫はやがて得られる収穫を期待して、じっとその雨を待ちます。必ずその時が来るからです。信仰には「待ち望む」(ヘブ10:11)という特徴があります。
「耐え忍びなさい。心を強くしなさい。」とは、将来への期待や希望を抱いて、じっと待ち続ける姿を教えています。絶望は、私たちの心と人生を破壊します。心が騒ぐときにこそ、神に望みを置いて、主イエスの再臨という結末を思い巡らしましょう。
②「互いに文句を言い合うのはやめなさい」(5:9)
ここに「互いに文句を言い合うのはやめなさい」とあるのは、とても現実的です。苦しい時、辛い時、私たちの心はゆとりを失います。すると、周囲には、冷ややかな見方や厳しいことばで接してしまいます。それは仕方がないことでしょう。ただし、だからと言って、お互いにそのままの態度でいて良いわけではありません。
ヤコブは、「さばかれることがないように」と言います。文句を言い合うのは、キリスト者にはふさわしくないからです。(ピリ2:14-16)「すべてのことを、不平を言わずに…」、神の救いに信頼して、心の平静を保つよう励ますのが信者の交わりです。
③「預言者たちを模範にしなさい」(5:10,11)
「苦難と忍耐」というのは大変な課題です。ですが、「主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい」という手がかりがあります。私たちには預言者というモデルがあるのです。聖書は彼らを「耐え忍んだ人たち」と言いますが、実際には途中で弱音を吐いて、浮き沈みもありました。しかし、それでも失望せずにいたので、「耐え忍んだ人たち」とされました。
ヨブの幸いな結末(ヨブ42:10)にも、「主は慈愛に富み、あわれみに満ちて」いるのは明らかです。預言者たちをモデルに「耐え忍びなさい」と教える神は、私たちにも幸い(マタ5:3-10)を約束しています。困難な時こそ、主を待ち望む心を新たにしましょう。
2020.3.29.
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。