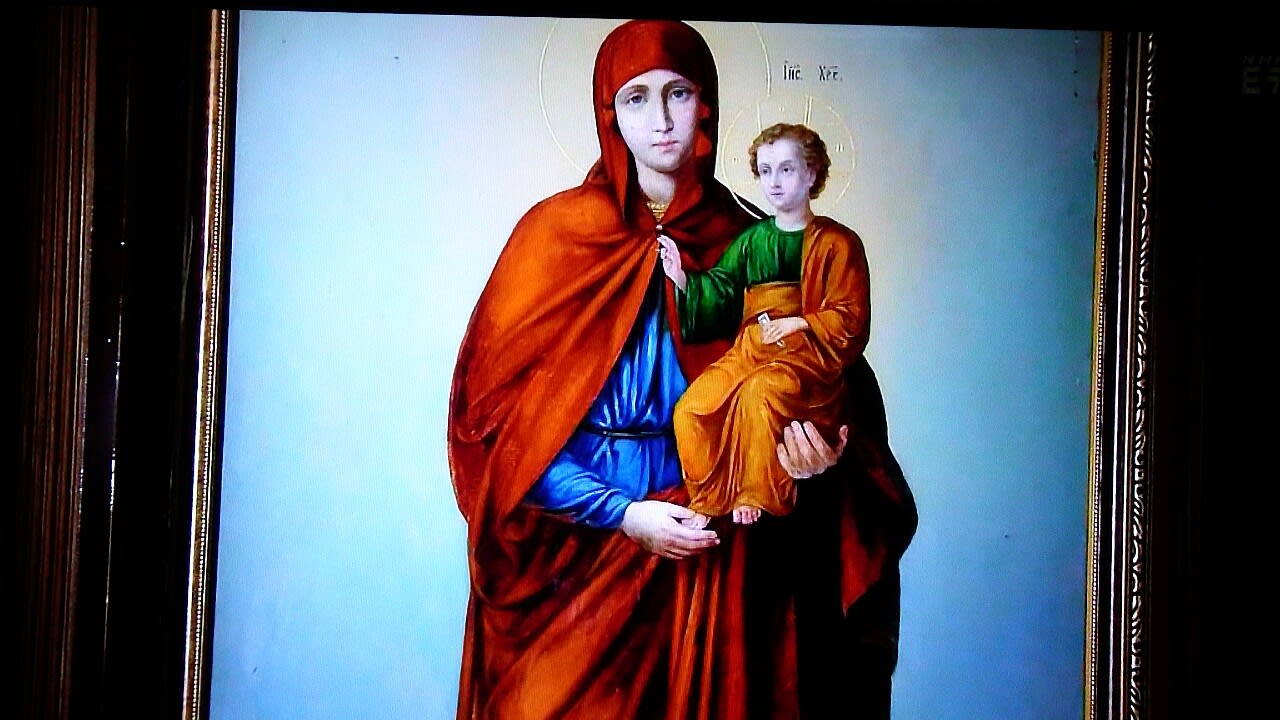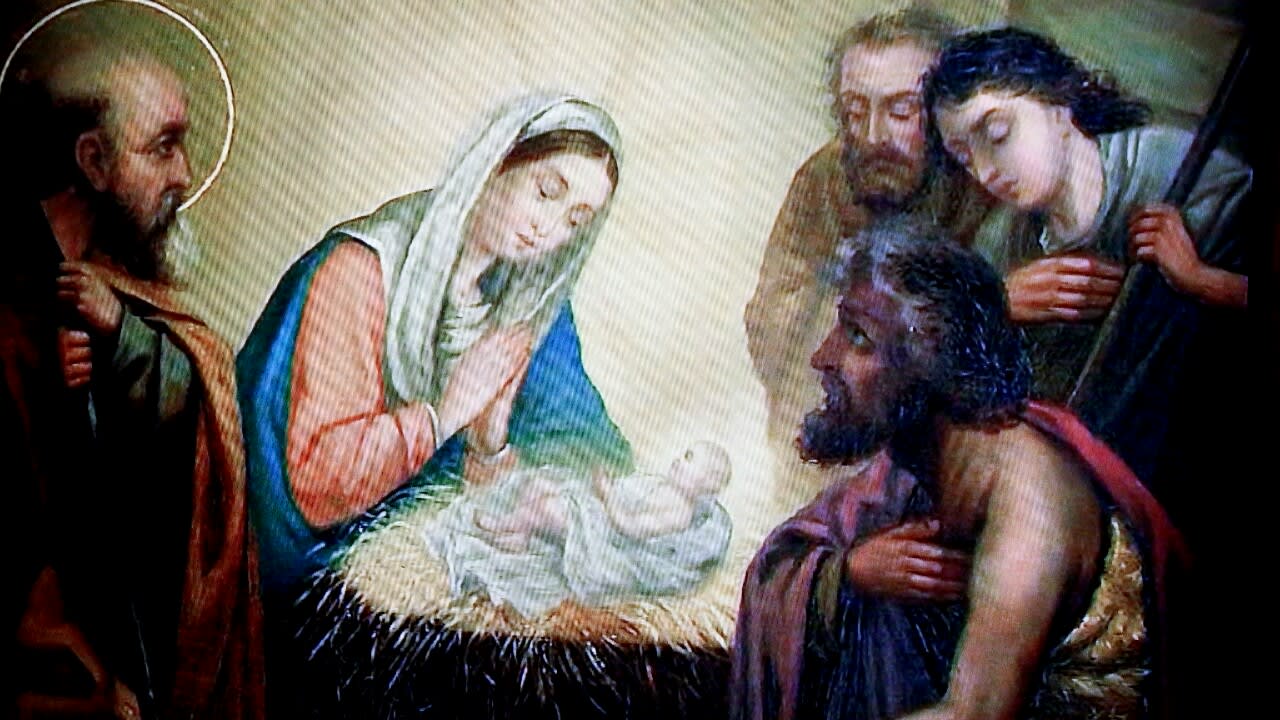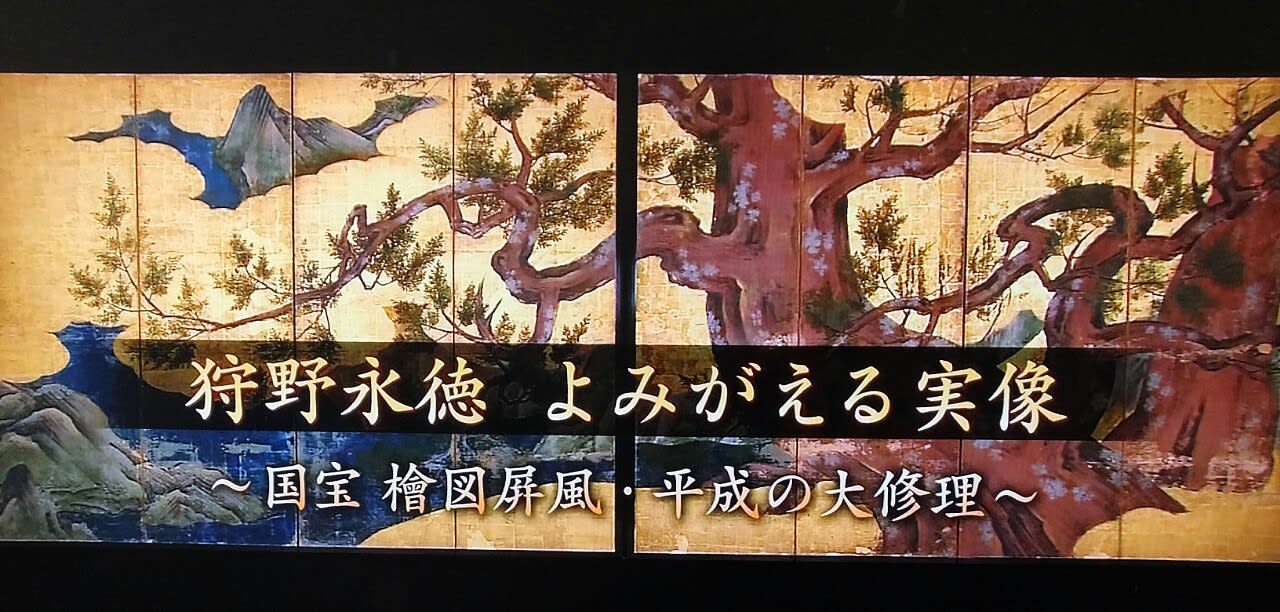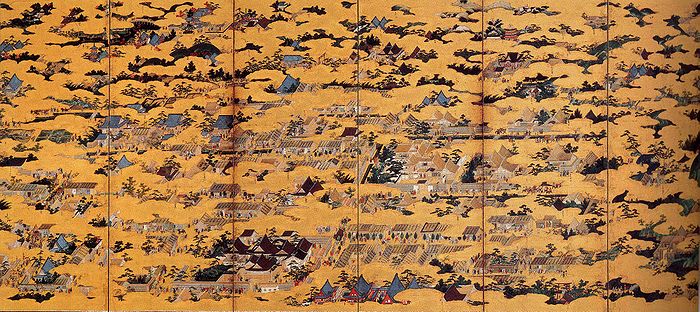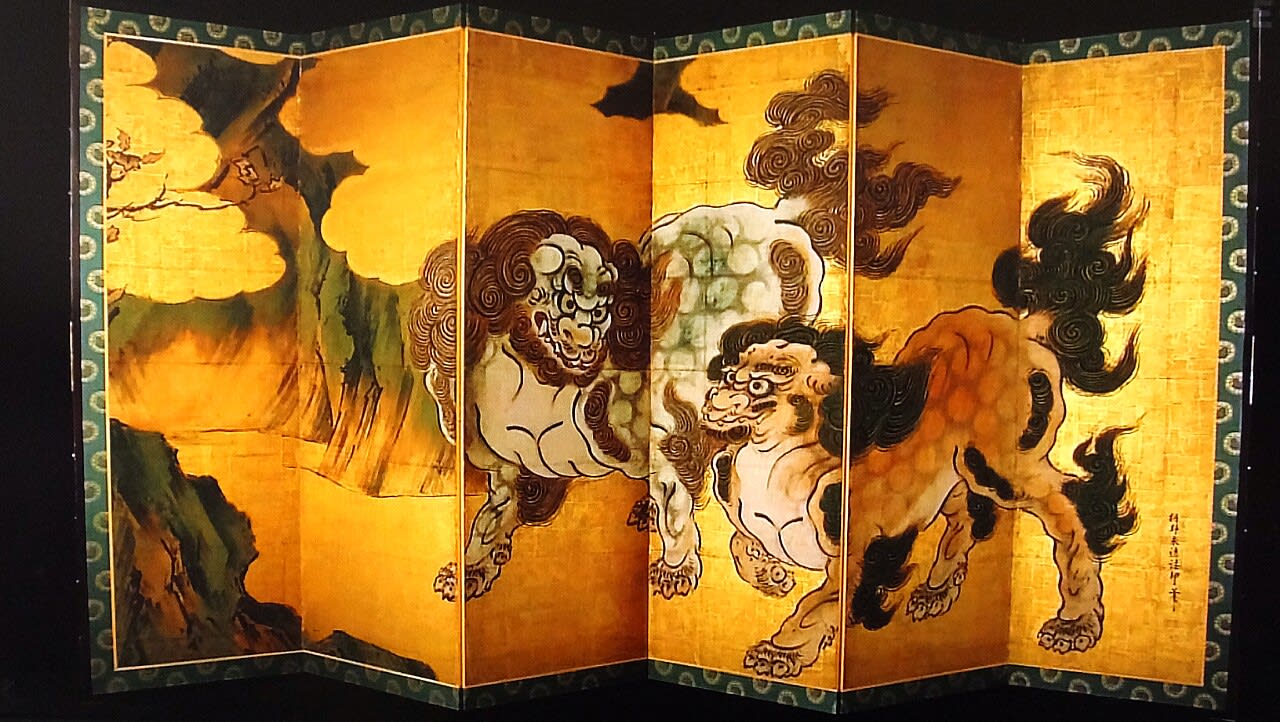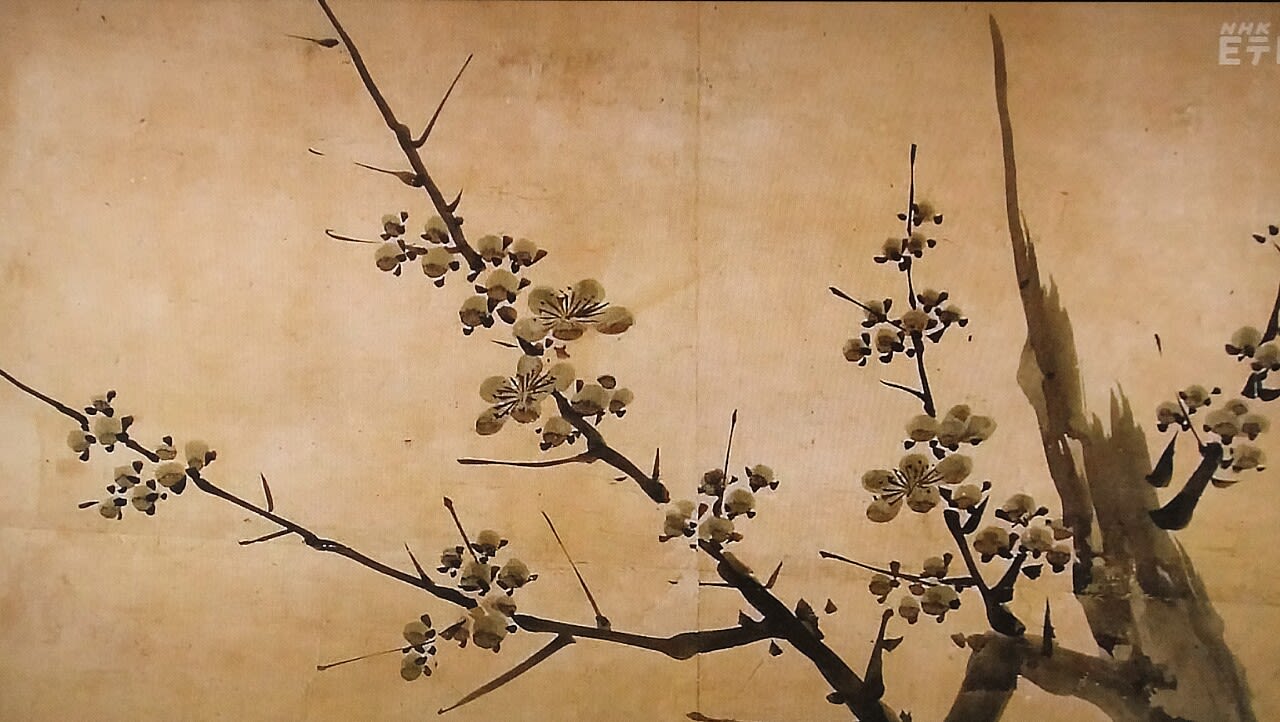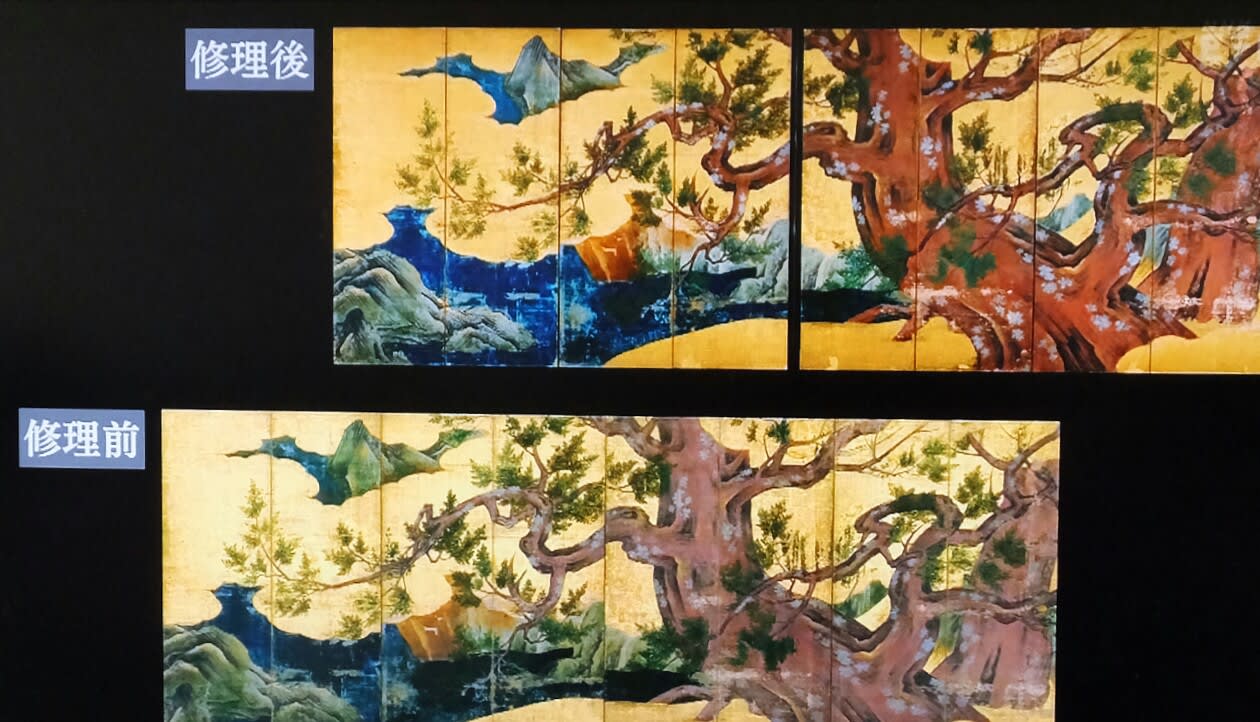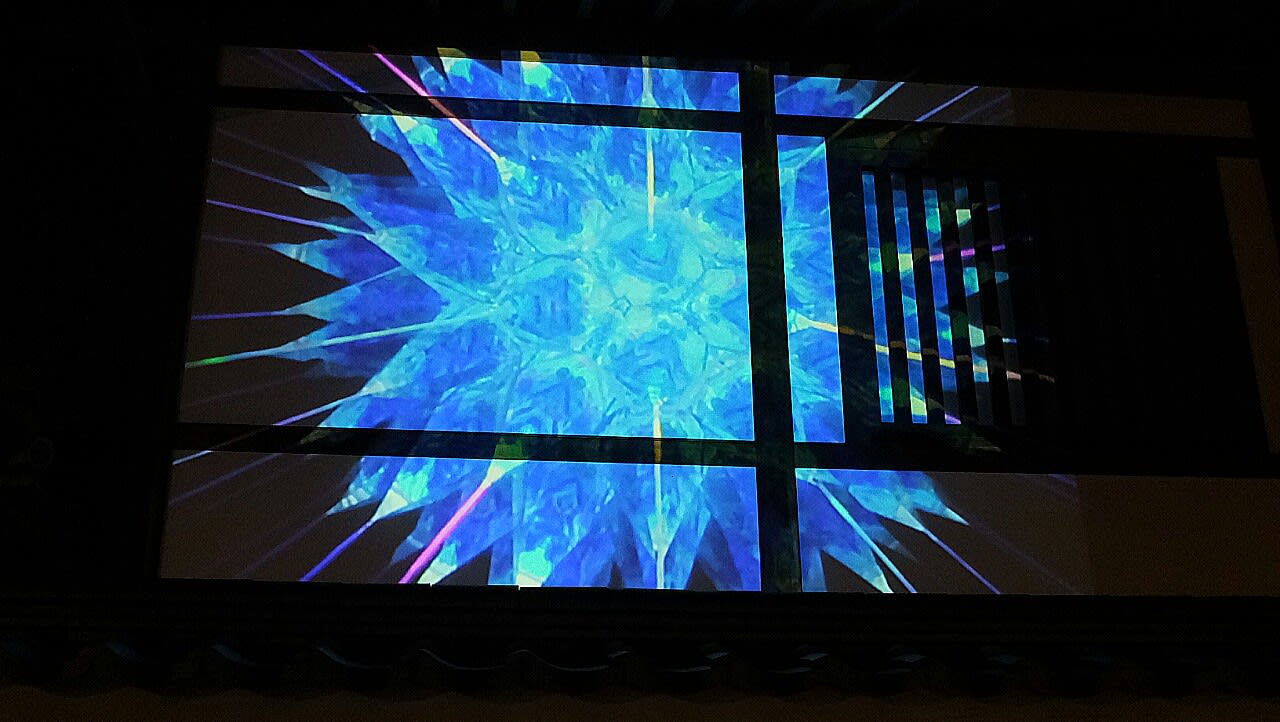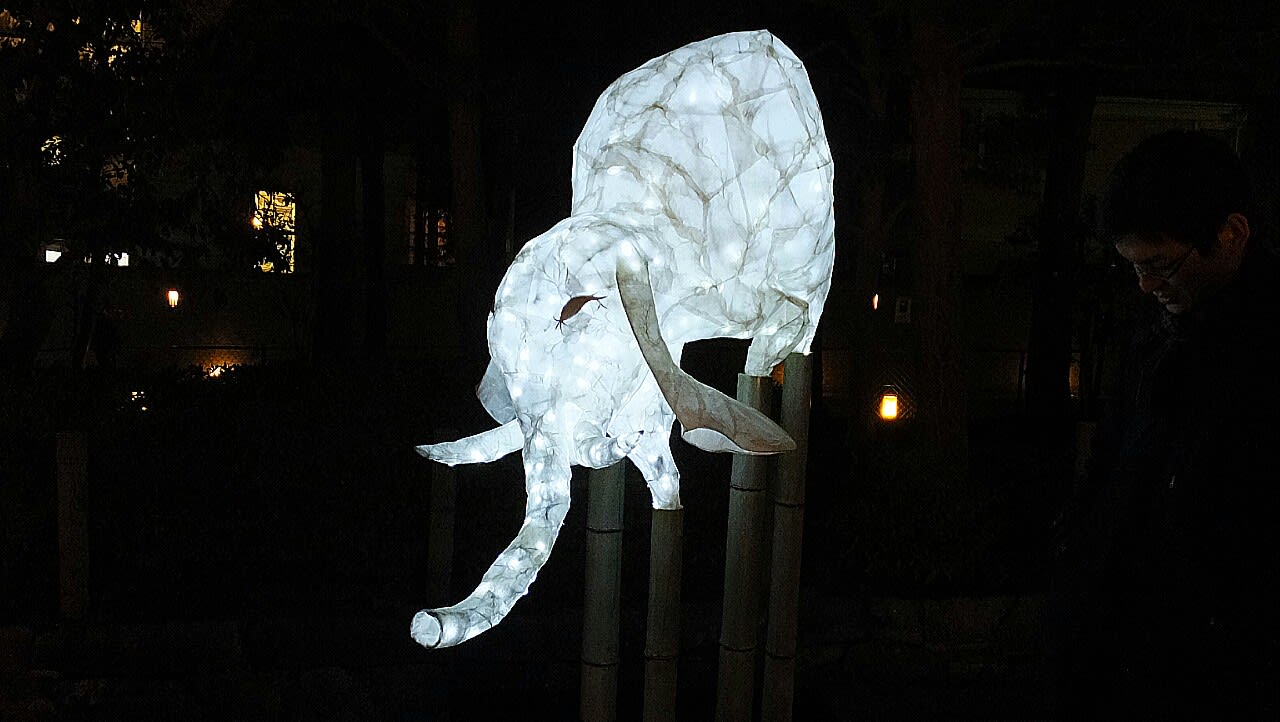昨日は暑いくらいの天気でした。
京都市内は22度と、4月下旬のようです。
昨日、日の出(6時9分)前に散策にでました。
撮影場所は、「山紫水明」と京都を表した頼山陽の住居前の鴨川です。
日の出間もない東山の稜線は、おもわず、枕草子の一節を思い浮かべました。
『春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少し明かりて、
紫だちたる雲の細くたなびきたる。』です。

北山の稜線も美しい景色です。

鴨川です。

柳もだんだん春の装いになりつつあります。

まだ早いのはわかりつつ、京都御苑の近衛跡に立ち寄ってみました。
画像左上、糸桜が少し頬紅に色づきはじめています。

つぼみもずいぶん膨らんできました。

近衛跡の糸桜とほぼ同時期に咲く、平野神社の魁(さきがけ)桜のつぼみも膨らんでいます。

桃桜は満開です。

コデマリの若葉も大きくなってきました。

あと少しで、開花の御報告ができそうです。