
「学問のススメ」ではなく「乾物のススメ」である。
この頃の人達は、あまり乾物を使うことが得意でないようだ。何かというと化学調味料や即席の合成調味料を使う。そうでないと料理そのものが成り立たないと思い込んでいるふしもある。スーパーの売り場には○○の素、粉末食品、乾燥食品、レトルト食品、冷凍食品などの即席具材が所狭しと並んでいる。チャーハンを作るのも中華丼を作るのも野菜炒めを作るのもお好み焼きを作るのも果ては味噌汁さえもレトルトや粉末状の具材が揃っている。しかし、私はこんなものは一切使わない。使うのは乾物である。使い慣れると簡単だし、上等の味になるし栄養も満点である。
乾物は読んで字のごとく乾燥したものであり、当然日持ちが良い。
密閉容器に入れておけば1年でも2年でも保存可能である。私の言う乾物とは具体的には、煮干、昆布、しいたけ、鰹節、乾燥海老、スルメ、乾燥ニンニク、ゴマ、豆類、高野豆腐、麩、そうめん、うどん、パスタ、春雨などなどである。他にもいろいろあるだろうが、あまり面倒臭いことは嫌いなので、使い勝手の良いものを揃えて常時使っている。使いにくいものはどうしてもお蔵入りになって持て余してしまう。以前は鰹節をいちいいち削っていたが、面倒なのでこの頃は削ったもので済ましている。ただし、カビ付けしたものでないと質が落ちるので、そこはこだわって選択している。少量ずつパックされたものは安くて手軽だが、たぶんカビ付けした鰹節を使っていないと思う。だしを取った時によく解る。
料理の真髄は「だし」だと思っている。
多くの人は乾物からだしを取るのは難しいし面倒だと思っているが、実際はそれほどでもない。たとえば、味噌汁のだしは夕食の分は朝に仕込む。仕込むと言っても鍋に水を張って煮干と昆布と乾燥しいたけを入れておくだけである。昆布は調理バサミであらかじめ細かく切っておく。しいたけも細かく切って入れる。めんどくさいと思えば一度に細かく切って密閉容器に入れておけば一つまみ掴んでバサッと入れるだけである。夕方になれば上等のだしが取れている。朝食用であれば寝る前に仕込んでおく。このだしさえあれば何でもできてしまうが、こればかりは今すぐだしを取れといっても出来ない相談だ。しかし、手間はほとんど要らない。この事前の仕込みさえ怠らなければいつでも上等のだしで料理ができる。
世間では「何とか健康法」と銘打っていろんな方法が推奨されている。
たとえば、昆布の抽出物であり、キノコの抽出物であり、大豆の抽出物である。エキスの濃縮度がどれ程だか知らないが、私に言わせれば、濃縮度は低くても毎日少しずつ摂取すれば良いと思う。それが前述の「だし」であり、これを毎日使って料理していれば、毎日健康に良い昆布やキノコや大豆の抽出物を食していることとなる。煮干は貴重なカルシウム源でもある。だしを取った素材そのものも一緒に食べてしまうので一石二鳥である。ということで、この乾物利用をずっと続けている。この頃ではこのだしを使った料理を食べないと体調がおかしくなるほどである。反対に時々だしの効いた料理を無性に食べたくなる。
だしは水だしだけではない。
油だし、酢だし、醤油だしもある。これを使って料理すれば格段に美味しくなる。化学調味料も必要ないし、○○の素なんても必要ない。原価はたぶん一回分5円もしないと思う。なんでこんな便利なものを活用しないんだろうと反対に不思議に思う。このだしを使った味噌汁は当然の事、各種鍋、雑炊、中華スープ、お好み焼き、チャーハン、刺身のたれ、酢飯、おでん、炊き込みご飯、茶碗蒸し、野菜炒め、煮込みうどん、などなどである。○○の素を使うよりも美味しくできるし倹約できるし第一健康的である。あと、料理をしていて気付くのだが、素材から出ているだしの大切さである。特に野菜だしは貴重である。野菜のだしがあるとないとでは全然風味が違ってくる。私の特に好きなのはトマトだしである。私は何かにつけトマトをだしに使っている。トマトは生で食べるだけでなく煮込めば上等のだしが出る。イタリア料理はほとんどがトマトだしだと思って良い。
自宅のキッチンには、
私専用の乾物が密閉容器に入れられてずらりと並んでいる。この中から適当なものを選んでだしを取るのが料理を始める前の欠かすことの出来ない段取りである。当然密閉容器にはあらかじめ下処理されてスグに使える状態でストックされている。だしは少なくとも仕込んでから24時間は使える。時間が経てば経つほど濃くなるが、それはそれなりにうまいだしである。夏場は長く置くとどうしても傷んでしまって臭いが出てくるが、これこそ自然の健康的な食材である事の証明だと思っている。いつまでも腐ったり傷んだりしない食物はどう考えても健康的な食材とは思えない。また、上等のだしには調味料は少なくて済み、減塩の効果もある。面倒くさいと思わずに大いに乾物を利用してもらいたいものである。

















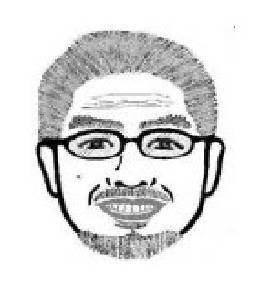





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます