
昨年の歳末助け合い運動は終わったが、
いつも疑問に思うことがある。あれだけの人が募金のために時間を割いているのなら、その時間を別の労働力に振り向けて、その賃金で救済した方がよっぽどいいし、街頭で不特定多数に呼びかけるのではなく金持ちの家を訪問して大口で寄付して貰えば効率的だという天の邪鬼な考え方である。当然、いかがわしい助け合い運動もあって、市民の善意がそのまま恵まれない人達の救済に使われているかは定かでない。
歳末助け合い運動は西欧からの流れである。
慈善鍋と呼ばれる宗教的な風習で、街頭に鍋を据えてこれに市民の善意の寄付を募るというものである。日本の場合は宗教的な後ろ盾がなく形だけで行われているようだが、根底にはキリスト教の博愛精神に通じるものがある。慈善は人に対して行うものではなく神に対して行うものである。ある人が可哀想だから恵んでやるのではなく、自分が救われるために神に対して寄進し、少しでも神に近づく行為である。そして、不特定多数の一般市民に対してその行為を推奨する場が慈善鍋なのであろう。
どちらかというと、寄付の金額ではなくその心である。
そして、不特定多数の一般市民に対する布教活動の一環でもあり、どちらかというとその意味合いの方が強い。しかし、日本の歳末助け合い運動にその精神を感じることはないし、参加している人達もそんな心を持っているとは思えない。「恵まれない人達に愛の手を」といった発想であろう。日本の宗教にもこの精神は宿っている。「布施」と呼ばれるもので、今ではお坊さんに対する心付けかお恵みくらいにしか考えていないようだが、本来は神に対する寄進であり、寄進により寄進した人が救われるのである。
何でお坊さんは戸別に訪問し門前で布施を募るのか、
布施をする心が神を信じ自分が救われることに通じるのであり、言わば布教活動の一環なのである。このごろ戸別に布施をして回るお坊さんを見なくなって、ただの神社仏閣への寄進としてのお金の受け渡しだけが具体的な行為になってしまっているが、本来の意味を考え直すことも必要ではないかと思う。お賽銭は何のためにあげているのか、自分を救うためである。間違っても拝観料ではない。宗教関係者も勘違いしているのではないだろうか。
困った人を救済できる機会を得られることは光栄である。
自分のできる範囲で喜んで救済すべきである。それが少しでも神に近づく行為でもある。万能の神は全ての人を救済できる力を持っているが、人間にその力はない。しかし身近の人を救済することは、少しでも神に近づくことができる。そしてそんな機会が得られたことと、救済できる自分の幸福に感謝しなければならない。そんな機会が容易に与えられるのが歳末助け合い運動であり、自分の幸福感をかみしめ、神に感謝し、自分が救われる瞬間でもある。
救済の機会は万人に平等に与えられるべきである。
我々人間は神ではない。救済の機会を独り占めすることは許されないし、神への冒涜である。ある金持ちがある困った人へ個別に施した救済は人間と人間の行為であり、神の行う救済ではない。救済されるべき人がたくさんいて、救済する人がたくさんいて、みんなで平等に救済すべきである。この場合の平等とは機会の平等であって金銭の平等ではない。それぞれの立場でそれぞれの状況に応じて救済され救済することは当然である。
日本人は平等というとすぐに「みんな同じ」と思う。
それは間違いだ。富める者はより多く寄進し、貧しい者はそれなりに寄進する。金銭の多少はあってもその心は一緒だし、その多少こそがそれぞれの心の著れであろう。救済される側も全員一律である必要はない。必要とする者に必要な分だけ救済の手が伸べられる。たとえ貧しくとも自立できる人には救済の必要はない。救済にも「格」がある。自分の食べる物に困っている人と、救済事業の資金繰りに困っている人、と、同じ額でいいはずがない。
さて、
歳末助け合い運動は宗教的な意味合いがある。困った人を救済することは自分を救うことである。救済の機会は独り占めしてはいけない。ということで、歳末助け合い運動はみんなでやらなければならないということに納得できるが、現実の歳末助け合い運動はそこまで考えられていない。募金をする人も募金を募る人も何となく慣習でやっている気がするし、本来の目的を達成するなら、宗教的意味合いと、自分を救う行為であることと、みんなで救済する意義を説明する義務があると思われる。
最新の画像[もっと見る]
-
 議員先生と学校の先生との違い
2年前
議員先生と学校の先生との違い
2年前
-
 SDGsともったいない精神
3年前
SDGsともったいない精神
3年前
-
 発想の転換
4年前
発想の転換
4年前
-
 発想の転換
4年前
発想の転換
4年前
-
 ワンニャン仲良し
18年前
ワンニャン仲良し
18年前
-
 ワンニャン仲良し
18年前
ワンニャン仲良し
18年前











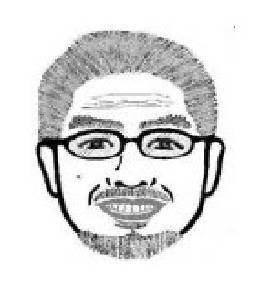





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます