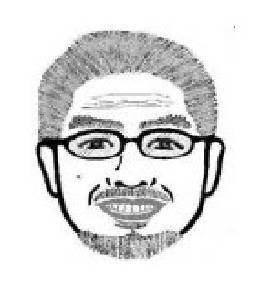かつて日本の住宅は「ウサギ小屋」であると言われたことがある。
この頃はあまり騒がれないが、以前は日本人自ら自虐的に面白がって取り上げたものである。日本の住宅を「ウサギ小屋」にしたのは日本国政府である。この「オクトシティー正直村」の熱狂的な読者(いるわけがないが・・・)は「またはじまった」と思われるかも知れない。なんでもかんでも「日本国政府」の責任である。しかし、一方的に日本国政府の責任にするつもりは毛頭ない。歴代の日本国政府を代表として選んできたのは日本国民である。何も文句を言わないで従ってきたのも日本国民である。日本国政府の責任は我々日本国民の責任でもある。
日本の住宅を「ウサギ小屋」にしたのは、住宅金融公庫の融資基準である。
今現在少しは見直されているが、住宅金融公庫が発足したばかりの頃は融資対象は45平方メートル以下であった。45平方メートルは当時の一般的な公団住宅の広さである。一旦基準が決められるとなかなか修正できないのが日本の慣例である。今現在この基準で建てられた住宅が「ウサギ小屋」として主流を占めている。基準は見直されてはいるが、徐々にしか修正できず、「45平方メートル以下」という過去の明確な基準の縛りから逃れることができないようだ。
住宅の戸数そのものを増やすことを目的とすれば、
1戸当たりの家屋面積を小さくすることの意義はある。しかし、現在は住宅の戸数を増やすことよりも住宅の質の向上が叫ばれている。しかも、国際的な基準からすると日本の新築住宅は一般的に貧弱である。もっと早い時期に見直すべきであったと思う。
ところで、この45平方メートルという基準はどのようにして決まったのであろうか。
住宅金融公庫などと言われるものがなかった時代は、もっと広い家に住んでいたような気がする。45平方メートルと言えば、落語に出てくる下町の長屋の広さくらいであろうか・・・。江戸時代の下町の長屋の広さが現代日本の住宅の広さの上限であるとはどうも解せない。
45平方メートルとは当時の一般的な公団住宅の広さでもある。
公団住宅と言えば公務員の官舎の規格も公団住宅並であったと思う。この基準を決める作業を担当したのは「公務員」である。どうやら「我々公務員が住んでいる官舎より広い住宅に一般庶民が住むのはけしからん」ということらしい。別に45平方メートルの基準が悪いとは言わないが、いったん基準を決めたら杓子定規にいつまでも固執するのはいただけない。その基準に重要な意義があるならまだしも、大して固執すべき理由もない基準であれば即刻見直してもいいはずである。外国から「ウサギ小屋」と言われないためにも・・・。
日本人の生活水準を著しく悪くしているのは、住宅と交通と物価である。
住宅が高いのは土地が高いからである。土地を高くしたのは「土地神話」に浮かれた土地への闇雲な投機である。住宅そのものも高い。これを高くしているのは高くても売れる市場の異常さである。これを支えるのは国の住宅金融公庫のテコ入れであり、閉鎖的な市場である。金融公庫を見直し市場を開放すれば安くて良い住宅が出回り暴利はなくなるであろう。
交通は、特に都市部が最悪の状態になっている。
これは何としても改善しなければならない。相当な犠牲と困難を伴い問題点も山積しているが、何とかしなければならない。無理難題はほったらかしにして、事業を行いやすい土地の余っている場所に必要のない施設(箱モノ)を建てたり整備新幹線や高速道路を伸ばしてもあまり意味がないと思う。必要とするところには必要なものを設けなければならない。たとえどんな困難があろうとも・・・。
物価が高いのは、輸入規制から生じている。
これも市場を開放すれば国際水準並に落ち着くはずだ。国内産業の保護のために輸入を規制することは長い目で見れば時代に逆行し、あまりにも現状に固執し過ぎる無意味な行為である。スローガンとして国際平和を唱えていて、各論において国内産業を保護するために「有事の際の自活能力保持」を持ち出しても説得力がない。世界に依存すること即国際平和希求に通じると思う。それとも最悪の場合世界各国すべての国を敵にまわして戦うことも想定しているのだろうか・・・。そんなことがないようにするのが外交努力であり相互安全保障であると思う。
日本の国内総生産は世界の上位を占めている。
もっと豊かな暮らしをしてもいいはずである。豊かな暮らしと感じられないのは、どこかに無駄があるのか、何かが機能していないのか、力を注ぐ力点が間違っているのではないか・・・。景気が悪くて雇用が伸びないのであれば、国民が熱望している分野に光を当てて生活の改善を図るべく産業振興と雇用対策を促進する施策をやるべきである。それは、使いもしない公共施設や利用価値のない道路や鉄道や橋の新設でもなく、時代に取り残された産業の保護でもなく、見通しのつかない一大事業でもなく、平等なバラ蒔き政策でもない。もっと地に足をつけた政策を熱望する。