平成30年7月28日(土)、29日(日)、主人が予てから行きたがっていた「相馬野馬追」へ行ってきた。
それというのも、主人の祖父は、福島の郡山の生まれで、結婚してから、北海道の江差という所に開拓に行った人で、自分の裏山に、相馬の「中村神社」の分社を建てたということだ。義母は新婚旅行に、祖父からぜひ行ってこいと言われ、その中村神社に行ったと話していた。
何か月も前に、「戦国絵巻、相馬野馬追と会津名所めぐり」という丁度いいツアーがあり、会津には4,5年前に職員旅行に行ったことがあったが、それはそれとして、参加した。
1日目は会津名所めぐりで、最初に、下野街道の「大内宿」に行った。お殿様が参勤交代の時に利用したという。ここでは、とちもち(ドングリをつぶして餅にしたもの)を食べたり、古代米のおむすびを食べたりと、昔の食べ物を食べてみた。













次に、「会津鶴ヶ城」、丁度幕末の戊辰戦争や白虎隊のことが展示していた。
1866年第2次長州征伐から
1867年大政奉還、
1868年鳥羽伏見の戦い、そこで徳川慶喜や松平容保(かたもり)は江戸に逃げ、江戸城が開城され、会津戦争とつながる。白河城や二本松城が落城し、飯盛山での白虎隊の自刃になる。






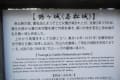

白虎隊が自刃した「飯盛山」へ行く。
自刃の際に一人生き残った人の墓や、イタリアのムッソリーニーはこの白虎隊の話に感動して、大きな塔が贈られたという。また、会津の武士の奥さんは、夫が出兵する際に夫が気兼ねなく戦えるように、負けて辱めを受けないように、自刃する。家老の西郷頼母の家でもそのようなことが起きていて、でも一人の娘さんが死にきれずに息をしていた時に、敵の武将がきて、殺してもらったという逸話もある。その武将はその後政治家になって、国会でその話をして、それ以来、同じ日本人同士が殺し合うという不幸な出来事は起きていない。
会津には、黒い看板のセブンイレブンがあった。どうも「景観条例」なるもので、観光地や指定されたところでは、派手な景観は罰せられることがあるとか。かえって目立った感じであったが。






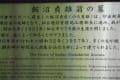


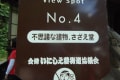
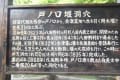


2日目に念願だった「相馬野馬追」へ。
馬追の由来は、相馬家の祖といわれる「平将門」は一千年前の昔、新しい軍事力として馬の活用を考えて、「牧」(馬の放牧場)で野生の馬を放牧し、野馬を敵兵に見立て野馬を追い、馬を捕らえる軍事訓練として、また、捕らえた馬を神前に奉じたお祭りとして行ったのが、この相馬野馬追の始まりという。その後、1323年相馬氏はこの南相馬市に移り住んでからも、代々の相馬領主が、明治維新までこの行事を連綿と続けたことが今日までつながったという。
西に進むという前代未聞の台風12号が通り過ぎたので、雨は大丈夫かと思ったが、何度も通り雨が降っては止み、降っては止みを繰り返し、合羽を着たり脱いだりを繰り返した観戦であった。





一人一人が甲冑を付け、馬を操り、騎馬武者たちが勇猛果敢な戦国絵巻を見せてくれた。
甲冑競馬では、神太鼓が鳴り響くと、兜を脱ぎ白鉢巻きを締めた若武者が、先祖伝来の旗指し物をなびかせて人馬一体となり走り抜けっていった。10レースがあってその都度、1着から3着までの武者にはお札が渡され、それを持ってお山の上まで駆け上る。殿さまに報告する感じで、昔からこんな風だったんだなと実感できた。


神旗争奪戦では、騎馬武者たちが雲雀が原一面に広がる中、天高く打ち上げられた花火からゆっくり出てきた御神旗を数百騎の騎馬武者がこの旗を目指して群がり奪い合う。そして、旗を勝ち取った騎馬武者は、会場に紹介されて、小丘を駆け上がる。その際観客は拍手喝さいを送る。
古式ゆかしい伝統行事が観戦できて楽しかったが、とにかく人が多い。これを見に、全国各地から集まっているようだ。原発事故による休止が続いていたので、福島を応援するためにも毎年賑わってほしいと思った。帰り道の常磐自動車道脇には、まだ黒く覆われた残土が所々にあったので。
それというのも、主人の祖父は、福島の郡山の生まれで、結婚してから、北海道の江差という所に開拓に行った人で、自分の裏山に、相馬の「中村神社」の分社を建てたということだ。義母は新婚旅行に、祖父からぜひ行ってこいと言われ、その中村神社に行ったと話していた。
何か月も前に、「戦国絵巻、相馬野馬追と会津名所めぐり」という丁度いいツアーがあり、会津には4,5年前に職員旅行に行ったことがあったが、それはそれとして、参加した。
1日目は会津名所めぐりで、最初に、下野街道の「大内宿」に行った。お殿様が参勤交代の時に利用したという。ここでは、とちもち(ドングリをつぶして餅にしたもの)を食べたり、古代米のおむすびを食べたりと、昔の食べ物を食べてみた。













次に、「会津鶴ヶ城」、丁度幕末の戊辰戦争や白虎隊のことが展示していた。
1866年第2次長州征伐から
1867年大政奉還、
1868年鳥羽伏見の戦い、そこで徳川慶喜や松平容保(かたもり)は江戸に逃げ、江戸城が開城され、会津戦争とつながる。白河城や二本松城が落城し、飯盛山での白虎隊の自刃になる。






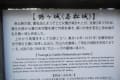

白虎隊が自刃した「飯盛山」へ行く。
自刃の際に一人生き残った人の墓や、イタリアのムッソリーニーはこの白虎隊の話に感動して、大きな塔が贈られたという。また、会津の武士の奥さんは、夫が出兵する際に夫が気兼ねなく戦えるように、負けて辱めを受けないように、自刃する。家老の西郷頼母の家でもそのようなことが起きていて、でも一人の娘さんが死にきれずに息をしていた時に、敵の武将がきて、殺してもらったという逸話もある。その武将はその後政治家になって、国会でその話をして、それ以来、同じ日本人同士が殺し合うという不幸な出来事は起きていない。
会津には、黒い看板のセブンイレブンがあった。どうも「景観条例」なるもので、観光地や指定されたところでは、派手な景観は罰せられることがあるとか。かえって目立った感じであったが。






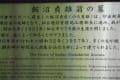


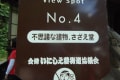
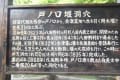


2日目に念願だった「相馬野馬追」へ。
馬追の由来は、相馬家の祖といわれる「平将門」は一千年前の昔、新しい軍事力として馬の活用を考えて、「牧」(馬の放牧場)で野生の馬を放牧し、野馬を敵兵に見立て野馬を追い、馬を捕らえる軍事訓練として、また、捕らえた馬を神前に奉じたお祭りとして行ったのが、この相馬野馬追の始まりという。その後、1323年相馬氏はこの南相馬市に移り住んでからも、代々の相馬領主が、明治維新までこの行事を連綿と続けたことが今日までつながったという。
西に進むという前代未聞の台風12号が通り過ぎたので、雨は大丈夫かと思ったが、何度も通り雨が降っては止み、降っては止みを繰り返し、合羽を着たり脱いだりを繰り返した観戦であった。





一人一人が甲冑を付け、馬を操り、騎馬武者たちが勇猛果敢な戦国絵巻を見せてくれた。
甲冑競馬では、神太鼓が鳴り響くと、兜を脱ぎ白鉢巻きを締めた若武者が、先祖伝来の旗指し物をなびかせて人馬一体となり走り抜けっていった。10レースがあってその都度、1着から3着までの武者にはお札が渡され、それを持ってお山の上まで駆け上る。殿さまに報告する感じで、昔からこんな風だったんだなと実感できた。


神旗争奪戦では、騎馬武者たちが雲雀が原一面に広がる中、天高く打ち上げられた花火からゆっくり出てきた御神旗を数百騎の騎馬武者がこの旗を目指して群がり奪い合う。そして、旗を勝ち取った騎馬武者は、会場に紹介されて、小丘を駆け上がる。その際観客は拍手喝さいを送る。
古式ゆかしい伝統行事が観戦できて楽しかったが、とにかく人が多い。これを見に、全国各地から集まっているようだ。原発事故による休止が続いていたので、福島を応援するためにも毎年賑わってほしいと思った。帰り道の常磐自動車道脇には、まだ黒く覆われた残土が所々にあったので。
















