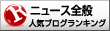<まえがき>
このレーゼドラマ(読むための戯曲)は、40年前に書いた中国現代史劇『文化大革命』の続編である。対象の期間は1975年12月末から1989年6月(第2次天安門事件)にかけてだ。史実に基づいてはいるが、戯曲のため創作・フィクションであることをご了解願いたい。 なお、登場人物や参考文献などについては、後日まとめて表示する予定である。(2020年10月12日)

第1幕・・・“四人組”の権勢と周恩来の死
第1場 <1975年12月の某日。北京・中南海にある江青の居室。江青(61歳)のほかに、張春橋(58歳)、王洪文(40歳)、姚文元(44歳)が集まっている。4人はテーブルを囲んで歓談中>
江青 「この冬は特に寒いわね。みなさん、お体に気をつけてくださいよ」
張春橋 「私たちは大丈夫です。江青同志こそお体に気をつけてください」
江青 「ホッホッホッホ、私は大丈夫、まだやらなければならないことが沢山ありますからね」
姚文元 「でも、養生なさってください。あなたは私たちの“指導者”ですから」
江青 「ええ、養生していますよ。でも、私が還暦を過ぎたからといって、年寄り扱いをしないでくださいね、ホッホッホッホ」
王洪文 「それは分かっています。しかし、周恩来総理の容体が悪いとなると、来年は何が起きるか分かりませんね。われわれはいっそう気を引き締めて対処しなければなりません」
江青 「ええ、そうです。周総理の容体はとても危険な状態になっていますよ。みなさんにも言いましたが、周恩来は4年ほど前に上海で療養中にガンが見つかったのに、われわれの努力でそれを“極秘”扱いにしましたね。
彼がガンだということは、共産党中央でも知らないことです。だから来年こそ、周恩来の余命はいくばくもないということです」
張春橋 「そうか、いよいよわれわれが先頭に立って戦う時が来たのだ。周恩来はあの鄧小平を筆頭副首相に据えた。文化大革命に反対し走資派、実権派の親分として威勢を張ったあの“チビ猫”を、今度こそ抹殺しなければならない! われわれは戦うぞ!」
姚文元 「張同志、えらく張り切ってますね(笑)」
張春橋 「いやいや、つい興奮してしまった。あのプチ・トン(鄧小平のこと)のことを思い出すと、つい体中に血が湧いてくるのさ。ごめん、ハッハッハッハッハ」
江青 「いえ、それは当然です。われわれが始めた『文化大革命』は、毛沢東主席の指示に従った光栄ある戦いだったのですよ。それを陰に陽に邪魔をした首謀者は、あの劉少奇と鄧小平でした。
劉少奇はとっくに失脚して死んだのに、チビ猫はいつの間にか復権して、また大きな顔をしてのさばっています。そのバックには周恩来がいるのですね。彼が亡くなれば、今度こそ鄧小平を必ず叩きのめさなくてはなりません。そうしなければ、われわれ“文革派”もどうなるか分かりませんよ」
王洪文 「まったく同感です。文化大革命はまだまだ続いていますよ。いや、いっそう続けなければならない。それなのに、毛主席はわれわれよりも、最近ではむしろ華国鋒という男を重用していますね。あれはどういうことなのだろうか?」
江青 「それは私も疑問に思っています。華国鋒は自分でも文革派と言っていますが、本当はどうなのか分かりません。単なる出世主義者かもしれないし、出生(しゅっしょう)にも疑問の点が多いですね。
でも、毛主席はつい最近、彼を国務院副総理に任命しました。信頼している証(あかし)ですよ」
姚文元 「出生に疑問の点が多いのですか?」
張春橋 「それは私も聞いているよ。われわれも調べたが、華国鋒は誰かの“私生児”ではないか、ひょっとすると毛主席の“隠し子”ではないかと噂されているんだ」
王洪文 「えっ! 毛主席の・・・?」
江青 「ホッホッホッホ、そんな噂も出ていますよ。主席は女に持てるし、なにせ女性が好きだときているから。それに、彼は主席とまったく同郷の湖南省の湘潭県(しょうたんけん)にずっといましたからね。そこで身を立てたのです。だから、そんないい加減な噂も出てくるのです」
姚文元 「そうか、主席にもいろいろな噂が・・・・やはり、英雄 色を好むか。おっと、ごめんなさい。江青同志、気を悪くなさらないでください」
江青 「いえ、いいんですよ、私もあの人の4番目の妻だから(笑)。 それより、文化大革命を忘れたかのような最近の風潮には、とても情けなくなります。
毛主席も体調が優れず、話すのも億劫な感じですね。人は寄る年波には勝てません。いつ何時、何が起きるか予断を許しません。私たちはさらに結束を固め、来たるべき難局に備えましょう。文化大革命の成就と勝利のために」
張春橋 「そうだ、江青同志が言われるように、われわれ4人は最後の勝利を目指して頑張ろう! さあ、乾杯だ」
(江青、王洪文、姚文元が大きくうなずき、4人は杯を挙げて結束を誓い合う)
第2場 <1975年12月の某日、北京・海淀区(かいでんく)の学生街にある大衆食堂。 北京大学の学生・宋哲元(そうてつげん・21歳)が、友人である精華大学の学生・李慶之(りけいし・21歳)と会食している。2人は楽しく談笑中、背後に数人の学生の姿が見える>
宋哲元 「本当に久しぶりだね。ところで、君のご両親や妹さんは元気に過ごしているの?」
李慶之 「ああ、元気にやってるよ。父は少し老けた感じだが、母は元気そのものだ。妹はいま受験勉強中で頑張っているよ」
宋哲元 「そうか、それはけっこうだ。うちも両親や弟、妹とも元気にやってるよ。健康が一番だね」
李慶之 「うん、そうだね。ところで、大学の授業の方はどうなの?」
宋哲元 「僕は経済や管理学の方だけど、まあ面白いかな。君は理系だけど何が専門なの?」
李慶之 「建築関係だよ。特に都市計画などに興味があるね」
宋哲元 「そうか、僕は理系の方はまったく駄目だ。文系しか分からないから、理系の人を尊敬するよ。ハッハッハッハッハ」
李慶之 「そんなことはないさ。で、いま何が面白いの?」
宋哲元 「そうだな・・・人口問題かな」
李慶之 「へえ~、中国の人口は増えすぎていると聞いたけど」
宋哲元 「このところは少し治まってきたよ。だけど、この5年間に1億人近く増えて、今は総人口が9億人を超えたからね。まだまだ増えるさ」
李慶之 「それじゃ、10億人になるのも時間の問題だね。何か対策を考えているんだろ?」
宋哲元 「うん、政府はもちろん考えているさ。異常気象や自然災害が起きたら、食糧生産に大打撃になるからね。餓死者だって出るかもしれない。それに、以前の『大躍進』時代の失敗もあるから。集団化や人民公社化を改める必要があると思うんだが・・・
おっと、これを人前で言うと睨まれてしまうね。今のは内緒だよ。これはあくまでも僕の考えなんだ。だけど、鄧小平副総理らはまじめに考えているはずだ」
李慶之 「それより人口問題だよ。何か対策はあるのかな」
宋哲元 「そうだったね、人口問題だ。これは周恩来首相も『計画出産活動』を提唱するなど、政府も真剣に取り組んでいるんだ。だけど、今のままでは手ぬるいな・・・ 大学の中では“一人っ子”政策を考えているのもいるよ」
李慶之 「えっ、一人っ子政策だって!?」
宋哲元 「そうさ、一組の夫婦に子供は1人と制限するんだ。そうしなければ、中国の人口問題は解決しない」
李慶之 「そんな・・・ でも、仕方がないか。僕たちは結婚しても子供は1人しか産めないのか。なにか寂しいね」
宋哲元 「うん、寂しくなるね。いや・・・もう、こんな話はやめよう。
ところで、君の妹さんは受験勉強で忙しいんだって? だいぶ会っていないな」
李慶之 「うん、美瑛も北京のどこかの大学に入りたいらしい。あまり聞いてないよ、はっきり言わないから」
宋哲元 「そうか、美瑛さんも成長したんだろうね」
李慶之 「いや、まだ“子供”だよ。少し気になるようだな、君は」
宋哲元 「いや、聞いてみただけだよ。子供のころ、みんなでよく遊んだものだ。あの頃がなつかしい。うちの弟がいちばん“悪ふざけ”をしていたな」
李慶之 「明元君は元気なの?」
宋哲元 「うん、このごろは少し真面目になって勉強するようになったよ。だけど、相変わらず外で遊ぶのが好きだね」
李慶之 「仕方がないよ。誰だって子供のころは外で遊ぶもんだ」
(その時、若い男が宋哲元に近寄ってきて彼の肩を叩く)
宋哲元 「やあ、陶円方(とうえんぽう)じゃないか・・・ ちょうどいい。僕の友人で精華大学生の李慶之君だ。一緒に食事をしないか?」
陶円方 「うん、いいよ」
宋哲元(李慶之に向かって)「僕のクラスメートの陶円方君だ。一緒に食事をしてもいいか?」
李慶之 「もちろん」
(李慶之と陶円方が立って挨拶をしたあと、互いに席につく)
宋哲元 「やあ、嬉しいな。友人を紹介し合えるなんて」
(そして、宋哲元を中心に3人の歓談が始まる)
第3場 <1975年12月の下旬、北京・中南海にある鄧小平の居宅。鄧小平(71歳)が居間で、妻の卓琳(たくりん・59歳)とウーロン茶を飲みながら話している>
鄧小平 「周総理の容体は相当に厳しいようだな。また、お見舞いに行かなければ」
卓琳 「そんなに危ない状態なのですか」
鄧小平 「うむ、あと2~3カ月というところか・・・ 医者がそう言っている」
卓琳 「また、政情が不安になるのですか」
鄧小平 「たぶん、そうなるだろう。あの“四人組”がいろいろ画策しているようだから。毛主席にも最近 何か進言したらしい。主席はバランス感覚があるからそこは上手に采配すると思うが、周総理が亡くなったら、私の立場も微妙にならざるを得ない」
卓琳 「あなたは筆頭副総理ではありませんか。順序から言えば、あなたが周総理の後を継いでなんらおかしくはありません。党の長老たちもそれを望んでいるでしょう」
鄧小平 「うむ、そういうことだが、江青たちがどう出てくるのかな・・・ もうやめよう。こんな話をしていると、気分がだんだん悪くなる」
卓琳 「そうですね、あの文化大革命のころの嫌な思い出がよみがえってきますよ。二度とあんな不当な仕打ちは受けたくありませんね。
それにしても酷いものでした。劉少奇主席のように幽閉されて、非業の死を遂げることはなかったのですが」
鄧小平 「うむ、劉主席は本当に哀れだった。それに比べると、われわれはまだ良かった方かな。トラクターの修理工場に放り込まれたぐらいで済んだからね、ハッハッハッハ」
卓琳 「笑いごとではありませんよ。あなたは“逆境”に強いのですね。その点だけは認めます」
鄧小平 「おいおい、私ももちろん苦しんだよ。もう再起することはないかと覚悟したが、周総理のお陰で復活することができたのだ。それにしても、江青たち四人組はひどい奴らだな。あんなに残忍な奴らはいない」
卓琳 「ええ、本当に。樸方(ぼくほう。鄧小平夫妻の長男)などは紅衛兵の仕打ちで下半身が麻痺になりましたからね。本当に許せません!」
鄧小平 「息子のことを思うと、何をか言わんやだ。ああ、文化大革命を思い出すと胸くそが悪くなる。しかし、あの四人組はまだ文革に固執しているのだ。
毛主席が生きている間になんとか“後継”の地位を確保して、われわれを追い落とそうとたくらんでいる。その足がかりが周総理の死去ということになるのだろう。こちらも気にはなっているが、毛主席にはなかなか会えない」
卓琳 「主席も具合が良くないようですね」
鄧小平 「うむ、話すのが辛いのだという。だから人に会いたがらないし、なんでも“筆談”になるらしいな」
卓琳 「筆談ですか?」
鄧小平 「うむ、こちらがしゃべっても筆談で返事をして終わりということだな。いずれにしろ先が見通せないから、不安がつのるが仕方がない。気を引き締めてやっていこう」
<卓琳がうなずく>
第4場 <1976年1月8日の夜。江青の家の書斎に、江青と張春橋、王洪文の3人がいる。姚文元は他の用事があって欠席>
江青 「今年は何が起きてもおかしくないわね。だから、私たちも体に気をつけてこの冬を越しましょう」
張春橋 「春節(注・旧正月のこと)は楽しく過ごしたいですね」
王洪文 「上海へ行って旧友たちと賑やかにやりたいな~」
張春橋 「君は若いからエネルギーが余っているのだろう。ほどほどにしないといけないぞ!(笑)」
江青 「ホッホッホッホ、王洪文同志は元気がいいですね。うらやましい」
王洪文 「いや、そう願っているだけです。北京にいると息が詰まってくることもあるので、馴染みの上海で羽を伸ばせないかと思っているだけですよ(笑)」
張春橋 「そうだな、上海はいいなあ~、知り合いも多いし遠慮がいらないから」
(その時、書斎の電話が鳴る)
江青 「あら、こんなに遅く何かしら(江青が受話器を取り上げ話し始める) もしもし、あら、あなた・・・ えっ、なんですって!」
(江青がしばらく絶句。やがて電話を切ると2人に話しかける)
江青 「大変よ、周恩来総理が亡くなったんですって!」
張春橋 「えっ、本当ですか」
王洪文 「とうとう亡くなったか、えらいことになった」
江青 「いまのは毛遠新(注・毛沢東の甥)からの電話よ。病院から“急報”があったので、すぐに私にかけてきたの」
張春橋 「ずっと容体が悪いと聞いていたが・・・こうなると、いよいよ鄧小平たちとの戦いですね」
江青 「そうです、あの連中との戦いが始まるのです。後任の総理には、あなた方のどちらかがなるのですよ。絶対に鄧小平にはさせません!
明日にも毛主席にお会いして・・・ でも、主席は体調が悪くてほとんど人に会っていないし、白内障も酷くなっているからどうなるか・・・」
王洪文 「いや、後任の総理の問題はけっこう長引くと思います。毛主席はこういう場合、じっくりと考えますからね。あまり出すぎたことをして、主席の機嫌を損なわない方が得策だと思います。
それより、周総理の追悼式がどうなるのか、その方が問題ですね」
張春橋 「うむ、そうだ、君はけっこう冷静だね。われわれは追悼式を挟んで、世論を喚起しよう。走資派の連中には絶対に総理の座を渡さない。文化大革命はまだ進行しているのだ。
そのことは毛主席も分かっているはずだから、世論を盛り上げわれわれの勝利を目指していこう! その点は姚文元同志にもすぐに知らせる。こういうことでどうですか、江青同志」
江青 「そうですね、あなた方の方が冷静で賢明です。私はすぐにカッとなるからいけない(笑)。でも、毛主席には私からしっかり伝えますよ。
私たちの要望を主席は必ず分かってくれると思います。さあ、新たな戦いが始まりました。みんなで頑張りましょう!」
(張春橋、王洪文が同意する)
第5場 <それから数日後、鄧小平の家に葉剣英・党副主席兼国防部長(78歳)が訪れてくる。彼は卓琳の案内で居間に入り、鄧小平と話し始める>
鄧小平 「これはこれは、副主席、用があれば私の方からそちらへ伺ったのに」
葉剣英 「いや、一刻も早く相談しなければならないから。周総理の死去にはみんなが悲しんでいる。それで、あなたは筆頭副総理だから、追悼大会の“弔辞”の準備を始めているんでしょうね」
鄧小平 「もちろんですとも。いま、いろいろ考えています」
葉剣英 「それはけっこうだ。ところが昨日、あの張春橋が私のところへやって来て、私に弔辞をやってくれないかと言ってきたのだ」
鄧小平 「えっ、そんな・・・」
葉剣英 「もちろん私は断った。つまり、四人組はあなたに絶対に弔辞を読ませないように、いろいろ画策しているんだね」
鄧小平 「そうですか、それは驚きました。彼らはそれほどまでに、私を排斥したいのですね」
葉剣英 「うむ、だからできるだけ早く政治局常務委員会議を開いて、あなたに弔辞を読んでもらうことを決めたいと思う。それだけ言いたかったのです」
鄧小平 「わざわざ、ありがとうございます」
葉剣英 「鄧同志、周総理の死去で事態は大きく動くかもしれない。私どもはあなたを支持しますが、四人組はなにを仕出かすか分からない。それに、毛主席の考えがまったく不明だ。あなたが周総理の後を継いでくれれば良いと思うが、くれぐれもご用心を」
鄧小平 「はい。でも、私はなにが起きようとも覚悟はできているつもりです。文化大革命の時も何年も“失脚”しました。だから全力で戦っても駄目なら、いさぎよく諦めます。
こういう話は終わりにして、さあ、老酒(ラオチュウ)でもいかがですか」
葉剣英 「うむ、いただきましょう」
(鄧小平が居間の奥から老酒を持ち出してくる)
第6場 <1月16日の夕方、北京大学の構内。ベンチに座って読書中の陶円方(とうえんぽう)に、宋哲元が声をかけて隣に座る。近くに学生が数人いる>
宋哲元 「やあ、お待たせ、少し立ち寄るところがあったので遅れてしまった。ごめん」
陶円方 「いや、いいよ。本を読んでいたから」
宋哲元 「昨日(きのう)の周総理の追悼大会は立派なものだったね。様子をテレビで見たけど人民大会堂が人で一杯だったよ」
陶円方 「うん、僕も見た。みんな、周総理の死去を悲しんでいたね。あの模様は、日本など外国でも大きく報道されたそうだ。周総理が亡くなって、これからどうなるのだろう?」
宋哲元 「いや、まったく分からない。政治は混迷するのかな・・・ 鄧小平副総理が弔辞の中で『団結して、大きな勝利を勝ち取ろう』と言っていたが、党の幹部が団結するなんてまったく見通しが立たないよ。あの四人組がますます大きな顔をするんじゃないのか!」
陶円方 「おいおい、声が大きすぎるよ。どこかに“文革派”がいるかもしれないぞ」
宋哲元 「鄧副総理の弔辞は素晴らしかった。50年以上も前からの周総理との交流を振り返り、その人柄を称賛していたからね。胸にじ~んときたよ」
陶円方 「それに比べて、毛主席はいったいどうしたのだ。大切な追悼大会を欠席するなんて・・・体が悪いのは分かっているけど」
宋哲元 「“車椅子”で出席するはずだったが、そうはならなかったな。最近は周総理に嫉妬していたそうだ。いろいろ負い目があるのだろう。江青たち四人組が欠席するように、そそのかしたのかな」
陶円方 「これで鄧小平副総理が矢面に立つから、四人組との対決は決定的になった。そこを毛主席がどう判断するのか、次の総理が誰になるのか見ものだよ」
宋哲元 「それもそうだが、一般大衆は周総理の死去を心から悲しんでいる。どんな動きが出てくるとも限らないぞ」
陶円方 「うむ」
第7場 <1月中旬過ぎのある日、北京・中南海にある毛沢東の居宅。書斎にいる毛沢東(82歳)がよろけながら立ち上がると、窓越しに外を眺めながらモノローグ>
毛沢東 「ああ、わしもすっかり年を取った。医者に来てもらったり病院へ行くなど、体は“がたがた”でいつ死んでもおかしくない。が、わしより5歳年下の周恩来が先に亡くなるとは・・・ これも寿命だから仕方がないか。
周恩来の後継総理を誰にするか、それが問題だ。鄧小平には絶対にしない。それは彼も分かっているだろう。わしに会いたいと言ってきたり、政治局に自己批判書を出したりしているが、そんなことは問題外だ!
だからと言って、江青らが推す張春橋を充てるわけにはいかない。党幹部や官僚、軍部の大半は張春橋に反対している。彼らは“文革派”を嫌っているのだ。しかし、彼らが推す李先念(りせんねん)に対しても、江青らは猛反対だ。
困ったものだ。どちらにしても、党は分裂の危機にある。そこで、苦肉の策だが第三の道を考えるしかない。第三の道、第三の男・・・それは妥協の産物だが、どちらにも属さない男、華国鋒(かこくほう)にするしかないのではないか。
華国鋒なら、江青らもそれに敵対する連中も仕方がないと思うだろう。これで、党の分裂は当分 避けられる。彼はわしの故郷である湖南省・湘潭県(しょうたんけん)などで22年もよく働いてくれたし、わしに極めて忠実な男だ。
よし、もう言うことはない。これで一安心だ」(毛沢東が手元の呼び鈴を押すと、女性秘書Aが現われる)
毛沢東 「政治局委員の華国鋒氏に連絡を取りたい」
女性秘書A 「かしこまりました」 <続く>