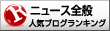☆ 以下の記事(2011年9月17日付)を復刻します。
<記者クラブは特権組織ではない>
福島原発の周辺地域を「死の町」と呼んで鉢呂経産大臣がクビになったが、これはマスコミの“言葉狩り”が功を奏したのである。ここで、「死の町」発言が失言かどうかはもう論じない。再三論じてきたからだ。この発言は“客観的事実”をはっきり述べたものだと高く評価しておこう。
それよりもまず、マスコミのあり方について述べていきたい。マスコミとは「大衆伝達」のことである。伝達とは送り手と受け手がいることで成り立つが、その媒体になるのが「メディア」である。よくマスメディアと言う。普通、マスコミとはこの「マスメディア」のことを指しているのだ。
この辺のことはもう多くの人が知っているのだが、問題は媒体になるメディアがどういう性格を持ち、正しく伝えているかどうかということである。現代では新聞、テレビ、ラジオ、通信社、雑誌などがあるが、インターネットもその一つである。
前置きが長くなったが、ここで一つ問題を提起しよう。それは「記者クラブ」制度の問題だ。大方の官庁や公的機関には通常、記者クラブがある。そこに新聞、テレビ、通信社などの記者が詰めているのだが、こういう「記者クラブ」の形態が最良というわけではない。なぜなら、官庁など送り手の発表内容が直接、国民には伝わらないからだ。
大衆伝達というのは本来、送り手が“直接”受け手に伝えるのがベスト(最良)なのだ。その方が、何の介在もなくストレートに伝わるからだ。その点はインターネットが最も有効で、ホームページやメルマガなどが当たり前になってきたが、その話はまた後で触れる。
それなら何故、まだ「記者クラブ」が存在するのか。それは送り手(官庁など)にとってもメディアにとっても、極めて便利だからだ。新聞やテレビなどがある限り、送り手はそれを利用しない手はない。また、メディア側にとっても情報やニュースを次々に提供してもらえる。つまり、双方が持ちつ持たれつの関係にあるのだ。新聞やテレビなどがある限り、記者クラブはなくならないだろう。
問題は記者クラブの“弊害”である。あえて弊害と言ったのは、これが大衆伝達の間に「介在する」ことによって、情報やニュースが正しく伝えられているのか、つまり意図的に歪曲されたり、誤って伝わる危険性がないのかといった問題である。
記者たちも受け手である。彼らが情報やニュースを“取捨選択”するのである。そして、自らの判断でそれを伝えるのだ。そこには、どうしても恣意的な要素が入ってくる。
例えば、政治や経済などの話で、各新聞の内容が大きく異なることがある。政治面では全く逆の記事が出ることさえある。それは、“第1次受け手”の記者(新聞社)の判断によって違ってくるからだ。そうなると、“第2次受け手”である一般大衆は、読んでいる新聞によって認識が大きく変わってくるのだ。
どうも難しい話になったが、それなら記者クラブを介在せずに、われわれ一般人が直接、送り手の情報などを有りのままに知ろうとして、インターネットが最近活用されるようになった。これは良い意味での“垂れ流し”とも言える。
「垂れ流し」とは普通、悪い意味で使われる。つまり、官庁などの発表を記者たちがそのまま伝えるということだ。これを戦中の例から“大本営発表”だと皮肉ったり、そういうメディアを「御用新聞」「御用テレビ」などと批判する。しかし、当局の発表を正確に伝えていることだけは間違いない。
問題は、そういう情報を受け取るわれわれに、しっかりとした「批判精神」があるかどうかということだ。メディアが垂れ流しをしようが、意図的に情報を取捨選択しようが、受け手のわれわれに「批判精神」がなければ、ただメディアの意のままに動かされることになる。あとは受け手の問題なのだ。
新聞も読まないし、テレビも見ないという人が増えてきた。それは各人の自由だからどうでもいいが、一つだけはっきりと言っておく。それは特に新聞の場合だが、各紙とも“特徴”を出そうとしている。新聞離れが進むと余計にそうなる。
経済紙は別としても、一般紙はそれぞれ特徴を出すことによって、生き残りを賭けているのだ。保守系の新聞もあればリベラルな新聞もある。色とりどりなのだ。
最後に、新聞やテレビはしょせん「商業新聞」「商業放送」(NHKは別か?)なのだ。広告主がいなければやっていけない。その点は、しっかりと認識しておく必要がある。
記者クラブの問題を先ほど話したが、そこにもし弊害があるなら、政府等はなぜインターネットをもっと活用しないのか。例えば、官房長官の発表があるなら、まずインターネットに流せば良いではないか。その方が、国民もマスコミも同時に情報を入手できるのである。記者クラブを介さなくても良い。記者クラブは「特権組織」ではない。生の情報が国民にもストレートに伝わってくるのだ。
記者クラブは猛反対するだろうが、その後で会見を開いて質問を受ければ良いのだ。情報は正確に、公平に行き渡らねばならない。もう、そういう時代に入っているのではないか。
以上、今日は第1回なので概略的な話になってしまったが、今後、過去の事例などを含めて具体的に話をしていきたい。
<メディアを制する者が勝つ>
前の記事で、記者クラブなど第三者が介在しない方が、情報は正確にストレートに国民に伝わると述べたが、これは何も政治や経済の話ばかりではない。芸能だってスポーツだって、今やホームページ、ブログ、ツイッターなどを通じて当事者の意見や気持が直接、一般大衆に伝わるのである。スポーツ紙やテレビはそれを後追いしていることが多い。時代は大きく変わったと言える。
何であれどんなものでも、国民は「知る権利」を持っている。それに応えるのが「メディア」の役割だが、逆に言えば為政者でも誰でも、そのメディアを十分に活用できるかどうかが勝負になってくるのだ。
全体主義の国家、例えばナチス・ドイツや旧共産主義国家ではメディアが統制・管理されていたので、為政者の思い通りだった。日本でも戦時中は、メディアは完全に統制・管理されていた。
これが民主主義社会になると変わってくるのだが、それでも、メディアを制した者が大いに有利になるのは昔も今も変わりはない。
例えば、戦前のアメリカでは、時の大統領フランクリン・ルーズベルトが、当時の主要メディアであるラジオを使って「炉辺談話」を大いに行なった。これはラジオを通じて直接国民に呼びかけるものだが、ルーズベルトはこれを毎週やったという。
大不況後の経済悪化と国際緊張で、ルーズベルトは内政面で決して優位な立場に立っていなかったが、この「炉辺談話」によって国民の支持を大いに取り付けたといわれる。つまり、メディア(ラジオ)の使い方が上手かったのだ。
日本では、最近の例が余りにも有名で誰もが覚えているだろう。6年前、小泉純一郎首相は「郵政解散」を断行した。この解散自体が非常に問題なのだが、それに触れる時間はない。
善し悪しは別にして、小泉首相は解散を断行するや否や、自分に反対する与党議員の選挙区に、次々と対立候補を立てた。すると、マスメディア、特にテレビはこれを「刺客」候補として大々的に報道し、国民の多くがそれに目を奪われたのである。中には“ホリエモン”と呼ばれる異色の候補も立った。結果は投票率が大幅に伸び、「小泉自民党」の大勝利で終わったのである。人はこれを“小泉劇場”と呼んだ。
ルーズベルトの話はともかく、郵政解散や小泉劇場、刺客のことはよもや忘れていないだろう。善し悪しは別にして、これなどはメディアを十分に活用、利用した典型的なものである。
もちろん、小泉戦略にまんまとハマったメディアの責任も大きい。私はフジテレビという会社と少しは縁があるので、選挙中から、「あの報道はおかしいだろう。変じゃないか」と某局長らに何度も言ってやった。しかし、刺客候補に熱中する姿勢は最後まで変わらなかった。メディア自体が完全に“はめられた”感じだったのである。
あの時は異例なことだが、居酒屋でも家の食卓でも、また会社の昼の食事時でも、選挙の話に花が開いたというから珍しいことだ。投票率が大幅に伸びたのは(前回選挙より7,65ポイントも伸びた)、民主主義にとっては良いことだが、どこか異常な感じがしたのである。
これは、メディアを制する者が勝つという典型的な例だ。テレビや新聞に責任があろうとも、結果はこうなったのだ。それを覆すことは出来ない。「メディアを制する者が勝つ」・・・これが現代である。
それから言うと、ニューメディアであるインターネットを制する者が、これから優位に立つのではないか。中東の政変や革命を見ると、つくづくそう感じるのである。
今日は別の話に進む時間がなかった。次回はメディア同士の戦いの歴史を振り返ってみよう。
<新聞対テレビの戦い>
個人的な話をしたい。私がフジテレビという会社に入ったのは1964年(昭和39年)だったが、当時のメディアは新聞、通信社が圧倒的に強かった。中でも新聞は歴史と伝統があり、大勢の記者を抱えて日本社会の隅々まで取材網を張り巡らせていた。それに、新聞も通信社も海外支局を持ち、主な外国の取材も独自に行なっていた。
それに比べると、テレビ(NHKを除く)は歴史が浅く取材網は貧弱なものだった。国内では国会や首相官邸、警視庁などにわずかな記者を配置して細々と報道を続けていたが、海外支局(外国特派員)などはまだなかったと思う。
面白い話がある。私が入社する少し前だったか、千葉県内である事件が発生したため、報道の先輩が取材に行って地元の人に、「フジテレビですが・・・」と言って挨拶した。そうしたら、「どこの電気屋さんですか?」と逆に聞かれたという。先輩からその話を聞いて大笑いしたが、当時は会社の存在さえ知られていない一面があったのだ。
当時のニュース原稿は、出先のわずかな記者から送られてきたものもあったが、主に共同や時事といった通信社の配信記事を使っていたと思う。共同などはラテ用(ラジオ・テレビ用)の記事も送ってきたので、それらをまとめて放送原稿にしていた。とにかく、弱小の報道機関だったのだ。ニュースの時間枠がとても短かかったので、それで何とかやり繰りしていたのだろう。
しかし、テレビメディアが拡大発展していくにつれて、そんな弱小報道機関のままで良いはずがなかった。記者の数も増やし、アメリカなど外国にも特派員を出すようになった。しかし、国内で最も大きな問題は「記者クラブ」へなかなか加入できなかったことだ。先ほども述べたが、国会や首相官邸など主な所には記者を配置できたが、各省庁のクラブにはほとんど入ることができない。その大きな理由は、大新聞社などが強く反対したからである。つまり、新聞から妨害を受けたのだ。
例えば、最も重要な大蔵省(今の財務省)記者クラブに入るのに、何年かかっただろうか。私の入社後もなかなか入れなかった。このため、某先輩はクラブの部屋にも入れず、廊下を行き来しながら広報室などに行ったりして取材を続けていた。NHKを除いて、他のテレビ各局はみなこういう苦労を積み重ねてきたのだ。
「記者クラブ」というのは極めて保守的、閉鎖的、差別的な所だから、なかなか常駐を認めない。民放テレビ各局は、初めは“常勤”ではなく“非常勤”として差別を受けていた。だから、部屋にも入れてもらえず、もちろん机も与えられなかった。せいぜい各省庁の広報室に出入りしたり、「廊下トンビ」と言って省庁内をうろうろ歩いていたのだ。その頃は、新聞社が本当に嫌だなと思ったものだ。
しかし、時代の流れは争えない。テレビの力が徐々に発揮されてくると、各省庁の方がテレビを無視するわけにもいかず、これを逆に利用しようとしたのか、新聞各社に働きかけ記者クラブ加入を認めさせていった。大方こういう流れだったと思う。
その頃は、テレビ局内にも、記者クラブを「ボイコットせよ」という勇ましい意見も出ていた。新聞がそんなに妨害するなら、あえて記者クラブなんかに入らず、堂々と自由な取材活動をしようではないか。今やテレビの時代になったのだから、各省庁もテレビの取材に応じないわけにはいかないだろう・・・といった強気の意見も出ていた。
しかし、記者クラブに入れば、基本的な情報はいつも知ることができる。そのメリットの方がやはり大きいという意見が強く、頭を下げ下げ次々に記者クラブに入っていったのである。ただし、クラブに加入しても、新聞社との間にはまだ“差別”が残っていた。例えば、ある省庁では、幹部との「記者懇談会」からテレビ記者は排除されるなど、いろいろな差別的ケースが続いたのだ。新聞社は既得権益を守ろうという姿勢が強かったのだろう。まあ、「縄張り根性」と言ってよい。どこの世界にもそういうものはあるのだ。(2011年9月17日)