
先週の火曜日に開幕した、欧州の春を告げる自動車のお祭りであるジュネーブショーに足を運んだ。 フランクフルトで前泊し、朝8時のフライトでこの湖とアルプスに囲まれたこの中立国に向かうが、飛行時間は1時間足らずである。 EU加盟国が30数カ国になったとはいえ、空港ではパスポートコントロールに列ができるし、何よりも煩わしいのは、セキュリティーチェックだ。 ベルトや時計をはずしても、金属プレートが底に入った靴を履いていると、必ず「ビー」と引っかかる。 警官の棍棒のようなメタルディテクターで全身を撫で回され、脱いだ靴をX線スキャンに通してようやく無罪放免となるが、後ろの人は辛抱強く待たされる。 ラップトップPCをトレイに入れるのはまだしも、2年ほど前から始まったスプレーや液体の入った容器を、透明なビニールケースに入れて出すのも面倒だ。 うっかりサイズを超えたものを持ち込むとそのまま廃棄されてしまう。 さらに、アメリカに入国する外国人は(今や日本もそうだが)、両手人差し指の指紋と虹彩の写真を撮られるからとても面倒だし、EU国間の行き来は便利になったとはいえ、パスポートコントロールの担当官の無愛想な目と向き合う瞬間は、肌の色や背格好で分類されているようで、いつまでも慣れない、居心地の悪いものである。
さて、ジュネーブショーの会場のメッセだが、空港に隣接して歩いていける。 9時半過ぎには会場に入ったが、この日は日曜とあって、午前中も早い時間からごった返してきて、洋の東西を問わず、若いカップル、ベビーカーを引く家族連れ、若い男の子の群れが通路に溢れ、フェラーリなどのスポーツカーのブースやイタルデザインなどのカロツェリアの前には人垣を作っている。 ジュネーブショーは、コーチビルダーやチューナーが、自動車メーカーに混じって主要なスペースを与えられているのに特長があるが、日本には失われつつあるスタイリッシュなクーペやスポーツカーに対する熱気が感じられるし、出展側もそれに応えて、高性能車を目玉に据えている。 ワールドプレミアは多くはないが、アルファ8Cスパイダーや、ブガッティヴェイロンのエルメス仕様、モーガン、大和の国のNissan GT-Rにも熱い視線が注がれていた。
もう一つ特徴的だったのは、CO2、環境への配慮を各メーカーがこぞって大々的にアピールしていることだ。 トヨタとレクサスは、ハイブリッドシステムを前面に押し出して展示していたし、フォルクスワーゲンもCO2排出量89g/km(プリウスは104g/km)というディーゼルハイブリッドのゴルフの試作車を展示していた。メルセデスはBlue Efficiencyという各モデルのトップ低燃費バージョンをプロモートしていたし、BMWはEfficiencyDynamicがそれで、すべての展示車のボディサイドに、燃料消費量(例:3シリーズのディーゼルで4.9L/kmなど)を大書して、経済性、環境性能をアピールしていた。これらプレミアムブランドは、大型で高性能エンジンを搭載しているからCO2のメーカー平均値はもちろん200g/km近くで良くないが、消費者の罪悪感を払拭し、環境への配慮を企業としてアピールせざるを得ないところに来ているようだ。 因みに、展示車のスペックシートには、赤から緑までのバーでCO2の排出量によって各車の環境性能を分類する表示が義務付けられていた。
会場の若者達を見ていると、彼らはそこまでCO2を気にしているとはどうしても思えず、EUの政治家や環境団体の動きが少し過剰すぎるのではという感じも持った。彼らは、常に何かアジェンダを必要としているし、ノーベル賞をIPCCとアル・ゴアに与えたのも、多分に政治的に利用しようという北欧環境先進国の意図が感じられる。 日本は、7月の洞爺湖サミットでポスト京都議定書のリーダーシップを取りたいといっているが、政府に切り札はなさそうで、EUに主導権を握られそうである。(ただ、京都議定書の枠組みは日本に不利との批判がずっとあるが、少なくとも97年から10年間、Kyoto Protocolの名を世界の人々の頭に刷り込んだ点は積極的に評価しないといけないだろう。)
というわけで、ジュネーブショー滞在は5時間余りで、フランクフルトにとんぼ返りして日本からの出張者グループに合流したのだが、話題のインドの会社TATAモータースが秋に本国で発売する30万円の国民車Nanoも見れたし、短時間ながらやはり一般日の会場の雰囲気を肌で感じ取れて、日本ではお眼にかかれないクルマやブランドを見れて参考になった。


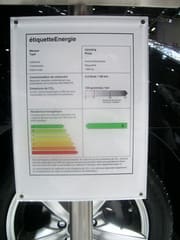

さて、ジュネーブショーの会場のメッセだが、空港に隣接して歩いていける。 9時半過ぎには会場に入ったが、この日は日曜とあって、午前中も早い時間からごった返してきて、洋の東西を問わず、若いカップル、ベビーカーを引く家族連れ、若い男の子の群れが通路に溢れ、フェラーリなどのスポーツカーのブースやイタルデザインなどのカロツェリアの前には人垣を作っている。 ジュネーブショーは、コーチビルダーやチューナーが、自動車メーカーに混じって主要なスペースを与えられているのに特長があるが、日本には失われつつあるスタイリッシュなクーペやスポーツカーに対する熱気が感じられるし、出展側もそれに応えて、高性能車を目玉に据えている。 ワールドプレミアは多くはないが、アルファ8Cスパイダーや、ブガッティヴェイロンのエルメス仕様、モーガン、大和の国のNissan GT-Rにも熱い視線が注がれていた。
もう一つ特徴的だったのは、CO2、環境への配慮を各メーカーがこぞって大々的にアピールしていることだ。 トヨタとレクサスは、ハイブリッドシステムを前面に押し出して展示していたし、フォルクスワーゲンもCO2排出量89g/km(プリウスは104g/km)というディーゼルハイブリッドのゴルフの試作車を展示していた。メルセデスはBlue Efficiencyという各モデルのトップ低燃費バージョンをプロモートしていたし、BMWはEfficiencyDynamicがそれで、すべての展示車のボディサイドに、燃料消費量(例:3シリーズのディーゼルで4.9L/kmなど)を大書して、経済性、環境性能をアピールしていた。これらプレミアムブランドは、大型で高性能エンジンを搭載しているからCO2のメーカー平均値はもちろん200g/km近くで良くないが、消費者の罪悪感を払拭し、環境への配慮を企業としてアピールせざるを得ないところに来ているようだ。 因みに、展示車のスペックシートには、赤から緑までのバーでCO2の排出量によって各車の環境性能を分類する表示が義務付けられていた。
会場の若者達を見ていると、彼らはそこまでCO2を気にしているとはどうしても思えず、EUの政治家や環境団体の動きが少し過剰すぎるのではという感じも持った。彼らは、常に何かアジェンダを必要としているし、ノーベル賞をIPCCとアル・ゴアに与えたのも、多分に政治的に利用しようという北欧環境先進国の意図が感じられる。 日本は、7月の洞爺湖サミットでポスト京都議定書のリーダーシップを取りたいといっているが、政府に切り札はなさそうで、EUに主導権を握られそうである。(ただ、京都議定書の枠組みは日本に不利との批判がずっとあるが、少なくとも97年から10年間、Kyoto Protocolの名を世界の人々の頭に刷り込んだ点は積極的に評価しないといけないだろう。)
というわけで、ジュネーブショー滞在は5時間余りで、フランクフルトにとんぼ返りして日本からの出張者グループに合流したのだが、話題のインドの会社TATAモータースが秋に本国で発売する30万円の国民車Nanoも見れたし、短時間ながらやはり一般日の会場の雰囲気を肌で感じ取れて、日本ではお眼にかかれないクルマやブランドを見れて参考になった。


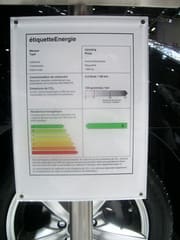






















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます