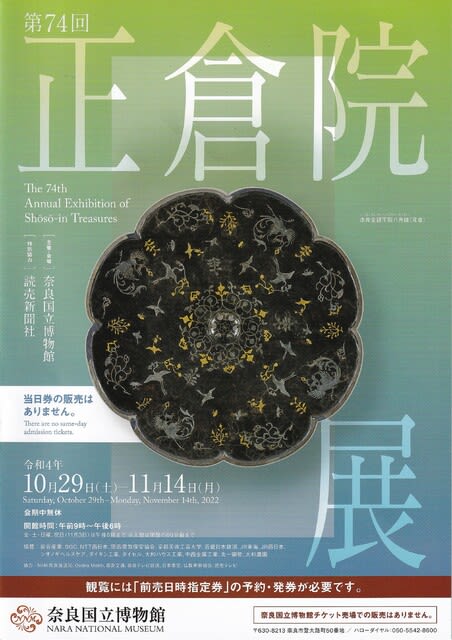《二十七、請以続類求賢》
「
問、自古以來、君者無不思求其賢、賢者罔不思效其用。然兩不相遇、其故何哉。今欲求之、其術安在。
臣聞、人君者無不思求其賢、人臣者無不思効其用。然而君求賢而不得、臣效用而無由者、豈不以貴賤相懸、朝野相隔、堂遠於千里、門深於九重。雖臣有慺慺之誠、何由上達、雖君有孜孜之念、無因下知。上下茫然、兩不相遇。如此、則豈唯賢者不用、矧又用者不賢。所以從古已來、亂多而理少者、職此之由也。
臣以為、求賢有術、辨賢有方。方術者、各審其族類、使之推薦而已。近取諸喩、其猶線與矢也。線因針而入、矢待弦而發。雖有線矢、苟無針弦、求自致焉、不可得也。夫必以族類者、盖賢愚有貫、善惡有倫、若以類求、必以類至。此亦由水流濕、火就燥、自然之理也。何則、夫以德義立身者、必交於德義、不交於險僻、以正直克己者、必朋於正直、不朋於頗邪、以貪冒為意者、必比於貪冒、不比於貞廉、以悖慢肆心者、必狎於悖慢、不狎於恭謹。何者、事相害而不相利、性相戾而不相從。此乃天地常倫、人物常理、必然之勢也。則賢與不肖、以此知之。伏惟、陛下欲求而致之也、則思因針待弦之勢、欲辨而別之也、則察流濕就燥之徒。得其勢、必彙征而自來、審其徒、必群分而自見。求人之術、辨人之方、於是乎在此矣。」
〇
問ふ、古より以來、君者は其の賢を求むるを思はざる無く、賢者は其の用を效(いた)すを思はざる罔(な)し。然れども兩つながら相遇はざるは、其の故何ぞや。今之を求めんと欲するに、其の術安(いず)くに在るや。
臣聞く、人君は其の賢を求むるを思はざる無く、人臣は其の用を效すを思はざる無しと。然れども君は賢を求めて得ず、臣は用を効すに由無きは、豈に貴賤相懸て、朝野相隔て、堂は千里より遠く、門は九重より深きを以てならずや。臣に慺慺(るる)の誠有りと雖も、何に由りて上達せん、君に孜孜(しし)の念有りと雖も、下知するに因無し。上下茫然とし、兩つながら相遇はず。此くの如ければ、則ち豈に唯に賢者の用ひられざるのみならん、矧んや又用者の賢ならざるをや。古より已來、亂多くして理少なき所以の者は、職ら此に之れ由るるなり。
臣以為へらく、賢を求むるに術有り、賢を辨ずるに方あり。方術とは、各々其の族類を審らかにし、之をして推薦せしむるのみ。近く諸を喩へに取れば、其れ猶ほ線(いと)と矢とのごとし。線は針に因りて入り、矢は弦(つる)を待ちて發す。線矢有りと雖も、苟くも針弦無くんば、自ら致すを求むるも、得べからざるなり。夫れ必ず族類を以てするは、盖し賢愚貫ぬる有り、善惡倫(ともがら)有り、若し類を以て求むれば、必ず類を以て至る。此れ亦た由ほ水の濕に流れ、火の燥に就くがごとく、自然の理なり。何となれば則ち、夫れ德義を以て身を立つる者は、必ず德義に交はり、險僻(けんぺき)に交はらず、正直を以て己に克つ者は、必ず正直を朋とし、頗邪(はじゃ)を朋とせず、貪冒(たんぼう)を以て意と爲す者は、必ず貪冒に比(なら)び、貞廉(ていれん)に比ばず、悖慢(ぼつまん)を以て心を肆(ほしいまま)にする者は、必ず悖慢に狎れ、恭謹に狎れず。何となれば、事相害して相利せず、性相戾(もと)りて相從はざればなり。此れ乃ち天地の常倫、人物の常理にして、必然の勢なり。則ち賢と不肖とは、此を以て之を知る。伏して惟ふに、陛下求めて之を致さんと欲すれば、則ち針に由り弦を待つの勢を思ひ、辨じて之を別たんと欲すれば、則ち濕に流れ燥に就くの徒を察せよ。其の勢を得れば、必ず彙征(ゐせい)して自ら來り、其の徒を審らかにすれば、必ず群分して自ら見れん。人を求むるの術、人を辨ずるの方、是に於てや此に在らん。
(白氏文集・巻四十六 策林二│岡村繁著:新釈漢文大系「白氏文集 八」, p159-163, 明治書院, 2006)
以上は、1月14日の漢文問題設問(太字部分)に採択された白氏文集の全文である。君が賢者を求め、賢者は君の御役に立たんと願うも、両者のマッチングは容易ではない。水が湿に流れ火が燥に広がる様に、賢者は賢者、善人は善人同志で親交を深め、一方愚者は愚者、悪人は悪人仲間でつるむのであり、類は類を呼ぶ、同じ羽の鳥は集まるのが自然の理である。そして糸は針穴に入り、矢は弦があってこそ己の力量を発揮できる。水や火の性の如く自然に道理を重んじ徳を積む方に寄る人間かを見極め、その良材が志を同じくする同類の新たな良材を推挙し導いてくる体制を整える事こそ、天下の逸材発掘の要であるとの結論である。
優れた人間の同類が呼び集まり、其処からそうでない人間は遠ざかる、いわば無限の自浄刷新作用を備えたダイナミックな組織集団の成立である。
-----名ならぬ人脈は体を表す。例えどのような立場や境遇であるとも、良質な縁を紡ぐには、まずは自分自身を律して高めておかねばならない。