日本では政治の話はしないように躾けられている?と思うことがありませんか。かく言う私も、勤めていた頃は、政治の話をする時には気を遣いました。しかし、よく考えてみるとこれはおかしなことですね。「戦争は政治の延長である」ということを聞いたことがありませんか。戦争を防ぐには政治に関心を持たなければ、政治の延長にある戦争にも反対できないではないでしょうか。
湧き上がる疑問を並べてみました。皆さんはもっとあるでしょうか。
①政治の話はしないと躾けられた?
これは江戸時代では、お上の批判は許さないとか、「見ざる聞かざる言わざる」と政治を行う権力者が支配階級としてあり続けるための教えでした。明治になっても、国民の権利の制限は当然とされ、男女差別や選挙権の制限がありました。それが残念ながら敗戦を経た現在も続いているということでしょう。
自らの力で民主主義を勝ち取った経験がない私たちが、どんなに良い憲法を持っていても無関心だったり、主権者意識がない限り、このような状態は続くのでしょう。いつでも政治の話や批判ができなければならないのに残念なことです。
②政治の話はなぜ制限されるの?
上記とも重複しますが、制限した方が都合のよい権力者がいるからでしょうね。民主主義では、本来大いに政治のことを話題にして政治のことを知らなければ権利の行使ができないはずです。日常の政治談議さえも、隣組や特高が見張り、国民が政府に疑いの目をもったりしないように放送や言論出版を制限していた時代はつい70年ほど前です。
今も、政府は特定秘密保護法とか、共謀罪などを設けて政府批判などを許さないようにしていますが、よほど国民が自覚しないと真の「民主主義」は実現しないのだと痛感します。
憲法ではそのことを見越しているのでしょうか、12条で「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と定めています。新聞を読んで、本を読んで学ばなければ、情報操作する強大な権力を持っている政府のやることを見抜くことは難しいですね。実際、麻生副総理も言っています。「新聞を読まない人は自民党を支持してくれる。」と。
③政治抜きには私たちの生活はない!?
憲法を守ろうというチラシなどを配っている人が嘆いていることは「戦争が始まって一番最初に被害に遭うはずの若者が受け取らない」とか「政治に関心がないので」などと言う人がいるということです。
教育の内容や受験制度、教育費、働く者の労働時間や権利、給料、医療費や保険、老後の問題などどれ一つとっても政治に無関係なものはないはずですね。もちろん、権利、平和の問題、裁判など、霞でも食べているのなら別ですが全てに関わっているはずです。だからこそ、権力を握っている人は、国民の自覚とやらがうっとうしいのでしょうね。
先進民主主義国では、学校で憲法や権利の大切さがたっぷり時間をとって教えられ、一人一人が政治に関心をもって参加していると言います。わが国では投票率が50%ほどであり、学校では「平和教育」なども教えるのに勇気がいるなどと言うことを聞きます。事実、教科書も国が検定して、国民の権利をしっかり教えようとする教科書は、義務を教えないのは偏っているとかということで修正させられたりします。また、現場の教師が教科書を選択する権利が著しく制限されています。これでは、権力には従順で、長いものには巻かれろとばかりに「政治の話はご法度」と自制してしまうのは当然かもしれません。うーん。
④政治家のレベルは国民のレベルとか?
政治の話をしないと誰が得かは明らかです。一国の政治家のレベルは、それにふさわしい国民のレベルであるというようなことも言われます。今、ウソを平気で言ってのがれている政治家などが大きな問題ですが、そのような政治家を選んでいるのが国民でもあるのですから辛いところです。
9月3日の朝日新聞の「声」の欄に、原爆の語り部が体験を話す時、主催者から「政治の話はしないで」と言われる投稿を紹介していました。今まで考えてきたように、「政治の結果の戦争」ですから、原爆の被害そのものは政治の話抜きには考えられないはずです。投稿者のように、「しっかり目を開けて政治を見ていかないと平和は築けない」のにです。大いに政治の話をしていきましょう。それが大人の責任かもしれません。
湧き上がる疑問を並べてみました。皆さんはもっとあるでしょうか。
①政治の話はしないと躾けられた?
これは江戸時代では、お上の批判は許さないとか、「見ざる聞かざる言わざる」と政治を行う権力者が支配階級としてあり続けるための教えでした。明治になっても、国民の権利の制限は当然とされ、男女差別や選挙権の制限がありました。それが残念ながら敗戦を経た現在も続いているということでしょう。
自らの力で民主主義を勝ち取った経験がない私たちが、どんなに良い憲法を持っていても無関心だったり、主権者意識がない限り、このような状態は続くのでしょう。いつでも政治の話や批判ができなければならないのに残念なことです。
②政治の話はなぜ制限されるの?
上記とも重複しますが、制限した方が都合のよい権力者がいるからでしょうね。民主主義では、本来大いに政治のことを話題にして政治のことを知らなければ権利の行使ができないはずです。日常の政治談議さえも、隣組や特高が見張り、国民が政府に疑いの目をもったりしないように放送や言論出版を制限していた時代はつい70年ほど前です。
今も、政府は特定秘密保護法とか、共謀罪などを設けて政府批判などを許さないようにしていますが、よほど国民が自覚しないと真の「民主主義」は実現しないのだと痛感します。
憲法ではそのことを見越しているのでしょうか、12条で「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と定めています。新聞を読んで、本を読んで学ばなければ、情報操作する強大な権力を持っている政府のやることを見抜くことは難しいですね。実際、麻生副総理も言っています。「新聞を読まない人は自民党を支持してくれる。」と。
③政治抜きには私たちの生活はない!?
憲法を守ろうというチラシなどを配っている人が嘆いていることは「戦争が始まって一番最初に被害に遭うはずの若者が受け取らない」とか「政治に関心がないので」などと言う人がいるということです。
教育の内容や受験制度、教育費、働く者の労働時間や権利、給料、医療費や保険、老後の問題などどれ一つとっても政治に無関係なものはないはずですね。もちろん、権利、平和の問題、裁判など、霞でも食べているのなら別ですが全てに関わっているはずです。だからこそ、権力を握っている人は、国民の自覚とやらがうっとうしいのでしょうね。
先進民主主義国では、学校で憲法や権利の大切さがたっぷり時間をとって教えられ、一人一人が政治に関心をもって参加していると言います。わが国では投票率が50%ほどであり、学校では「平和教育」なども教えるのに勇気がいるなどと言うことを聞きます。事実、教科書も国が検定して、国民の権利をしっかり教えようとする教科書は、義務を教えないのは偏っているとかということで修正させられたりします。また、現場の教師が教科書を選択する権利が著しく制限されています。これでは、権力には従順で、長いものには巻かれろとばかりに「政治の話はご法度」と自制してしまうのは当然かもしれません。うーん。
④政治家のレベルは国民のレベルとか?
政治の話をしないと誰が得かは明らかです。一国の政治家のレベルは、それにふさわしい国民のレベルであるというようなことも言われます。今、ウソを平気で言ってのがれている政治家などが大きな問題ですが、そのような政治家を選んでいるのが国民でもあるのですから辛いところです。
9月3日の朝日新聞の「声」の欄に、原爆の語り部が体験を話す時、主催者から「政治の話はしないで」と言われる投稿を紹介していました。今まで考えてきたように、「政治の結果の戦争」ですから、原爆の被害そのものは政治の話抜きには考えられないはずです。投稿者のように、「しっかり目を開けて政治を見ていかないと平和は築けない」のにです。大いに政治の話をしていきましょう。それが大人の責任かもしれません。










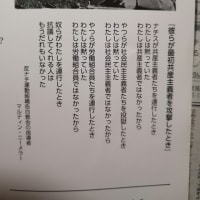










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます