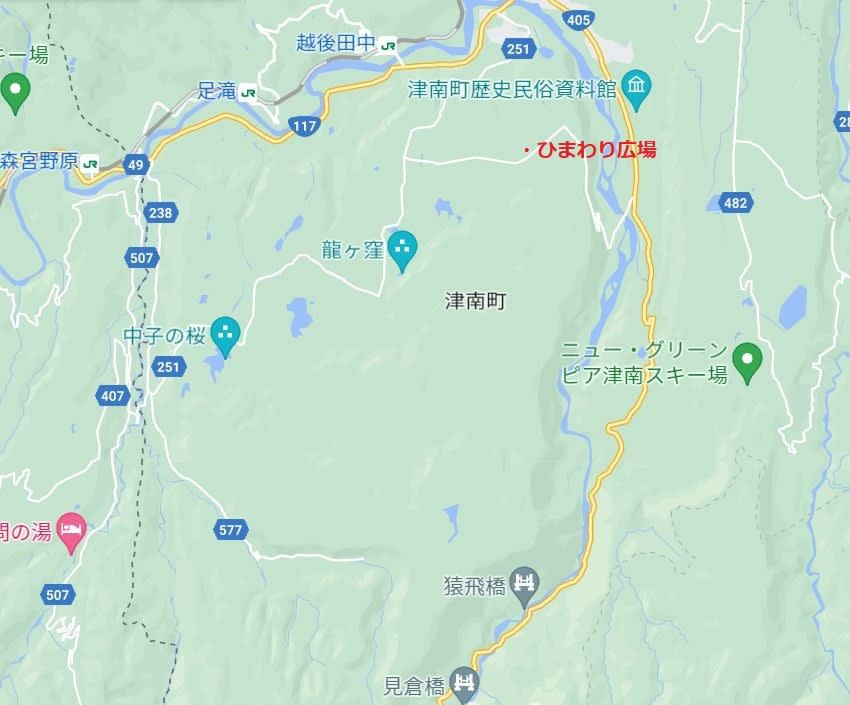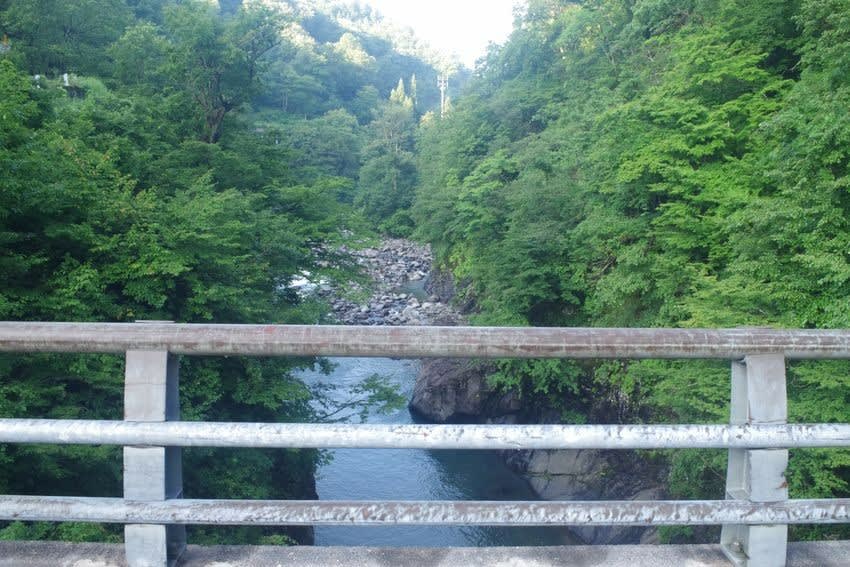昼頃から晴れる予報の下越。
のんびり午前中を過ごし、昼前に自宅を出て阿賀野市へ。
3~4時間で帰ってこられる下越の名所で、坂の上り下りが少ない場所(=高齢者でも行ける場所)は、だいたい行き尽くした感があり、さてどこ行こう?
国道49号で安田を通過する際に、いつも目にしてる「やすだ瓦ロード」の看板。
正直、安田は、阿賀町や福島県に行く際の通過点、であることが多いのだが、最近、雑誌などで安田瓦ロードを目にすることが増えた。行ってみよう。

国道49号からやすだ瓦ロードに入り、しばらく進むと「瓦テラス」

レストランとカフェ、お土産の売店など。

背面から見ると安田瓦がふんだんに使われている。


壁面に掲げられた瓦テラスの案内。
裏庭には、


うなぎのぼり神社

このウナギも、安田瓦の工房で作られた。右奥は菅名山塊
さて、ウナギ料理は魅惑的だが、「昼からがっつり食べるのは、ちょっと重い。カフェのラーメンならお腹に入るかな?」と言うので、やすだ瓦ラーメンに。

器も、瓦工房で作られたんだろうな。器の裏面に瓦と描かれていた。
あっさりした、美味しいスープ。全部飲み干したのは数十年ぶり?飲み干すと器の底にも瓦の文字があるかなと思い、塩分過多もたまになら大丈夫かと飲み干したが、無かった(;^_^A

さて、やすだ瓦ロードを探索



安田瓦協同組合の建物。

丸三安田瓦工業


煉瓦煙突


瓦庭園



さんかく広場


やきもの広場 高さ3m超?比較するものがなくて正確にはわからないが、でっかい焼物

多くの工房があるが、その中の一つ、村秀鬼瓦工房の庭先を見学









色んな工房の焼物が並ぶやすだ瓦ロード。一見の価値あり。
さて、瓦テラスに、旦飯野神社のポスターが張られていた。そんな神社があったなんて知らなかった。

まあ、訪れてみるか。県道55号を北上すると、
うわ!立派な神社。なんで今まで知らなかった?


駐車場は、すぐに停められない満車状態。赤い鳥居の奥は山門。
そこに施された彫刻


狛犬が焼物


その先は、

これはさすがに登れん、というので独りで。

旦飯野神社(あさいいのじんじゃ)のHPより。
創建の歴史とご利益
旦飯野神社の創建は、御宇元年(391年)8月15日に大山守皇子へ貢米を奉った際に「角鹿笥飯大神、飯津神を祭れば汝の里に百姓また種物が出来る」との御教によって、旦飯野神社と号し、奉祭したことによります。
長野麿(神官の大祖)なるものが、応神天皇(第15代天皇)の御弓、御衣、御石を祀ったとされる八幡宮であり、日常生活に根ざした諸願成就の神様です。
御祭神は誉田別命(応神天皇=八幡大神)です。御恵と威力の強い神様として祀られています。
丸石「御神霊石」について

社殿の裏にある直径1.5メートルほどの大きな「御神霊石」は神様が宿る石として、触れると神様の御力が授かるとされています。邪気を祓い、災難を消除し、様々なご利益があるといわれ、旦飯野神社の神様の御恵を感じることができます。
また、人の手を一切加えていない天然のままの丸い形状は、妊婦のおなかにも似ており、触れた後に「子を授かった」という声も多く聞かれます。
神様のおさがり
旦飯野神社では、おみくじや福飴、御朱印などを神様からの “ おさがり(めぐみ)” としてご参拝の皆様へ無料で頒布(お配り)しています。「無料」とは金銭を表すものでなく、おさがりを表しています。





























 すでに秋の気配が?
すでに秋の気配が?