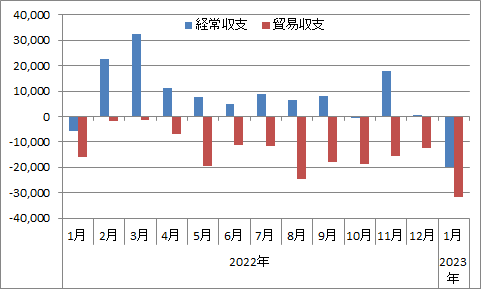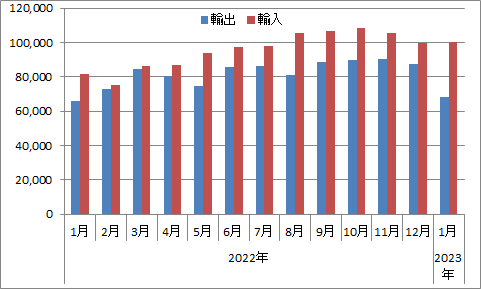岸田総理は訪米から帰ってすぐに、福島へ。お忙しい事は解りますが、国内の重要課題である景気の先行きに蔭りが出て来ている事にお気づきでしょうか。
政府と日銀の関係がどうなっているのか解りませんが、日銀も消費者物価の上昇には「注視」だけのようですし、政府は、4-6月の四半期GDP速報が年率6%の成長で気を良くしているのでしょうか。
確かに昨年は、コロナ終息の予測の中で、消費の活発化が見られましたが、今年に入っては物価上昇に食われて連続のマイナス化、家計は財布の紐を締め始めたようですが、物価の方は今後、公共料金(電気など)や10月予定の一斉値上げの予告など、生活必需品を中心に値上がりが続きそうです。
春闘賃上げがこれまでより多少高かったのも、最低賃金の4%上昇と物価上昇の深刻化で、霞んでしまったような感じです。
更に加えて円安が異常な進み方で、これが物価上昇圧力になる可能性が高く、日銀は円安を放置、輸出関連企業は為替差益で増益かも知れませんが、それがすぐ賃金に還元されるわけではありません。
円安の異常進行を一時的と見るか基調変化の部分もあると見るか、日銀は無言ですが、このままいけば、アベノミクスの初期、円安で景気回復と思われましたが、結局消費不振で「幻滅のアベノミクス」だったのと同じことになりそうです。
今回はそれに加えて物価も日本としては異常な上昇傾向で、家計はすでに、生活防衛に舵を切り始めているようですから、景気の腰折れは一層早い可能性も出て来ます。
日銀の物価は早晩沈静という予測は、そのままで良いのでしょうか。
円安の時はその分だけ日本の国際競争力が自動的に強くなるわけですから、その分賃金も引き上げないと消費需要不足から景気は良くならないのです。
それに加えて、輸出大企業の収益が、自動的に高まり、企業の財務体質は改善するのですがPBRが低くなって、海外投機資本から文句が出るのは昨年来経験済みの事です。
ついこの間やったのと同じ失敗を繰り返すのは、あまりにも情けないのですが、賃上げは来春闘が来ないと上がりませんし、物価上昇は続きそうな気配です。後は円安がどこまで続くかですが、これは日銀の金利政策(口先介入も含めた)次第でしょう。
日銀は、ここで金利を上げて円安を早期に解消するといった事には、それが景気の腰折れにつながると恐れるかもしれませんが、それは何処まで円高にするかというテクニークの問題でしょう。
若しかしたら、政府も日銀も、アメリカが何というか気にしなければならない立場なのでしょうか。日本は日本独自の都合で、金融政策を取っていいのではないでしょうか。
もともと今回の円安は、アメリカのインフレ抑制から発したもので、アメリカの勝手な都合で、他国に迷惑をかけているのです。
4-6月のGDP速報で見ましたように、日本経済は急速に元気をなくしています。岸田さんは、何かというと補助金を出しますと言って、支持率を継ぎ止めようとしているようですが、何故か基本的な考察がお留守のような気がして、心配です。
政府と日銀の関係がどうなっているのか解りませんが、日銀も消費者物価の上昇には「注視」だけのようですし、政府は、4-6月の四半期GDP速報が年率6%の成長で気を良くしているのでしょうか。
確かに昨年は、コロナ終息の予測の中で、消費の活発化が見られましたが、今年に入っては物価上昇に食われて連続のマイナス化、家計は財布の紐を締め始めたようですが、物価の方は今後、公共料金(電気など)や10月予定の一斉値上げの予告など、生活必需品を中心に値上がりが続きそうです。
春闘賃上げがこれまでより多少高かったのも、最低賃金の4%上昇と物価上昇の深刻化で、霞んでしまったような感じです。
更に加えて円安が異常な進み方で、これが物価上昇圧力になる可能性が高く、日銀は円安を放置、輸出関連企業は為替差益で増益かも知れませんが、それがすぐ賃金に還元されるわけではありません。
円安の異常進行を一時的と見るか基調変化の部分もあると見るか、日銀は無言ですが、このままいけば、アベノミクスの初期、円安で景気回復と思われましたが、結局消費不振で「幻滅のアベノミクス」だったのと同じことになりそうです。
今回はそれに加えて物価も日本としては異常な上昇傾向で、家計はすでに、生活防衛に舵を切り始めているようですから、景気の腰折れは一層早い可能性も出て来ます。
日銀の物価は早晩沈静という予測は、そのままで良いのでしょうか。
円安の時はその分だけ日本の国際競争力が自動的に強くなるわけですから、その分賃金も引き上げないと消費需要不足から景気は良くならないのです。
それに加えて、輸出大企業の収益が、自動的に高まり、企業の財務体質は改善するのですがPBRが低くなって、海外投機資本から文句が出るのは昨年来経験済みの事です。
ついこの間やったのと同じ失敗を繰り返すのは、あまりにも情けないのですが、賃上げは来春闘が来ないと上がりませんし、物価上昇は続きそうな気配です。後は円安がどこまで続くかですが、これは日銀の金利政策(口先介入も含めた)次第でしょう。
日銀は、ここで金利を上げて円安を早期に解消するといった事には、それが景気の腰折れにつながると恐れるかもしれませんが、それは何処まで円高にするかというテクニークの問題でしょう。
若しかしたら、政府も日銀も、アメリカが何というか気にしなければならない立場なのでしょうか。日本は日本独自の都合で、金融政策を取っていいのではないでしょうか。
もともと今回の円安は、アメリカのインフレ抑制から発したもので、アメリカの勝手な都合で、他国に迷惑をかけているのです。
4-6月のGDP速報で見ましたように、日本経済は急速に元気をなくしています。岸田さんは、何かというと補助金を出しますと言って、支持率を継ぎ止めようとしているようですが、何故か基本的な考察がお留守のような気がして、心配です。