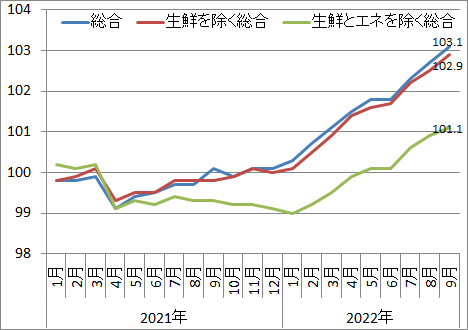日本人の平均寿命が世界トップクラスの長さになり、年金問題は国民にとっても政府にとっても深刻になっています。
これは、素直に、客観的に見れば、日本人の順調な平均寿命の延び、健康寿命に延びに対して、社会制度的な制度設計が追い付いていない事によるという事でしょう。
子どもが大きくなっているのに、これまでと同じ服を少し手直しして着せ、「うまく合わない」といっているようなものだと言えるでしょう。
過去の経緯から見れば、戦後、高校・大学への進学率の向上によって出生から就職までの期間が長くなり、子育ての費用が増えましたが、これは主として親の負担で、奨学金制度などで対応して来ています。法律や制度は余り関わりがありませんでした。
そして、今の問題は、引退の時期をどこにするかという事で、定年や年金制度と言った法律や制度が、日本人の寿命の延びによって合わなくなっているという問題です。
昔のように、定年はそれぞれの会社で決め、老後は退職金で、という事ですべて企業レベルで決まっていれば(今でも定年制のない会社は結構ありますが)、その辺りは民間の柔軟性で対応したでしょう。
しかし、政府がいろいろと世話を焼くようになり、定年制も法律が出来たり、公的年金制度も充実して、国民もそれに頼るようになり、次第に近代国家になってきたのです。
それによって国民生活は安定したというのが現実ですが、他方で問題も生まれました。
子供が大きくなったら年々衣服を大きくするような柔軟な対応、つまり日本人の寿命の伸びにおうじて柔軟に法律や制度を見直すことは極めれ困難な問題なのです。
という事ですから、問題解決の鍵は、当然解っていて、就職から引退までの期間を長くすることで、自分の蓄積も増やし、年金で対応する期間が一定以上伸びないようにしなければならないのですが、これが大変なことなのです。
結局のところ、定年制、公的年金設計という法律制度を、今日これからの日本人の寿命の伸びに合わせなければ問題は解決しないというのがこのブログの基本的な考え方です。
多分、誰もがそう考えているからこそ、政府も定年を延長したり、年金支給開始年齢を遅くしたりしてきていますが、前回指摘しましたように,55歳定年の定着期から2040年までに日本人の平均寿命は20年ほども伸びる(厚労省推計)のです。
あ、それならば、もう現状のつぎはぎはやめて、現状は勿論、これからの日本人の寿命の伸び(伸び率は大分低くなっていますから)も勘案、全く新しいサイズの服に着替えるのが良いという事ではないでしょうか。
それが出来て、はじめて国民の将来不安、老後不安が解消され、国民生活が安定し、日本社会全体が安心して将来に向かって頑張れるという、国民にとって基本的な必要条件整備が出来るという事でしょう。
ところで、このブログが主張するのは、定年年齢や年金支給開始年齢を何歳にすればいいとかいった具体的な数字の問題ではありません。
大事なことは、だれが中心になって、この問題に取り組めばいいかという事、もう一つは、それが適切に決まれば、日本経済社会は改めて大きな発展のポテンシャルを持つことが出来るのではないかという可能性を生む雇用労働市場についての指摘です。
次回はそれらの点について日本経済の明るい展望とともに見ていきたいと思います。
これは、素直に、客観的に見れば、日本人の順調な平均寿命の延び、健康寿命に延びに対して、社会制度的な制度設計が追い付いていない事によるという事でしょう。
子どもが大きくなっているのに、これまでと同じ服を少し手直しして着せ、「うまく合わない」といっているようなものだと言えるでしょう。
過去の経緯から見れば、戦後、高校・大学への進学率の向上によって出生から就職までの期間が長くなり、子育ての費用が増えましたが、これは主として親の負担で、奨学金制度などで対応して来ています。法律や制度は余り関わりがありませんでした。
そして、今の問題は、引退の時期をどこにするかという事で、定年や年金制度と言った法律や制度が、日本人の寿命の延びによって合わなくなっているという問題です。
昔のように、定年はそれぞれの会社で決め、老後は退職金で、という事ですべて企業レベルで決まっていれば(今でも定年制のない会社は結構ありますが)、その辺りは民間の柔軟性で対応したでしょう。
しかし、政府がいろいろと世話を焼くようになり、定年制も法律が出来たり、公的年金制度も充実して、国民もそれに頼るようになり、次第に近代国家になってきたのです。
それによって国民生活は安定したというのが現実ですが、他方で問題も生まれました。
子供が大きくなったら年々衣服を大きくするような柔軟な対応、つまり日本人の寿命の伸びにおうじて柔軟に法律や制度を見直すことは極めれ困難な問題なのです。
という事ですから、問題解決の鍵は、当然解っていて、就職から引退までの期間を長くすることで、自分の蓄積も増やし、年金で対応する期間が一定以上伸びないようにしなければならないのですが、これが大変なことなのです。
結局のところ、定年制、公的年金設計という法律制度を、今日これからの日本人の寿命の伸びに合わせなければ問題は解決しないというのがこのブログの基本的な考え方です。
多分、誰もがそう考えているからこそ、政府も定年を延長したり、年金支給開始年齢を遅くしたりしてきていますが、前回指摘しましたように,55歳定年の定着期から2040年までに日本人の平均寿命は20年ほども伸びる(厚労省推計)のです。
あ、それならば、もう現状のつぎはぎはやめて、現状は勿論、これからの日本人の寿命の伸び(伸び率は大分低くなっていますから)も勘案、全く新しいサイズの服に着替えるのが良いという事ではないでしょうか。
それが出来て、はじめて国民の将来不安、老後不安が解消され、国民生活が安定し、日本社会全体が安心して将来に向かって頑張れるという、国民にとって基本的な必要条件整備が出来るという事でしょう。
ところで、このブログが主張するのは、定年年齢や年金支給開始年齢を何歳にすればいいとかいった具体的な数字の問題ではありません。
大事なことは、だれが中心になって、この問題に取り組めばいいかという事、もう一つは、それが適切に決まれば、日本経済社会は改めて大きな発展のポテンシャルを持つことが出来るのではないかという可能性を生む雇用労働市場についての指摘です。
次回はそれらの点について日本経済の明るい展望とともに見ていきたいと思います。