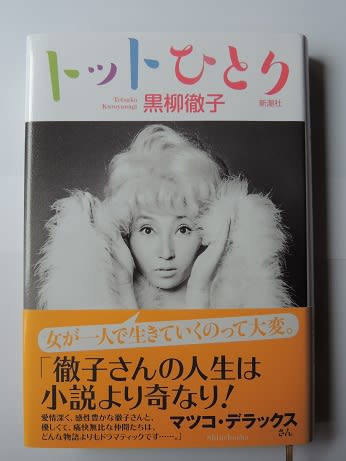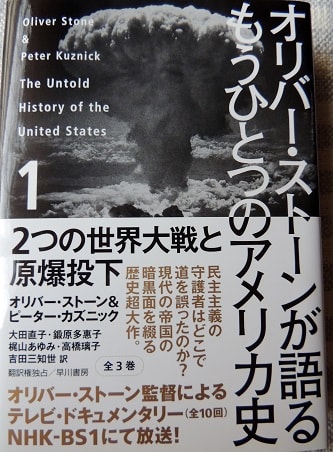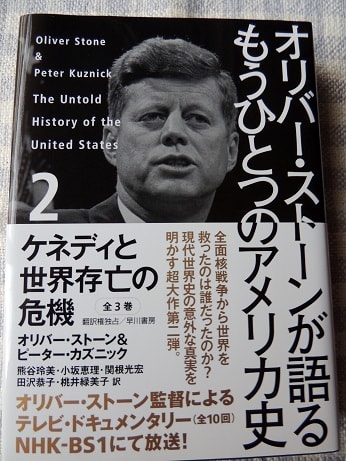国際政治学者の中西輝政(なかにし・てるまさ)氏が『迫りくる日中冷戦の時代 』(PHP新書)が、
過日発刊されて、副題は『日本は大義の旗を掲げよ』と題して、
《 日本は中国にいかに対峙してきたか?
今後どのように付き合うべきか?
歴史的考察を踏まえた国際政治学者からの提言。 》
と概要テーマが掲げられている。
そして出版社からの解説文とはて、
《 いま、アジアを舞台に新たな冷戦が始まろうとしている。
冷戦の次の主役は中国だ。
アメリカが世界唯一の超大国だった時代は終わりを告げたのである。
急速な経済成長を遂げ、アジア太平洋への露骨な膨張政策をとる中国をいかに封じ込めるか?
2012年7月に露首相が国後島へ再上陸し、八月に韓国大統領が竹島に不法上陸、同月香港の活動家は尖閣諸島に強行上陸した――
これら一連の出来事の背後にある大きな構図に目を向けよ。
アメリカはすでに新国防戦略で対中封じ込め政策へと軸足を移している。
日本が対中戦略でもつ最も有効な武器は何か?
「人権・民主化」という大義の旗を明確に掲げることである。
日米同盟の再活性化に全力で取り組む以外に、もはや日本の選択肢はないだろう。
大中華圏なるものは、たとえ二十二世紀になっても現出しないのだ――。 》
私は政治・経済も専門知識もなく素人の疎(うと)い身ながら、昨今の日中の国難に憂い、
読売新聞を読んだり、NHKのテレビのニュースを視聴したりしてきた・・。
そして拙(つたな)い私さえ、困惑を重ねてきた。
私はやむなく二年前の2010年9月25日に、このサイト上で、
【 やがて中国はアジアの宗主国と君臨し、日本は属国となり・・。】
と題して投稿して、ささやかな日中の難題に投稿してきたので、
今回、あえて再掲載する。
【・・
私は東京郊外の調布市に住む年金生活6年生の65歳の身であるが、
日本の文化を限りなく愛し、読書をしたり、散策をしたりし、季節のうつろいに心を寄せたりしている。
そして、ときには家内との共通趣味の国内旅行をし、
その地の風土、お住まいの人たちと談笑を重ねたり、美景な情景を享受している。
こうした私でも、日本の政治の混迷、経済の低迷、社会の劣化などを憂い、
無力ながらNHKのニュースを視聴したり、新聞、雑誌を読んだりしている。
このように拙(つたな)い身であるが、過ぎし一昨年の2008年の夏、
中国の首都で、『北京五輪』が開催された時、開会式の実況中継をNHKで視聴し、
心の片隅で戦慄を感じたりした・・。
祭典の初めに紙、墨字による文字と絵、印刷、航海などの絵巻物のような美麗なシーンを観て、
かって中国の明の時代に思いを馳せたのである・・。
この当時の明王朝は、ヨーロッパの主要国より、あらゆる面に遥かに凌駕していた。
紙はもとより、印刷に寄る大量の書物があり、数多くの図書館が存在していた。
そして明王朝の最盛期には、軍事力を背景とした経済力で、
周辺各国の異民族の宗教、文化、習慣を束ね、圧倒的な海軍によりアフリカの沖まで航路し、制覇した。
その結果、海上貿易で巨額な収益をもたらし、繁栄をした。
この頃は、世界の主要国の中で、圧倒的な軍事・外交・経済の超大国として、
明王朝は存在していたのである。
やがて清の時代になと、イギリスからアヘン戦争を仕掛けられ、
その後は世界の列国から侵略などによる剥奪され、
中国の長い歴史上からしても屈辱の長い期間となった。
今日の中国は、外交・軍事・経済の背景とした政治が行われ、
超大国への道を国家の理念とし、確実に躍進させ、
今回のスポーツの祭典のひとつ『五輪』としても、大国の威信をかけて、実現させた。
そして世界各国の首脳陣を招き、
鳥の巣と称される9万人が収容される国家体育場で、
国家主席が高らかに開催宣言を発せられると、会場に居る中国の民衆の熱気はもとより、
13億人の民の熱気を私は感じられながら、戦慄を感じたりした。
果たして、五輪後はどのように中国は躍進しながら変貌するのかしら、
そして東アジアの宗主国となるか、やがて中国はアジアの宗主国と君臨となるのか。
或いは異民族問題が多発したり、沿岸都市部と内陸農村部での格差問題などで、共産独裁国は崩壊するか。
このような思いで、政治はもとより軍事、外交などに疎(うと)い身ながら、
ときおり注視したりしてきた。
先ほど、総合ビジネス情報誌として名高いビジネス情報サイトの【ダイヤモンド・オンライン】を見ていたら、
『シリコンバレーで考える 安藤茂彌』の連載記事で、
『第36回 海底に国旗を立てて領有権を主張する中国に日本はこんなに無防備でいいのか』
と題された記事を何気なしに読んだのがあるが、私なりに多々教示された。
無断であるが転載させて頂く。
《・・
【シリコンバレーで考える】 安藤茂彌 [トランス・パシフィック・ベンチャーズ社CEO、鹿児島大学客員教授
『第36回 海底に国旗を立てて領有権を主張する中国に日本はこんなに無防備でいいのか』2010年9月22日
最近中国は、近隣諸国と領有権紛争が起きている東シナ海において、
乗員3人を乗せた深海潜水調査艇を海底まで沈め、中国の国旗を海底に植え込んだ。
日本の「しんかい」にそっくりな深海潜水艇である。
中国のテレビ局はその様子を撮影したビデオを国家的快挙として大々的に報道した。
ニューヨーク・タイムズが中国日報の報道をスクープし、
同紙の一面に掲載してアメリカでも話題になった。
この事件は多くのアメリカ国民に2007年にロシアが取った行動を想起させた。
ロシアは北極点の海底にロシア国旗を立てて領有権を主張したのである。
だが日本のメディアは、尖閣諸島で同じことが起きる可能性が強いにもかかわらず、
中国のこの事件を一切報道しなかった。
中国はなぜこんなことをするのか。
海底に眠る豊富な地下資源を支配下に置くためである。
一例をあげよう。
電気自動車の電池材料として注目されている希少金属リチウムは、中国国内に豊富に埋蔵されている。
従来はその多くを他国に輸出していたが、
戦略物資と分かるや否や他国への輸出を制限し始めた。
最近日本政府が中国政府に輸出制限の解除を交渉したが、全く応じる様子はなかった。
今回の行動はその「海底版」である。
海底に眠る希少金属をできるだけ多く支配下に置くことで、
地下資源を独占し、輸出制限を通じて他国の生産能力を奪い、自国経済を更に拡大することを目論んでいる。
アメリカ政府はこうした中国の戦略を既に察知し、
希少金属に頼らない代替材料の開発を促す政策を採っている。
今回の国旗植え込み事件は、
現在領有権で争いになっているベトナム沖の海底であると推測される。
中国はベトナム沖の西沙諸島を自国の領土であると主張し、
領海を侵犯したとしてベトナム漁船を数多く拿捕している。
中国はベトナムと個別の交渉に応じることはあっても、
多国間の交渉には応じられないとしている。
ベトナムは個別の交渉であれば、
中国の軍事力と威嚇でねじ伏せられることを恐れているのである。
中国の暴挙に堪りかねたベトナムは、米国とASEAN諸国を抱き込み、
ASEAN会議の議題にして集団で中国に立ち向かう外交を展開している。
中国の領土主張の被害国は、ベトナムに止まらない。
シンガポール、マレーシア、インドネシアとの間でも同様な紛争を起こしているからだ。
去る7月に米国のクリントン国務長官はアセアン会議で
「ASEAN諸国のこの海域での航行の自由を守ることが重要だ」
と発言し、中国代表との間で厳しい論戦を展開した。
ASEAN諸国が狙うのは、米国と連携した「中国包囲網」作りである。
中国の挑発行為は、日本に対しても行われている。
今年4月には中国海軍の艦艇10隻が沖縄本島と宮古島の間の公海を南下し、
中国のヘリが監視中の自衛隊の護衛艦に、異常接近する事態が発生している。
今月に入ってからも尖閣諸島で、海上保安庁の巡視船と中国の漁船が衝突する事件が起きている。
すでに新聞等で報道されている通り、中国は猛烈なスピードで軍事力を増強している。
軍事予算は過去20年間に18倍に膨れ上がり、今では米国に次ぐ第2位の軍事大国になっている。
2009年での軍事予算は米国の6610億ドルに対して、中国は1000億ドルとまだまだ開きがある。
だが、米国が近年軍事予算を削減しているに対し、中国は毎年予算を大幅に増やしており、
その差は縮まりつつある。
因みに、日本は510億ドルで第6位である。
日本と在日米軍の軍事力は、中国、北朝鮮、極東ロシアの兵力と比較すると明らかに見劣りする。
日米の戦力を合わせても桁が一桁少ない。
中国のこうした軍備増強は、1982年に策定された「海軍海洋計画」と呼ばれる国家計画に基づいている。
それによると、2000-2010年に沖縄、台湾、フィリピンを結ぶ「第1列島線」内の制海権を確保し、
2010-2020年には「小笠原諸島、グアム、インドネシアを結ぶ「第2列島線」内の制海権を確保して航空母艦の建造を行う。
そして2020-2040年には
「米海軍による太平洋、インド洋の支配を阻止する」最終ゴールを達成する計画となっている。
中国は今年中に原子力航空母艦の建設にも着手することを明らかにしたが、
これも「海軍海洋計画」に沿って実施されるものである。
数年後にこれが完成すれば極東の米軍兵力にかなり接近した兵力になると考えられる。
日本近海に中国の航空母艦が出没するのも時間の問題になっている。
戦力の比較は、単なる装備の数値比較では計れない状況が起きている。
サイバー戦力が重要になっている。
これは地球を旋回する人工衛星によって、敵の動きを把握しコントロールする能力を指す。
カーナビや携帯に位置情報を送るGPS(全地球測位システム)衛星もそのひとつで、
衛星の大半は米国が押さえている。
米国がその気になれば意図的にGPSを遮断することができるのである。
現在、中国上空を通過するGPS衛星の95%は米国が所有している。
中国は2020年までに世界のGPS衛星の1/3以上を中国版にして、
中国上空から米国の衛星を追い出す計画である。
こうすれば自国の通信網を守れる、米国に覗かれないで自由に軍事行動を取れる。
もうひとつのサイバー戦力は、ウイルスによる敵のコンピュータ網への攻撃である。
米国の軍事機密情報を盗み出すために、
国防総省のコンピュータシステムにサイバー攻撃が仕掛けられたというニュースはよく聞く。
米国内ではこうした攻撃を組織的に行っているのは、中国であると見ている。
では米国は、中国の軍事力増強をどう見ているのだろうか。
米国国防総省は8月16日に「中国の軍事力に関する年次報告書」を発表した。
中国軍が「国産空母の建設に着手し、南シナ海などで広範囲に行動を拡大しているうえに、
外交上の利益を得るために、軍事力を活用する度合いが増えつつある」と指摘している。
米国の軍関係者は、中国は口先では
「古い兵器の改良である」「中国は覇権主義をめざさない」と言っているが、
実際の行動を見るとまったく違う、と指摘する。
その上、軍事交流も拒否している。
中国国防省は今年1月の米国の台湾への武器売却の決定に反発して、
米軍との交流停止を発表した。
その後ゲーツ国防長官が訪中を申し込んだが断られた。
中国側と軍事面での意思疎通は途絶えたままである。
では米国は、日本をどう見ているのだろうか。
こういう微妙な時期に日本政府の行動は不可解であると見ている。
鳩山首相はアジア共同体構想なるものを持ち出して米国から離れようとした。
これがアメリカ政府の不信をかき立てた。
米国大統領は、鳩山首相を相手にしなかったし、面談も拒否し続けた。
鳩山政権から菅政権に変わった。
鳩山氏より数段マシであるし、小沢氏より良い選択であると認識しているようだ。
小沢氏のように対等な日米関係を表立って口にしないし、国連主義も主張しない。
だが、菅氏の国防戦略の具体的なものは何も聞こえてこない。
まずは普天間問題をどう解決するのか見てから菅首相の評価を決めたいというのが本音ではないだろうか。
米国側は日米防衛協議の場で、
日本側にRole and Mission(役割と使命)を求めてくるようになったという。
これは「自国の領土を自分で守る覚悟を示せ」と日本側に求めていることだという。
米国にしてみれば、中国の脅威が高まる中で、
前首相は現状認識を誤り、あらぬ方角に走り出すし、普天間の移設問題もいまだに解決できていない。
米国政府にしてみれば今こそ日米同盟を強化して、
共同して中国の脅威に立ち向かうべきと考えているのに、
日本政府の方向性の定まらない動きに苛立ちを感じている。
一方で、米国内ではG2(Great2)という考え方が台頭しつつある。
Great2とは超大国である米国と中国の二カ国を指す。
日本を同盟国と当てにしていては極東戦略が何も進展しないので、
重要事項は日本には関係なくGreat2で決めればよい、とする考え方である。
この考え方は日本をバイパスするジャパン・パッシングである。
中国の脅威は軍事面、領土面のみならず資金面でも感じられるようになっている。
バングラデシュ、スリランカ、パキスタン、ミャンマーといった国々に対して、
中国は港湾建設、道路建設、通信網建設といったインフラ・プロジェクトに多額の海外援助を行っている。
もちろん、そうしたプロジェクトでは中国の業者が特注して工事を請け負うことになるが。
こうした海外援助も見方を変えれば、軍事的な意図を含んでいる。
こうした地域に張り巡らせた港湾や道路や通信網を中国側が制御すれば、中国軍の軍事行動がとり易くなる。
またその国と経済摩擦や利害衝突が起きた場合には、中国が軍事力を背景に交渉を有利に進められる。
いままで中国のこうした投資を歓迎してきた諸国も、最近では警戒心を強めるようになってきた。
日本では、中国の資金面での脅威はどこにあるのだろうか。
最近の顕著な動きは、中国が膨大な対米黒字から得たドル資金を米国国債の購入ではなく、
日本国債を買うようになったのである。
確かに米国財務省の資料を見ると、中国はこの半年間に米国国債の保有高を1割ほど減らしている。
日本国債の93%は日本の金融機関が保有しているが、
残る7%の中で中国政府が最大の債権者になった模様である。
日本政府は中国政府の購入を歓迎しているようであるが、国債管理はより難しくなったと見るべきだろう。
中国がもし日本国債を大量に売却すれば、
金利は高騰し、日本の財政収支は一気に悪化する。
中国側がこの手段を意図的に使うと大きな攪乱要因になる。
中国政府の動かせるドル資金の規模が極めて大きいだけに、
為替市場への影響も無視できない。
最近の80円台なかばへの円高は、中国による国債の大量購入がひとつの原因と考えられる。
このことは何を意味するのか。
中国政府は日本国債の大量購入により円高を作り出し、
日本の輸出にブレーキをかけることができるようになったということである。
中国は今後、軍事面、領土面、資金面で、
日本を含むアジア諸国に更に強い影響力を及ぼすであろう。
中国が日本にとって最大の貿易国であるにもかかわらず、軍事面、領土面での中国は違う顔を覗かせる。
アメリカにとっても今や最大の貿易相手国は中国である。
だが、アメリカ政府は、中国に対して経済面の親密さと、軍事面の脅威とを峻別して考えている。
日本ではこの峻別ができていない。
中国を情緒的に捉えている。
今回の民主党の代表選挙でも、国防が全く論点にならなかったのは、
こうしたところに原因があるのではないだろうか。
日本国民が、国防の観点から大きな決断をしなければならない時は、刻々と近づいてきている。
米国と同盟強化を図るのか?
それとも、曖昧なままズルズルと中国の強硬な外交圧力に屈していくのか?
日本人はこの数10年、明確な国家戦略を持ったことがない。
だが、もしこの決断ができなければ、
日本は「自国を取り囲む現状の認識が甘い上に、自国の運命を自分で決められない国民である」
というレッテルを諸外国から貼られても仕方がない。
それでも本当に良いのだろうか。
・・》
注)記事の原文にあえて改行を多くした。
私は今年の5月の時、読売新聞に【意見広告】として、
市民意見広告運動事務局という団体が広告を出され、
《 基地はいらない
核の傘もいらない
人間らしく生きたい・・》
日本国憲法の第9条、第25条も掲載されており、
私は読みながら、どうしてこうした平和ボケの多い人たちがいるのかしら、と苦笑したのである。
私は若き日には映画・文学青年の真似事をした後、あるレコード会社に35年ばかり勤めて定年退職となり、
こよなく文化を愛するひとりであるので、政治・外交・軍事・経済などは恥ずかしながら疎(うと)い身である。
しかし、国際主要国はもとより怜悧な国益に基づいて、
外交、軍事、経済力などを背景とした政治が行われている現状ぐらいは少し判っているつもりである。
かの世界第二次大戦の敗戦後、何とか日本が戦争に巻き込まれなかったのは、
『第9条』とは関係がなく、長らくアメリカとソ連との巨大国に寄る冷戦であり、
互いの核の強化で均衡のような形で続き、お互いに恐怖を抱き、牽制しあったからである。
そして日本はアメリカの軍事力に守られ、隣国の大国である中国、ソ連に脅かさせられることもなく、
幸運にも経済だけに専念できて、経済大国となってきたのが怜悧な実情と思ったりしている。
ここ10年、中国の大躍進を私なりに思考すると、かって中国の明の時代に思いを馳せたりする・・。
1400年代の明の永楽帝の時代に於いては、盛んに勢力を広げ、
隣国の元朝の余党を遠征により制圧したり、満洲では女真族を服属させ、
南方ではベトナムを陳朝の内乱に乗じて征服した。
そして海外の東南アジア、インド洋にまで威信を広げるべく鄭和に率いられた大艦隊を派遣し、
一部はメッカ、アフリカ東海岸まで達する大遠征の結果、多数の国々に明との朝貢関係を結ばせた。
この頃の明王朝は、ヨーロッパの諸国より遥かに凌駕し、
世界の諸国の中で、圧倒的な軍事・外交・経済の超大国として、
そして陸路はもとより、海上貿易で巨額な収益をもたらしていたのである。
やがて清の時代になると、イギリスからアヘン戦争を仕掛けられ、
その後は世界の列国から侵略などによる剥奪され、中国の長い歴史上からしても屈辱の長い期間となった。
今日の中国は、軍事・経済の超大国への道を国家の理念と思われ、
日本が幼児のように指をくわえていれば、太平洋さえもアメリカと分け合いながら躍進すると思われる。
私は平和は何よりも大切と思っているが、
この前提としては自国を守れる防衛能力が必要なのである。
単なる念仏のように『戦争は嫌いだ・・平和こそが・・』と唱えても、過去の歴史が証明するように、
隣国から侵されれば、お終いとなる。
そして、憲法など戦勝国に簡単に変えられる。
このように私は軍事力は必要悪と思い、『平和を維持するために、防衛能力が・・』と、
確固たる自国を守れる軍事力が必要と確信している。
この上、何よりも軍事力も険悪し、平和こそがと唱える人たちは、隣国の大国を限りなく喜ばせ、
中国を宗主国としてあがめ、属国人として生き延びるのかしら、と妄想をする。
或いは江戸時代のように一部だけ海外と交易し、あとは国内だけで清き貧しく共に生活を送るのかしら、
と思ったりしてしまうのである。
現世の国際の主要国はもとより怜悧な国益に基づき、
他国と競合したり、やむえず協調する時代であり、
アメリカの少年・少女たちにも判ることなのに、日本の一部に平和ボケの人がいるのに唖然としている。
このように私は日頃思ってきたので、
今回の安藤茂彌氏の寄稿文の『シリコンバレーで考える』の連載記事で、
『第36回 海底に国旗を立てて領有権を主張する中国に日本はこんなに無防備でいいのか』
精読したのである。
私はこのままの日本の政治の混迷を続けれならば、
中国はしたたかな国家戦略に基づいて、数年のうちに沖縄、台湾、フィリピンを結ぶ「第1列島線」内の制海権を確保し、
アメリカが少しでも弱体化すれば、あと10年ぐらいで、
「小笠原諸島、グアム、インドネシアを結ぶ「第2列島線」内の制海権を確保し、
太平洋をアメリカと分かち合い、
中国は東アジアの宗主国と君臨し、日本は属国のように低下する。
この後、中国は更に躍進し、アジアの宗主国と君臨し、もとより日本は属国なる、
と妄想を重ねたりしている。
・・】
このような思いを無力の拙(つたな)い私は、国民のひとりとして二年前の頃から思案したりしてきた・・。
《つづく》
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪
 にほんブログ村
にほんブログ村
 散文 ブログランキングへ
散文 ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村