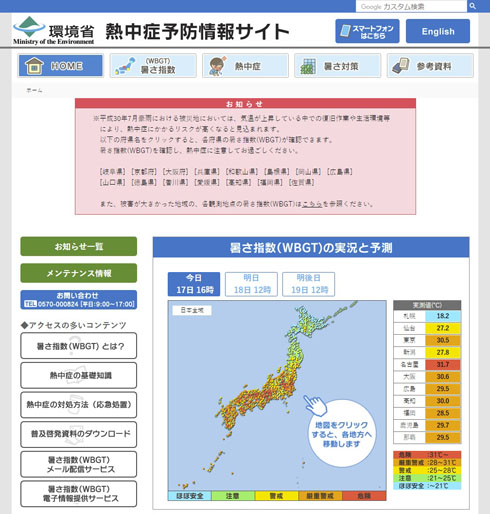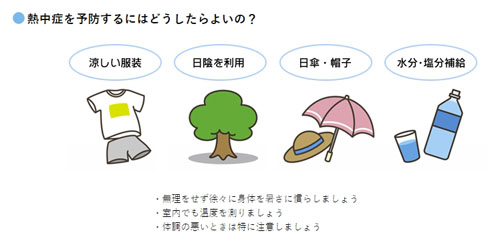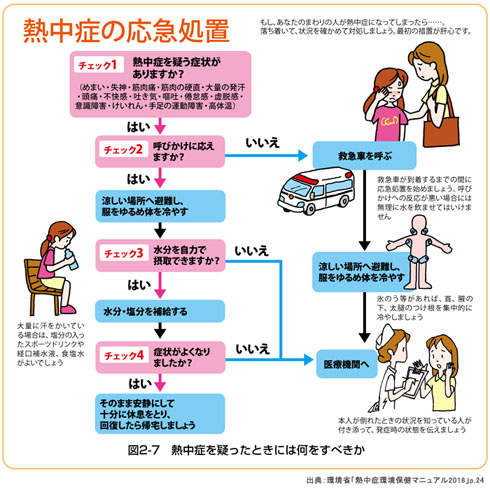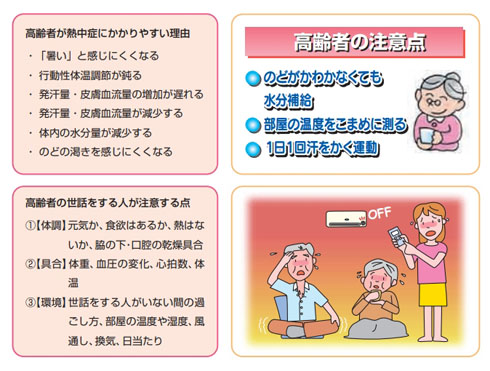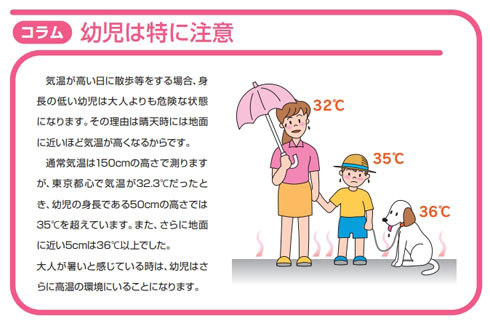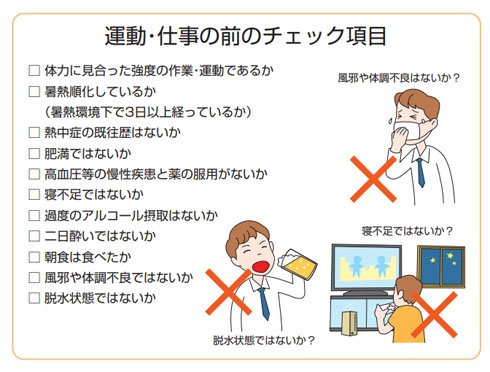先程、ときおり愛読している文藝春秋の公式サイトのひとつ【文春オンライン】を見ている中で、
『 急増する最新の墓「ビル型納骨堂」を選んではいけない 』
と見出しを見てしまった。
私は都心の郊外の調布市に住む年金生活をしている73歳の身であるが、
最寄駅のひとつには寺院が多い街並みとなり、この中のひとつの寺院に於いて、
ここ10年、都心に見られる「ビル型納骨堂」と同じような形態ができて、驚いたのは3年前であった。
私は最新の形態のお墓「ビル型納骨堂」は無知であったので、どのようなことですか、
と思いながら記事を精読してしまった。
この記事は、『老いる東京、甦る地方』(PHPビジネス新書)などで
私が愛読している牧野知弘(まきの・ともひろ)さんの寄稿文であり、
【文春オンライン】に7月31日に配信され、無断であるが記事の大半を転載させて頂く。

《・・(略)人間誰しもが亡くなれば入居するのが墓である。
亡くなった方を想うお盆の季節、今回は墓の問題を考えてみたい。
日本の人口は、2015年の国勢調査で初めて減少に向かっていることが発表された。
人口が減少する理由は、生まれる赤ちゃんの数より亡くなる人の数が多い、
つまり「人口の自然減」の状態に日本があることを示している。
2017年の出生数は94万1000人だったのに対して、死亡者数は134万4000人。
なんと日本は人口の自然増減においては、年間で40万人もの純減を記録している。
実際の日本の総人口は、22万人ほどの減少と発表されているが、
この差は在留外国人の数が急激に伸びているからである。
今や日本の人口減を、一生懸命外国人在留者の伸びという「社会増」で、
補っているというのが現代日本の姿なのである。

☆今後10年で約1000万人が死んでゆく
さて日本は高齢社会に突入したといわれているが、
この影響は今後死亡者数の激増という形で、社会に様々な問題を投げかけてくる。
1966年(昭和41年)日本の死亡者数は、67万人と戦後最低を記録している。
当時の日本は、戦後生まれの男女が世の中を闊歩する若々しい社会だったのだ。
それがこの50年間で、死亡者数は倍増したことになる。
医療施設が整い、高齢者施設が数多く建設され、長寿社会が実現したとはいえ人間、いつかは死ぬ。
そしてこれからの日本は「死ぬ」可能性の高い人が、激増する状況にあるのだ。
厚生労働省の予測によれば、2040年には死亡者数は166万人と
今よりさらに24%も増加するとしている。
それもそのはずである。
2015年9月総務省の発表によれば、現在国内では80歳以上の人口が1002万人。
対前年比で38万人の増加となり、初めて1000万人の大台を超えたという。
さらに90歳以上の人口は206万人、100歳以上の人口でも6万7000人となっている
(2017年総務省、厚労省発表)。
どんなに長寿社会になるからといっても、この数値だけから判断して、
今後10年くらいの間で、1000万人近くの人が亡くなっていくことは、誰が見ても明らかだからだ。

☆墓地を作る場所がない!
いっぽう現在、日本の人口の約3分の1が、
東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県で構成される首都圏に集中している。
つまり、今後は首都圏での死亡者数が、激増することが容易に予測できる。
ところが、首都圏で墓地として提供できる土地は、少ないのが実態だ。
墓を持つ側のニーズにも、変化が表れている。
墓地といえば、これまでは地方の実家の近くにある、
あるいは郊外の山などを造成して開発した霊園に多く存在したが、
こうした施設に対する不満も多い。
年に数回の墓参りに行くにも、遠くて交通利便性に欠ける、墓参り時の天候に影響を受ける、
墓の清掃や雑草取りなど手間暇がかかる、土地使用料や墓石代などの費用が高いなど
といった理由が挙げられている。
何事にも合理的に考える世代が台頭していく中で、既存の施設に対する不満が高まっているのである。

☆「手軽」、「ハイテク」、「安上がり」の罠
このような状況を反映して、現在人気なのがビル型納骨堂(以下、墓ビル)である。
墓地の形態をとらずに、建物の中に収容する納骨堂は、何も今に始まったものではないが、
最近増加しているのが、ビルを建てて、あるいは既存のオフィスビルやマンションを改装して
建物全体をお墓の収容場所にしようというものだ。
墓もマンションのように、みんなで「一緒に住む」という時代になったのだ。
墓ビルでは、ハイテク化も進んでいる。
以前は建物内に棚を設えて、骨壺などを並べるだけの簡素なものだったのが、
機械化され、参拝者は決められたブースに来て、ICカードで登録番号を読み取ってもらい、
該当するお札などの一式が、目の前に出現するのを待つ。
まるで銀行の貸金庫室に行って、自分の金庫を取り出すときのような感覚だ。
線香などもあらかじめ備わっているので、手ぶらで参っても大丈夫。
何事も手軽に済ますことも、人気の秘訣になっている。
費用も墓地であると区画にもよるが、
墓石などを含めるとなんやかんやで200万円から300万円程度はかかってしまうが、
自動式納骨堂であれば100万円程度。
永代使用権や永代供養料なども含まれているものが多いので、安上がりである。
また近年は少子化が進み、「おひとりさま」需要も増える中、
墓守をする後継者がいない人にとっても、負担が少ないといえそうだ。
さて一見すると、良いことづくしの墓ビルであるが、実は多くの問題を抱えている。
墓地は土地の中に収容されるスタイルであることから、
土地が永遠に存続する限りにおいては、墓としても永久に存続していくことが前提となる。
ところが建物内に収まっている墓ビルは、当たり前のことだが、
建物は「永久不滅」でないということを考えなくてはならない。

墓ビルは、建物内を自動化して収容力を高めている。
中には1棟で1万基もの収容力を持つビルまであるという。
1基100万円だとして1万基で100億円にもなるのだから、おいしいビジネスともいえる。
だがこれらも「満杯」になったあとは、ひたすら「管理」していくことが必要になる。
一般的には管理費などを徴求する形をとっているが、さて管理費はいつまで取ることができるのだろうか。
最初に永代供養としてまとまった費用を徴求できたとしても、墓守は永遠である。

☆大規模修繕できるのか
建物は「有限」であることから、当然のことだが大規模修繕も必要になる。
50年、60年先には、「建替え」も必要となるかもしれない。
そのときこうした費用は、どこから出ていくのだろうか。
墓ビルに対しては、宗教法人施設の敷地内限定とする、
あるいは宗教法人が一定以上関与する法人の所有に限定するなど、規制を施す自治体もあるが、
どのようにして建物を維持管理していくのか、まだ不透明な部分も多いのが実態だ。
建造費や管理費に莫大な資金がかかるため、
約5000基を管理する自動搬送式納骨堂を建造した寺が、破産(福井県永宮寺)したり、
寺院ではなく運営会社が、脱税で逮捕される(大阪府「梅旧院光明殿」)といった事件も起こっている。
維持費用が途絶え、誰も管理せず、放置されるような墓ビルが
将来都内のあちこちに出現したらどうなるのだろうか。
墓ビルが「スラム化」して、お化け屋敷になるなどという笑えない話にもなりかねない。
墓ビルそのものが、都市における大量の「墓碑」そのものになっていくのだ。
永遠に存続することができない器に、
「永久に存在するはずの」お墓を管理していくことの矛盾に、まだ多くの墓ビルが気付いていない。・・》
注)記事の原文、あえて改行を多くした。

私は1944年(昭和19年)の秋に農家の三男坊として生を受け、
分家のような形で、実家の近くに住んでいる。
しかしながら実家のお墓の近くに墓地を買い求めるに、
たまたま私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、一代限りとなる。
いつの日にか、私たち夫婦が亡くなった後、長兄の子供である甥っ子ふたりに何かと面倒をかける、
と思いながら、長らく躊躇(ためら)ってきた・・。
やがて私たち夫婦は、死者は土に還ることがふさわしい、とお墓は樹木葬と決め、
いずれも永代使用権、永代供養料、永代管理料などを一括納入すれば、
片割れの残された方が、体力の衰えた身であっても、お墓参りが出来る、と思ったりしている。
そして二年前にある里山にある樹木葬ができる一角を買い求めて、
私か家内が亡くなった後は、100年ばかり指定された地に眠り、この後は合同で管理される、
こうした希望で私たち夫婦は、ある寺院と確約している。

そして葬儀に関しては、私は家内には、俺が死んだ時は家族葬で、
和花と音楽に包まれて、出来うる限り質素にして貰いたい、とここ15年ぐらい言ったりしている。
私は父親、祖父、次兄、母親、そして親戚の叔父、叔母、或いは知人などの数多くの葬儀に参列してきた。
こうした中で、自宅で通夜、告別式、或いは寺院の斎場で通夜、告別式が執り行われ、
多くの会葬者を観たりしてきた・・。
私はサラリーマンを定年退職し、早や13年半が過ぎた年金生活の身であり、
官公庁、民間会社で栄達された人とは、遥かに遠い平凡な人生を歩んできたりした。
こうしたことで、遠い親戚、知人、友人も高齢者の方が多く、わざわざ通夜、葬儀に参列して頂くより、
これまでの私の人生の歩みで、欠かすことのできない血は水よりも濃いと称せられる親族で、
ささやかに葬儀をしてもらいたい、と願っている。
そして私の生家(実家)は曹洞宗なので、やはり生家(実家)の墓地のある寺院の方に読経して頂くが、
通夜、告別式の5分ぐらいの簡略なお経でよい、と思ったりしていたが、
これらを省略しても差し支えないと思ったりする時もある。
こうした私の思いは、葬儀、墓地にも寺院には、わずかに影響すると思われるが、
ここ10数年、従来の形態の寺院が衰退していく事情を真摯に学んだが、
私の諸事情もあり、勘弁して欲しい、というのが本音となっている。

今回の記事で、「ビル型納骨堂」について、初めて私は真摯に学んだりした。
確かに「ビル型納骨堂」の墓、余りにも利便性もあるが、寄稿文を綴られた牧野知弘さんのご指摘通り、
《・・維持費用が途絶え、誰も管理せず、放置されるような墓ビルが
将来都内のあちこちに出現したらどうなるのだろうか・・》こうしたことにも動顛したりした。
やはり亡くなわれた御方は、生きている御方の慰めであったとしても、
従来の墓石のあるお墓が望ましいと私は思ったりしている。
そして私たちのような一代限りで、死後に関係者に迷惑を配慮し、
私たち夫婦は、やむなく樹木葬をし、死者は土に還る・・と思い深めたりしている。