原因と自己チェックリスト【医師解説】 』
と題された見出しを見たりした。
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、たった2人だけ家庭であり、
そして私より5歳若い家内と共に、古ぼけた戸建てに住み、ささやかに過ごしている。
私は亡き母の遺伝を素直に受け継いだ為か、男の癖におしゃべりが好きで、
何かと家内と談笑したりしている。
そして私は、食べながら家内に話したりしていると、一か月に一度ぐらい、
食物が食道へ入るべきものが気管に入ってしまうらしく、
一分ぐらい、むせたり咳き込んだりすることがある。
こうした時、家内は
『高齢者になると誤嚥(ごえん)になる人が多いから、気を付けてねぇ・・』
と私は言われたりしている。
私は5年前の頃までは、こうした体験がなく、
やはり高齢者になると食べ物がのみ込む力の嚥下(えんげ)の力が衰えたのかしら、
と戸惑いながら不安を秘めたりしている。
と私に微苦笑しながら言ったりしてきた。

少しばかり体験をしてきたので、やはり注意1秒で食べる時、お茶を飲む時は、
ゆっくりと頂くことが肝要だなぁ・・と思い深めてきた・・。
一歩間違えると死のリスクがあると学んだりしてきたが、
今回、《・・「声が出にくい」・・「むせやすい」 ”のど老化”のサイン・・》、
具体的にどのようなことなの・・と私は学ぼうと精読してしまった。
この記事の原文は『女性セブン』の2021年7月22日に掲載された記事であり、
関連の【 介護ポストセブン 】に7月27日に配信され、
無断であるが記事を転載させて頂く。

外出や会食の自粛が引き続き求められる中、
「声が出にくい」、「むせやすくなった」などと訴える人が増えている。
これは、会話する機会が減り、声を出さなくなったことによる
“のど老化”が進んでいるサインかもしれない。
☆声が出づらくなった人が増えている3つの原因
「運動不足による体の不調とともに、のどの運動不足も進んでいる」
と言うのは、音楽・音声ジャーナリストで「声・脳・教育研究所」代表理事の山﨑広子さん。
「20~70代まで、幅広い年齢のかたから、
『最近、声が出づらくなった』という話をよく聞きます。
その主な原因として考えられることは、3つあります」(山﨑さん・以下同)
【原因1】
会話をすることが減ったため、のどや声帯を使うことも減り、のどが運動不足に陥っていることだ。
「手足などの筋肉を使わないと弱っていくように、
のどの筋肉も使わなければ衰えていくので、動かして鍛えることが必要です」
【原因2】
マスクをしている影響で、呼吸が浅くなっていること。
「呼吸は、声のエネルギー源。
しっかりと呼吸をして、新鮮な酸素を肺に取り入れなければ、
吐く息が弱くなり、力強い声を出すことができません」
【原因3】
マスクをすることで、口の動きが封じられてしまい、
口を大きく開けずに、“もごもご”としゃべっていること。
「声を出すときは、口からのど、声帯にかけて、たくさんの筋肉が連動しています。
意識して声を出すように心がければ、のどの運動不足の解消につながり、
ある程度は元に戻ると考えられます」

☆日常生活での「のど老化」のチェックリスト
□最近、会話が減った
□食事中にむせることが増えた
□声が弱く、かすれたりしゃがれたりする
□のどに違和感がある
□せき払いをよくする
□たばこを吸う
□毎日、たくさん飲酒する
□脂っこいものが好き
□野菜をあまり食べない
□血圧が高い
□いびきや睡眠時無呼吸の症状がある
□胸やけがする(胃酸の逆流)
<判定>
1つでも当てはまる人は、のど老化のリスクがある。
数が多いほど老化は進行している。
上から5項目は、のどの筋力低下リスク、
その下の7項目は、のどを老けさせる生活習慣と症状を示している。

☆食事中の「むせる」は、のど老化の始まり
声の違和感に加え、「むせる」、「せき込む」などの回数が増えてきたら、
「のみ込む力(嚥下(えんげ)力)が衰えている可能性がある」と言うのは、
呼吸器内科の専門医で、「池袋大谷クリニック」院長の大谷義夫さん。
「食事中に、食べ物や飲み物が気管に入って、むせたりせき込んだりすることが、
40代頃から少しずつ増えていきます。
これは、のどの老化の始まりで、誤嚥しやすくなってきたサインです」(大谷さん・以下同)
食べ物や唾液、逆流した胃液などが、口からのどと食道を通って胃に送られるはずが、
誤って気管や肺に入ってしまうことを誤嚥という。
このとき、細菌が含まれていると肺で炎症を引き起こし、誤嚥性肺炎になってしまうのだ。

☆のどの衰えから誤嚥性肺炎にも…
厚生労働省が発表した「2020年人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、
昨年の誤嚥性肺炎による死者数は4万2746人で、3年連続で増加している。
それ以外の肺炎による死亡者は7万8445人で、
両方を合わせると12万1191人となり、死因別死者数の第4位に位置する。

「肺炎を予防するには、肺炎球菌ワクチンを接種することと、
歯磨きやうがいなどの口腔ケアをして、
口の中を清潔に保つことが有効というエビデンスもあります。
これに加え、のどが衰え始める40代から、
のみ込む力やせき反射(※)が衰えないように、口腔内のストレッチなどに取り組み、
誤嚥性肺炎のリスクを下げるように心がければ、健康寿命を延ばすことにつながると思います」
(※)せき反射とは、異物がのどの奥まで侵入すると
気道の表面にあるセンサーが察知し、脳に伝え、のどに吐き出すよう指示を出し、せきを起こさせること。

☆教えてくれた人
山﨑広子さん/音楽・音声ジャーナリスト
「声・脳・教育研究所」代表理事。
著書に『声のサイエンス あの人の声は、なぜ心を揺さぶるのか』(NHK出版新書)などがある。
大谷義夫さん/池袋大谷クリニック院長。
呼吸器内科のスペシャリスト。
著書に『肺炎を正しく恐れる』(日経プレミアシリーズ)などがある。
取材・文/山下和恵・・ 》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

改めて多々教示されたりした。
そして自己チェックリスト、こっそりと私は受診したりした。
□食事中にむせることが増えた
一か月に一度ぐらい、食物が食道へ入るべきものが気管に入ってしまうらしく、
一分ぐらい、むせたり咳き込んだりすることがある。
□血圧が高い
平均男性より少し高い。
この2つが該当して、やはり76歳の齢は隠せないよなぁ・・と微苦笑したりしている。





































 </picture>
</picture>



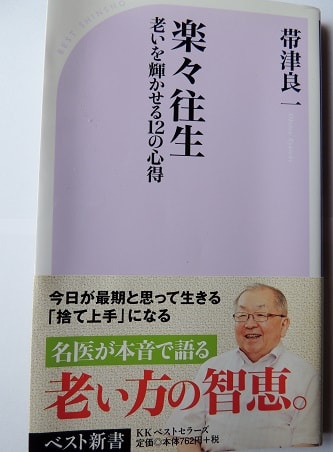













 </picture>
</picture> </picture>
</picture>






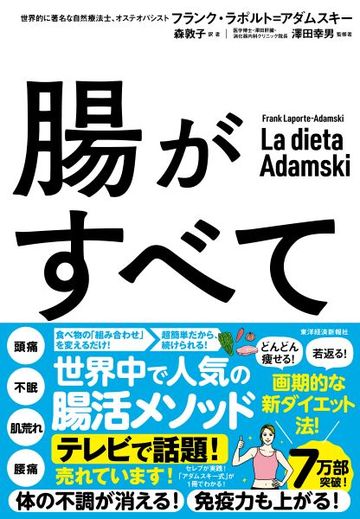




































この記事は、読売新聞の主幹ネットの【読売新聞オンライン】が7月28日に配信された記事であり、
私は読売新聞を購読して51年目で、よしみに甘えて転座て頂く。
《・・新型コロナウイルスの新規感染者が27日、
過去最多の2848人に達した東京都では、若い世代の感染拡大が鮮明になっている。
最近1週間の感染者に占める30歳代以下の割合は約7割。
感染者増加の要因とみられる人出も多くを若い世代が占めており、
都は危機感を募らせる。