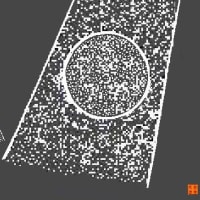炭川は、いよいよ今年もその季節か…と思っていた。手間はかかるが、植木消毒の頃合いとなったのだ。だが、昨年の冬の蓑虫(みのむし)取りも気が進まなかった炭川である。当然、植木の消毒も気が乗らなかった。というのも、ある意味で虫の生活妨害なのだ。
植木側の民事告訴により裁判で争われるようになったこの問題は、被告、原告双方の当事者を一堂に会し、華々しい論戦を展開していた。炭川は裁判長席に裁判長として座り、被告、原告双方の言い分を冷(さ)めた目耳で見聞きしていた。
「裁判長! 我々にとっては死活問題なのであります。他人の生活を脅(おびや)かす権利は誰にもない! そもそも、害虫などと呼ばれること自体、我々としては心外なのであります! 終わります」
虫の代表が、かくかくしかじか…と、さも我々が正しいのだと言わんばかりの声高(こわだか)で論じ、席に腰を下ろした。
「原告!」
「散々、我々の茎や葉を食い散らかして、なにを言わっしゃる! 害虫以外のなにものでもないではありませんか!!」
「裁判長! ただ今の発言は、我々を冒涜(ぼうとく)しております。名誉棄損(めいよきそん)のなにものでもない! 取り消しを求めます!」
「静粛(せいしゅく)に願います!」
炭川は左右の裁判官と小声で相談した。
「原告側は感情的にならないように…」
「失礼しました。害虫、益虫の判断は人間が生活上、判断するものですから、棚上げいたします。しかし、我々が被害を被(こうむ)っておるのは、厳然(げんぜん)とした事実なのであります」
裁判は被告、原告側の交互の口頭弁論により進行していった。そのとき、炭川はクラクラッとし、意識が遠退(とおの)いた。そして、いつの間にか、法廷の場面が変わっていた。
「そうだ! 人間が一番、悪いんだ! 人間には生れた仔馬は可愛いとか言って、その馬肉を食うことを何とも思わない野蛮さがある!」
原告席の虫の代表が叫び、裁判長席の炭川を見た。
「それは言える! 森林を伐採(ばっさい)してゴミ捨て場にし、それをなんとも思わん!」
被告席の植木側の代表も叫んで、枝を揺らした。
「人間に判決を下す資格はないっ!」
「そうだそうだ!!」 「今すぐ、裁判長席を下りろっ!!」
「静粛に!! 静粛に!!」
炭川は立ち上がり叫んでいた。だが、騒然とした法廷内は、いっこう収まる気配がなかった。駄目だっ…と炭川が思いながら腰を下ろそうとしたとき、裁判長席の椅子は消えていた。炭川は奈落の底へ落ちるような気分で意識がふたたび遠退いた。
気づくと、炭川は野原の真ん中で眠っていた。額(ひたい)の先に虻(あぶ)が止まっていた。
『フフッ!』
炭川は笑い声を感じた。虻は炭川を刺しもせず、どこかへ飛んでいった。人間は思いあがっている…と、炭川は思った。
THE END












![連載小説 幽霊パッション 第三章 (第百五[最終]回)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/19/cf/a4d652a78f65b5a64a7098195c68c8c7.jpg)