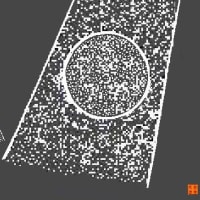高速道の車は渋滞していた。大阪出身の鴻川(ごうのかわ)は諦(あきら)めたようにハンドルを放し、座椅子に身体を預けた。
「しょうもな…」
鴻川は、ぽつりとそう呟(つぶや)いた。前も車、後ろを見ても車・・鴻川の計算では、こんなはずではなかった。今頃は露天風呂に浸(つ)かり、沈みゆく夕陽を眺(なが)めながら、湯舟に浮かせた盆の上の熱燗(あつかん)をグビッ! と一杯、やってるところだったのである。それが、味も素(そ)っ気(け)もない車列を見る破目に陥(おちい)っていた。これなら、もうひとつ考えていた前日の夜、出るべきだった…と、鴻川は思った。が、時すでに遅し・・である。車を放(ほう)って外へ脱出しないかぎり、動きようがなかった。点(つ)けたカーラジオの交通情報が、この周辺は30km渋滞だと言っている。
「しょうもな…」
鴻川は、ふたたびそう呟いた。言いながら、鴻川がふと、前方を見たとき、突然、前の車列が消えていた。ば、馬鹿な! と、鴻川は目を擦(こす)った。だが確かに、前に続いていた車列は消え去り、前方の道に障害物は何もなかった。驚いた鴻川は戸惑(とまど)いながら後ろを振り返った。すると、後続車の車列も一台残らず消えているではないか。鴻川は有り得ない現実に手指で反対の手を抓(つね)った。感覚があり、痛かった。とすれば、これは現実なんだ…と、少し鴻川は怖(こわ)くなってきた。そうはいっても、日は傾き、日没が近づいていた。鴻川は、なるとままよ! と思い切り、アクセルを吹かすと車を発進させた。渋滞なら当然、前に車があるのだから、追突して偉(えら)いことになる。だが、車はスムーズに走行を開始して加速していった。半時間ばかりで高速を下(お)り、あとは夕陽を見ながら下の道を走った。そして、なんとか予約した一流旅館へと無事着いた。日はとっぷりと暮れていたが、それでも露天風呂に浸かりながら波の音で一杯は飲めた。計画通りではなかったが、まあいいさ…と、鴻川は思った。車中泊では目も開いてられない話だからである。出された美味い料理をホロ酔い気分で賞味し、満腹になった鴻川は、いつしか目を閉じ、ウトウトしかけた。しばらく、いい気分でいると、突然、鋭いクラクションの音がし、鴻川は驚いて目を見開いた。渋滞の車列が進み始めていた。鴻川の前の車はすでに10mばかり前方を走っていた。クラクションの音は鴻川のすぐ後ろの車だった。慌てた鴻川は、エンジンを急いで始動すると車を発進させた。外はすでに薄暗かった。前照灯をあと点けし、しばらく走ったとき、ようやく鴻川は冷静さを取り戻していた。
「しょうもな…」
鴻川は三度(みたび)、そう呟いた。俺は夢を見ていたんだ…と、鴻川は思った。だがどういう訳か、鴻川の心には旅を終えたような満足感があった。鴻川の車の後部座席に、ないはずの旅館のタオルが一枚、置かれていた。
THE END












![連載小説 幽霊パッション 第三章 (第百五[最終]回)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/19/cf/a4d652a78f65b5a64a7098195c68c8c7.jpg)