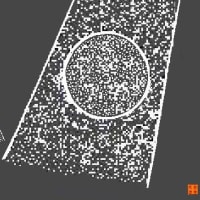猛暑が去り、少し秋めいた休日の朝、三崎は庭で空を見上げていた。空は曇(どん)よりと灰色の雲に覆(おお)われ、ポツリポツリと雨粒が落ち始めていた。慌(あわ)てて家の軒(のき)へと小走りに退避した。そういや、子供の頃、二百十日の前後には雨ん魔という妖怪が天から降りてきて屋根を小突(こづ)くという話を聞かされたことがあった。今から思えば埒(らち)もない作り話に思えたが、三崎はふとその話を思い出し、馬鹿馬鹿しいながらも確かめようと、空を見上げていたのだ。今はちょうど二百十日の頃で、時期的にも話と一致していた。
雨は本格的に降り出したが、これといってなんの変化も空にはなかった。どうせ、雨ん魔が屋根を小突くというのは雹(ひょう)かなにかが降る気侯のことだろう…と三崎には思えた。そのときだった。空から雨ん魔が雲に乗って下りてきた。顔はちょうど俵屋宗達が描いた風神雷神図の二神を合わせたような姿で、いかにも妖怪らしく見えた。三崎は目を擦(こす)った。雨ん魔は片手に笊(ザル)のようなものを持って三崎の庭の屋根 辺(あた)りの高さまで降りながら漂(ただよ)った。そして、片方の手で笊の中に入った氷の粒(つぶ)を辺り構わず投げ飛ばし始めた。まるで花咲じいさんだな…と三崎には気楽に思えた。というのも、どうせ夢を見てるんだろう…という潜在意識があったからだ。ところが、雨ん魔が投げ始めたその氷粒の一つが三崎の脳天にコツン! と当たった。三崎は、その場で気を失った。三崎はハンモックのネットに気づかず転んだだけだった。気を失う訳がないのに失ったのだ。
気づくとベッドに寝かされていた。妻の美登里が三崎の様子を窺(うかが)っている。
「お医者さまが今、帰られたわ。別にどこも悪くないって…」
「ああ、そうか…」
「怪(おか)しいって、不思議そうな顔されてたわ。変な人ね…。ふつう、あんなところで転んで、気は失わないわよっ!」
美登里が訝(いぶか)げに三崎を見た。三崎には美登里の言葉が雨ん魔の投げた氷粒より痛かった。
完
最新の画像[もっと見る]












![連載小説 幽霊パッション 第三章 (第百五[最終]回)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/19/cf/a4d652a78f65b5a64a7098195c68c8c7.jpg)