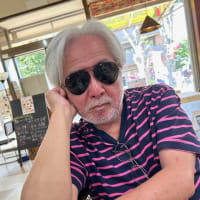【連載エッセー】岩崎邦子の「日々悠々」(69)
あちこちの生垣には冬の花の山茶花が咲き誇り、傍らには水仙の花が冷たい風で揺れている。が、日差しはどうだろう。「もう冬は去ってゆく」と思わせてくれる。梅はふっくらとした蕾を見せており、庭先に植えられているパンジーなどの花も元気を増す一方だ。春の訪れを感じるのは、なぜか嬉しいものである。
そんな折、蕗の薹(フキノトウ)をいただいた。まさしく春が来ているのだ。子供の頃には祖母が蕗味噌を作っていたが、なぜこんな苦いものをと敬遠していた。最近では、マーケットで蕗の薹を見つけると、無性に懐かしさが湧いてくる。この頂いたもので蕗味噌を少し作ったが、他の食べ方はどうだろうか。
ネットを見れば、あれこれとあるものだと感心する。さっと茹で、胡麻油で痛めて軽く塩をし、最後にゴマを振るとあったのを採用してみた。ゴマの代わりに、エゴマの買い置きを使ってみたが、ほろ苦さもちょうど良く、美味しく食することが出来た。
次いで、芹を頂いた。鍋料理に入れるような栽培のものではなく、田のあぜ道に生えているものだ。これまた懐かしい春の野菜である。茹でてお浸しにして、かつお節をかけるのが定番だが、芹ご飯を勧められた。初めての試みである。さっと茹でて2センチくらいに切り、これもゴマ油で痛めて塩を振っておく。ご飯が炊けたら、先の芹と、炒りゴマを混ぜ込む。香り、味、彩り。「春が来たぁ~」であった。
パークゴルフに出かけた日のことだ。一緒の組で回ったTさんに、
「蕗の薹をもらってね」
と、話しかけた。すると、即答が返って来た。
「あ、てんぷらにすると美味しいよね」
前のグループのプレーを待つ間、彼女は春を感じる野草の料理法をいくつか教えてくれた。菜の花を店で見つけたので辛し和えをしたとか、ウドの酢味噌和えが好きだとか、タラの芽のてんぷらは最高だとか……。
彼女の話はさらに続く。筍の時期に採れたものは茹で、それを細かく切って冷凍保存し、食べたい時に筍ご飯を作るのが楽しみなのだとか。私から話しかけたのだが、Tさんの話しが尽きない。今は一人暮らしとなった彼女は、しっかりとした食生活をしているのだと、ただ黙ってうなずきながらも感心した。
春先から春本番にかけての食材を自分流に食べられることも、体が元気で前向きの気持ちがなければ出来ないことだろう。しかし、今の私はどうか。蕗の薹や芹という野草を頂いてみると、無性に土筆が食べたくなってくる。というか、子供の頃に姉たちと堤防の草むらで土筆(ツクシ)や、ヨモギを摘んだことが懐かしく思い出されるのだ。
まぶしい陽光が差すなかで、スギナの生える近くに土筆は群生していた。頭が伸びすぎたものは避けて、少し緑がかっていて、つんと締まったものを、根元からもぎ取るのだ。そして要らない布で作った袋に入れる。家に帰り新聞紙に広げて、今度は土筆の節(袴)を指で剝ぐ。指先はアクで黒くなるが、それらの作業が終わると、なぜか達成感あってホッとしたものだ。姉は油で炒めて醤油味のものを作ってくれた。
昨今は、造成地が増えているので私の住まいの近くでは土筆をみかけることがない。あの、姿の可愛い土筆は、スギナの地下茎から出る胞子茎。だが、スギナは農家にとっては何とも、厄介な雑草でもあるとか。だから、今では農薬が使われているかも知れないが、土筆が生えている場所はあるのだろうか。白井健康元気村のKさんに聞いてみると、白井にも群生するところがあるらしい。見かけたら早々に教えてくれるというので、今から楽しみだ。
ちなみに、土筆の花言葉は「向上心」「努力」。成長するスピードから、前向きな言葉となっているのだろう。これからは、日に日に日照時間も増える。さあ、「桜咲く春」へまっしぐらだ!