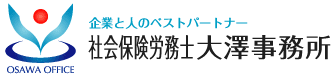近頃は、割増賃金の支払いで頭を悩ましている経営者の方は多い。
なぜなら、労働局のあっせん、労働審判、割増賃金専門弁護士事務所の
台頭など、使用者を取り囲む労働者側の「訴え機関」が増大しているからです。
使用者からのご相談の多くは、割増賃金未払い問題で、そのような問題で
労働者から訴えられないにはどうすればいいのか、そんな質問が多く
寄せられています。
勢い、あの会社もこの会社も「定額残業代」制度へシフトすることが多くなり、
それはそれで一つの対策とはいえますが、ちょっと待ってください。
そもそも、その残業は本当に必要だったのですか?
●もっともっと残業削減
割増賃金の支払いにびくついている使用者は多いですが、肝心の、
そもそも「残業を減らす」という基本中の基本を忘れている方が多い
のが残念でなりません。
平気で、残業命令も出さずに、労働者の好きなようにタイムカードを
押させ、どこからどこまでが本当に残業時間なのか、
その残業は必要だったのか、残業野放し又は管理意識が飛んで
いる使用者の方がいらっしゃいます。
そんな会社は、早晩、「割増賃金未払い」問題で訴えられるでしょう。
「残業の野放し」--。非常に残念な「習慣」です。
残業は削減しましょう。
1日15分でも30分でもいいんです。
「無駄な」残業は、有意義に減らしましょう。
●残業削減は意識の問題
そもそも残業は、労働契約における特別の「業務命令」であり、その業務命令を
出さずには「使用者の指揮・命令に基づいて労務を提供する」という労働者の
労働契約上の義務が成立しません。
よく「15分でも残業になればいい」と、15分を過ぎてからタイムカードを
押して残業代を稼いでいる者がいる、と憤慨している使用者の方が
いらっしゃいますが、それは、あなたが「残業命令」「業務命令」も
出さずに、野放しで残業を許容しているからです。
ここは、本来の姿に戻って、残業を許可するときは、しっかりと、
「残業命令」又は「残業許可」を出さないといけません。
すなわち、「業務命令のない残業は残業として認めない」。
もし必要があって残業しなければならないときは、
しっかりと、上長判断により残業許可を出してください。
残業は、努力又は工夫によって減らすことができます。
「残業削減キャンペーン」をはりましょう。
●誰でもできる残業削減
少しの工夫で1日15分の残業を減らすことができれば、
10日で150分、20日で300分(5時間)、1年で60時間の残業を
減らすことができます。これを10人でやれば年間600時間の削減です。
30分削減だと、10日で300分、20日で600分(10時間)、1年120時間
の削減です。10人でやれば年間1200時間削減です。
従来からある「ノー残業デー」などという実行不可能? なことを
言っているのではありません。会社での残業を減らす代わりに
家での持ち帰り残業が増えたなどとなると元も子もありません。
大切なのは、会社が「残業削減」のキャンペーンをやるという厳然たる事実。
自分たちも少しの工夫で残業を減らさなければならない、としたら、
その班、そのグループごとに少しは意識の改善がみられるはずです。
・残業許可の適正な申請
・上長による適正な残業管理
・残業命令のない「残業」は認めない(ダラダラ残業の削減)
・一人一人の残業削減目標づくり
・残業を月〇時間減らした人への奨励金
・残業削減キャンペーンのキャッチフレーズの募集
・残業削減ポスターの募集
・残業削減のコツ、アイデア募集
思いつくままに書いてもまだまだ出てきそうです。
残業削減キャンペーンは、ダラダラ残業を減らします。
全員参加型で、あなたの会社でも、「残業削減キャンペーン」を
やってみませんか。
割増賃金を「定額残業代」で、などという話は、それからでいいのです。