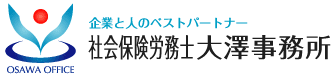健康保険法において、「介護保険料」は給与・賞与から源泉控除できるとされている。
(健康保険法第167条第1項第2項)
私たちの給料や賞与から、一般保険料(健康保険料)と共に介護保険料が控除されるのは、
介護保険法に規定する「第2号被保険者」期間中(40歳~65歳未満)である。
しかし、この介護保険料の源泉控除の給与計算はよく間違っている。
現行法では、健康保険は75歳になると資格を失うので、75歳到達の翌月の給与計算時に
健康保険料を控除しないとすることは、大抵ミスなくできる。もっとも、
その年齢まで勤務している社員、役員は少ないであろうから、「75歳に到達したら」
健康保険料は控除しない、ということは、案外容易い。
介護保険料は、40歳到達と65歳到達の2回、必ず、「控除するのか」「控除しないのか」
の判断の時期がやってくる。
特に、「40歳」という年齢は働き盛り、会社の主力層が多いため、対象社員数も多い。
1、40歳の誕生日の前日の属する月分から、それまでの一般保険料(健康保険料)に加えて
介護保険料を徴収する。源泉控除するのは、原則として、その「翌月に支払われる給与」から。
2、65歳の誕生日の前日の属する月分から、介護保険料は徴収しない。一般保険料のみとなる。
原則として、その「翌月に支払われる給与」から控除しない。
ここまでは、給与計算のイロハ。
現在では、給与計算ソフトが「介護保険第2号被保険者」の該当・非該当のチェックを
かけてくれるので、間違う人は少ないかもしれない。
よく間違えるのは、「賞与」支払時の保険料控除の計算だ。次のような場合。
1、介護保険料率が改正になった月(3月)に「賞与」を支払った(3月)。
→→改正後の介護保険料率で控除する。
2、40歳の誕生日の前日の属する月に「賞与」を支払った。
→→介護保険料を控除する。
3、40歳の誕生日の前日の属する月に「賞与」を支払うが、その後、その月の途中で退職する。
→→介護保険料は徴収しない。
4、(賞与ではないが)40歳の誕生日の前日の属する月に「介護保険料率の改正」があった。
→→その月分の介護保険料を翌月給与から源泉徴収する。改正後の介護保険料率を使う。
5、65歳の誕生日の前日の属する月に「賞与」を支払った。
→→介護保険料は徴収しない。
以上が正しく控除できていない代表例だ。
また、間違って控除されたり、されなかったりしていても、
大抵の場合、当人は、「誤り」だということに気付かない。
事業主も、誰も、気付かない。
年齢による各種保険料の控除、非控除は、その他のものを含めると、
1、40歳到達
2、64歳到達以後の最初の年度の初日
3、65歳到達
4、70歳到達
5、75歳到達
と5回出現する。
給与計算ソフトも自動的に注意を喚起してくれるが、
「賞与」や「料率改正」については、人的知識、注意力にに頼らざるを得ない。
翻って考えると、「いい給与計算ソフト」とは、
限りなくゼロに近く人為的ミスを防いでくれるソフトだということができる。
現在、当事務所で使っている「セルズ給与」は、その点、第1位のソフトと評価している。
あまりにも「誤り」が多い例なので、今回、特記させていただいた。
★労務相談、就業規則、助成金、派遣業許可、給与計算
起業支援、パート雇用、社会保険手続ならこちら
“企業と人のベストパートナー”社会保険労務士大澤事務所
 にほんブログ村
にほんブログ村
(健康保険法第167条第1項第2項)
私たちの給料や賞与から、一般保険料(健康保険料)と共に介護保険料が控除されるのは、
介護保険法に規定する「第2号被保険者」期間中(40歳~65歳未満)である。
しかし、この介護保険料の源泉控除の給与計算はよく間違っている。
現行法では、健康保険は75歳になると資格を失うので、75歳到達の翌月の給与計算時に
健康保険料を控除しないとすることは、大抵ミスなくできる。もっとも、
その年齢まで勤務している社員、役員は少ないであろうから、「75歳に到達したら」
健康保険料は控除しない、ということは、案外容易い。
介護保険料は、40歳到達と65歳到達の2回、必ず、「控除するのか」「控除しないのか」
の判断の時期がやってくる。
特に、「40歳」という年齢は働き盛り、会社の主力層が多いため、対象社員数も多い。
1、40歳の誕生日の前日の属する月分から、それまでの一般保険料(健康保険料)に加えて
介護保険料を徴収する。源泉控除するのは、原則として、その「翌月に支払われる給与」から。
2、65歳の誕生日の前日の属する月分から、介護保険料は徴収しない。一般保険料のみとなる。
原則として、その「翌月に支払われる給与」から控除しない。
ここまでは、給与計算のイロハ。
現在では、給与計算ソフトが「介護保険第2号被保険者」の該当・非該当のチェックを
かけてくれるので、間違う人は少ないかもしれない。
よく間違えるのは、「賞与」支払時の保険料控除の計算だ。次のような場合。
1、介護保険料率が改正になった月(3月)に「賞与」を支払った(3月)。
→→改正後の介護保険料率で控除する。
2、40歳の誕生日の前日の属する月に「賞与」を支払った。
→→介護保険料を控除する。
3、40歳の誕生日の前日の属する月に「賞与」を支払うが、その後、その月の途中で退職する。
→→介護保険料は徴収しない。
4、(賞与ではないが)40歳の誕生日の前日の属する月に「介護保険料率の改正」があった。
→→その月分の介護保険料を翌月給与から源泉徴収する。改正後の介護保険料率を使う。
5、65歳の誕生日の前日の属する月に「賞与」を支払った。
→→介護保険料は徴収しない。
以上が正しく控除できていない代表例だ。
また、間違って控除されたり、されなかったりしていても、
大抵の場合、当人は、「誤り」だということに気付かない。
事業主も、誰も、気付かない。
年齢による各種保険料の控除、非控除は、その他のものを含めると、
1、40歳到達
2、64歳到達以後の最初の年度の初日
3、65歳到達
4、70歳到達
5、75歳到達
と5回出現する。
給与計算ソフトも自動的に注意を喚起してくれるが、
「賞与」や「料率改正」については、人的知識、注意力にに頼らざるを得ない。
翻って考えると、「いい給与計算ソフト」とは、
限りなくゼロに近く人為的ミスを防いでくれるソフトだということができる。
現在、当事務所で使っている「セルズ給与」は、その点、第1位のソフトと評価している。
あまりにも「誤り」が多い例なので、今回、特記させていただいた。
★労務相談、就業規則、助成金、派遣業許可、給与計算
起業支援、パート雇用、社会保険手続ならこちら
“企業と人のベストパートナー”社会保険労務士大澤事務所