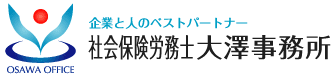変更の内容が一部の従業員の労働条件を低下させる可能性がある場合などだ。
労働者の合意なく就業規則の内容を(不利益に)変更することはできないのだろうか。
労働契約法第9条本文前段では、労働者と合意することなく就業規則を変更し労働条件を不利益に
変更することができないと規定している。
「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に
労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。……(以下後述)」
しかし、企業経営が常に順風満帆に推移するとは限らない。
経営上の已む得ない状況、他社との競合、地域水準、社会経済情勢などにより、
やむを得ず労働条件を低下又は変更せざるを得ない場合もあろう。
労働条件は時代と共に、経営状態と共に、一定程度の修正を余儀なくされる。
従って、労働契約法第9条本文ただし書きにおいて、
「ただし、次条の場合は、この限りではない」と定め、
労働条件は労働者の合意なく、不利益変更が許される場合がある可能性を示している。
では、いったい、どの様な場合に許されるのであろうか。
「次条」である労働契約法第10条をみてみよう。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合には、変更後の就業規則を
労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更の内容が合理的なものである場合には、
労働契約の内容である労働条件は、変更後の就業規則の定めるところによる、としている。
就業規則変更の効力について、労働者の合意の例外を認めているのだ。
就業規則の変更が合理的なものであるか否かは、次により判断される。
①労働者の受ける不利益の程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の相当性
④労働組合等との交渉の状況
⑤その他就業規則の変更に係る事情(我が国社会における一般的状況)
この労働契約法第10条の規定は、「就業規則の変更による労働条件の変更が
労働者の不利益となる場合に適用されるものであること。」(平24.8.10基発0810第2号)
という通達がでている。
労働条件を変更する場合、とりわけ労働者の不利益に変更する場合には、
上記①~⑤のすべての条件を満たすことが必要であり、かつ、労働者にあまねく周知しなければならない。
決して、使用者の恣意的な思いで労働条件を不利益に変更したり、不十分な説明のないまま実行してはならない。
なお、通達によれば、⑤の「その他就業規則の変更に係る事情」の中には、
(労働条件不利益変更に代わる)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況」が含まれている(同通達)。
就業規則変更に反対する労働者がいる場合は、労働契約法第9条、同第10条を
参考に、労働条件変更の必要性について、十分な検討をされたい。
★雇用問題でお悩みの使用者の方は、特定社会保険労務士大澤朝子へ
 埼玉で派遣業許可申請なら社会保険労務士大澤事務所へ
埼玉で派遣業許可申請なら社会保険労務士大澤事務所へ★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
介護保険事業所知事指定、パート雇用、社会保険手続ならこちら
“企業と人のベストパートナー”社会保険労務士大澤事務所