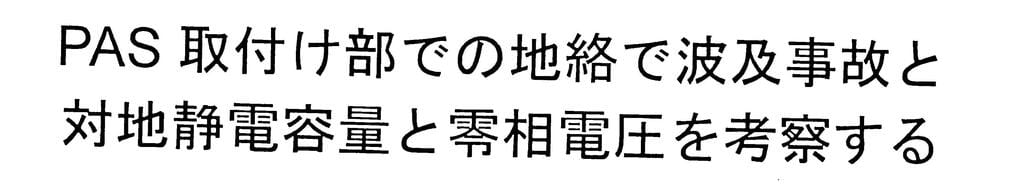

配電線等の地絡事故におけるタイトルのIc(対地静電容量)と零相電圧(Vo)は地絡抵抗Rgの変化で、どの様に変化するのかエクセルで計算してみる。
静電容量2.5μFは一般的に架空配電線100kmに相当する。
グラフに作図すると、自家用設備のPAS以降の静電容量は主に高圧ケーブル程度の少ない静電容量となるので地絡した場合、Rg5000Ωでも零相電圧(Vo)は対地電圧6600/√3=3810VのMAXとなる事が判る。
エクセルの2.5μF<なった場合の零相電圧(Vo)は2桁となる。
この場合、PASの零相電圧(Vo)整定5%(190V)では零相電流(Io)は動作しても、この数値では零相電圧動作検知はしない...方向性地絡継電器(DGR)、方向性SOG等。
零相電流(Io)マグサインは出ているが零相電圧(Vo)は出ていない事も、これを見るとあり得るカモ。
☆
この式も机上のノーガキであり、現場の地絡事故では5000Ωなどキープしている訳など無く、一瞬に完全地絡となるのは誰でも判る。
一瞬の風雨での立木接触もあるが、これは軽故障となり再送電で復旧する。
下の写真は電力変電所、再閉路失敗し重地絡事故で広域停電となった事例。


2mはあるヤマカガシか...。

人間も感電すると電流でた箇所は爆発的に破裂、そして電気裂傷は再生しないと言われているので壊死する、死ななくても皮ふ移植しなない。
肩から感電して膝下に抜けた工事やさんの例だと退院まで3カ月を要したので長期の入院となる。
先の5000Ω例は人体抵抗3000Ωと言われているが、この抵抗値でも良い。
再送電失敗したのは何故か:
通常、小動物は感電した場合、電撃ショックで飛び跳ね充電部電線等より離れ再送電成功するが、ヘビなどの長いものは一旦、離れても再度引っかかる可能性もあり2回、強制送電してもNGの例もある。

こんな写真もあった配電線をガッチリ咥え昇天したクマ...何を狙ったら、こうなるのか意味がワカラン。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます