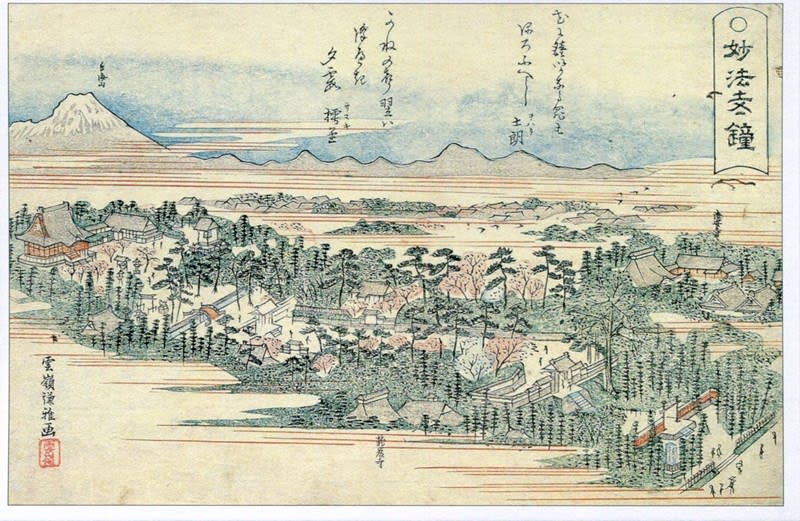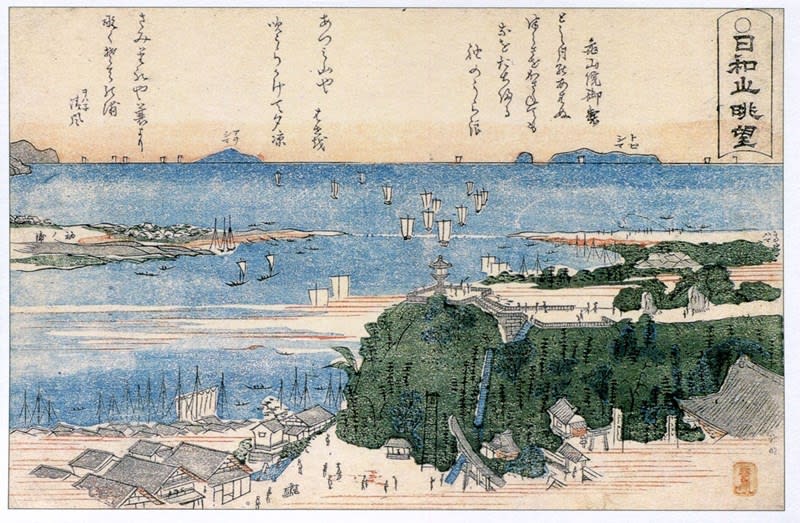世の中様々な検定があるもので神社検定なるものまでありました。

神社検定テキスト
正解は、〇【古来、厄年の年齢は「満年齢」で行う】
いやいや、満年齢は明治5年12月3日を以て明治6年の1月1日とした太陽暦への改暦以降でしょう。明治6年以降を古来といっているのでしょうか。検定問題は一問でも間違った物を作成したらアウトです。厄年を満年齢で数えるなど聞いたことがありませんが神社庁ではそうすることにしたのでしょうか。
うちの和尚さんが言っていました。「人がこの世に生を受けて0歳ではありません。母親のお腹にいる間も命と考え、生まれた年は0歳ではなく1歳です。」そういえばヒトはいつから「人」になるのかという問題がありましたね。
民法では私権の享有は出生に始まる、とあります。さあ、そこからが難しい。母親の体から胎児の体が全部露出した時点からか、一部でも露出した時点からか、民法、刑法で解釈が異なる、ともありますがご興味がありましたら一度調べてみてください。母親にとっては妊娠が判明した時点でわが子と思うのは間違いないですけどね。最近は生まれてもわが子と思わない親も多いようですけれど。
怪しい検定といえば、漢字検定があります。漢字検定に関しては高島さんの本がおもしろいです。

例えば、
つくづく感じるのは、 漢字検定の問題の作者たちには、言葉のレベルの感覚がまるでないことである。
文字や言葉というものは、その前後の環境のなかで出てくるものである。 小学生でもわかるごくやさしい文章のなかに、 ふつうの現代文には出てくるはずのない言葉や文字が突如として出てきてはおかしい。いや、 おかしいどころか、そもそもそんなことはあり得ない。
ところが漢字検定の問題には、 言語のバランスを失した文章がぞろぞろ出てくる。そればかりだと言ってもよい。
いまちょっと開いた問題集のよみがな問題に「心ばかりの品を献芹致します」というのがあった。「心ばかりの品」というやさしい表現につりあうのは「さしあげます」くらいである。こん なところへ「献芹」というカタイ言葉がくっつくものじゃない“。
そのそばに「船頭さんは蓑笠を付けていた」というのがある。答は音読みで記せとある。ミノ カサならまあ常識的だがそれてはだめなのである。「せんどうさんはサリュウをつけていた」が 正解らしい。アホらしいと思いませんか?
「船頭さん」には「船頭さん」にふさわしい、つりあいのとれた言葉というものがある。
「蓑笠」は「孤舟蓑笠の翁」とでも言う時に使う言葉だ。
それでいて、「漢検で文章作成能力を育てよう!」「漢字・熟語の意味をきちんと理解し、正しく使いこなすことで、はじめて文章が成り立ちます」と呼号しているのである。あっかましい。漢検で、ことばを理解し、正しく使いこなすことなんかできっこない。文章を書く能力が育つ どころか、破壊されてしまう。
どうです、全部読みたくなりませんか。