福山での発達障害相談支援スキルアップ研修2日目終わりました。
本当にワクワクする時間が続いています。
受講生の多くが、本当に演習を丁寧に取り組まれています。
さて、今回のセミナーもそうですし、本日より2日間の鹿児島の研修もそうですし、私がコーディネートする研修、セミナーの多くが1つの一貫した視点を軸にしています。
それがジャック・ウォール氏の『TEACCHの6つの考え方』です。
・自閉症(・発達障害)の特性を軸にする
・個別化する
・アセスメントからスタートする
・実証された方法を活用する
・自立が目的である
・親やチーム間の協働を尊重する
の6つの自閉症(・発達障害)指導・支援の6つの考え方です。
実際の指導・支援で重要な視点で、この軸からぶれているものは、どんなに良いアイデアもうまくいきません。
これは実践の中の考えだけではなく、講演やセミナーでも意識することが重要です。
私がコーディネートする研修は、特性が中核にあります。特性を押さえないで、様々なアイデアを説明したり、支援計画を考えてもらったりはしません。
演習でも、できるだけ様々なケースを体験することを重視して、個別化の意味を伝えます。
必ずアセスメントからはじめた、プロセスを重視して、どうしてもアセスメントの時間がとれないワークショップでは、アセスメント情報を添付するなどを重視します。(プランからはじまる、Plan・Do・See やPDCAサークルは、重要な視点ですが、受講生がプラン先行になるのであえて入れません。)
科学的に明確な方法を活用します。ただ、様々な科学的な実証された方法をすべてを盛り込むと基本を学びにくいので(例えば受講生の中には、視覚的構造化を勉強している時にプロンプトのレベルに注目しすぎる傾向の方がいます。)、構造化は構造化に絞り込んで、システマティックインストラクションはシステマティックインストラクションに絞り込んで研修をわけて設定しています。基本の研修と応用研修をごちゃまぜにしないで組織しています。
様々な研修の中には、研修内容そのものが目的になってしまい、マニアックな視覚支援やアイデアだけに注目する研修もよくネットでみます。1つ1つのケースの目的(自立課題、生活課題、行動目標など)を明確にした研修を設定します。
様々な研修では、協調しあうことが重要視されますが、私がコーディネートする研修では、みんなが学ぶために、一人ひとりに役割をもった上での協働作業を重視します。例えば、学びが進まない方も先に学んだ方がフォローするとか、研修の方向性から脱線する方もチームでそれを整理しながら進めることを求めます。
親さんのアイデア、チームのアイデアは、1つ1つが重要な意味をもつアイデアとして活用したろ、取り入れたり、そこからはじめたりすることを推奨します。
ちなみに、『フレームワークを活用した自閉症支援』は、上記の研修プロセスにそって構成されています。
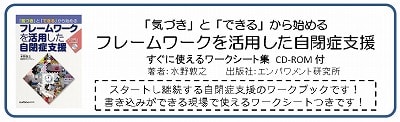
スペース96での購入はこちらから
Amazonでの購入はこちら
いつもランキングにご協力ありがとうございます。1日も1クリックお願いしま す。
 にほんブログ村 にほんブログ村
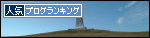 よろしければこちらもクリックお願いします よろしければこちらもクリックお願いします
コメント・感想をお待ちしています。
| Trackback ( 0 )
|
|



