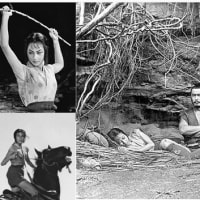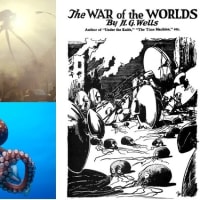「北辰一刀流免許皆伝は本当?」
今一つの疑問は、北辰一刀流免許皆伝云々について。
写真は、やはり今回展示されているものの一つで、先の記事でも触れた坂本弥太郎が坂本留に宛てた借用書の控えです。
一番右に見えている「以上合計参拾八本也」とあるのは龍馬の書簡類だと思います。次いで刀剣として、「朱鞘、束ナシ」とある脇差、「龍馬ギ遭難当時ノ遺物、刀キズノ鞘付キ 束ナシ」とある龍馬佩用の吉行、それと現在行方不明の「白鞘、束ナシ」とある兼定。兼定どうしたのかしらん。焼失したのかも。なら佩刀吉行だって焼失したのかも。鐔は焼失していることだし。
註)兼定については、先に述べた「土佐勤王遺墨展覧会」(昭和4年)の「出品目録控」には、龍馬の長刀「和泉守兼定」が釧路大火で甚だしく焼損したとあるそうです。かなりの業物である兼定なのに、吉行ほどの扱いを受けずに、現在は所在不明。
さて本題は、その後に続く「秘伝」とある3巻の巻物。それぞれ「北辰一刀流兵法箇条目録」、「北辰一刀流兵法皆傳」、「北辰一刀流長刀兵法皆傳」との記載があります。このことが、今に続く混乱(龍馬は北辰一刀流を学ぶために出府したと云う誤解)の原因にもなっているのですが。
今回展示されている巻物は、「北辰一刀流長刀兵法目録」、「小栗流和兵法事目録」、「小栗流和兵法十二箇条并二十五箇条」、「小栗流和兵法三箇条」の4巻だけ。
註)龍馬の「北辰一刀流長刀兵法目録」と並べて、清河八郎が千葉周作から授けられた「北辰一刀流兵法箇条目録」が展示されています。どうだ「借用書控」に記載されている名と同じだろ、と云うつもりなのかしらん。
なぜなら、弥太郎の「寄贈品目録控」(前年の「出品目録控」も同様)には、「日根野弁二より受領」のものとして、「小栗流和兵法事目録」、「小栗流和兵法一箇条並二十五箇條」、「小栗流和兵法三箇条」に続けて、「附記、千葉周作ヨリ受領ノ皆傳目録ハ於釧路市焼失セリ」との記載があるからです。
註)日根野弁二(正しくは「日根野弁治」)、「小栗流和兵法一箇条並二十五箇條」(正しくは「小栗流和兵法十二箇条并二十五箇条」)や「千葉周作ヨリ受領」(仮にそれが実存するのであれば「千葉定吉ヨリ受領」でなければならない)と生半可な知識がアリアリと見て取れます。ですから「北辰一刀流長刀兵法目録」が「北辰一刀流長刀兵法皆傳」になっていたりします。また「北辰一刀流兵法箇条目録」も、皆伝がある以上、目録もある筈だとの産物であって、何処からか聞きかじってきた(弥太郎か留か定かではありませんが)ものを控えたとしか思えません。何もかも固定観念(龍馬=北辰一刀流)のなせる業。江戸三大道場の中にあってもピカイチの北辰一刀流玄武館(千葉周作)。だから桶町道場(千葉定吉)よりもビッグネームの千葉周作の名が使われる。北辰一刀流に比べれば土佐の下級武士が学ぶ小栗流なんて歯牙にも掛けてもらえないローカル流派。龍馬をより大きく見せる装飾には北辰一刀流は必須のもの。以前にもどこかで述べたように、龍馬の二度に及ぶ出府はペリー来航に伴う沿岸警備が主目的。最初はその傍らに佐久間象山に就いて西洋砲術を学ぶことが副目的だったのですが、二度目はそれが叶わなくなった(弟子の吉田松陰の密航を示唆したとして、象山は獄に繋がれ、やがて国許蟄居)ことから出府理由(あくまでも副目的)に剣術修行としたことが混乱に拍車を掛けた。しかし龍馬がそうしたのは、最初の出府で、桶町道場での代稽古のアルバイト経験で、生活の目処がついていたから。
で、一等怪しいのは、「借用書控」には、小栗流の免状が一つも記載されていない!!
降って湧くようなものではありません。一体どこに消えてしまって、いつそれが出てきたと云うのでしょう。
その辺りのことは、次の記事で。
ブログトップへ戻る