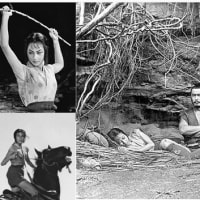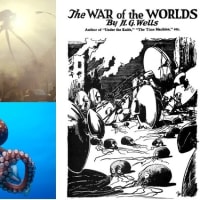「再発見されたいわくありげな脇差」
興味深いのは、「出品目録控」の翌年(昭和5年)10月26日付の弥太郎の「寄贈品目録控」。これも今回展示されているのですが、以前に昭和6年に寄贈と書きましたが、寄贈先の京都国立博物館(当時恩賜京都博物館)にある台帳ではそのようになっていたからで、この控で前年に寄贈されたことが分かりました。
註)京都国立博物館はチョンボが多い。今回の吉行の一件だけでなく、かつて千葉周作の孫にあたる千葉貞(てい)の錦絵を千葉定吉(貞吉では無くて定吉)の娘佐那と見誤ったのも、今では別人と判明した芸者「辰」の写真をお龍の写真と言い張ったのも、京都国立博物館の宮川禎一氏ですからね。
寄贈した龍馬所縁の品々は、「出品目録控」とほぼ同じであるとのことですが、3口の刀については別物吉行と埋忠明寿(写真上)の記載はあるものの脇差(写真下)の記載が無い。このことは寄贈前に、平成27年に再発見されたときの所有主である北海道在住の某氏に、誰かが譲るかした可能性があるということになります。
註)龍馬の遺品は、明治4年8月20日に朝旨により龍馬の跡目を相続した高松太郎(高松順蔵と龍馬の長姉千鶴との間にできた長男、この後「坂本直」と名乗る)が、直が明治31年11月7日に没した(享年57)後は妻の留が、その留が北海道の羅臼村で没した(大正4年12月15日、享年69)後は実子直衛へと引き継がれるのですが、その直衛が大正6年3月11日に太平洋上(船員であった)で賭博のもつれから射殺された(享年34)ため、弥太郎が保管することになったのですが、実は留が生存中に弥太郎が借用したまま返却しなかった節があるのです。(これについては次の記事で。)
弥太郎の「出品目録控」には、吉行は被災し研ぎに出したとあるのですが、埋忠明寿も脇差もそのような記載はありません。
埋忠明寿の場合、写真にあるように拵え(刀装のこと)もそのまま残されています。「出品目録控」には、「此刀ハ元ト龍馬ノ佩用セシモノヲ當時ノ志士二シテ海援隊ノ最髙幹部タル菅野覚兵衛ニ贈リタルモノ也 之ヲ明治四十年故アッテ菅野家ヨリ坂本家ヘ返戻アリ 爾来坂本家ニ蔵ス」とあるので火災に遭っている筈なのですが、吉行と違って慌てながらも運び出せた品々の中の一つであったのでしょうか。
一方、脇差の方は白鞘に収められているのですが、拵えは被災したのでしょうか。それに奇妙なのは白鞘には「阪本龍馬佩刀」(「阪本」としている)の墨書はあるものの、目釘孔の位置が違っていますし、反りも微妙に合っていないのです。ただ収めるだけのケースとして使用されたように見えます。
註)明治43年8月30日付の坂本留から遺品を預かった際の弥太郎の「借用書控」には、脇差は「朱鞘、束ナシ」とあります。鞘は被災したのでしょうか。
吉行も白鞘に収められているのですが、こちらの方はしっかりそれ用に作られたもので、弥太郎の手になると思える「坂本龍馬佩用 大正二年十二月二十六日釧路市大火ノ際罹災ス」が墨書されています。
面白いでしょ。大火の際、傷つき血塗られた禍々しい龍馬佩用の吉行は捨て置かれたのに、小奇麗な二振りの刀は運び出されたとしか思えない。その後、誰かから「吉行はどうした?」と訊かれて、その価値・重要性に気付かされた弥太郎は慌ててどこからか調達せざるを得なくなった。それが展示されている吉行。焼失した吉行の刃長も反りも、まして刀身の傷痕までも、全く同じものを探し出すなんてことは不可能。で、吉行の銘だけで探してきたものだから、先の記事で述べたような不都合が露呈する。
そして刀身の傷痕や刃文の微妙な違いを誤魔化すために、研ぎに出して真直ぐな刃文でそれを覆い隠そうとした。その研師は札幌市在住の富田秋霜氏。「出品目録控」にその名があるものの、翌年の「寄贈品目録控」にはその名も研ぎに出したこともすっぽり抜け落ちている。面白いね。口止めに脇差を与えたのかも。再発見先は北海道としか書いていないので確かなことは云えないけど、そこが富田氏の関係者なら、そういったことも有り得る。
吉行絡みはこのくらいにして、今一つの疑問は次の記事で。
ブログトップへ戻る