
大いに語っている(?)のは、わずかひとりだけですので、
別に「雑談広場」を設けました。
ここでは、ひとり寂しく、ブツブツ呟くことにします。
僕の呟きに興味のある方、コメント欄を覘いてくださいね。
勿論、呟きに対するコメントもOKです。お待ちしております。
僕と一緒に呟きたいひとも歓迎します。
コメントが多すぎるようになったら、新たなページを作ります
ので、ご安心ください!
◇コメントの閲覧の仕方◇
①このページの右下に「コメント (n) | トラックバック (0) | goo」があります。nは、それまでに投稿されているコメント総数を表す数字です。
②閲覧する場合、①の「コメント (n) 」の箇所をクリックします。
③すると、それまでに投稿されたものが「コメント」のタイトルの次に日付の古いものから順に羅列されて表示されます。
◇コメントを書き込む場合には◇
④書き込む箇所は、次の3箇所(太字の箇所)があります。
・名前欄:「何組の誰某です」と書いてください。
組は6年のときのものです。氏名のところは、旧姓でお願いします。
・タイトル欄:どのようなものでも構いませんし、ブランクのままでも
結構です。
・コメント欄:自由に書き込んでください。
文章を改行する場合、Shiftキーを押しながらEnterキーを押して
ください。
⑤最後に「投稿する」というボタンをクリックします。
⑥「入力内容を確認してください」と表示されて、数字4桁の入力を求められます。
・数字4桁入力欄:人手による投稿であることを証明するためのもの
です。この欄の真上にちょっと歪んで表示されている4つの数字を
順番通りに入力してから、再び「投稿する」ボタンをクリックしてくだ
さい。
注)4桁の数字は、半角文字でも全角文字でも構いません。
数字を間違えると、再び入力を促されますが、このときには
新たな4桁の数字に変わっていますので、それを入力するように
してください。
ブログトップへ戻る












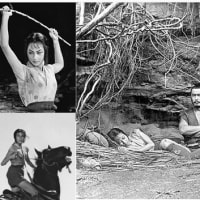
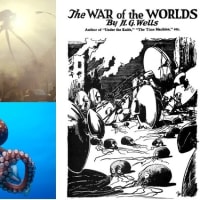






小雨交じりとは云え、五月の連休明けに行った時には、ここ数日のTV
で見るような混雑はありませんでした。来場者の大半が団塊世代を中心
としたシルバー世代で、アシュラーと称するような若い人の姿はチラホラ
としか見かけなかったように思いますが、女性が多かったことは確かです。
それにしても、私たちの世代はサユリストとかコマキストというように、
名前の後ろに「ist」を付けたものですが、今の若い女性たちはアムラー
とかアシュラーとか、「er」を付けるのですね。
どちらも「・・・する人」を表す接尾語ですが、「ist」が主義主張といった
意味が強く込められていたのに対して、「er」の方は漠然として感覚的な
思い入れを表現しているような気がします。
団塊の世代は男社会でしたから、憧れの対象に対しても「ist」という理屈
が必要だったのでしょうけど、現在のような女性の時代になると、そんな
屁理屈よりも感覚や印象を大切にして、サラリとした「er」が相応しいと
感じたのでしょうか。
昭和27年と云いますから、僕らの親の世代が目にしたのですね。日本橋
三越で三週間足らず展示されたようですが、50万人もの来場者があったと
云います。当時も人気があったのですね。
釈迦如来を守護する八部衆の一人に過ぎなかったものが、時代が下って主役
の座を占めるに至ったのは、1300年を経ても変わらぬ凛々しくも憂いを
帯びた面差しと、静謐な中にも凛として佇むその姿にあるからなのでしょう。
三越では硝子ケースに入れられていましたが、東京国立博物館平成館の展示
に囲い物は一切ありません。手を触れんばかりにして、ぐるりと観て回って、
その魅力を満喫することができます。八部衆も素晴らしいですよ。
まだ一週間ありますので、まだご覧になっていない方、一時間待ちは覚悟の
上、足をお運びください。団塊の世代、就中女性の方は、辛抱強く、何事にも
(とくにイケメンに対して?)興味を示されて行動的なのですから。
あるそうです。(後日になって近所のひとから教えて貰いました。)
文部省後援による第十七回全国児童美術展に第一小学校から二人も
入選したのは凄いことなのですが、二年生の幼い身にとってはその
有難さなど分かる筈も無く、そんなことよりも、その褒美として、
美味しいランチをご馳走になったり、ちょび髭を蓄えたアダチ龍光
の手品を見せて貰えたり、バッジだったか何だったか思い出せませんが、
お土産を頂くなどしたことの方が嬉しかったのですから。(団塊の世代
は花よりも団子。)
経緯はよく分からないのですが、夏休みの宿題に描いた絵が選ばれた
ことだけは覚えています。叔父と羽田飛行場へ見学に行って、そのとき
目に焼きついた滑走路に並ぶ飛行機を家に帰ってから思い出し思い出し
して描いたものです。もっとも今では、その図柄も覚えていませんが。
八歳の子供が自分の絵に題名を付ける筈もありませんが、賞状には
「飛行場」とあります。村田さんの絵には、どのような題名が付けられて
いたのでしょうか?
僕の絵は佳作に過ぎませんが、村田さんは2等賞とか銀賞とかであった
と記憶しています。凄い!(間違えていたらゴメンなさい。)
先日の同期会には村田さんんも出席してくれたのに、お話しする機会を
逸してしまって、本当に残念なことをしました。
直ぐのところに密乗院があります。その手前、右に折れたところに、T字路
とT字路に挟まれた100メートル足らずのちっぽけな横丁があります。
Iの横丁と名付けたいところですが、途中に脇道(ここもT字路ですが)が
あったりして、要するに徒の名も無い狭い横丁ですが、そこに同期生がなんと
6名も住んでいました。
密乗院のS.Tくん、そこからちょっと行った右手にK.Tくん、T.Kさん。
さらに少し行くと、左手にI.Mくん、道を挟んだ斜め前にS.Nさん。
そして、横丁の行き着くちょっと手前左側に僕の家がありました。
先日の同期会には、残念ながらS.Nさんは欠席でしたが、残りの5名は出席、
しかもきっちり三次会まで。
興味深いのは、横丁の右手3人が一中に進学したのに対して、左手3人は
八中に越境入学したことです。
掛け合って貰ったのですが、後で母から聞いたところによると、一中に通学
するには羽田国道を渡らねばならず危険であるという屁理屈を捏ねくり捏ね
くりしたらしいのです。八中だって間には第一京浜が横たわっているのにね。
どちらの交通量が多いとか信号の有無だとか、根拠も何もあったものでは
ありません。そんな愚にも付かない理由でも受け付けてくれたのは、矢鱈に
多い人数故。ちょっとぐらい、あっちがこっちに替わったところで、どうって
こたぁ無い、そんな大雑把な扱いをされるのが団塊の世代。
その越境を望んだ、最大にして唯一の理由だった坊主頭も、その年から廃止に
なったのです。
で、母の労苦が報われなかったかというと、そうでも無さそうなのです。
八中に越境入学した他のひと達の主たる理由は、別のところにあったのですね。
「進学率」という、僕だけでなく、母の頭の中にも全く存在しなかった現実。
霊験あらたかと云うべきか、摩訶不思議と云うべきか、八中に進学した3人は、
皆大学に進学しました。う~む。
僕がチアキスト(?)の端っくれということもありますが、
彼女もひとつ年かさではありますが、団塊の世代の一人だから
です。
本名は、瀬川三恵子。板橋の生まれですが、一時期、大森郵便局
の近くに住んでいて、大森三中に籍を置いてレッスンや地方巡業
に勤しんでいたそうです。ほらぐんと身近に感じるでしょ。
三人姉妹の末っ子だから三恵子としたのかどうか分かりませんが、
私たちの世代は現在のように矢鱈に凝った名前を付けたりは
しなかったですね。それでも医療技術の進歩のお蔭で、「熊」
「寅」「牛」「馬」などの文字の代わりに、モダンな文字が用い
られるようになったわけですが、現在のような「個」の時代では
無く、「集団」の世でしたから、右に倣え的な意識も多分に込め
られていたように思うのです。
「恵」もそういった文字の代表的な一つで、第一小の同期生の中
にもこの文字を用いているひとが少なからずいます。
フジテレビで昭和43年11月から始まった「夜のヒットスタジオ」
という番組がありました。彼女をその番組で見てビックリしたのは、
まだ司会が前田武彦、芳村真理の頃ですから、このコンビの期間の
昭和48年9月までのいずれかの回ということになります。
今では、何と云う曲であったのか覚えていませんが、新人紹介のような
形で歌を歌ったように、ボンヤリとではありますが、記憶しています。
彼女のデビューは、昭和45年7月の「悪女のすすめ」のようですから、
その頃に出演したのかも知れません。僕が興味を持って見ていたのは
学生の間(昭和46年3月まで)だったので、その可能性はかなり高い
と思います。
倉元さんは本名でデビューしましたが、そのプロフィールには昭和26年
6月2日生まれとあります。これだと団塊の世代からこぼれ落ちてしまい
ます。もっとも団塊の世代の名付け親である堺屋太一は、昭和26年まで
を含めているようですから、「十代でデビューした私だって、団塊世代の
端っくれよ」と、私たちとの絆を辛うじて繋ぎ止めてくれているわけです。
があって、そんな日には爽やかな風が吹いて、6月は一年中で
最も清々しい季節であると、昔なにかの記事で読んだことがあり
ます。
それで想い付くのが、川上澄生の「初夏の風」と云う詩です。
かぜ と なりたや
はつなつ の かぜ と なりたや
かのひとの まへに はだかり
かのひとの うしろより ふく
はつなつの はつなつの
かぜ と なりたや
衣更えも6月1日からですし、それで、てっきり6月が初夏だと
思ったのですが・・・
なり、新暦では5月に当たります。立夏が5月初旬(今年は5月5日)
であるのも頷けます。
衣更えは、古くは平安時代に始まり、旧暦の4月1日(初夏)と10月
1日(初冬)に行われたといいますが、現在のように6月1日と10月
1日になったのは明治6年に太陽暦が採用されるようになってからです。
「初夏の風」、実は木版画に刻まれていた詩なのですが、僕は最近まで
図版すら目にしたことが無かったのです。
それで「川上澄生/詩と絵の世界」(毎日新聞社刊)を手に入れて、
「初夏の風」(T15制作、22.8×34.9cm)を観ました。納得しました。
グレーがかった緑の風にローズピンクのドレスの裾が翻っている図
です。薄紫色の鹿鳴館を思わせる大振りの帽子を右手で押さえながら、
ドレスと同色の日傘を持った左手でスカートの前を押さえています。
七分袖のドレスですが、やはり5月の服装なんですね、これが。
この絵、栃木県鹿沼市の市立川上澄生美術館所蔵の逸品中の逸品ですが、
展示されるのは毎年5月だけ。やはり初夏は5月なんです。
(設置母体が宗教法人八幡神社なので、正式には「八幡神社ひめゆり幼稚園」と
云うらしいですが。)
過去形であるのは、少子化の影響で、今から4、5年前に廃園となったからです。
「ひめゆり」は、この時季にオレンジ色の小さい花を咲かせるユリ科の多年草で、
その花言葉は「プライド」そして「変わらない愛らしさ」だそうです。(今井美樹
の「PRIDE」の歌詞そのものですね。)
そういった思いを込めて設立された幼稚園に僕もバスケット片手に通いました。
手許に当時撮影された集合写真がたった1枚ですが遺されています。セピア色に
染まったあどけない顔が、鈴生りに100名ほども写り込んでいるものです。
その大半が第一小に入学しているようですから、1/3強を占める一大勢力でも
あったわけです。
母が危険な国道として屁理屈を捏ねた羽田国道、その向こう側から通っていた園児
も何名かいました。う~む。