
この絵は、中山忠彦画伯の「サッフォー」と題する絵を模写したものです。
やはりパステル画ですが、20号(72.7 x 50.0cm)くらいの大きな絵です。
(実際はもっと明るい色彩の絵なのですが、暗いところでフラッシュを焚かず
に撮ったので、こんな色合いになってしまいました。)
模写に使用した図録、それは月刊の美術雑誌に掲載されていたのですが、
ハガキの半分くらいの大きさで、それを拡大して仕上げたのですが、
昨年、日本橋の高島屋で開催された「中山忠彦 永遠の女神展」に展示
されてあった実物(油彩)は、もっと大きくて80号(145.5×97.0cm)もありました。
それにしても、30代前半は根気もあったし、目も良かった。今ではとても
無理です。
中山画伯は、白日会の伊藤清永に師事しましたので、この頃(S47)の作品には
(伊藤清永はルノワールに師事していたので)その影響が多分に現れています。
絵のモデルは、作品の大半がそうであるように、画伯の夫人の良江さんです。
画伯も若い頃(このとき37歳)には未だ貧しくて、純白の薄着の衣裳は夫人の
手作りに依るものですし、右手が軽く握るハープは鏡の縁を利用したそうです。
僕は、その純白のドレスにピンクの帯、それと緑の背景といった色彩のコント
ラストに惹かれたのですが、顔だけは意識するしないに関わらず、僕好みの
ものになってしまいました。(画伯の絵では、奥様の凛とした佇まいがその
表情によく現れているのですが、僕の方は少し妖艶です。 )
)
中山画伯が何故「サッフォー」と題したのか全くもって存じませんが、サッフォー
は紀元前6世紀頃に活躍した古代ギリシアの女流詩人です。
恋愛を扱った作品(その中には女友達を讃美したものもありました)が多かった
こともあって、後になってのことですが、キリスト教の隆盛とともに異教的頽廃的
とされ、有り難くない代名詞を戴くことになります。
「サフィスト」といっても分からないかも知れませんが、彼女の出身地である
レスボス島からとった「レスビアン」なら分かりますよね。
僕が中山画伯を知る切っ掛けとなったのは、赤坂にあった本社ビルのロビーに画伯の
絵が飾られてあったからです。「サッフォー」より少し前(S41)に制作された「椅子
に倚(よ)る」という絵で、夫人と結婚した翌年の、そして夫人をモデルにした三作目
の、そして第9回新日展に見事入選した、作品です。(この絵、珍しくルノワール風
ではなくて、小磯良平風です。)
同じ題名の作品がもう一点ありますが、本社にあったのは、椅子に座った夫人の衣裳
が薄地の純白の半袖ブラウスに、胸のところに黒い結び紐の付いた袖無しの赤い服
(何と呼ぶのか分からないのですが、「THE SOUND OF MUSiC」のレコードジャケット
のマリアの服装に似た物です。前年に映画が公開されていますので、触発された可能
性はありますね)、そして刺繍の入ったイエロー系のエプロンを着けたもので、背景
がグレーで、正面ではなくて斜め45°に向いた構図の作品です。
この衣裳も知人から借りたそうですし、エプロンは鏡掛けを代用したそうです。
この絵、社友から寄贈されたものとばかり思っていたのですが、そのうちに姿を消した
ところを見ると、借り受けていただけだったのですね。現在は、ウッドワン美術館蔵と
なっています。
借り物尽くしのお話でした。
ブログトップへ戻る












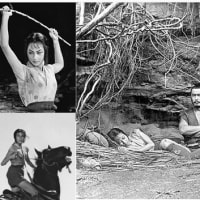
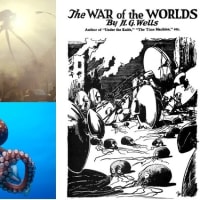






歳を重ねるにつれて砂時間の括れは広がる一方で、一年と
いう月日の砂はあれよあれよという間に流れ落ちて、砂の
一粒一粒の色合を確かめる間もなく、むなしい堆積を溜息
交じりに見遣るのが常でしたが、今年ばかりは少なくとも
2つの熱く光輝く砂を見詰めることができました。
今日は冬至、ゆず湯に浸かって、懐かしい思い出に浸って
みては如何?
誤)「永禄十年(1667)のことです。」
正)「永禄十年(1567)のことです。」
失礼しました。
「でも、どっちゃでもええねん。なんであれ龍馬とちょっとでも係わりが
あるんなら、それでもええねん。」と半ば捨て鉢のお話でした。
それにしてもごちゃごちゃして分かり難かったでしょ。書いている本人も
頭がこんぐらかって、結局書き直す破目になったのですから。
書いた本人も疲れましたが、これをしっかり読んでくれたひとは、さぞや
疲労困憊のことと思います。お疲れ様でした。
もう、このような無謀なことは金輪際止めよっと(と今は思っています)。
話を続けてきましたが、明智末裔伝説にとって(こじ付けに近い)都合の良い
ストーリーを作るとすると、
弘治二年の美濃の内乱により、美濃可児郡の明智の庄を追われた一族郎党のうち、
太郎五郎は一時何処かの国に逃れ、やがて明智光秀が信長に仕えて頭角を現す
ようになると(明智氏の再興を見届けると)、一緒のところに避難していたのか
どうかまでは分からないが、須藤加賀守ともども、その許に馳せ参じた。
しかし天正十年に光秀が敗死し、光俊が自刃して果てると(このときに須藤加賀
守も戦死したのだろう)、太郎五郎は光俊の子(彦三郎)のみならず須藤加賀守
の三人の遺児をも引連れて、四国へ、それも最も遠地である土佐へと逃れた。
光秀の幕将には、四方田但馬守の他にも、諏訪飛騨守、荒木山城守、
村上和泉守など、その本地をして「何々の守」と称している者が多い。
であるならば、須藤加賀守も加賀(石川県)出身である可能性は高く、
光秀に仕えて大和(奈良県)に派遣されていたのではないだろうか。
そして太郎五郎も同じく幕将のひとりであり、その本地が畿内のいずれ
かであったかも知れないのだ。(荒木山城守、村上和泉守などと関係が
あるのかも。)
そして、光俊の遺子彦三郎を郷士坂本氏の始祖とした、となります。
表にすると、次のようになります。
・二代目彦三郎◇----->1656
・三代目太郎左衛門◇------>1676
・四代目八兵衛◇1640------------->1697
・五代目正禎◇◇◇◇1669--------------->1738
・六代目直益◇◇◇◇◇◇◇◇◇1705------------>1779
彦三郎からの言い伝えは、三代目のみならず四代目も本人からしっかり聞き取
っているであろうことが分かりますし、五代目は三代目と四代目の二人から、
六代目直益は五代目から、というように実質三代で伝承されています。
ですから、直益は先祖のことについてかなり正確な知識を持っていたに違い無
いのです。
とは云え、直益が坂本姓から坂本城に結び付けて考えることは有り得ません。
なぜなら前述したように、直益は「坂本」姓から紀氏の末流であるとしたの
ですから、源氏の末流である明智氏と矛盾することは、国学を学んでいる者
にとっては常識だからです。
ただし、光秀の女婿である光俊であればどうなのでしょうか。光俊は三宅光安
の子ですが、三宅光安が明智一族の者なのかどうかまでは分からないのです。
もしも、三宅氏が紀氏の流れを汲むものであるならば、光俊の所縁の地名である
「坂本」を姓にすることは考えられますし、明智の一門に加わったことで、家紋
に桔梗を使用したことも有り得る話なのです。
郷士に取り立てられることは決まっていたものの、父正禎はその身分
では無かったので、そのような曖昧な表現をとったのでしょう。
初代太郎五郎の墓を建立したのは明和四年(1767)ですが、
父正禎が亡くなったのは元文三年(1738)で、その30年以上も
前のことです。
この元文三年から明和四年の間に、「坂本」に改姓したことはハッキリ
しているのですが、それ以上に特定できる史料は残念ながら未だ見つ
かっていません。
家紋が父正禎のみならず直益本人まで「丸に田」であることは、大変に
悩ましい問題です。
これをどう解釈するかによって、結論が180°違ってくるからです。
・坂本姓までは決めていたが、家紋までは決めていなかった。
・家紋まで決めていたが、初代から使用するよう遺言していた。
前者であれば、坂本姓は『日本書記』から都合の良さそうなものを引いて
きたことになり、明智末裔伝説は敢え無く潰え去ることになります。
質屋からでも100年ほどあるのですが)で土佐で屈指の豪商に
のし上がった背景には、それなりの元手があったからということで、
「明智一族が逃れるときに大判小判を抱えてきた」という黄金伝説
までが生まれることになります。
質屋も初めは借家であったと云いますし、商人としての才覚があれば
それなりの財を成すことは出来ると思うのですが、明智末裔伝説を
信じるものにとっては、黄金伝説も不可分の事柄なのです。
うーむ、藪の中か・・・・。
おっと、未だ直益の墓碑が「前大濱」となっていることと家紋の疑問が
残っていました。疑問は解決の布石でもあるのですから、それらを解い
て行けばもう少し見えてくるものがあるかも知れません。
するのですが、その中身は
・貸付金の利子や売買での利益の配分として、百貫目につき
郷士兼助(直海)には、三分二、三厘
才谷屋八次(直清)には、六分四、五厘
・米百石の配分として
郷士兼助(直海)には、四十石
才谷屋八次(直清)には、三十石
(残りの三十石は、直益の隠居料)
・屋敷の配分として
郷士兼助(直海)には、一丁目の屋敷
才谷屋八次(直清)には、本家屋敷
その他諸々の物もありますが、上記のものだけでも大した分限者で
あることが分かります。
米だけでも、一石が一両としても、年に100両(現在の価値だと
凡そ1000万円ほどでしょうか?もっと多いかな?)の副収入が
あったのですから。
ですが、質屋を始めて30年ほどで大濱姓を追贈されているのは、この
間に土佐藩の要請に応じて多分の献金をしたからです。
六代目の直益が初代太郎五郎の墓を建立したのは明和四年(1767)
ですが、この直前に郷士株を手に入れていたかというと、そうでも
なさそうで、以前に疑問として挙げましたが、四代目八兵衛の墓は「大濱」、
五代目正禎の墓は「前大濱」になっているからです。
このことは、直益が初代から三代までの墓を「阪本」姓で建立したときには、
四代目、五代目のものは既に建てられてあったことを示しています。
五代目正禎は元文三年(1738)に70歳で亡くなっていますが、その
墓を建立したのは当然のことながら六代目直益です。その直益が「前大濱」
としたのですから、その頃には既に郷士に取り立てられることが決まって
いたとしか思えません。
ということは、質屋を始めてから70年余りで、そこまでのし上がった
ことになります。
太郎五郎の田畑は僅かに七反ちょっとしかありません。これにソバ・芋・
小豆といった雑穀を栽培するための切畑が三反余りあるだけです。
1反=300歩、1歩=400/121m2ですから、
7反=7×300×400/121=6942m2
つまり7反は83.3m四方の広さでしかありません。
弘治・永禄の頃に移り住んだとするなら、三十ニ、三年も経っているのに
これだけしか開墾できていないのは疑問です。天正十年であれば、六年間
ですから、納得できるのです。
しかも検地帳によると耕地のランクは「下」に属するというのですから、
作付面積に比べて収穫量はかなり低いものであった筈です。
どうやって生計を立てていたのでしょうか。
それが四代目の八兵衛に至って(寛文六年、1666)城下で質屋を
始めたのですから、天正十六年(1588)から数えても、僅か80年
足らずで、荒地を耕してその元手を手に入れたことになります。
眠る龍馬の墓標には「坂本龍馬紀直柔」と刻まれてあります。源氏では
なく紀氏だというのです。
これについても先祖書に坂本氏は紀武内の子孫であると記してあります。
紀武内とは孝元天皇の曾孫である武内宿禰(すくね)のことで、俄には
信じがたいことですが、その末流の坂本氏を先祖とすると云うのです。
初代から三代の墓を建立した直益は、国学に傾倒していましたので、
『日本書紀』を紐解いて、「坂本」という姓から、任那の戦で功のあった
坂本長兄(ながえ)や、天武天皇が皇太弟になったときに、その将と
なって高安城を攻め落とした坂本財(たから)を引き出してきて、その
始祖である武内宿禰に至ったのかも知れません。
このことは初めに坂本ありきということを物語っていることになります
ので、やはり「譲受郷士」であったのかと思ってしまうのですが、そうでも
なさそうなのです。
なぜなら、先祖書には「明和八年五月二十七日に新規郷士に召し出される」
とあるからです。
そこには「(太郎五郎の)生年月日や享年は分からないが、某氏を娶り
一男を産む。(その男子の名は)彦三郎と云う」とあります。
彦三郎は二代目ですが、その生年は、先に挙げた龍馬の父八平直足の
手になる先祖書にしっかり書かれてあります。そこには「元亀二年
(1571)出生」とあります。
であるならば、明智光俊が自刃した天正十年(1571)の時は、数え
で12歳ということになります。
さらに先祖書には彦三郎の妻についても触れています。そのひとは、
大和国吉野の武将須藤加賀守の次女で、須藤加賀守が戦死したときに、
姉のおかわと弟との三人で土佐の須江村という所に落ち延び、やがて
太郎五郎の許へと嫁いだというのです。
畿内(大和国)というキーワードが出てきましたね。しかも、彦三郎の
出自がただ者でないことも暗示しています。
こざと偏は旁(つくり)のおおざとと同様に、「里」の意味があります。
また、「こざと」は漢字では「阜」と書きます。岐阜の「阜」です。
「岐阜」の名は、『信長公記』によると、織田信長が美濃国を攻略した
際に、稲葉山の城下の井ノ口を岐阜と改めたとされています。
信長の攻め滅ぼした相手は、稲葉城城主の斎藤義竜でした。永禄十年
(1667)のことです。
その由縁は、中国の周の文王が八百年の泰平の世を築く出発点となった
ところが「岐山」で、孔子の生誕の地が「曲阜」で、その両方を併せて
「泰平と学問の地ならん」と名付けたと云います。
つまり、「阪」は太郎五郎らの出身地もしくは出自を暗に示しているの
ではないかととも考えられるのですが、しかし畿内というと、京都に近い、
山城・大和・河内・和泉・摂津の五ヶ国をいいますので、明智城のあった
美濃や坂本城のあった近江は含まれません。
土佐国長岡郡植田郷才谷村に住み着いた」と刻んであるのですが、
そうだとすると、弘治元年(1555)~三年(1557)、永禄
元年(1558)ですから、山崎の合戦が起こった天正十年(1582)
とは二十数年の開きがあることになってしまうのです。
質屋の屋号「才谷屋」は、この村の名に由来しているのですが、
読みは「さいだに」と濁ります。ですから、龍馬が近江屋で暗殺に
あったときに名乗っていた変名の「才谷梅太郎」も「さいだにうめ
たろう」が正しい音になります。NHKの「龍馬伝」では、ここの
ところをよくチェックしてくださいね。
しかし、弘治二年(1556)には美濃の斎藤道三が、息子の義竜と
戦って敗死しています。
この内乱では、道三に与していた明智一族も明智城に火を放って、それ
ぞれ逃れることになります。光秀と従兄弟の三宅弥平治(光俊)も二人
して越前に落ちていきました。
あっても粗末なものだったのでしょう)ときに、いずれもが「阪本」
としてあるのに、建立者(直益)名には「坂本」を使用しているの
です。
自分の代からなら分かりますが、遡ってまで普通はしないものです。
それに何故「阪本」と「坂本」を使い分けているのでしょうか。
加えて四代目と五代目の墓は「大濱」のままというのも不思議です。
しかも直益の父正禎の墓と直益本人の墓に刻まれた家紋は「丸に田」
つまり丸で囲った轡紋なのです。
明智末裔伝説の最大の根拠である桔梗の家紋が直益の墓に刻まれて
いないのも大いなる疑問です。
手に入れた郷士株の名跡が坂本氏であって、家紋付きでそれを継承
したようにも思えますが、それであったとしても上記の疑問には答
えてくれません。
その当時、郷士になる場合、「譲受郷士」(売買で手に入れる
もので、その場合、その氏をも相続する)と「新規郷士」(新田
開墾や献金などの功績によるもの)とがありましたが、坂本氏が
そのいずれであったかは、この後を引き続き読み進めて頂けば
お分かり頂けます。
までは農業を営んでいて姓そのものが無かったのです。
(ここからが僕のところと違うのですが)
四代目の八兵衛になって高知城下で才谷屋という質屋を始め、
やがて土佐藩への貢献が認められて、大濱姓(諱守之)を追贈
されます。
なぜ大濱なのかと云いますと、天保九年に藩命により龍馬の
父八平直足が提出した先祖書、その家系図の初代太郎五郎の脇に
「言い伝えでは、生国は山城国(京都府)で、郷村まではよく
分からないものの武士として仕えていたが、患ったため戦の難
を避けるために土佐国の長岡郡才谷村に移り住んだ。冬の十二月頃
という。代々大濱屋敷に住んだので、子孫が大濱を名乗るようにな
った」(意訳)とあることから分かります。
五代目の八郎兵衛のときに年寄役となり初めて大濱正禎(まさよし)
と名乗るようになります。
六代目の直益のときに郷士に取り立てられて、その長男直海が坂本家
の初代郷士となり、次男の直清に才谷屋を継がせます。
そして、龍馬の父直足が三代目郷士となるのですが、二代目郷士
の直澄には娘(幸)しかいなかったので、白札の山本家の次男で
あった常八郎が女婿となって、名を八平直足(なおたり)と改め
て、坂本家の家督を相続します。
(坂本氏の家紋が「違い桝桔梗紋」であることから、桔梗紋
の明智氏と何か関係があるのではないかと。)
光秀の甥でもあり女婿でもあった明智佐馬介光俊(小説では
「光春」となっています)が琵琶湖近くの坂本という地に
あった坂本城の城主でしたので(坂本城が落ちたときに、
光俊は自刃しますが)、その妾腹の子が土佐に落ち延びて、
その後士分に取り立てられたときに、明智姓では支障があると
して、所縁のある地名「坂本」を名乗るようにした、という
のです。
この坂本城について、ポルトガルの宣教師ルイス・フロイス
の『日本史』では、「豪壮華麗なもので、信長が安土山に
建てたもの(安土城)に次ぎ、この明智の城ほど有名なもの
は天下にないほどであった」と記述されています。
光秀が丹波の亀山城(本能寺へ向った軍勢はここからです)
に移ってから、光俊が居城としたようです。
それだと「明智」というか、その落ち武者繋がりで、それなり
の縁があるじゃん、なんて糠喜びしていたのですが・・・。
ご存じのように山崎の合戦で秀吉軍に敗れ、光秀は
落ち武者狩りに遭って落命しますが、家臣の幾分かは命
からがら海を渡って未だ信長の覇権の及んでいなかった
四国(長宗我部元親のもと)に逃れたらしいのです。
四方田又兵衛もそのひとりで、讃岐に流れ着き、そこで
農民として土着しました(ということです)。
四方田氏は元々は但馬の出石辺りの豪族で、光秀が丹後・
丹波を切り従えていったときに、その傘下に加わりました。
そして明治の世を迎えて、姓が許されるようになったとき、
元の四方田(よもだ)ではなく、出身地である出石を姓と
したとのことです。
それだけ勝者側の付けた「逆賊」という汚名への拒絶反応
が強かったのでしょう。(それで念にも念を入れて、読み
までも若干違えたのかしらん?)
最後の将軍足利義昭のために信長が造った邸宅で、
丸太町通と烏丸通の交差した角(現在の二条城の北東
辺り)にありましたが、本能寺の変で焼失しました。
信長は本能寺には70余人の小姓や女中しか引連れて
いませんでしたが、近くの妙覚寺には信長の長男信忠
の率いる2000ほどの軍勢がいました。
しかし、光秀の率いる約13000の軍勢の前には
物の数ではなく、信長ともども信忠も自刃して果てます。
信忠の自刃した場所が二条城(本能寺の変を知って、
妙覚寺から手勢を引連れて駆けつけるのですが、本能寺
に近づくことができず、兵500ほどと二条城に立て籠
もって防戦した)でしたので、信長が二条城に宿陣した
としても結果は同じであったと思います。
*2この発句、後に秀吉から色々と糺されたようで、そのとき
に連歌師の里村紹巴が秀吉に差し出したものでは「天が
下知る」のところが「天が下なる」と直してあったとか、
またある資料では「あめが下くる」となっていたりします。
でも、そのときの光秀の心境を考えると、やはり「天が
下知る」が最も相応しいと思います。
「とき」は「土岐」(明智氏は土岐氏の支流、土岐氏は源
頼光を始祖とする)とも読めますし、「天が下知る」は
「天下をすべておさめる」と解釈することができるから
です。平氏である信長と源氏である光秀、そんなことも
謀反に関係しているのかも知れません。
出石という苗字、随分変わっているでしょ。
生まれは香川県の高松市ですが、遠い遠い先祖は
山陰の小京都と呼ばれる兵庫県但馬の出石(いずし)
に居たそうです。
自分の目で先祖書を確かめた訳でもなく、亡父が嘗て
語ったところだけを信用すると、明智光秀の重臣に
四方田但馬守政孝というひとが居て、その甥の又兵衛
というのがその先祖だそうです。
吉川英治の『新書太閤記』によると、その四方田又兵衛
は光秀の寵臣のひとりであったようで、光秀の密名を
帯びて安土城にいる織田信長の動静を探り、京都での
宿陣先が二条城*1ではなく本能寺であることを探り当てます。
そして、その報が光秀の揺らぐ心を定めます。とはいえ、
愛宕山の愛宕権現に参詣し、引いた神籤(みくじ)が「凶」
、次も「凶」、やっと「大吉」と、三度までも引いている
ところを見ると、まだ揺らいでいたのですね。
そして翌五月二十八日、愛宕権現の西坊の連歌会で有名な
発句を詠みます。「ときは今 天が下知る 五月かな」*2。
取り組みました。中でも僕が好きだったのはタンゴの楽曲で、「エル
チョクロ」「奥様お手をどうぞ」「ヘルナンドスハイダウェイ」など
です。
就中好きだったのが「エルチョクロ」で、左手で相手の右手を握って、
右手は相手の腰に手を当てて、ぐっと引き寄せて反った相手を抱くよう
にして踊ります。さすが情熱のタンゴ、若い僕らには少しく刺激的で、
魅惑的で、蟲惑的ですらあって、胸の鼓動もタンゴのリズムに波打って
いたように思います。
TVを見ていて、「ああ踊りたい」とつくずく思いましたが、ステップを
思い出せるかどうか自信がありません。それに、胸打つリズムは不整脈
でしょうしね。
一学期までをフォークダンスに打ち興じていたのです。(三年生の
二学期は受験対策で授業が無かったのです。)
部員はさほど多くなく、十数名で踊っていたので、彼女と踊る機会も
自然と増えます。
後夜祭などでは、校庭の中ほどに薪を焚いて、その周りに輪を描く
ようにして全校生でフォークダンスを踊るのですが、そこでは上記の
曲の他に新しいものも加えます。「第三の男」とか「ワシントン広場
の夜は更けて」などです。そのときが唯一僕ら部員の活躍時で、手本
に踊って見せるなど、指導に当たります。
の姿があります。そのうちの一人は、何とついこの間まで僕と一緒
に竹刀を振っていた仲間ではありませんか。
そこに誘われるでもなくつい顔を出したのが剣道との終の別れと
なりました。
正直に告白しますと、目を凝らした先、彼らの横には、ひとりの
美少女の姿があったのです。
彼女は入学したばかりで、おそらく音楽は以前から流れていたので
しょうが、彼女の姿を目に留めるまでは僕の耳を素通りしていたの
です。
ので、体育館がありませんでした。
ですから体育の授業のみならず体育系のクラブ活動は、校庭か
校舎屋上で行っていました。(雨が降れば中止です。)
僕は剣道部に入部しましたので、池上本門寺までマラソンさせ
られたり、そこの階段でうさぎ跳びさせられたり、といった荒行
を除いては、殆どを屋上で素振りや掛り稽古をしていました。
そうして一年が過ぎた或る日のこと。
横合いから楽しそうな音楽が流れてきたのです。
ので、「高校三年生」のところで語り足りなかったことを
少しばかり・・・。
オクラホマミキサーはアメリカの、マイムマイムはイスラエルの、
そしてコロブチカはロシアの民謡で、それぞれに振りが付けられて、
祭事などで踊られるようになったものだと云います。
日本の炭坑節のような盆踊りもその仲間に数え上げることができ
ますが、老若男女が手を繋いで仲良く踊るというところが違います。
上から下に落ちるというイメージが縁起悪いとのことで、当時
飛ぶ鳥を落す勢いであったフジテレビプロデューサーの千秋
与四夫の威光にあやかって、その苗字を読み替えて「ちあき」に
決まったそうです。
当時、いしだあゆみの「ブルーライトヨコハマ」が大ヒットして
いたこともあって、ひらがなだけの芸名でもOKと相なりました。
そしてデビューのときのキャッチコピーは「苗字がなくて名前が
ふたつ」。
龍馬の忌み名も最初は直陰だったのですが、「陰」の持つイメージ
を嫌って直柔(なおなり)に変えています。「ちあきなおみ」も
柔らかくて丸みがあって、中々に好い芸名だと思います。
以上、ややこしい関係のお話でした。
が坂本龍馬の熱烈なファンで、直道(なおみち)の「なおみ」
のところを龍馬にあやかって使用したということなのですが、
直道の了解を取ったか否かまでは定かではありません。
(吉田氏は業界を去った後、赤坂で焼肉の店を開いていたの
で、そのときにでも確認しておけばよかったのですが、その
うちに店を畳んで、病を得て、亡くなられてしまいましたので
残念ながら確かめようもありません。)
龍馬の長姉千鶴の長男であった高松太郎が名を坂本直と改めて
継ぎます。二代目はその次男(長男は夭折)直衛が継ぎますが、
喧嘩がもとで死亡してしまい、跡目が絶たれます。
そしてやや時が経って、直の実弟直寛の長男直道が跡目を相続
します。
この直道がちあきなおみの名付け親ということなのです。
直道は、昭和47年に享年80で亡くなっていますが、ちあき
なおみがデビューしたのがその三年前の昭和44年ですから、
有り得ない話ではないのです。
といっても、やましい関係ではありません。
龍馬が慶応三年十一月十五日(1967.12.10)に暗殺されてから
四年後の明治四年八月二十日、太政官政府から龍馬の家名を
新たに建て、永世禄十五人扶持を下賜する旨の特旨が下り
ます。
一人扶持は日に米五合ですから、一年間には五俵の支給と
なりますので、十五人扶持だと年に七十五俵になります。
石数にすると二十七石余りですので、下級武士並で大した
ことはありませんが、何代にも亘って未来永劫頂ける年金
のようなものですから、バカにはできません。(残念ながら
大日本帝国とともに終焉となりますが。)
隠語にも面白いものがあります。
例えば、トイレは「遠方」、食事は「きざえもん」と云います。
不浄な便所は店先から遠いところにあったから、台所を取り仕切って
いたのが「きざえもん」さんだったから、なのでしょうか。
昼食は無料です。朝出勤したときに「きざ券」と称するものを1枚与え
られます。これでビル1棟が食堂になっているところで、定食を食べる
ことができます。
偶に忙しくて残業となるときがあるのですが、そのときには夕食の
「きざ券」が与えられます。
ですから、お金を使うのは煙草代くらいで、時給は幾らであったか忘れて
しまいましたが、期間は短かった(1週間くらい?)ものの、ちょっと
した小遣い稼ぎにはなりました。
今年はまだ暖かい日が続いていますが、木枯らしが吹く季節になると、
既に40年前後の歳月が流れているにも拘らず、当時を懐かしむ思いが
込み上げてきます。アートシトッタナー
たかったのですが、なぜそうなったのか理由は分かりませんが、
「受渡し」という部署に回されました。(もっとも班ごとにスピ
ードを競ったりしたものですから、僕も混ぜてもらって、色々な
重さ、形の商品の包装を覚えさせて貰ったものです。箱詰め石鹸
が一番包みやすくて、一つ包装するのに1秒も掛からなかった
くらいに習熟しました。)
「受渡し」というのは、包装された商品を伝票と照らし合わせて、
間違いの無いことを確かめる仕事で、包装紙の端を留めたビニール
テープの両端に小さな四角い検印を押しながら、数を確認します。
ですから通常は三越の社員(もしくは就職内定者)が務めます。
最初のときに何らかの理由で欠員が出て、不運にも僕が選ばれた
のかもしれません。
僕以外は皆三越の社員ですから、休憩時間になっても、その休憩所
は決して居心地の好いところではありません。それでも何一つ不平
を漏らすことなく、静かに出涸らしのお茶を啜っているのを見て、
四年間、同じ仕事をあてがってくれたのかしらん。
貿易センターを期間中だけ借り切って設営された)配送センターで、
集荷された商品を、包装して、伝票を貼って、紐掛けをして、出荷
できるまでにする仕事です。
大体は、体育会系の学生がグループでやって来るのですが、僕の
ように友人と2人でなんていうレアケースもあります。
このアルバイトが気に入っていたのには、いくつかの理由があり
ました。
ひとつは、接客の仕事よりも若干ながらも時給が好かったこと。
ひとつは、作業着が支給されたので着て行くものに頓着せずに
済んだこと。
今ひとつは、バスで送り迎えをしてくれたことです。朝は大井町
駅前から、夕方は東京駅前まで送迎してくれました。晴海の貿易
センターは交通の便の悪いところでしたので大変助かりました。
それに、ちょっとした遠足気分に浸れて、帰りのバスでは当時流
行っていた「ラブユー東京」などを皆で合唱したりしたものです。
のですが、最近では十一月末に贈るひともあるほど、世の中
忙しくなっているようです。
僕が学生であった頃、歳暮のとき(だけでなく中元のときも
そうでしたが)には三越デパートでアルバイトをしていました。
それも四年間皆勤です。
夏休みは7月11日からでしたので、中元時期とぴったり合う
のですが、冬休みは12月21日からでしたので、当時は字義
通りの歳時だったわけです。
のときでした。当時、オクラホマミキサー、マイムマイムそれにコロ
ブチカなどのフォークダンスを校庭で踊ったりしたこともあって、高校、
中学の違いはありますが、この歌を大変身近に感じたものです。
丘は作詞で「♪フォークダンスの手をとれば、甘く匂うよ黒髪が」の
ところが一番最初に出来たと後になって述べていますが、丘の青春時
代には男女間には未だそのような自由が無かったので、前年に訪れた
高校の文化祭で男女が踊る光景を見て衝撃を受けたそうです。そして
その詩がまず心に浮かんだそうです。
それと丘は、西条八十に師事して作詞を学んだのですが、師から唯一
褒められたのがこの「高校三年生」だったそうです。
舟木一夫の学園三部作(「高校三年生」「学園広場」「修学旅行」)
は、残念ながら「学園広場」だけは関沢新一の作詞ですが、いずれも
同じ年にヒットし、私たちの心に決して朽ちることの無い、甘酸っぱい
感傷の歌碑を深く刻み付けてくれました。合掌。
作曲(遠藤実)、作詞の両大御所が鬼籍に入られたわけです。
今から7年前(平成14年4月13日)には、舟木一夫と三人
揃って福島県の郡山駅前に建てられた歌碑の除幕式に元気な
姿を見せていたのに。
丘は体が病弱だったため、鉛筆1本で出来る仕事として、新聞
記者(毎日クラブ記者)と作詞家の道を選んだそうです。
虚弱体質ではありましたが、92歳の長寿を全とうしたのですから、
(無病息災ならぬ)一病息災とはよく云ったものです。
丘は除幕式の席で、「私はこの世であんまり歌を作りすぎたので、
今度はあの世で歌を作って舟木さんに歌を贈ります」と述べて
笑を誘ったそうですが、「千の風になって」のような詩を、もう
鉛筆舐め舐めして作り始めているのでしょうか。
①紅い花(11/14⑰と同じ映像)
②黄昏のビギン
③夜間飛行
④かなしみ模様
⑤かもめの街
⑥雨に濡れた慕情(オリジナル)
⑦四つのお願い(11/14③と一部同じ映像)
⑧私という女(オリジナル)
⑨港が見える丘
⑩上海帰りのリル(カヴァー)
⑪すみだ川(カヴァー)
⑫柿の木坂の家(カヴァー)
⑬さだめ川(オリジナル)
⑭酒場川(オリジナル)
⑮矢切りの渡し
⑯それぞれのテーブル(シャンソン)
⑰ラ・ボエーム(シャンソン)
⑱霧笛
⑲秘恋(ファド)
⑳星影の小径(11/14⑪と同じ映像)
21冬隣(オリジナル)
22うかれ屋(オリジナル)
23夜へ急ぐ人
24朝日のあたる家
25劇場(オリジナル)
26喝采(11/14①と同じ映像)
27紅とんぼ
感慨無量!∞
流れました。
それぞれの内容は、
◆11月14日(土)『歌伝説 ちあきなおみの世界』
①喝采(オリジナル)
②紅とんぼ(オリジナル)
③四つのお願い(オリジナル)
④X+Y=LOVE(オリジナル)
⑤夜間飛行(オリジナル)
⑥かなしみ模様(オリジナル)
⑦矢切りの渡し(オリジナル)
⑧朝日の当たる家(アメリカ民謡)
⑨夜へ急ぐ人(オリジナル)
⑩粋な別れ(カヴァー)
⑪星影の小径(カヴァー)
⑫港が見える丘(カヴァー)
⑬帰れないんだよ(カヴァー)
⑭ねえ、あんた(オリジナル)
⑮霧笛(ファド)
⑯かもめの街(オリジナル)
⑰紅い花(オリジナル)
⑱黄昏のビギン(カヴァー)
⑲喝采(オリジナル)
の兄権平や姉乙女、そして平井加尾も就いていた)ので、
その関係なのかも知れませんね。
そして、その門人仲間が芸歴に応じて順番に書き込んだ
のかも。
姉を訪ねて遣って来る加尾に恋慕の念を寄せた龍馬が、
頻繁に会えるようにと入門したのかも知れません。
そういったアグレッシブさが龍馬の持ち味ですし。
さて、この胴掛を渡すシーン、「龍馬伝」では用意されて
いるのかしらん。
裏面の右半分には三太、龍馬の順で、そして十右衛門の
和歌は裏面の左半分に後で縫い付けてあります。
年齢の順でないことは明らかで、皆軽格の家柄ですが、
清平は上士(山内侍)と下士(長曾我部侍。坂本家の
ような新規取立て郷士も含まれる。郷士以下の家格)との
間に位置する白札であって、他の四人よりも家格は高い
のですが、内蔵太は、三太や十右衛門の家格である用人
よりも低い徒歩(かち)ですので、そういった基準でも
なさそうです。
吉村三太、そして宮崎十右衛門の四人(と思えます)。
清平の生年は不詳なのですが、弟の望月亀弥太が天保9年
生まれですし、龍馬の手紙には清平のことを「大兄」と
してありますので、龍馬(天保6年生まれ)よりも年長
だけども、それほど歳は離れていないと思います。
内蔵太(くらた)は天保12年生まれ、三太は天保7年
生まれ、そして十右衛門は生年不詳ですが皆とはそんな
に歳が離れていないように思います。
しっかり「胴掛」と書いていますしね。
寸法が縦36cm×横32cmもありますし、それを二つ折り
(36×16)にして使用するように折癖もついているそう
です。
胴掛は三味線を弾くときに、三味線の胴の下に敷いて、
撥を持つ手のすべりを止めるためのものですが、加尾は
一絃琴(いちげんきん。長さ三尺六寸、つまり1m余り
の、桐や杉で作った胴に一本の絃を張った琴)を習って
いたので、そちらでも使用するものなのかも知れません。
誤りがあったので訂正します。
もうじきNHK「龍馬伝」が始まりますし、加尾の
出番も早そうなので、「あれっ違うじゃん」なんて
思われるのも癪に障りますし・・・。
加尾が山内容堂の妹友姫に付き添って郷里を後にする
ときに、龍馬とその友人が寄せ書きして加尾に贈った
袱紗。その中の和歌「あらし山 花にこころの とまる
とも 馴れしみ国の 春なわすれそ」を加尾本人のもの
としましたが、「春なわすれそ」は、「な」(副詞)と
「そ」(終助詞)とが呼応して禁止の意味を表しますので、
「(生まれ育った土佐の)春を忘れないでください」と
なり、加尾への送辞としか考えようがありません。
第一、送別品に、贈られた本人が書き込む筈は無いです
ものね。
では誰が、となりますが、署名に「八本こ(やほこ)」と
ありますので、「八矛」の号を持つ、宮崎十右衛門と
考えられています。
ひとつは、大きな作品を制作する場合など、沢山のパステル粉末が
飛び交いますので、咽喉を痛めたりします。特に冬場は部屋を閉め
切っての制作になりますので、息苦しくともマスクは必需品になり
ます。
いまひとつは、作品の保存方法です。制作中は、画板にそのまま画鋲
で留めて、何処かに立て掛けて置けばよいのですが、完成した作品は
硝子の嵌め込まれた額縁に入れて飾ることが出来れば、それに越した
ことは無いのですが、全てそうすることは出来ません。そのような
場合には、パラフィン紙で表面を覆って、カルトンなどに挟んで、
擦れないように保存しなければなりません。
このページに臆面も無く載せた「サッフォー」ですが、額縁に入れて
あるので、硝子に外光や室内の明かりが映ったりするので暗いところで、
しかもフラッシュの光も映ってしまいますので、それも使用せずに
撮りました。それでも薄明かりが差していますので、僕のカメラを
持って差し出した手がちらっと写ってしまいました。額縁から絵を
取り出して撮れば良いのですが、そのときに擦れたりするのが怖いの
です。育てるのは比較的に楽なのですが、成人してからが大変なんです、
ぱすてるくんは。
パステル画の便利なところは、描き損じても、消しゴムで簡単
に消すことができる点です。
それだけでなく、ハイライトなどの効果を出す場合にも消しゴム
を使ったりします。(僕の場合には、殆どが前者で使用していま
すが。)
フィクサチーフというスプレータイプの定着液を使用するひとも
います。
指や擦筆などでゴシゴシ擦り込んでも、それでも定着力は弱く、
何かに触れただけで、その箇所は擦れてしまって、描き直さねば
ならなくなったりします。そういったことを防ぐために定着液を
用いるのですが、発色が悪くなったりして、折角のパステルカラー
が台無しになったりすることがあるので、僕は使っていません。
(厚塗りなど、色を塗り重ねる場合に使用することもあるようです。)
僕は、ソフトパステル、ハードパステル、パステル鉛筆を
使用しています。今は150色もあるソフトパステルを使用
していますが、未だに色に迷うほどで、初めて学ぶひとは
36色のもので良いと思います。
ソフトパステルだけでも構わないのですが、エッジの効いた
強い線を描いたりする場合にハードパステルを用いたりします。
パステル鉛筆は、繊細な線など細密な表現を必要とするとき
に使用します。(普通の色鉛筆だと、そこだけがツルツルと
光ってしまいます。
さて筆ですが、まず10本の指が筆代わりになります。紙に
描いたパステルの粉末を、ゴシゴシと紙に擦り込むのが指の
役目です。汗腺から滲み出る油まじりの水分が役立つのか
どうかまでは存じませんが、ボカシなどの色調を上手く出す
ことができます。塗る箇所の広さなどに応じて親指を使ったり
小指を使ったり、また色が混じらないようにあれやこれやの
指を使用したりします。
指だけでも良いのですが、擦筆(さっぴつ)という用具も
使ったりします。
擦筆は、紙を何重にも巻いたもので、先が尖っています。
硬い材質のものと、軟らかいものとがあって、前者は強い線
を描くときなどに用いて、後者は広い面をボカスように塗る
場合などに使用します。どちらも細いものから太いものまで
何種類もあって、塗り込む線・面の違いに応じて使い分けます。
大丈夫というところが、パステル画の魅力でもあります。
僕がパステル画に惹かれる直接の切っ掛けとなったのは、
パステル画の巨匠でもあったドガの「舞台の踊り子」と
いう有名な絵でした。
それから実際にパステルを手にするまで時間がかかりまし
たが、30代に入ってから意を決して、道具を一式揃え
ました。
まずは用紙です。
パステルは、水で溶いた顔料をアラビアゴムなどの薄い
溶液で煉って棒状に固めて乾燥させたものですので、定着
力が弱いのが特徴です。
ですから、紙にゴシゴシ擦り付けて着色させる必要があり
ます。そのためには、ケント紙のように表面がツルツル
したものではなくて、表面の凸凹が目立つ、目の粗い紙を
使用します。
パステル用紙には、沢山の色数のものがあります。
ルノワールは、肌を描くときの下地に赤を引いて温かみの
ある色調を作り出していますが、パステルでは基本的には
このようなことは出来ませんので、下地として赤い紙を用
いたりします。
同じ色を使って絵を描いても、下地となる紙の色によって
まったく趣の異なる絵に仕上がりますので、テーマに応じた
色の紙(目の粗さも風合いに関係しますが、ここではカット)
を選ぶことが肝心です。
水彩は、手軽ですが、塗り重ねに不向きであったり、
発色の面でも物足らなさを感じます。
油彩は、発色も良いし、重ね塗りも出来て、僕のように
アレコレ手直ししたがる往生際の悪い者にとっては有難
いものですが、不注意で服などに付いた絵の具を落すの
が大変であったり、使用した絵筆やパレットなどの後片
付けが面倒であったりして、僕のようなウッカリ者の面
倒臭がり屋は、つい敬遠し勝ちです。
それにどちらも下の色が乾かないと色を重ねることが
出来ないので、僕のようなセッカチな者にとっては途中
で戦意喪失となり兼ねません。
その点、パステルは子供のときから使い慣れているクレ
ヨンやクレパスのように(それらに比べて多様な表現が
可能ですが)簡単に扱えて、油彩よりも発色が良く、重ね
塗り(も可能ですが)などせずに済むほどに色数が多く、
その上、あちこち汚しても水で洗い落せるのですから、
まさに僕のために天が与え賜うたような絵の具だったわけ
です。