白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんの、ビルコック(Billecocq)神父様による哲学の講話をご紹介します。
※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております
Billecocq神父に哲学の講話を聴きましょう
また、ルソーは特に生徒の自律について強調しています。
「自然人は自分がすべてである。彼は単位となる数であり、絶対的な整数である」
ですから、御覧の通り、人間は社会の一部ではないということです。人は自律した全体であり、絶対的な単位だと。絶対的ですよ。
「自分に対して、あるいは自分と同等のものに対して(他人を一応認めますね)関係を持つだけである。」
「社会人は分母によって価値が決まる分子にすぎない。この価値は社会という全体との関係において決まる。」
ですから、ルソーにとって、社会に入ると人間は自分の本性が否定されると言います。なぜかというと、全体として自分がなくなるから、社会は反自然(本性に反する)からだと。
「立派な社会制度とは、人間をこの上なく不自然なものにして、」 明記していますね。「絶対的存在を奪いさって、相対的な存在をあたえ、」ルソーにとってこれこそは人を腐敗させます。
「「自我」を共通の統一体の中に移すような制度である。そこでは、個人の一人一人は自分を一個の人間とは考えず、その統一体の一部分だと考え、何ごとも全体においてしか考えない。」
要するに、社会は人間を反自然な存在にし、「自分において自分自身であるという絶対的な存在かつ全体」としての性格を奪うので、社会は人々を堕落させると。これは、ある種の実存主義の始まりだとみてもよいでしょう。以上は人間の自律についての部分でもあります。
次の引用の最後の部分に移します。
「生きること、それが私の生徒に教えたいと思っている職業だ。」 繰り返します。「生きること、それが私の生徒に教えたいと思っている職業だ。」「生きることは、それは呼吸することではない。活動することだ。私たちの器官、感官、能力を、私たちに存在感を与える体のあらゆる部分を用いることだ。」
ルソー論だと、いつも「自分」が中心です。
「もっとも長生きした人とは、最も多くの歳月を生きた人ではなく、最も良く人生を体験した人だ。」
体験とかは、まさに、「自分中心」主義ですね。純粋な個人主義だといえます。現代風にいうと、「生きるとは、充実していることだ」といったような感じですね。「彼は好きなことをやったらそれでよい」といった発想です。「多くの体験をして、やりたいことをする人生を送るのが良いことだ、それが生きていることなのだ」といった感じです。
「百歳の葬られる人が、生まれてすぐ死んだのと同じようこともある。そんな人は、若いうちに墓場に行った方がましだったのだ。せめてその時まで生きることができたならばのはなしだが。」
ルソーの教育論の目的です。「生きること、それが私の生徒に教えたいと思っている職業だ。」
要するに、人間の目的は「自分自身」であり、「自分自身」に従っての人間だと言います。
続いて、ルソーはいくつかの「偏見」を非難します。
「私たちの知恵と称するものはすべて卑屈な偏見にすぎない。私たちの習慣というものはすべて屈従と拘束にすぎない。社会人は奴隷状態の内に生まれ、生き、死んでいく。」
また出てきましたね。以前にもみたとおり、ルソー主義の中心となる概念がまた出てきます。「自由」です。自分のために人間が生きなければならないのは「完全に自由になる」ためです。自分が自分自身の主である、これがルソーの目的であり、自律するのは絶対的な目的だとするのがルソーのスタンスです。従って、ここに、実存主義の始まりが潜んでいます。というのも、近代的な実存主義でいうと、つまり、サルトルから流行ってきた実存主義だと、「人は自分自身を自分の力で形成していく」とされています。

「自分自身はなんであるかを自分自身で決める」が実存主義だからです。つまり人は実存するのだから、活動していることによって存在理由を持つ、やりたいことをやって存在理由を持つと説明します。シモーヌ・ド・ボヴォワール(Simone de Beauvoir)は「生まれながら女性ではなく、女性になる」といった有名な発言は象徴的です。現代においてまさにそういった空気ですね。
それはともかく、これは何を意味しているでしょうか。「個人が全体であるから、自分自身の望み通り、やりたい放題で自分自身を形成する力がある」ということの断言です。ですから、「自分自身の形成」あるいは、現代風にいうと「自己実現」の裏に、自由という前提があります。限りのない自由がなければ「自分自身やりたい放題に実現できない」からです。
自由というのはやはりルソーの思想の根本的な中心なる理想です。ルソーは続いて、奴隷について次のように語ります。
「生まれると産衣にくるまれる。」生まれたばかりなのに、もう奴隷になると言います。
「死ぬと棺桶にいれられる。」まあ、これも奴隷の一種かなあ。今、死んだルソーはそれについてどう感じているかは知りたいぐらいですね。
「人間の形をしている間は、社会制度に縛られている。」
それから、かなり時間がかかりましたが、いよいよ出てきますよ。文章はのびのびしていますが。次の引用になる前に、母の役割についてちょっと触れます。母の役割に関しては、常識的なことを口では言います。また、父の役割についてもちょっと触れます。ルソーが「子供には父と母が必要だ」といっているから、それだけは常識的だと認めざるを得ません。
しかしながら、ルソーの文章の流れにおいて以上の意見は逆説です。ルソーの文章にはいったん、直感的に常識的なことを言っていることはもちろんあります。しかしながら、次に、同時に逆なことを遺憾なく述べていきます。「母と父が子供に必要だ」といっているのに、次はその教育論において母と父は完全に否定されていて、取り消されています。というのも、エミールを教育するのは家庭教師しかいないのですから。父と母の存在はどこにもありません。さすがにルソーです。優しい夢想家のルソーです。
「そこでわたしは、一人に架空の生徒を自分に与え」ここではルソー自身が言っていますね。「わたしは」です。
「そこでわたしは、一人に架空の生徒を自分に与え、その教育にたずさわるにふさわしい年齢、健康状態、知識、そしてあらゆる才能を自分がもっているものと仮定し、その生徒を、生まれた時から、一人前の人間になって自分自身のほかに指導する者を必要としなくなるまで導いていくことにした。」
面白いでしょう。社会は一切子供を導くことはない、法は一切子供を導くことはないと。象徴的でしょう。
「この方法は自分の力を危ぶんでいる著者が幻想に迷いこむのをふせぐのに有効だと思われる。ふつうの方法から離れることになったら、生徒に自分の方法を試してみればいいことになるので、子供の進歩と人間の心の自然の歩みに従っているかどうか、彼にはすぐにわかってくる、あるいは、彼のかわりに読者にわかってくることになるからだ。」
要するに、ここで、架空の生徒を作ります。「エミール」と名付けます。また家庭教師を与えます。家庭教師から見ましょう。次の引用です。
「ただ注意しておきたいのは、一般の意見に反して、子どもの教師は若くなければならない」
教育者として「さすが」な意見でしょう。
「賢明な人であれば、できるだけ若い方がいい、ということだ。できれば教師自身が子どもであれば」
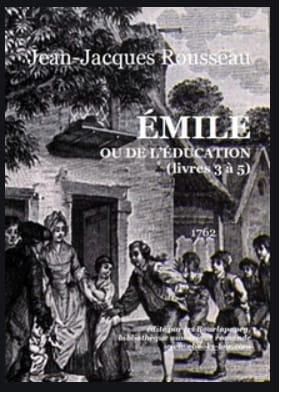
御覧の通り、現実を知らない小説にすぎませんね。
「生徒の友だちになって一緒に遊びながら信頼を売ることができれば、と思う。子どもと成熟した人間とのあいだにはあまり共通なものがないし、そんなに年齢の差があっては十分にかたい結びつきは決してできあがらない。子どもはときに老人に媚びることもあるが、決して老人を愛することはない。」
また次に出てきます。
「それに、この学問の先生は教師ではなく、むしろ師傅(しふ)と呼びたい。教えることよりも導くことが問題だからだ。彼は教訓を与えるべきではなく、それを見出させるべきだ。」【師傅(しふ)とは、貴人の子弟を養育し教え導く役の人、もりやくのこと】
先ほど申し上げましたね。教えるのではなく、導くだけだと。真理を教えるのではなく、子どもが自分なりの真理を見出せるということです。
「彼は教訓を与えるべきではなく、それを見出させるべきだ。」
どちらかというと、子ども自身が自分の教育をするようにすべきだとルソーは言っています。それは、矛盾しています。また最後にご紹介しますが、矛盾があります。
教師は子供に「自由であることを思いこませておく」ことによって、子どもを自分の奴隷にしているという矛盾です。教師は導くから、子どもが自分の力で「真理」を見出しているように教師は子供に思いこませるのです。「自由だ」といっても、教師は導くままですから、教師は実際は子供の支配者です。
まさに、現代の民主主義と同じです。「民主主義で権利がある」と思い込ませつつ、結局、現実にぶつかってみると権利など私たちにはありませんね。
「子どもにつけさせてもいいただ一つの習慣は、どんな習慣にもなじまないということだ。」
ですから、このように教育するため、立派な「師傅」が必要だと言います。
それから、生徒ですね。これらの引用は配布資料に乗っていませんが、なかなか才能のある生徒をルソーは作っておきます。さすがにね。教育を成功させるために、その子供は、そもそも優秀ではないと。ひどいなあ。
いわく「貧乏人は教育する必要はない。」「金持ちを生徒に選ぶことにしよう。わたしたちは少なくとも一人の人間を増やすことになるのは確実だ。一方、貧乏人は自分の力で人間になることができる。」
エミールは金持ちでなければなりません。
「同様の理由によって、エミールが名門の生まれであっても私は困らない。」
貴族出身の方が悪くないと。「とにかく一人の犠牲者が偏見から救われることになる。」
「エミールはみなし子である。」先ほどは父と母があった方が良いといっていたが、理想のエミールはみなし子です。
「父と母があっても同じことだ。父母の義務を引き受ける私は父母の権利のすべてを受け継ぐのだ。」さすがです。
「エミールは両親を敬わなければならないが、わたしにだけ服従しなければならない。」ルソー曰くですよ。
「それが私の第一の、というより、ただ一つの条件である。」
「この条件に、その当然の結果として、私たちの同意がなければ、私たちは互いに離れることはないという条件をつけくわえなければならない。」
ルソーは師傅と生徒の間の絆は非常に強いということを前提にしています。
次に、ルソーの教育論では「強壮で健康な生徒でなければならない」という条件を出します。ですから、空疎な小説にすぎませんね。現実では、ルソーが出している状況にかなう子どもはどれほどいるかちょっと疑問です。以上が「エミール」で、これで、小説の設定ができました。
それから、第一編の残りは、生まれてから二歳までの子供について語ります。本質的に何も面白いことはないのですが、のびのびと多くの詳細に入っています。ルソーは、次のようなことを言います。幼児を苦しませなければならないとか、病気にさせなければならないとか、また産衣で拘束しないようにして、それで自由を覚えさせるべきだとか。中心は自由です。第一編の最後を引用します。
「自然の習性をたもたせることによって」自然のままにほったらかせばよいということです。
「いつでも自分で自分を支配するように、ひとたび意志を持つに至ったなら、何ごとも自分の意志でするようにしてやることによって、早くから自由の時代と力の使用を準備させるのだ。」
ルソーは「気まぐれ」ではなく「意志」とあえて書いてありますが。ルソーにとって、意志とは実際に何かを実現できることであることに対して、気まぐれとは実現する力がないとしています。それは勝手な定義で成り立たないのですが。
「子どもは、ただ事物にだけ抵抗をみいだし、けっして人々の意志に抵抗をみいだすことがなければ、反抗的にも怒りやすくもならず、いっそう健康に身を保つことになる。」
要するに、教育者として、子どもの意志に一切抵抗してはならないということです。一言でいうと、かなり悪い子になるようにと言うのです。しかも社会で生きていない生徒ですから、躾はもちろんゼロです。
これで、第一編を閉めます。
・・・続く
※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております
Billecocq神父に哲学の講話を聴きましょう
また、ルソーは特に生徒の自律について強調しています。
「自然人は自分がすべてである。彼は単位となる数であり、絶対的な整数である」
ですから、御覧の通り、人間は社会の一部ではないということです。人は自律した全体であり、絶対的な単位だと。絶対的ですよ。
「自分に対して、あるいは自分と同等のものに対して(他人を一応認めますね)関係を持つだけである。」
「社会人は分母によって価値が決まる分子にすぎない。この価値は社会という全体との関係において決まる。」
ですから、ルソーにとって、社会に入ると人間は自分の本性が否定されると言います。なぜかというと、全体として自分がなくなるから、社会は反自然(本性に反する)からだと。
「立派な社会制度とは、人間をこの上なく不自然なものにして、」 明記していますね。「絶対的存在を奪いさって、相対的な存在をあたえ、」ルソーにとってこれこそは人を腐敗させます。
「「自我」を共通の統一体の中に移すような制度である。そこでは、個人の一人一人は自分を一個の人間とは考えず、その統一体の一部分だと考え、何ごとも全体においてしか考えない。」
要するに、社会は人間を反自然な存在にし、「自分において自分自身であるという絶対的な存在かつ全体」としての性格を奪うので、社会は人々を堕落させると。これは、ある種の実存主義の始まりだとみてもよいでしょう。以上は人間の自律についての部分でもあります。
次の引用の最後の部分に移します。
「生きること、それが私の生徒に教えたいと思っている職業だ。」 繰り返します。「生きること、それが私の生徒に教えたいと思っている職業だ。」「生きることは、それは呼吸することではない。活動することだ。私たちの器官、感官、能力を、私たちに存在感を与える体のあらゆる部分を用いることだ。」
ルソー論だと、いつも「自分」が中心です。
「もっとも長生きした人とは、最も多くの歳月を生きた人ではなく、最も良く人生を体験した人だ。」
体験とかは、まさに、「自分中心」主義ですね。純粋な個人主義だといえます。現代風にいうと、「生きるとは、充実していることだ」といったような感じですね。「彼は好きなことをやったらそれでよい」といった発想です。「多くの体験をして、やりたいことをする人生を送るのが良いことだ、それが生きていることなのだ」といった感じです。
「百歳の葬られる人が、生まれてすぐ死んだのと同じようこともある。そんな人は、若いうちに墓場に行った方がましだったのだ。せめてその時まで生きることができたならばのはなしだが。」
ルソーの教育論の目的です。「生きること、それが私の生徒に教えたいと思っている職業だ。」
要するに、人間の目的は「自分自身」であり、「自分自身」に従っての人間だと言います。
続いて、ルソーはいくつかの「偏見」を非難します。
「私たちの知恵と称するものはすべて卑屈な偏見にすぎない。私たちの習慣というものはすべて屈従と拘束にすぎない。社会人は奴隷状態の内に生まれ、生き、死んでいく。」
また出てきましたね。以前にもみたとおり、ルソー主義の中心となる概念がまた出てきます。「自由」です。自分のために人間が生きなければならないのは「完全に自由になる」ためです。自分が自分自身の主である、これがルソーの目的であり、自律するのは絶対的な目的だとするのがルソーのスタンスです。従って、ここに、実存主義の始まりが潜んでいます。というのも、近代的な実存主義でいうと、つまり、サルトルから流行ってきた実存主義だと、「人は自分自身を自分の力で形成していく」とされています。

「自分自身はなんであるかを自分自身で決める」が実存主義だからです。つまり人は実存するのだから、活動していることによって存在理由を持つ、やりたいことをやって存在理由を持つと説明します。シモーヌ・ド・ボヴォワール(Simone de Beauvoir)は「生まれながら女性ではなく、女性になる」といった有名な発言は象徴的です。現代においてまさにそういった空気ですね。
それはともかく、これは何を意味しているでしょうか。「個人が全体であるから、自分自身の望み通り、やりたい放題で自分自身を形成する力がある」ということの断言です。ですから、「自分自身の形成」あるいは、現代風にいうと「自己実現」の裏に、自由という前提があります。限りのない自由がなければ「自分自身やりたい放題に実現できない」からです。
自由というのはやはりルソーの思想の根本的な中心なる理想です。ルソーは続いて、奴隷について次のように語ります。
「生まれると産衣にくるまれる。」生まれたばかりなのに、もう奴隷になると言います。
「死ぬと棺桶にいれられる。」まあ、これも奴隷の一種かなあ。今、死んだルソーはそれについてどう感じているかは知りたいぐらいですね。
「人間の形をしている間は、社会制度に縛られている。」
それから、かなり時間がかかりましたが、いよいよ出てきますよ。文章はのびのびしていますが。次の引用になる前に、母の役割についてちょっと触れます。母の役割に関しては、常識的なことを口では言います。また、父の役割についてもちょっと触れます。ルソーが「子供には父と母が必要だ」といっているから、それだけは常識的だと認めざるを得ません。
しかしながら、ルソーの文章の流れにおいて以上の意見は逆説です。ルソーの文章にはいったん、直感的に常識的なことを言っていることはもちろんあります。しかしながら、次に、同時に逆なことを遺憾なく述べていきます。「母と父が子供に必要だ」といっているのに、次はその教育論において母と父は完全に否定されていて、取り消されています。というのも、エミールを教育するのは家庭教師しかいないのですから。父と母の存在はどこにもありません。さすがにルソーです。優しい夢想家のルソーです。
「そこでわたしは、一人に架空の生徒を自分に与え」ここではルソー自身が言っていますね。「わたしは」です。
「そこでわたしは、一人に架空の生徒を自分に与え、その教育にたずさわるにふさわしい年齢、健康状態、知識、そしてあらゆる才能を自分がもっているものと仮定し、その生徒を、生まれた時から、一人前の人間になって自分自身のほかに指導する者を必要としなくなるまで導いていくことにした。」
面白いでしょう。社会は一切子供を導くことはない、法は一切子供を導くことはないと。象徴的でしょう。
「この方法は自分の力を危ぶんでいる著者が幻想に迷いこむのをふせぐのに有効だと思われる。ふつうの方法から離れることになったら、生徒に自分の方法を試してみればいいことになるので、子供の進歩と人間の心の自然の歩みに従っているかどうか、彼にはすぐにわかってくる、あるいは、彼のかわりに読者にわかってくることになるからだ。」
要するに、ここで、架空の生徒を作ります。「エミール」と名付けます。また家庭教師を与えます。家庭教師から見ましょう。次の引用です。
「ただ注意しておきたいのは、一般の意見に反して、子どもの教師は若くなければならない」
教育者として「さすが」な意見でしょう。
「賢明な人であれば、できるだけ若い方がいい、ということだ。できれば教師自身が子どもであれば」
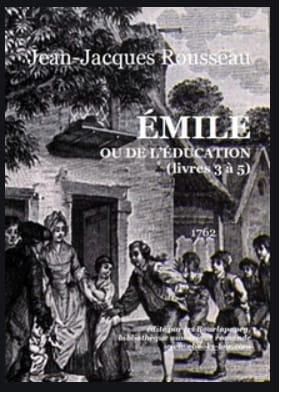
御覧の通り、現実を知らない小説にすぎませんね。
「生徒の友だちになって一緒に遊びながら信頼を売ることができれば、と思う。子どもと成熟した人間とのあいだにはあまり共通なものがないし、そんなに年齢の差があっては十分にかたい結びつきは決してできあがらない。子どもはときに老人に媚びることもあるが、決して老人を愛することはない。」
また次に出てきます。
「それに、この学問の先生は教師ではなく、むしろ師傅(しふ)と呼びたい。教えることよりも導くことが問題だからだ。彼は教訓を与えるべきではなく、それを見出させるべきだ。」【師傅(しふ)とは、貴人の子弟を養育し教え導く役の人、もりやくのこと】
先ほど申し上げましたね。教えるのではなく、導くだけだと。真理を教えるのではなく、子どもが自分なりの真理を見出せるということです。
「彼は教訓を与えるべきではなく、それを見出させるべきだ。」
どちらかというと、子ども自身が自分の教育をするようにすべきだとルソーは言っています。それは、矛盾しています。また最後にご紹介しますが、矛盾があります。
教師は子供に「自由であることを思いこませておく」ことによって、子どもを自分の奴隷にしているという矛盾です。教師は導くから、子どもが自分の力で「真理」を見出しているように教師は子供に思いこませるのです。「自由だ」といっても、教師は導くままですから、教師は実際は子供の支配者です。
まさに、現代の民主主義と同じです。「民主主義で権利がある」と思い込ませつつ、結局、現実にぶつかってみると権利など私たちにはありませんね。
「子どもにつけさせてもいいただ一つの習慣は、どんな習慣にもなじまないということだ。」
ですから、このように教育するため、立派な「師傅」が必要だと言います。
それから、生徒ですね。これらの引用は配布資料に乗っていませんが、なかなか才能のある生徒をルソーは作っておきます。さすがにね。教育を成功させるために、その子供は、そもそも優秀ではないと。ひどいなあ。
いわく「貧乏人は教育する必要はない。」「金持ちを生徒に選ぶことにしよう。わたしたちは少なくとも一人の人間を増やすことになるのは確実だ。一方、貧乏人は自分の力で人間になることができる。」
エミールは金持ちでなければなりません。
「同様の理由によって、エミールが名門の生まれであっても私は困らない。」
貴族出身の方が悪くないと。「とにかく一人の犠牲者が偏見から救われることになる。」
「エミールはみなし子である。」先ほどは父と母があった方が良いといっていたが、理想のエミールはみなし子です。
「父と母があっても同じことだ。父母の義務を引き受ける私は父母の権利のすべてを受け継ぐのだ。」さすがです。
「エミールは両親を敬わなければならないが、わたしにだけ服従しなければならない。」ルソー曰くですよ。
「それが私の第一の、というより、ただ一つの条件である。」
「この条件に、その当然の結果として、私たちの同意がなければ、私たちは互いに離れることはないという条件をつけくわえなければならない。」
ルソーは師傅と生徒の間の絆は非常に強いということを前提にしています。
次に、ルソーの教育論では「強壮で健康な生徒でなければならない」という条件を出します。ですから、空疎な小説にすぎませんね。現実では、ルソーが出している状況にかなう子どもはどれほどいるかちょっと疑問です。以上が「エミール」で、これで、小説の設定ができました。
それから、第一編の残りは、生まれてから二歳までの子供について語ります。本質的に何も面白いことはないのですが、のびのびと多くの詳細に入っています。ルソーは、次のようなことを言います。幼児を苦しませなければならないとか、病気にさせなければならないとか、また産衣で拘束しないようにして、それで自由を覚えさせるべきだとか。中心は自由です。第一編の最後を引用します。
「自然の習性をたもたせることによって」自然のままにほったらかせばよいということです。
「いつでも自分で自分を支配するように、ひとたび意志を持つに至ったなら、何ごとも自分の意志でするようにしてやることによって、早くから自由の時代と力の使用を準備させるのだ。」
ルソーは「気まぐれ」ではなく「意志」とあえて書いてありますが。ルソーにとって、意志とは実際に何かを実現できることであることに対して、気まぐれとは実現する力がないとしています。それは勝手な定義で成り立たないのですが。
「子どもは、ただ事物にだけ抵抗をみいだし、けっして人々の意志に抵抗をみいだすことがなければ、反抗的にも怒りやすくもならず、いっそう健康に身を保つことになる。」
要するに、教育者として、子どもの意志に一切抵抗してはならないということです。一言でいうと、かなり悪い子になるようにと言うのです。しかも社会で生きていない生徒ですから、躾はもちろんゼロです。
これで、第一編を閉めます。
・・・続く









