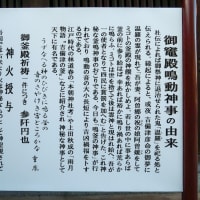たまには夕方からふらりと出かけるのもいい。
この季節は夕方から少しだけ涼しい風が吹いて、足がよく進む。
ゴールデンウィークは日中はどこも混んでいるので、毎年出かける気が起きないのだが夜ならいいか。
そうだ、夜の下町に行ってみよう。
誰もが知っている観光地でも、いつもとは違う景色に出逢えるかもしれない。
※
5月5日の火曜日、急に思い立って始まった「夜の下町さんぽ」。
集合場所となった地下鉄押上駅には9人もの参加者が集まった。
3時間前に参加者を募って、ここまでの人数が集まるのだから驚きである。
後々に2名合流して最終的には11人となった。
顔ぶれはお馴染みの方から、フレッシュな1年生まで様々。
半袖Tシャツで着てしまった子はユニクロでパーカーを買っていた。
さすがにまだ半袖では寒いようだ。
押上駅といえば、スカイツリーとソラマチの最寄駅である。
東京メトロ半蔵門線が押上まで延伸したころには、殺風景な場所で、近ごろの賑わいには想像できなかった。
とりあえず、このようなミーハーな場所ではあるが一度スカイツリーの夜景も見てみたかったのでちょうど良い。
北十間川と、東武伊勢崎線(最近ではスカイツリーラインといらしい)に沿って、隅田川まで歩いてみよう。
スカイツリータウンから少し離れれば、閑静な住宅街が広がっている。
高架線を走る鉄道と電信柱にくっついた街路灯をみるとほっとする。
ぼんやりと歩いていたら、すぐに隅田川のテラスに到着。
行き交う屋形船と、橋を渡っていく東武線。遠くにはライトアップされた吾妻橋が見える。
いよいよ対岸は繁華街の浅草である。
隅田川の両岸は下流までテラスとして整備されているので、居心地がいい。
何故か勝海舟の像があったりと観光情報誌にはあまり載らないが、おすすめの場所。
すぐ近くにはアサヒビールタワーと、スーパードライホールが建っている。
浅草に来ると必ず見える、金色のアイコンはこのシンボルと言ってもいい。
こどもは必ず、「ウ〇コ」と覚えるのだが、燃える炎をデザイン化したものらしい。
お隣のアサヒビールタワーはビールジョッキをイメージしているのだが、知らない人が多いだろう。
吾妻橋を渡っている最中はスカイツリーが並んで見えるのだが、アサヒの存在感が凄まじく、スカイツリーが霞む。
完成から25年以上経っているが、色あせない存在感である。
橋を渡りきれば、浅草駅。
近年改修工事が行われ、美しさを取り戻した東武浅草駅兼松屋浅草店。
東武鉄道が、無理やり進出して起点としたほど、前世期の浅草は栄えていたらしい。
ビルの3階に東武線のホームがある構造はいかにも私鉄ターミナルっぽくて好き。
日本はヨーロッパのような櫛形のターミナル駅を造らずに、通過型の駅が多いのは鉄道が軍事輸送に重宝されていたためだという。
最近では、東急東横線の渋谷駅のように相互乗入れを重視して櫛形ターミナルを捨てるケースもある。

しばらく歩けば、浅草寺の雷門に到着。
小中学生の頃は幾度も訪れたが、夜に来たのは初めてだ。
夜の寺院など何もないような気がするが、意外と人は多い。
浅草寺に続く仲見世も、大半の店舗は閉まっているが、雷おこしや人形焼のお店はまだ商売をしている。
19時半を回っているのにご苦労様です。



浅草寺境内も本堂は閉まっているものの、主要建築はライトアップされている。
仁王様までライトアップされていて幻想的な雰囲気である。
右を見ればスカイツリーが、左を見れば五重塔がある。
100年前には浅草十二階こと凌雲閣もあった。
浅草は塔の似合う街である。
そろそろ夕食でもとろうかとフラフラ歩いていると、呑みが好きな人々は旧浅草六区近くの飲み屋に吸い込まれていった。
確かに、これからの時期は露店のように道路に席を出したお店で飲むのも一興。
残った我々も、夕食を探そう。

ふらふらと伝法院通りや観音通りを渡り歩いて、辿り着いたのは創業明治十三年の神谷ビルである。
登録有形文化財にも指定されている本館1階は電気ブランで有名な神谷バー。
私たちは2階に上がってレストランカミヤにお邪魔してみる。
カレーライスやチキンライスを頼んで、ほっと一息。
ノスタルジックな店内、暖かい電球の下ではなんともお酒を飲みたくなってしまうが今日は我慢。

夕食後は隅田川沿いの隅田公園で一休み。
呑み屋に入っていた人たちがすぐに切り上げて帰ってこないことはうすうすわかっていた。
それだから、スカイツリーでも見ながらのんびりと散策。
隅田川とスカイツリーの周辺にはGTS観光アートラインと呼ばれる観光ルートがあって、多くの野外アート作品がちりばめられている。
GTSとは藝大・台東・墨田の頭文字を採ったものらしい。
現代アートというものはよくわからないが、出会えたら何となく楽しいから好き。

グリーンプラネットという作品も不思議だ。
台東区の観光サイトによれば「宇宙の気を集めるお椀の形は隅田川と調和し、この場所を、一つのパワースポットに変えてしまうような作品です。」とある。
御椀の中を覗く友人は宇宙へトリップしているようにも見える。
さてさて、呑み組が満足したころには解散しようと思っていたのだが、まだまだ元気なようなので次の目的地へと向かう。
行先は夜の上野公園。
上野なら銀座線で一本だが、都営ワンデーパスを持っていたので蔵前駅経由で上野御徒町駅から歩く。
御徒町方面から北上すると、まず上野公園の入り口となる大階段が現れて、上り詰めると西郷さんがいらっしゃる。
この上野公園を船に例えれば、西郷さんは船頭といったところである。
普段は賑やかな西洋美術館も、動物園前もすっかり静まり返っている。
大噴水の先には国立博物館の本館が堂々と建っている。

上野動物園のほど近くに、立派な台座付きの銅像が立っているのを見つけた。
こんなものがあったろうかと思った矢先、友人からの「誰?」という問いに言葉を失ってしまうのであった。
それにしても月明かりが綺麗だ。
(後に調べると小松宮像でした)

さらに奥へ進むと、こども遊園地。
昭和時代の小型のライドアトラクションが静かに眠っている。
井の頭自然動物園の園内にもこのような小さな遊園地があって、いつかみた雨の中、屋根付きのカルーセルで遊んでいた小さな男の子の姿が忘れられない。
眺めていると物悲しくなるのは、懐かしさ故なのか、それとも無人の機械たちへの憐れみなのか。
人を乗せるための機械のそばに人気がなくなると、存在意義が宙ぶらりんになってしまって不思議な異世界が出来上がる気がする。
気付けばもう1日が終わろうとしている。
花園稲荷や清水観音堂を横目に、帰路へ着こう。
日中、365日賑わっている場所を、あえて夜間に歩いてみるのもいい。
浅草が日没以降も楽しめる街だということを知って、東京の光のしぶとさを感じてしまったのだが、上野公園はひっそりとしている。
丸の内と同じく、昼夜の人口差の激しい場所である。
さて、次はどの街を歩こうか。