「悉曇梵字」

一、聖語としての梵字の歴史
まず、梵字、梵語、悉曇、サンスクリット、種7 、梵字仏、文字仏など、本書に出てくる梵字に関する用語を整理しておきましょう。ともすると混乱することがありますから、正しく理解しておくことが大切です。
古代よりインドで使われている言語「サンスクリット」を「梵語」といいます。この梵語を記すときに用いる文字が「梵字」です。梵字の書体は時代とともに変化しましたが、ふつう日本で梵字といえば、その中の一書体である「悉曇梵字」をさします。
さて、前述しましたように、仏、菩薩、明王、天部などの諸尊を象徴表示する梵字を「種子」といいます。この種fは、単なる仏のイニシャルとして記されるのではなく、一尊のもつすべてを包蔵しているとされ、梵字の仏さま、つまり「梵字仏」として大切に扱われてきました。三井先生は、これを「文字仏」と名づけたのです。
1、聖なる文字、法の文字
アショーカ王の碑文と梵字
梵字は、梵語のブラーフミーの漢訳です。ブラーフミーは「ブラフマン(叩Iヨ~)
のもの」という意味で、ブラフマンとは仏教がおこる前からインドにあったバラモン教の創造神、梵天のことです。「梵天によってつくられた文字」という伝説に基づいて「梵字」の名があるのです。
しかし、実際にいつ頃ブラーフミー文字が誕生したかについては定説はありません。ブラーフミ上又字で書かれた現存最古のものは、有名なアショーカ王の詔勅刻文で、時代的には紀元前三世紀中頃のものといわれています。
アショーカ王(在位紀元前二六八―二三二年)はマウリア朝の第三代目の王で、インド半島の南部を除くインド全土を統}して大帝国を築きました。王は仏教に深く帰依し、仏教の信仰と保護を領民に告示するため、石刻の詔勅文を全土に設置しました。詔勅文は石柱や岩石に刻まれ、梵語(実際は梵語方言のプラークリット語)が使われていますが、なかにはギリシヤ語やアラム語(当時の西アジア世界における国際語的な言語)などで、記されているものも発見されている ということです。
さてヽその碑文は、ぼとんどがブラーフミー文字で記されています。(ごく一部に、当時の西北インドで使用・されていたカローシュテイ字の碑文も発見されています)
その碑文にはダムマリピー 、すなわち「法の文字」と記されております。梵天創造に通じるブラーフミーという名称は、仏教がバラモン教の神々を護法神などに取り入れた後の
こととされています。
時代、地域によって変化した字体
このブラーフミ上又字は、時代を経るにしたがって、あるいは地域によって、その形状がしだいに変化していきました。はじめは単純な線や点によって構成されていましたが、四世紀に入っ
てグプタ朝のころになると、全体的に曲線が入り、優美な書体へと変化していきます。この頃の字体をグプタ型といいますが、このグプタ型を基本にして、五つの字体が登場します。
そのうちのひとつが、シッダマートリカー型と呼ばれる字体で、六世紀頑か
ら使用され、中国を経て日本に伝えられた梵字悉曇文字です。
悉曇とは「完成したもの」 「成就したもの」という意味の梵語シッタン
「完成したもの」とは、ひとつには、その文字だけで単独に発音できることをいったものです。また、インドでは学業の成就を祈って、学習用のテキストにシッダラストウ
られよ」という語を記す習慣がありました。それがやがてテキスト(字母表)のタイトルとなり、さらにシッタン(悉曇)と呼称されるようになったということです。
サンスクリット語を表記する文字の字体は、時代によって、地域によって、変化していきましたが、悉曇文字(シッダマートリカー型)も十世紀を境にナーガリーに吸収されてインドから消えてしまいます。
なお、現在インドで使用されているデーヴァナーガリー字体は、七世紀頃から使用され始め、インドの大部分に広圭ったIこのナーガリー型に端を発し、やがて「聖なる」
という意味の「デーヴア」という言葉加冠されました。十三世紀の二ろ成立したといわれています。この字体は、各文字の頭部が一続きの線で結ばれ、細長い帯状になっているのが特徴です。











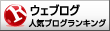









 不動明王
不動明王









