 2=社会における解体と変身
《破局からの創造》理論
現代創造理論の世界的権威とされる市川亀久弥教授は、著作「破局からの創造」において、破滅に真面した現代文明の危機につき、つぎのように述べておられる。
″社会システムの変遷パターン″という項で、氏は、まず初めに、ヒトの生産能力のおそるべき増大を論ずる。
すなわち、ヒトの歴史において、今から一千万年、ないし一万年くらい前までは、ヒトの生産出力は、だいたい八分の一馬力、ないしI〇分の一馬力くらいであった。もっとも単純な人力時代だったわけである。
ところが、一万年前くらいになると、古代国家が誕生することになり、大型動物の飼い馴らしがはじまって、これを動力として活用することになり、これが、一馬力、すなわち馬一頭分の出力数の段階に入る。
それがしばらくっづいて、数百年くらい前の段階になると、機械が発明される。そして、千馬力というような、当時の動力源としては面期的な規模に立つスチームーエンジン(蒸気機関)が出現する。
これが、現代の原子力時代にひきつがれてくるわけなのだが、いきなり原子力の力にふれる前に、たとえば、先年のアポロ11号を飛ばせたサターン5型ロケットの出力をとりあげてみると、なんとこれは、一億六千万馬力という想像を絶した馬力数なのである。この値は、いまから百年くらい前の段階とくらべて考えてみても、一基あたりの馬力数が、約二八万倍になっている。さらにさかのぼって、ネアンデルタール人の生きておったあたりから、古代国家が誕生して最盛期になるあたり(奴隷労働社会)にまでさかのぼって比較すると、実に二八億倍ということになる。
つぎに、スピードの増加による運動エネルギーの増加の度合を考えてみると、いま、ヒトは、
ようやくI〇〇メートルをI〇秒フラットくらいで走っている。だから、ち・ようど一秒間に一〇メートルの速度で走っているわけだ。ところでいまさきに述べた宇宙ロケットが地球引力圏から月に向かって発進したときの速度は、秒速一一・ニキロということであるから、だいたい、ヒトの1000倍である。スピードが}○○○倍ということであれば、運動予不ルギーの増加分は、運動の方程式により、VV 1Amv2であるから}合飛倍、ナなわち百万倍ということになるわけである。
このように、人類史において社会システムが駆使する動力予不ルギーの増大傾向は、過去から現代に接近すればするほど、急角度に増大しているのであるが、それでは、こういう動カエネルギーの増大に対して、それをうけいれているところの社会機構、社会体制というものはいったいどのような変化をしているかというと、それは、つぎのように変わってきている。
2=社会における解体と変身
《破局からの創造》理論
現代創造理論の世界的権威とされる市川亀久弥教授は、著作「破局からの創造」において、破滅に真面した現代文明の危機につき、つぎのように述べておられる。
″社会システムの変遷パターン″という項で、氏は、まず初めに、ヒトの生産能力のおそるべき増大を論ずる。
すなわち、ヒトの歴史において、今から一千万年、ないし一万年くらい前までは、ヒトの生産出力は、だいたい八分の一馬力、ないしI〇分の一馬力くらいであった。もっとも単純な人力時代だったわけである。
ところが、一万年前くらいになると、古代国家が誕生することになり、大型動物の飼い馴らしがはじまって、これを動力として活用することになり、これが、一馬力、すなわち馬一頭分の出力数の段階に入る。
それがしばらくっづいて、数百年くらい前の段階になると、機械が発明される。そして、千馬力というような、当時の動力源としては面期的な規模に立つスチームーエンジン(蒸気機関)が出現する。
これが、現代の原子力時代にひきつがれてくるわけなのだが、いきなり原子力の力にふれる前に、たとえば、先年のアポロ11号を飛ばせたサターン5型ロケットの出力をとりあげてみると、なんとこれは、一億六千万馬力という想像を絶した馬力数なのである。この値は、いまから百年くらい前の段階とくらべて考えてみても、一基あたりの馬力数が、約二八万倍になっている。さらにさかのぼって、ネアンデルタール人の生きておったあたりから、古代国家が誕生して最盛期になるあたり(奴隷労働社会)にまでさかのぼって比較すると、実に二八億倍ということになる。
つぎに、スピードの増加による運動エネルギーの増加の度合を考えてみると、いま、ヒトは、
ようやくI〇〇メートルをI〇秒フラットくらいで走っている。だから、ち・ようど一秒間に一〇メートルの速度で走っているわけだ。ところでいまさきに述べた宇宙ロケットが地球引力圏から月に向かって発進したときの速度は、秒速一一・ニキロということであるから、だいたい、ヒトの1000倍である。スピードが}○○○倍ということであれば、運動予不ルギーの増加分は、運動の方程式により、VV 1Amv2であるから}合飛倍、ナなわち百万倍ということになるわけである。
このように、人類史において社会システムが駆使する動力予不ルギーの増大傾向は、過去から現代に接近すればするほど、急角度に増大しているのであるが、それでは、こういう動カエネルギーの増大に対して、それをうけいれているところの社会機構、社会体制というものはいったいどのような変化をしているかというと、それは、つぎのように変わってきている。
原始家族共同体―氏族社会-古代社会・国家の誕生II神聖王朝その他の封建体制-現代・民主的近代体制、という変遷である』
市川氏は、この変遷を、それぞれの社会的出力規模(生産力)に対応した制御パターンの変化にほかならないと断定する。
氏は、大阪大学の石谷清幹教授の発見した技術の一般法則「一定の技術装置には、その技術装置を成立させている方式に対応した最適の出力規模がある」という、規模(量的内容)に対応するシステム原理(方式)の基本法則が、そっくりそのまま、社会と、社会が持つようになった生産出力との関係に適用されるのだと説く。〃最適の出力規模″をけるかに超えた千不ルギーはその技術装置を破壊してしまう。
つまり、ヒトが持つ動力エネルギーの規模に応じて、それを受けいれる社会体制もまた、それに相応した規模の制御パターンを持だなければならない、ということである。実際の歴史をしらべてみても、昆虫の成長過程にあらわれてくる″脱皮現象″と全く同じように、その規模の段階に対応して社会変革がなしとげられているのであって、それが今日までの人類史にあらわれてき
ている政治革命とか宗教革命というものなのだと市川氏は論断する。
もしも、動カエネルギー(生産)の規模と、これに対応する社会の制御パターンが適応しないと、それは破滅へ暴走することになる。
『具体的な実例についで考えてまいりますと、一国の行政が、生産力の規模と質的内容に対応できなくなってきますと、行政施策は当然のことながら、後手、後手ということになっていくわけであります。こういう社会システム制御の障害が、適当な時期までに回復しなかった場合は、当然の結果として、その社会システムは、収拾のできない暴走状態に突入してしまうことになりまナ。高度工業社会の巨大な生産力の一頂点にまで登りつめてまいりました段階のわが国におきましては、率直にいって、すでに、暴走状態の第一段階は始まっていることを、思わしめるものがあります。すでに公害という名の自家中毒的なシステム破壊と、社会的な連帯意識、共通の価値観としてのモラルの急速な崩壊がまき起こっている反面、物の生産と、その物を生産ナるためのシステムのみが、いよいよとび離れて巨大化の一途をたどっております現状は、否定することはできないと思います。もとより、これは、単にわが国のみに顕在化してきた兆候ではなく、大なり、小なり、アメリカやソ連などをはじめとして、およそ今日高度工業社会のなかに急速に顕在化しつっある傾向であると思います』
つまり、現在の人類が持っているところの社会体制、制御パターンは、たかだか数十万馬力程度の規模の生産出力に対応するものでしかなく、億単位の規模の莫大なエネルギーを制御することなどまったく思いもよらぬことだということである。ましてや、もう現実化しつつある原子力iエネルギーの制御ということになると、これに対応する社会体制というものは、いったいどのよ
うなパターンを持つものなのか。人類はどのような変化をしたなら、そういう高度のパターンを持つことができるようになるのか? 市川氏はかつての人類がおこなってきた程度の適応変化ではとうてい追いつくものではなく、もし、その変化に失敗したならば、人類は絶滅してしまうであろう、と、昆虫の完全変態のパターンを例にあげて、つぎのように論ずる。
『かつての人類の変革を見てみると、ひと言でいうなら、それぞれの時代における制御パターンの変遷史というものは、前段階のパターンがゆきづまって、十分な制御能力を喪失し、入れかわってあらたな、より発展段階の高い制御パターンが模索されてきたものなのであります。もとより、無から有がこつ然として出現してくることはありません。したがって、それはあくまでそれまでの、歴史的な経験の土台の上に再構成されてきたものであります。つまり、前段階までの、制御パターンの変換再構成なのであります。……人類は生理的に天賦の道具であった手足を動かして、生産を実現していた原始家族共同体の時代から、自然石の適当なものを手ににぎって、これに人工的な道具としての役割を付与する、いわゆる旧石器時代にはいっていくのであります。このようにして、以後、引き続いてまいります道具の変遷史は、同時に社会的な生産出力の増大と、また、これに関連した社会形態史上の変遷が対応していくことになっていくのであります。
およそ歴史的な発展というものは、前段階的状態があるところまで解体し、これにあらだなる能動的要求が加わりまして、それが新しい段階のもっべきイメージに向かって変換再構成されていくものであります。
ご承知のように、われわれのからだの中心部は骨でできております。ナなわち、内骨格なのであります。ところが、この骨というものは、子どものときには、おとなの何分のI、というくらいの短いものであります。しかし、かたい非可塑的な物質でできております骨格が、その成長段階に応じて、大きさを自由に伸ばしていくということは、いったいどういうプロセスをもって実現しているものなのでしようか。骨は炭酸カルシウムと、燐酸カルシウムとが七〇パーセントくらいも含まれている固体なのであります。このままではたとえば、直径一センチの骨は、三センチの太さの骨になれるはずがございません。これは、実のところ、内側の骨が徐々に分解させら
れる一方、外側の骨がしだいに形成されるというメカニズム、つまり△造骨機能▽と、△解骨機能▽の適当な組み合わせによって達成しているわけであります。
ところで、骨格の成長過程のような、単なる量的拡大の歴史的発展の場合は、造骨、解骨の両機能が、同一の時目的空目的条件のなかで、連続的な経過をたどって目的を達成することができます。しかしながら、単に量の展開にとどまらずに、質の変革をともなうような歴史的な発展に
おきましては、どうしても、解体と、再構成作業(再構築作業)とが、同一の時間的経過のなかで共存していくわけにはまいりません。必然的に、なんらかの形における解体作業が先行している
段階、すなわち適当な段階におきまして、あらたな観点に立った再構成的作業をおし進めていくよりほかに、方法はないわけであります』
319-社会における解体と変身
2 = Dismantling and transformation in society
"Creation from catastrophe" theory
Professor Kikuya Ichikawa, who is regarded as a world authority on modern creative theory, describes in his book "Creation from Catastrophe" about the crisis of modern civilization seriously facing ruin.
In the section "Transitional Patterns of Social Systems", he first discusses the tremendous increase in human production capacity.
That is, in human history, from now to about 10 million to 10,000 years ago, human production output was about one-eighth horsepower or one-third horsepower. It was the simplest human-powered era.
However, about 10,000 years ago, an ancient nation was born, and the tame of large animals began, and this was used as power, which is one horsepower, that is, the number of outputs for one horse. Enter the stage of.
The machine was invented when it continued for a while and reached the stage several hundred years ago. Then, a steam engine (steam engine), which stands on an epoch-making scale as a power source at that time, such as 1,000 horsepower, will appear.
This is what is drawn into the modern nuclear era, but before suddenly touching the power of nuclear power, for example, if you take up the output of the Saturn V rocket that flew Apollo 11 last year, this is what Is an unimaginable number of horsepower of 160 million horsepower. Even if you think about this value compared to the stage about 100 years ago, the number of horsepower per unit is about 280,000 times. Going back further, from the time when the Neanderthals lived to the time when the ancient nation was born and reached its peak (slave labor society), it is actually 280 million times.
Next, considering the degree of increase in kinetic energy due to the increase in speed, humans are now
Finally, I'm running IOO meters flat for IOO seconds. That's why I'm running at a speed of 10 meters per second. By the way, the speed of the space rocket mentioned earlier when it launches from the Earth's gravitational sphere toward the moon is 11 to 2 km per second, which is about 1000 times that of humans. If the speed is} ○○○ times, the increase in the motion pre-empty ruggie is VV 1 Amv2 according to the equation of motion}. ..
In this way, the increasing tendency of the power prediction and unpredictability that the social system makes full use of in human history is increasing at a steeper angle as it approaches the present from the past, but then, such an increase in dynamic energy. On the other hand, what kind of changes are being made to the social institutions and systems that are receiving it? They are changing as follows.
Primitive family community-clan society-ancient society / birth of a nation II Holy dynasty and other feudal systems-modern / democratic modern system. "
Mr. Ichikawa concludes that this transition is nothing but a change in the control pattern corresponding to each social output scale (productivity).
He said that the general rule of technology discovered by Professor Seikan Ishigai of Osaka University is that "a certain technical device has an optimum output scale corresponding to the method that establishes the technical device" (quantitative). It is explained that the basic rules of the system principle (method) corresponding to the content) are applied to the relationship between the society and the production output that the society has come to have. A thousand rubies that exceed the "optimal output scale" will destroy the technical equipment.
In other words, depending on the scale of motive energy possessed by humans, the social system that accepts it must also have a control pattern of the scale corresponding to it. Even if we look at the actual history, just like the "molting phenomenon" that appears in the growth process of insects, social change has been achieved according to the stage of its scale, and that is to this day. Has appeared in human history
Mr. Ichikawa argues that it is a political revolution or a religious revolution.
If the scale of dynamic energy (production) and the corresponding social control pattern do not adapt, it will run wild to ruin.
"If we think about concrete examples, when the administration of one country becomes unable to respond to the scale and qualitative content of productivity, the administrative measures will, of course, be behind and behind. That is to say. If these obstacles to social system control are not recovered by an appropriate time, the natural result is that the social system will enter an unmanageable runaway state. In Japan, which has climbed to the top of the huge productivity of a highly industrialized society, frankly, there is something that makes us think that the first stage of the runaway state has already begun. While self-addictive system destruction called pollution, social solidarity, and rapid collapse of morals as common values are already occurring, the production of things and the production of those things I think we cannot deny the fact that only the system is finally becoming huge and far away. Of course, this is not just a sign that it has become apparent only in Japan, but it seems that it is becoming more and more rapidly becoming apparent in the highly industrialized society today, including the United States and the Soviet Union. Masu ”
In other words, the social system and control patterns that human beings currently have are only compatible with production output on the scale of hundreds of thousands of horsepower, and control enormous energy on the scale of 100 million units. It's completely unexpected. Moreover, when it comes to the control of nuclear i-energy, which is already becoming a reality, what kind of social system corresponds to this?
Does it have such a pattern? What kind of changes will humankind be able to have such a high degree of pattern? Mr. Ichikawa said that the adaptive changes that human beings once made cannot catch up with them, and if the changes fail, human beings will become extinct. Taking an example, we argue as follows.
"Looking at the changes of humankind in the past, in a nutshell, the history of the transition of control patterns in each era is replaced by the patterns of the previous stage, which have lost sufficient control ability. A new, higher-stage control pattern has been sought. Of course, nothing comes out of nothing. Therefore, it has been reconstructed on the basis of historical experience. In other words, it is the conversion and reconstruction of the control pattern up to the previous stage. ...... Since the era of the primitive family community, where human beings have realized production by moving their limbs, which were physiologically natural tools, they have picked up suitable natural stones and used them as artificial tools. We are going into the so-called Paleolithic era, which gives the role of. In this way, the history of changes in tools that will continue thereafter will correspond to the increase in social production output and the related changes in the history of social forms. ..
Approximately historical development is something that is dismantled to the point where there is a pre-stage state, and with the addition of new active demands, it is transformed and reconstructed toward the desired image of a new stage. Is.
As you know, the center of our body is made of bones. That is, it is the endoskeleton. However, when you are a child, this bone is as short as I, which is a fraction of an adult. However, what kind of process is it used to realize that the skeleton, which is made of a hard non-plastic substance, freely grows in size according to its growth stage? Bone is a solid that contains about 70% of calcium carbonate and calcium phosphate. At this rate, for example, a bone with a diameter of 1 cm cannot become a bone with a thickness of 3 cm. This is, in fact, the gradual breakdown of the inner bone
On the other hand, it is achieved by the mechanism that the outer bone is gradually formed, that is, the appropriate combination of △ bone-forming function ▽ and △ bone-resolving function ▽.
By the way, in the case of the historical development of mere quantitative expansion such as the growth process of the skeleton, both the functions of bone formation and bone demolition follow a continuous course under the same spatiotemporal purpose condition. You can achieve your goal. However, it is not just a quantity development, but a historic development that involves a change in quality.
Therefore, dismantling and reconstruction work (reconstruction work) cannot coexist in the same time lapse. Inevitably, some form of dismantling work precedes
There is no other way but to proceed with the reconstruction work from a new perspective at the stage, that is, at the appropriate stage. "
319-Dismantling and transformation in society
 Photo by iStock
Photo by iStock Photo by iStock
Photo by iStock Photo by iStock
Photo by iStock









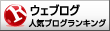








 こんにちは、ヨムーノライターのTOMOです!白い毛で覆われた丸いフォルムがかわいいとSNSでも人気を集めている「シマエナガ」。北海道に主に生息しているシマエナガの体長は約14cmと鳥の中でも小さく、真っ白な毛をまとい雪国を舞う姿から「雪の妖精」の愛称でも親しまれています。
こんにちは、ヨムーノライターのTOMOです!白い毛で覆われた丸いフォルムがかわいいとSNSでも人気を集めている「シマエナガ」。北海道に主に生息しているシマエナガの体長は約14cmと鳥の中でも小さく、真っ白な毛をまとい雪国を舞う姿から「雪の妖精」の愛称でも親しまれています。


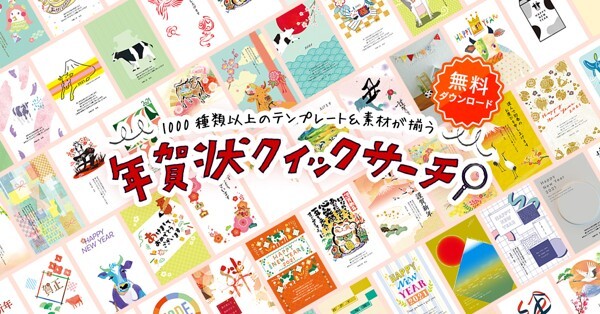


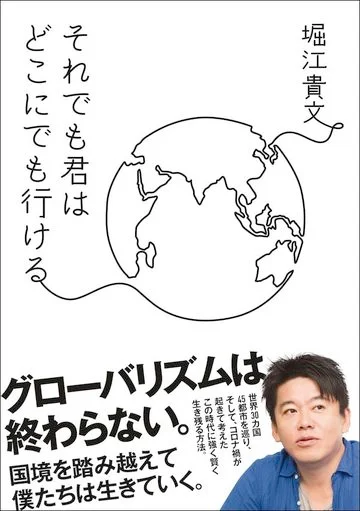

















 「アップルバンドゲート事件」と呼びたい人もいるかもしれない。Apple Watchの最新機種、Series 6を巡る最近のオンライン騒動だ。Solo Loop(ソロループ)の発表は、先週のイベントでちょっと目立った話題だった。時計のバンドがハードウェアイベントの中心になることなどめったにあることではない。よくあることだが、発売されるやいなや返品が相次いだ。もちろんそれは、どんな新製品でもあることだが、ここではいくつかの理由で問題が複雑化している。まず、この締め具のないバンドは、いろいろな太さの手首にフィットするようにさまざまなサイズが用意されている。そして、店頭で試すことか難しい昨今の事情がことをさらにややこしくした。返品した人たちは多くのイライラを募らせた。オンラインのサイズ測定で適切なサイズを見つけるのは困難だと多くの人が報告した。そして、返品するためにはApple Watch全体を送り返さなくてはならないことに、さらに不満を顕にし人がたくさんいた。
「アップルバンドゲート事件」と呼びたい人もいるかもしれない。Apple Watchの最新機種、Series 6を巡る最近のオンライン騒動だ。Solo Loop(ソロループ)の発表は、先週のイベントでちょっと目立った話題だった。時計のバンドがハードウェアイベントの中心になることなどめったにあることではない。よくあることだが、発売されるやいなや返品が相次いだ。もちろんそれは、どんな新製品でもあることだが、ここではいくつかの理由で問題が複雑化している。まず、この締め具のないバンドは、いろいろな太さの手首にフィットするようにさまざまなサイズが用意されている。そして、店頭で試すことか難しい昨今の事情がことをさらにややこしくした。返品した人たちは多くのイライラを募らせた。オンラインのサイズ測定で適切なサイズを見つけるのは困難だと多くの人が報告した。そして、返品するためにはApple Watch全体を送り返さなくてはならないことに、さらに不満を顕にし人がたくさんいた。 画像クレジット:Apple
画像クレジット:Apple






































