中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
中学受験のカリキュラム
中学受験のカリキュラムの進み方は以前にくらべて半年ぐらい早くなりました。
だから4年生の後半ぐらいから、入試に出題される内容を勉強することになるわけですが、まだ4年生ですから理解できる場合もあれば、そうでない場合もあります。
しかし、毎月組み分けテストとか月例テストがあって、その理解が進んでいかなければ「成績が悪い」とか「上位校への合格は難しい」というような感覚に陥りやすい。しかし、そんなに早くできる必要がなぜあるのでしょうか。
各塾がカリキュラムを速めたのは演習の時間を長くするためです。5年生までに大方受験に出る勉強を終えて、問題演習を中心にする。そこで以前に習ったことを復習しながら、入試問題を解けるように練習するわけです。
でも良く考えてみると、受験カリキュラムを勉強するのに1年半かかる子どもばかりではありません。算数についていえば、例えば応用自在のような参考書には、受験カリキュラムが全部載っているわけで、これを自分で1年間かけて勉強すれば、演習のときから塾に行ってもいい。そうすると、4年生とか5年生の間はもう少し時間を上手に使える可能性は出てくるわけです。
しかし、塾としてはこれでは困ります。
だから早く始めて、自塾に「囲い込む」ということをします。今の時期、各塾で無料の実力テストや入塾テストが行われていますが、なるべく早く入ってもらい、早く勉強してもらい・・・、と思っているわけですね。
でも、ここまで早くなるとタイミングを逃してしまえば、すでにわからないことが多くなる。「まだ習ってない」→「よくわからない」→「テストの成績が悪い」→「自信がなくなる」→「やる気がなくなる」という悪循環に入るくらいなら、「じゃあ、全部終わるまでは自分のペースで勉強しよう」でも本当は良いのではないか、と思うのです。
塾に言われるままに、早く始めてしまうばかりが方法ではありません。
どうせ6年の最初から演習が始まる、とわかっているのなら、そこまでに一通りの勉強をすませればいいわけで、それをどうやってやるか、を工夫する方法があっても良いのではないでしょうか。
最近は通信教育、動画配信などいろいろサービスの種類も増えているので、それを上手に組み合わせて4年生や5年生で勉強しつつも、スポーツをやったり、家族で旅行に行ったりする。そして6年生から本格的に塾で演習だけを始めるのでも良いのではないでしょうか。
実際に、6年生でも他塾から優秀な子が移ってくれば、塾は歓迎してくれます。だから、できるようになっていれば実は早く始めるかどうかは大きな問題ではない。
ちゃんとできるようになるか、そこに視点があるべきなのです。子どもは成長の度合いがやはりそれぞれ違います。早く成長する子もいれば、晩熟の子もいるわけです。だから子どもの成長度合いに本来は勉強の仕方を合わせていかないといけない。
それを画一的に進めるから、「しんどい」と思う子が増えるのではないでしょうか。
=============================================================
今日の田中貴.com
Kindle版発刊のお知らせ
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
11月1日の問題
==============================================================
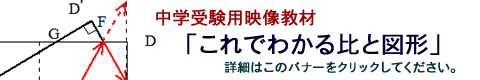
==============================================================
お知らせ
算数4年後期第11回 算数オンライン塾「分数の積と商」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================


にほんブログ村
だから4年生の後半ぐらいから、入試に出題される内容を勉強することになるわけですが、まだ4年生ですから理解できる場合もあれば、そうでない場合もあります。
しかし、毎月組み分けテストとか月例テストがあって、その理解が進んでいかなければ「成績が悪い」とか「上位校への合格は難しい」というような感覚に陥りやすい。しかし、そんなに早くできる必要がなぜあるのでしょうか。
各塾がカリキュラムを速めたのは演習の時間を長くするためです。5年生までに大方受験に出る勉強を終えて、問題演習を中心にする。そこで以前に習ったことを復習しながら、入試問題を解けるように練習するわけです。
でも良く考えてみると、受験カリキュラムを勉強するのに1年半かかる子どもばかりではありません。算数についていえば、例えば応用自在のような参考書には、受験カリキュラムが全部載っているわけで、これを自分で1年間かけて勉強すれば、演習のときから塾に行ってもいい。そうすると、4年生とか5年生の間はもう少し時間を上手に使える可能性は出てくるわけです。
しかし、塾としてはこれでは困ります。
だから早く始めて、自塾に「囲い込む」ということをします。今の時期、各塾で無料の実力テストや入塾テストが行われていますが、なるべく早く入ってもらい、早く勉強してもらい・・・、と思っているわけですね。
でも、ここまで早くなるとタイミングを逃してしまえば、すでにわからないことが多くなる。「まだ習ってない」→「よくわからない」→「テストの成績が悪い」→「自信がなくなる」→「やる気がなくなる」という悪循環に入るくらいなら、「じゃあ、全部終わるまでは自分のペースで勉強しよう」でも本当は良いのではないか、と思うのです。
塾に言われるままに、早く始めてしまうばかりが方法ではありません。
どうせ6年の最初から演習が始まる、とわかっているのなら、そこまでに一通りの勉強をすませればいいわけで、それをどうやってやるか、を工夫する方法があっても良いのではないでしょうか。
最近は通信教育、動画配信などいろいろサービスの種類も増えているので、それを上手に組み合わせて4年生や5年生で勉強しつつも、スポーツをやったり、家族で旅行に行ったりする。そして6年生から本格的に塾で演習だけを始めるのでも良いのではないでしょうか。
実際に、6年生でも他塾から優秀な子が移ってくれば、塾は歓迎してくれます。だから、できるようになっていれば実は早く始めるかどうかは大きな問題ではない。
ちゃんとできるようになるか、そこに視点があるべきなのです。子どもは成長の度合いがやはりそれぞれ違います。早く成長する子もいれば、晩熟の子もいるわけです。だから子どもの成長度合いに本来は勉強の仕方を合わせていかないといけない。
それを画一的に進めるから、「しんどい」と思う子が増えるのではないでしょうか。
=============================================================
今日の田中貴.com
Kindle版発刊のお知らせ
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
11月1日の問題
==============================================================
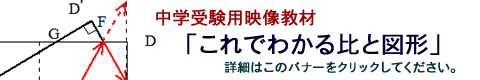
==============================================================
お知らせ
算数4年後期第11回 算数オンライン塾「分数の積と商」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )





