中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
競争させることは意味があるのか?
4年生の保護者のみなさまへ
中学受験パパママ塾「ONE」のご案内
受験教育は長きにわたり、子どもたちをずっと競争させてきました。
テスト会に始まり、週例テスト、月例テスト、組み分けテスト、と形は変わったにせよ、偏差値、順位、そういったことが重視されてきたわけですが、本来受験というのは自己目標を完結すれば良いだけのことで、麻布を受ける子と開成を受ける子が競争する意味は全くありません。
しかし、ここのところ中学受験は大学受験の不透明感からブームが再燃する傾向にあり、かつ過熱し始めています。
そうなると競争が激しくなる。ところがそうなると上位にいられる子は自己肯定感が強くなりますが、逆にそうでない子は自分に対して自信がつかなくなる。
それが、勉強に対する意欲を失わせる傾向にあり、最近とみに「勉強させられる子」が増えているのです。
決められたことをやらないのは、勉強に対する意欲が湧いてこない、勉強が面白くないからで、「どうせダメだから」というような気持ちに10歳ぐらいからなるのは、やはり多少なりとも問題がある。
もちろん子どもの力を把握する必要は当然あるわけですが、しかし、結果は自分だけが知っていれば良い話であって、別に人と比べなくても良い。
ところが今の塾は組み分けで座席まで決めてしまうので、子どものストレスは大きくなっているのです。
親もそうなると何とかしないと、ということになるわけですが、その無理が「勉強させられる子」を作ってしまいがち。
多少なりとも問題が出てきているようであれば、その競争から一旦離脱しても良いのです。
力の把握は6年生になってから、模擬試験を受ければ十分にわかる。
それよりも、子どもの自己肯定感を強くする方法を考えていかないと、受験結果ばかりか、今後の勉強に対する姿勢にも影響するので、気をつけてください。
2019-2020 合格手帳12ー1月号を差し上げています。
2019ー2020合格手帳4.5年生12-1月号申し込み
Newフリーダム進学教室からのお知らせ
冬期講習のお知らせ
今日の田中貴.com
個別指導だけで受験する
5年生の教室から
5年のうちに読解力をあげたい
算数オンライン塾
11月15日の問題


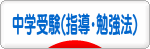
にほんブログ村
中学受験パパママ塾「ONE」のご案内
受験教育は長きにわたり、子どもたちをずっと競争させてきました。
テスト会に始まり、週例テスト、月例テスト、組み分けテスト、と形は変わったにせよ、偏差値、順位、そういったことが重視されてきたわけですが、本来受験というのは自己目標を完結すれば良いだけのことで、麻布を受ける子と開成を受ける子が競争する意味は全くありません。
しかし、ここのところ中学受験は大学受験の不透明感からブームが再燃する傾向にあり、かつ過熱し始めています。
そうなると競争が激しくなる。ところがそうなると上位にいられる子は自己肯定感が強くなりますが、逆にそうでない子は自分に対して自信がつかなくなる。
それが、勉強に対する意欲を失わせる傾向にあり、最近とみに「勉強させられる子」が増えているのです。
決められたことをやらないのは、勉強に対する意欲が湧いてこない、勉強が面白くないからで、「どうせダメだから」というような気持ちに10歳ぐらいからなるのは、やはり多少なりとも問題がある。
もちろん子どもの力を把握する必要は当然あるわけですが、しかし、結果は自分だけが知っていれば良い話であって、別に人と比べなくても良い。
ところが今の塾は組み分けで座席まで決めてしまうので、子どものストレスは大きくなっているのです。
親もそうなると何とかしないと、ということになるわけですが、その無理が「勉強させられる子」を作ってしまいがち。
多少なりとも問題が出てきているようであれば、その競争から一旦離脱しても良いのです。
力の把握は6年生になってから、模擬試験を受ければ十分にわかる。
それよりも、子どもの自己肯定感を強くする方法を考えていかないと、受験結果ばかりか、今後の勉強に対する姿勢にも影響するので、気をつけてください。
2019-2020 合格手帳12ー1月号を差し上げています。
以下からお申込ください。
無料です。
2019ー2020合格手帳6年生入試直前号申し込み
2019ー2020合格手帳4.5年生12-1月号申し込み
Newフリーダム進学教室からのお知らせ
冬期講習のお知らせ
今日の田中貴.com
個別指導だけで受験する
5年生の教室から
5年のうちに読解力をあげたい
算数オンライン塾
11月15日の問題


にほんブログ村
コメント ( 0 )





