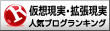なぜ、私は南直哉師の本を翻訳しようとしているのか。
なぜ、南直哉師の本を翻訳する人は私でなければならないのか。
これら二つの問いは私の現在の在り方であり、
過去と未来でもある。
私の今までの生きてきた人生を3で割ってみると
韓国での前期三分の一
日本での中期三分の一
残りの後期三分の一は
今アメリカでくぐり抜けている過程経過で
言い表すことができる。
私は前期、中期に亘って自ら課した課題を全部クリアした。
学歴、経済力、経歴において
私の自己を満足させることができた。
心残りが無い。
努力によって達成できる課題を自らに課し、
時間をかけて踏むべき段階を着実に踏んできた。
ところが、自ら設定した課題の頂きに上り詰め、
歩んできた道を見渡した時に見えたのは
課題の達成は目的地でなく、
他の歩むべき道への道なりの経路であるとのことであった。
与えてもらった我人生の三分の二を
ただ私個人の自己満足のために使ったのだが、
それはあくまでも飢餓を満たす行為に過ぎない。
飢餓や喉の渇きは充足させれば、
需要に応じて供給が成され、因果が済む。
私の人生に生じた自らの需要も
自らの供給で因果関係が成立したから、決着させた。
問題は因果が済み、
決着をつけた後に現れた方向性の無い私の心であった。
目的の無い努力は根幹を失い、
自然に淘汰していくように、
行先を失った私の心は
努力する理由を見つけることができなかったのであった。
そんな時に、ばったり南直哉師の生き方に出会い、
私の残り人生をかけて成すべき努力の方向性が定まったのである。
では、なぜ他の人でなく南直哉師なのかの
問いへの私の答えだが、
特に決めた理由は無いとしか言いようが無い。
理屈な理由は無いのだが、直感は確かにあった。
その直感は彼が使うことばで表れた以下の事実を根拠として成り立つ。
彼の発することばは生きている。
彼の言語力は死んだことばを甦らすことができる。
彼の説得力は固定観念を打ち砕ける実行力を合わせ持つ。
彼の使うことばは硬い何かを砕く力がある。
彼のことばは追及するための道具であり、
その道具を正しく使っている。
これらの私の彼への直感を証明していくことが
次の成すべき課題かもしれない。
なぜ、彼の本を翻訳する人が私でなければならないのか、
この問いも私に決まった答えが無い。
だが、彼の生きていることばを
英語で死なせることはしないとの確信はある。
それも直感に過ぎないが….
補足
これらのシリーズを読んで下さった方々へ
宣言した記事の英訳のアップですが、
訳わからず、中々手につかないでいます。
私はこのシリーズを書くことによって、
他の道への折り返し、その分岐点にしようとしています。
なので、私にとっては生き方がかかる記事なのです。
英訳はこの激流を乗り終えたら
自然に書けるようになるかも....