口径40cm反射望遠鏡の主鏡光軸修正装置を改善したことを 【 2025年2月のブログ記事 】に書きました。
改善した光軸修正装置の使い勝手を確かめようと、4月11日(金)の夜に使ってみました。

水色の3ヶ所のハンドルを回すことで微妙な光軸微調整が短時間で簡単にできるようになりました。
望遠鏡を向ける向きによって僅かに主鏡の光軸がずれるのを素早く修正できるようにしたのが今回の改善点です。

しし座のレグルスを導入後、口径40cm主鏡の光軸合わせを行い焦点外像をスマホで撮影してみました。肉眼では同心円に合わせたつもりですが、僅かに偏心というか非対象があります。左側外周の星像が僅かに欠けているのは、開閉式の主鏡蓋が光路を僅かに遮ってしまったからです。
スライディングルーフを開けてから50分しか経過しておらず、焦点外像に映り込む鏡筒内気流が反時計回りで15秒から20秒ほどで1回転している最中に露出2秒で撮影。

主鏡裏側の合焦位置(バックフォーカス)が設計値どおりの345mmになるよう、副鏡の光軸方向の前後位置(Z位置)を微調整しました。これで球面収差が計算上は最小になったはずです。
なお、副鏡を動かす仕組みはブログ記事 【 副鏡を前後に動かす理由 】に書いておきました。
さっそく、しし座のω星を導入。この星は SkySafari によると、主星5.42等級・伴星7.28等級・離角1.0秒角・位置角119.5度の二重星です。
口径15cm屈折330倍で分離。ただ、伴星は暗いためじっくりみないと分離できませんでした。口径40cm反射400倍だと集光力があるため伴星があっさりと確認できましたが、屈折望遠鏡よりも筒内気流の影響を受けやすいためシャープな星像ではありません。
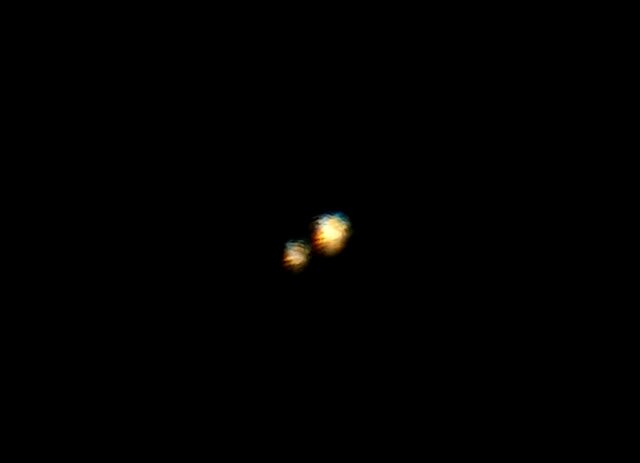
しし座のγ星アルギエバを口径40cm反射望遠鏡+スマホでコリメート撮影。
主星2.23等級・伴星3.64等級・離角4.8秒角・位置角127.9度です。大気の揺れもあって1枚の撮って出し画像だとギザギザな星像ですが、非点収差(コマ収差?)のようにも見えるのが気がかりです。眼視だと気がつきませんでした。副鏡のXY位置の微調整が必要かもしれません。
20時40分に屋上から撤収。気温は9度でした。
【4月17日21時:記事追加】
上記文章に「非点収差(コマ収差?)のようにも見える」と書きましたが、色々とテストしてみた結果、どうやら接眼鏡の光軸とスマホ撮影レンズの光軸が僅かにズレたのが原因のようです。
改善した光軸修正装置の使い勝手を確かめようと、4月11日(金)の夜に使ってみました。

水色の3ヶ所のハンドルを回すことで微妙な光軸微調整が短時間で簡単にできるようになりました。
望遠鏡を向ける向きによって僅かに主鏡の光軸がずれるのを素早く修正できるようにしたのが今回の改善点です。

しし座のレグルスを導入後、口径40cm主鏡の光軸合わせを行い焦点外像をスマホで撮影してみました。肉眼では同心円に合わせたつもりですが、僅かに偏心というか非対象があります。左側外周の星像が僅かに欠けているのは、開閉式の主鏡蓋が光路を僅かに遮ってしまったからです。
スライディングルーフを開けてから50分しか経過しておらず、焦点外像に映り込む鏡筒内気流が反時計回りで15秒から20秒ほどで1回転している最中に露出2秒で撮影。

主鏡裏側の合焦位置(バックフォーカス)が設計値どおりの345mmになるよう、副鏡の光軸方向の前後位置(Z位置)を微調整しました。これで球面収差が計算上は最小になったはずです。
なお、副鏡を動かす仕組みはブログ記事 【 副鏡を前後に動かす理由 】に書いておきました。
さっそく、しし座のω星を導入。この星は SkySafari によると、主星5.42等級・伴星7.28等級・離角1.0秒角・位置角119.5度の二重星です。
口径15cm屈折330倍で分離。ただ、伴星は暗いためじっくりみないと分離できませんでした。口径40cm反射400倍だと集光力があるため伴星があっさりと確認できましたが、屈折望遠鏡よりも筒内気流の影響を受けやすいためシャープな星像ではありません。
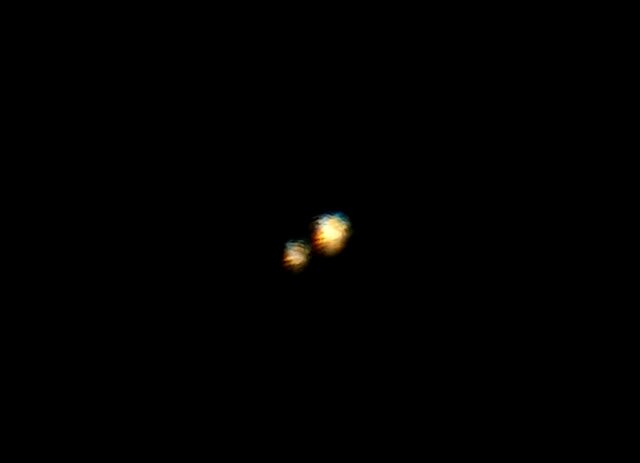
しし座のγ星アルギエバを口径40cm反射望遠鏡+スマホでコリメート撮影。
主星2.23等級・伴星3.64等級・離角4.8秒角・位置角127.9度です。大気の揺れもあって1枚の撮って出し画像だとギザギザな星像ですが、非点収差(コマ収差?)のようにも見えるのが気がかりです。眼視だと気がつきませんでした。副鏡のXY位置の微調整が必要かもしれません。
20時40分に屋上から撤収。気温は9度でした。
【4月17日21時:記事追加】
上記文章に「非点収差(コマ収差?)のようにも見える」と書きましたが、色々とテストしてみた結果、どうやら接眼鏡の光軸とスマホ撮影レンズの光軸が僅かにズレたのが原因のようです。






















 91340110
91340110 s2201182
s2201182 iP220212
iP220212 iP220212
iP220212 s220212
s220212 s220128
s220128 s220128
s220128 s220128
s220128 91450789F28RGBWUT
91450789F28RGBWUT




