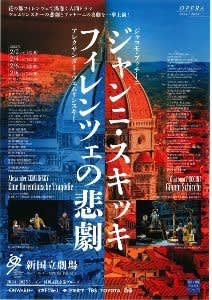東京春祭プッチーニ・シリーズ、2025年は『蝶々夫人』。バイロイトで初めてピットに入った女性指揮者として注目を集めているオクサーナ・リーニフが読響を率いた。タイトルロールはラナ・コス、ピンカートンはピエロ・プレッティ、シャープレス甲斐栄次郎さん、スズキ清水華澄さん。合唱は東京オペラシンガーズ。
演奏会形式といっても先日の『パルジファル』が譜面台つきだったのに対して、こちらはほぼ芝居付きオペラ。冒頭から糸賀修平さんのゴローとピンカートンのプレッティのやり取りが愉快なムードを醸し出した。プレッティは代役だが、素晴らしく勇敢なピンカートンで、声量も演劇性もバッチリ。1968年生まれで今年57歳なので実年齢的にはシャープレスの年だが、ものの分かった年頃の歌手が無茶で自分勝手な若者を演じる様子が味わい深かった。高音も迷いがなく、朗々として伸びやか。タイプとしては地味で堅実な歌手という印象だが、磨かれた職人肌の芸を聴かせてくれる。蝶々さんが登場するまでの15分間が個人的に最も泣けるシーンで、恋に浮かれるピンカートンに「よせよ。彼女は本気だぜ」とたしなめるシャープレスのフレーズが、オペラの悲劇性を先取りしている。とりあえずウイスキーで乾杯する二人。この時点ではまだピンカートンは罪人ではなく、夢見がちな無辜の青年なのだ。甲斐栄次郎さんのシャープレスには説得力があり、改めてこのオペラの鍵を握る役だと思った。
蝶々さん登場。ラナ・コスのピンクがかったホワイトのドレスがゴージャスで「これで蝶々さんを歌うのか!」と一瞬ひるんだが、堂々とした歌声の威力に飲み込まれ、「主役はわたしよ!」という気合に降伏した。スズキの清水華澄さんの着物風ドレスが妖艶だったのも、ラナ・コスに合わせたのかも知れない。髪型もディーバ仕様のまとめ髪で、次から次へと迷いなくお芝居を進めていく。蝶々さんのパートは確かにこうしたタフネスがないと聞きごたえがない。ピンカートンとの愛の二重唱は、トリスタンとイゾルデのようで、二人の大きな重唱がホール全体を埋め尽くした後、当然キスシーンがあると思い込んでいたが、プレッティのキャラクター的に無理だったのだろう。ピンカートンが若妻に敬意を表するようなポーズで一幕が閉じた。
オクサーナ・リーニフの後ろ姿は女版トスカニーニといった風情で、きびきびと凛々しく、細かいところまで妥協がない。リーニフはボローニャ歌劇場のシェフとしても来日しているが、祖国のオデッサの歌劇場で共演が長かったグレギーナが、自分よりだいぶ若いリーニフにしがみつくようにして信頼の情を表していたのが印象深かった。ボローニャ歌劇場の会見は、なぜかリーニフだけドイツ語で行われたが、最新の彼女はドイツ語で思考しているのかも知れない。
読響は素晴らしいのだが、先日の沖澤カルメンやヴァイグレのヴォツェックでは聴くことのなかった管楽器のミスや、分数が怪しくなる箇所があった。リーニフは既に色々なところで蝶々さんを振っているはずだが、もしかしたら指揮者のコントロールがきつすぎるのではないかとも思った。完璧主義者なのだろう。プッチーニのダイナミズムはプレイヤーの生命潮流に任せたほうがうまく着地する。それでも、蝶々さんが教会で改宗したことを告白する場面のエクスタシーに溢れた表現は見事だった。輝かしいプッチーニのオーケストレーションの中でも、さらに甘やかなシーンを何か所か際立てて鳴らしていた。
全編歌いっぱなしのラナ・コスは微塵の疲れも見せず、「ある晴れた日に」もオペラの一場面として自然に歌って聴かせた。ドレスは派手だが声は癖がなく、歌えば歌うほど聴き手の心を引き付けていく。生まれながらに大きな才能の持ち主だが、それに溺れず謙虚に積み上げてきた痕跡が見えた。無邪気な少女である蝶々さんを、声を自在に駆使して表現し、どの場面でもオケを味方につけていく。スズキとの花の二重唱は改めて音程の取り方が独特の歌だと思ったが、印象派的な響きが眩暈するほど麗しい。壮大な間奏曲の後に、つかの間の眠りをとる蝶々さんの子守歌が悲しく「可哀そうな蝶々さん…!」のスズキの声にも涙が溢れる。
自分の好きなオペラは『トスカ』『ボエーム』『蝶々さん』と即答できるほどで、『トゥーランドット』はやや特殊とはいえ、最高峰はやはり『トスカ』だと思っていた。しかしながら『蝶々夫人』を改めて聴くと、『トスカ』の構築性の見事さとは別の、繊細な織物のようなテクスチャーがパッチワークされている音楽の至芸に驚く。それは主に、年若い蝶々さんから見た世界で、玩具のような結婚式も、寄ってくるお大尽の滑稽さも、ピンカートンへの思慕も、ヒロインの主観から編み上げられている。『トスカ』とは全く違う作り方なのだ。日本の工芸細工のような意匠も盛り込まれている。アイデアの宝庫であり、愛の発明であり、間違いなくオペラの最高傑作で、この日ばかりはトップ・オブ・ザ・トップの作品だと崇拝せずにはいられなかった。蝶々さん不在の中で歌われるシャープレス、スズキ、ピンカートンの三重唱は、どの宗教曲より胸かきむしられる痛恨のレクイエムだ。
子役は登場せず、「可愛い坊や…!」もラナ・コスは子供を抱く仕草で歌いあげたが、「あなたは海をわたっていくこともできる」という字幕が殊更に心に響き、蝶々夫人の続編が書かれたり、二期会の亞門演出のようなプロダクションが作られることも自然だと思われた。ピンカートンはラストシーンまで悪役設定だが、現実として考えた場合、蝶々さんのような女性が全力で自分を愛してくれたことを生涯忘れるはずはない。どこまで行ってもこれはラブストーリーなのだ。
歌い損だなどと思わず200%の誠実さでピンカートンを歌ってくれたプレッティは、本当に信頼できる。ラナ・コスも伝説のバタフライだった。出番は短いが、圧倒するような存在感でオペラを切り裂いたボンゾの三戸大久さん、悪役ではなく良識ある年長者として温かいヤマドリを演じた畠山茂さんにも感謝は尽きない。ミュージカル・ファンが『レ・ミゼラブル』を数えきれないくらい観てしまうように、自分も『蝶々夫人』をマニアックに愛していて、残りの人生あと100回は無理でも、50回くらいは観たい。ドレスの両端を広げたラナ・コスのシルエットが「バタフライ」だったのに気づき、改めて大喝采。

演奏会形式といっても先日の『パルジファル』が譜面台つきだったのに対して、こちらはほぼ芝居付きオペラ。冒頭から糸賀修平さんのゴローとピンカートンのプレッティのやり取りが愉快なムードを醸し出した。プレッティは代役だが、素晴らしく勇敢なピンカートンで、声量も演劇性もバッチリ。1968年生まれで今年57歳なので実年齢的にはシャープレスの年だが、ものの分かった年頃の歌手が無茶で自分勝手な若者を演じる様子が味わい深かった。高音も迷いがなく、朗々として伸びやか。タイプとしては地味で堅実な歌手という印象だが、磨かれた職人肌の芸を聴かせてくれる。蝶々さんが登場するまでの15分間が個人的に最も泣けるシーンで、恋に浮かれるピンカートンに「よせよ。彼女は本気だぜ」とたしなめるシャープレスのフレーズが、オペラの悲劇性を先取りしている。とりあえずウイスキーで乾杯する二人。この時点ではまだピンカートンは罪人ではなく、夢見がちな無辜の青年なのだ。甲斐栄次郎さんのシャープレスには説得力があり、改めてこのオペラの鍵を握る役だと思った。
蝶々さん登場。ラナ・コスのピンクがかったホワイトのドレスがゴージャスで「これで蝶々さんを歌うのか!」と一瞬ひるんだが、堂々とした歌声の威力に飲み込まれ、「主役はわたしよ!」という気合に降伏した。スズキの清水華澄さんの着物風ドレスが妖艶だったのも、ラナ・コスに合わせたのかも知れない。髪型もディーバ仕様のまとめ髪で、次から次へと迷いなくお芝居を進めていく。蝶々さんのパートは確かにこうしたタフネスがないと聞きごたえがない。ピンカートンとの愛の二重唱は、トリスタンとイゾルデのようで、二人の大きな重唱がホール全体を埋め尽くした後、当然キスシーンがあると思い込んでいたが、プレッティのキャラクター的に無理だったのだろう。ピンカートンが若妻に敬意を表するようなポーズで一幕が閉じた。
オクサーナ・リーニフの後ろ姿は女版トスカニーニといった風情で、きびきびと凛々しく、細かいところまで妥協がない。リーニフはボローニャ歌劇場のシェフとしても来日しているが、祖国のオデッサの歌劇場で共演が長かったグレギーナが、自分よりだいぶ若いリーニフにしがみつくようにして信頼の情を表していたのが印象深かった。ボローニャ歌劇場の会見は、なぜかリーニフだけドイツ語で行われたが、最新の彼女はドイツ語で思考しているのかも知れない。
読響は素晴らしいのだが、先日の沖澤カルメンやヴァイグレのヴォツェックでは聴くことのなかった管楽器のミスや、分数が怪しくなる箇所があった。リーニフは既に色々なところで蝶々さんを振っているはずだが、もしかしたら指揮者のコントロールがきつすぎるのではないかとも思った。完璧主義者なのだろう。プッチーニのダイナミズムはプレイヤーの生命潮流に任せたほうがうまく着地する。それでも、蝶々さんが教会で改宗したことを告白する場面のエクスタシーに溢れた表現は見事だった。輝かしいプッチーニのオーケストレーションの中でも、さらに甘やかなシーンを何か所か際立てて鳴らしていた。
全編歌いっぱなしのラナ・コスは微塵の疲れも見せず、「ある晴れた日に」もオペラの一場面として自然に歌って聴かせた。ドレスは派手だが声は癖がなく、歌えば歌うほど聴き手の心を引き付けていく。生まれながらに大きな才能の持ち主だが、それに溺れず謙虚に積み上げてきた痕跡が見えた。無邪気な少女である蝶々さんを、声を自在に駆使して表現し、どの場面でもオケを味方につけていく。スズキとの花の二重唱は改めて音程の取り方が独特の歌だと思ったが、印象派的な響きが眩暈するほど麗しい。壮大な間奏曲の後に、つかの間の眠りをとる蝶々さんの子守歌が悲しく「可哀そうな蝶々さん…!」のスズキの声にも涙が溢れる。
自分の好きなオペラは『トスカ』『ボエーム』『蝶々さん』と即答できるほどで、『トゥーランドット』はやや特殊とはいえ、最高峰はやはり『トスカ』だと思っていた。しかしながら『蝶々夫人』を改めて聴くと、『トスカ』の構築性の見事さとは別の、繊細な織物のようなテクスチャーがパッチワークされている音楽の至芸に驚く。それは主に、年若い蝶々さんから見た世界で、玩具のような結婚式も、寄ってくるお大尽の滑稽さも、ピンカートンへの思慕も、ヒロインの主観から編み上げられている。『トスカ』とは全く違う作り方なのだ。日本の工芸細工のような意匠も盛り込まれている。アイデアの宝庫であり、愛の発明であり、間違いなくオペラの最高傑作で、この日ばかりはトップ・オブ・ザ・トップの作品だと崇拝せずにはいられなかった。蝶々さん不在の中で歌われるシャープレス、スズキ、ピンカートンの三重唱は、どの宗教曲より胸かきむしられる痛恨のレクイエムだ。
子役は登場せず、「可愛い坊や…!」もラナ・コスは子供を抱く仕草で歌いあげたが、「あなたは海をわたっていくこともできる」という字幕が殊更に心に響き、蝶々夫人の続編が書かれたり、二期会の亞門演出のようなプロダクションが作られることも自然だと思われた。ピンカートンはラストシーンまで悪役設定だが、現実として考えた場合、蝶々さんのような女性が全力で自分を愛してくれたことを生涯忘れるはずはない。どこまで行ってもこれはラブストーリーなのだ。
歌い損だなどと思わず200%の誠実さでピンカートンを歌ってくれたプレッティは、本当に信頼できる。ラナ・コスも伝説のバタフライだった。出番は短いが、圧倒するような存在感でオペラを切り裂いたボンゾの三戸大久さん、悪役ではなく良識ある年長者として温かいヤマドリを演じた畠山茂さんにも感謝は尽きない。ミュージカル・ファンが『レ・ミゼラブル』を数えきれないくらい観てしまうように、自分も『蝶々夫人』をマニアックに愛していて、残りの人生あと100回は無理でも、50回くらいは観たい。ドレスの両端を広げたラナ・コスのシルエットが「バタフライ」だったのに気づき、改めて大喝采。