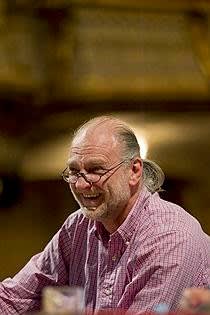二期会のペーター・コンヴィチュニー演出『影のない女』(ボン歌劇場との共同制作)の上演が連日熱い議論を呼んでいる。事前に「皆さんは死んだオペラを観ている」といったコンヴィチュニーの発言の一部が非難され、カーテンコールの映像では初日から激しいブーイングが飛んだ様子。プロの歌手や批評家からも、主に3幕の大幅カットについて批判が起こり、その他にもしかじかの性的表現や、歌詞や設定への変更が一種のアレルギー的な反応を引き起こしていた。
Bキャストのゲネプロを見たとき、最初は何が語られているのか分からなかった。前回このオペラを観たのは2011年のマリインスキー劇場の来日公演で、指揮はゲルギエフ、演出はジョナサン・ケントで、同じプロダクションを2010年にサンクトペテルブルクの白夜祭でも観ていた。霊界のカップルと地上のカップルが交差する幻想的な物語という印象だったが、コンヴィチュニー版ではバラクはそもそも染物屋でもないし、皇后と乳母は清掃スタッフの恰好をして現実に舞い降りる。皇帝はギャングのボスで、たくさんのシーンでピストルの暴発が起こる。
ゲネプロでは前半の100分がチンプンカンプンで、後半の45分で急に色々なことが覚醒した。皇后の腹から取り出された嬰児が「アナタノ子供ダヨー! ドウカ死ナセテ! モウタクサン!」と語り出す場面で、頭が真っ白になった。観る人によっては由々しい印象を得たかも知れない。この世界に生まれてくることが、子供にとって幸せなのか? ガザ地区やウクライナで殺されたり手足を失ったりしている小さな子供たちを思い出し、何よりいい年をしてこの世に存在している実感が湧かない自分のことを思った。
コンヴィチュニーの精神の内奥には、癒し難い厭世観があると思う。プログラムではドラマトゥルクのべッティーナ・バルツの長大なコンセプトが掲載されているが、そうしたアイデアに反応してしまうコンヴィチュニーは、「生存している」という当たり前のことに暗い気持ちを抱いているからなのではないか。今まで観てきたオペラにもそれを感じた。
R・シュトラウスが『影のない女』を完成させたのは1919年で、最初の世界大戦が始まった5年後で、その後の20世紀は戦争の時代となり、「産めよ増やせよ」の富国強兵のスローガンが欧州にも蔓延した。「女はまるで軍用道路!」と叫ぶ妻。それまで対立していたバラクとその妻が、急に和解する3幕が大幅にカットされたが、劇中最も甘美で豊饒な部分を「抜いた」ことに大きな意味がある。作品を愛する人々にとっては多大なフラストレーションだが、演出家はそこに嘘があると確信し、メスを入れた。
版権が切れているのだから、演出家は自由にカットする権利がある。一方で「オペラはみんなのもの」だから勝手なことはするな、という一般論がある。演出家は劇場と外の世界を交流させ、人間全体の意識を覚醒させたいと思っているが、一部の(多くの?)鑑賞者はそれを「要らない」という。このままではコンヴィチュニーが時代錯誤のエゴイストになってしまう。そんなことはあってはならないと思う。
本公演は26日の初日キャストを10列目で観た。ゲネは一階の最後列で観たので、その景色はずいぶん違っていた。本番3回目で上演として円熟していたということもあったが、間近で見る歌手たちが、愛と生命と性の本質を、暴力ぎりぎりになる局面も含めて真剣に演じていて、困難なはずの歌唱も全くそれを感じさせず、演劇的な迫力だけが横溢していたのが驚異だった。
女性歌手たちが特に凄い。バラクの妻の板波利加さんはコンヴィチュニーの愛弟子といっていいほどの歌手で、皇后の冨平安希子さんは2018年のコンヴィチュニー版『魔弾の射手』で好演し、乳母の藤井麻美さんは今回が初めてのコンヴィチュニー作品となる。その3人が、演出家の巨大な愛を受け取り、無限の可能性を舞台で花開かせ、嘘のない女性像を表現した。皇后はバラクとの性交を暗示させる長いシーンを演じなければならず、露骨ではないが大変な精神力を要すると思われた。個人的には最も素晴らしい場面だと胸打たれた。
最後列で観ていたものをステージ近くで観て印象が変わったことは、オペラ全体に精神的に近づく必然を感じさせた。バックステージツアーにも参加したが、ボンで制作された装置はハイテクで美しく、照明も回転する床も最新の機構が使われている。あの清潔なラボやカウンセリングルーム、夜景レストランの美術について、ほとんど指摘されないのが不思議である。装置の贅沢さには見るべきものがある。
近くに寄らないと見えないものがあるのに、見ようとしないのは何故なのか。性的表現も、自分自身に近づいて考えてみれば、拒絶反応以外の何かが起こるはず。バックステージツアーの後には、コンヴィチュニーによる『コジ・ファン・トゥッテ』のマスタークラスも見学した。2時間の間に若い歌手たちが驚くべき成長を遂げていた。演出家は真の天才であり、そのインスピレーションはエゴを超えた人間全体の洞察から来ていると確信した。
これだけ炎上してしまっては、もはや演出家を賞賛することは盲目的信奉者と同一視されかねないが、視野を広げれば、そもそもこうした刺激的上演を日本で観られるということ自体が凄いのである。あの巨大な装置は今日の夕刻には全部撤収され、ボンに送り返されてしまう(ほとんどの装置はボンで制作されていた)。跡形もなく消え去ってしまうあの世界が、まもなく虹のように感じられる。
アレホ・ペレスと東響の音楽は驚異的で、ペレスは演劇に寄り添った音楽を積極的に作り、ノットとの『サロメ』や『エレクトラ』が素晴らしかった東響も神業的なサウンドを聴かせた。歌手たちは全員エンジンを唸らせて、オーケストラと一心同体になっていた。
人間はショックなことが起こらないと眠ったままでいる、と言ったのはベジャールだった。眠ったままでいいはずがない。揺り起こそうとするコンヴィチュニーに「嫌だ!」とブーイングした観客まで、演出家が予測したアートの一部だったのかも知れない。黙示録的な上演だった。
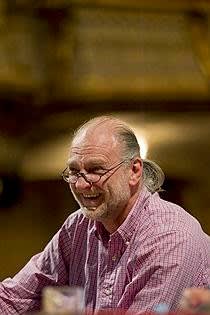
Bキャストのゲネプロを見たとき、最初は何が語られているのか分からなかった。前回このオペラを観たのは2011年のマリインスキー劇場の来日公演で、指揮はゲルギエフ、演出はジョナサン・ケントで、同じプロダクションを2010年にサンクトペテルブルクの白夜祭でも観ていた。霊界のカップルと地上のカップルが交差する幻想的な物語という印象だったが、コンヴィチュニー版ではバラクはそもそも染物屋でもないし、皇后と乳母は清掃スタッフの恰好をして現実に舞い降りる。皇帝はギャングのボスで、たくさんのシーンでピストルの暴発が起こる。
ゲネプロでは前半の100分がチンプンカンプンで、後半の45分で急に色々なことが覚醒した。皇后の腹から取り出された嬰児が「アナタノ子供ダヨー! ドウカ死ナセテ! モウタクサン!」と語り出す場面で、頭が真っ白になった。観る人によっては由々しい印象を得たかも知れない。この世界に生まれてくることが、子供にとって幸せなのか? ガザ地区やウクライナで殺されたり手足を失ったりしている小さな子供たちを思い出し、何よりいい年をしてこの世に存在している実感が湧かない自分のことを思った。
コンヴィチュニーの精神の内奥には、癒し難い厭世観があると思う。プログラムではドラマトゥルクのべッティーナ・バルツの長大なコンセプトが掲載されているが、そうしたアイデアに反応してしまうコンヴィチュニーは、「生存している」という当たり前のことに暗い気持ちを抱いているからなのではないか。今まで観てきたオペラにもそれを感じた。
R・シュトラウスが『影のない女』を完成させたのは1919年で、最初の世界大戦が始まった5年後で、その後の20世紀は戦争の時代となり、「産めよ増やせよ」の富国強兵のスローガンが欧州にも蔓延した。「女はまるで軍用道路!」と叫ぶ妻。それまで対立していたバラクとその妻が、急に和解する3幕が大幅にカットされたが、劇中最も甘美で豊饒な部分を「抜いた」ことに大きな意味がある。作品を愛する人々にとっては多大なフラストレーションだが、演出家はそこに嘘があると確信し、メスを入れた。
版権が切れているのだから、演出家は自由にカットする権利がある。一方で「オペラはみんなのもの」だから勝手なことはするな、という一般論がある。演出家は劇場と外の世界を交流させ、人間全体の意識を覚醒させたいと思っているが、一部の(多くの?)鑑賞者はそれを「要らない」という。このままではコンヴィチュニーが時代錯誤のエゴイストになってしまう。そんなことはあってはならないと思う。
本公演は26日の初日キャストを10列目で観た。ゲネは一階の最後列で観たので、その景色はずいぶん違っていた。本番3回目で上演として円熟していたということもあったが、間近で見る歌手たちが、愛と生命と性の本質を、暴力ぎりぎりになる局面も含めて真剣に演じていて、困難なはずの歌唱も全くそれを感じさせず、演劇的な迫力だけが横溢していたのが驚異だった。
女性歌手たちが特に凄い。バラクの妻の板波利加さんはコンヴィチュニーの愛弟子といっていいほどの歌手で、皇后の冨平安希子さんは2018年のコンヴィチュニー版『魔弾の射手』で好演し、乳母の藤井麻美さんは今回が初めてのコンヴィチュニー作品となる。その3人が、演出家の巨大な愛を受け取り、無限の可能性を舞台で花開かせ、嘘のない女性像を表現した。皇后はバラクとの性交を暗示させる長いシーンを演じなければならず、露骨ではないが大変な精神力を要すると思われた。個人的には最も素晴らしい場面だと胸打たれた。
最後列で観ていたものをステージ近くで観て印象が変わったことは、オペラ全体に精神的に近づく必然を感じさせた。バックステージツアーにも参加したが、ボンで制作された装置はハイテクで美しく、照明も回転する床も最新の機構が使われている。あの清潔なラボやカウンセリングルーム、夜景レストランの美術について、ほとんど指摘されないのが不思議である。装置の贅沢さには見るべきものがある。
近くに寄らないと見えないものがあるのに、見ようとしないのは何故なのか。性的表現も、自分自身に近づいて考えてみれば、拒絶反応以外の何かが起こるはず。バックステージツアーの後には、コンヴィチュニーによる『コジ・ファン・トゥッテ』のマスタークラスも見学した。2時間の間に若い歌手たちが驚くべき成長を遂げていた。演出家は真の天才であり、そのインスピレーションはエゴを超えた人間全体の洞察から来ていると確信した。
これだけ炎上してしまっては、もはや演出家を賞賛することは盲目的信奉者と同一視されかねないが、視野を広げれば、そもそもこうした刺激的上演を日本で観られるということ自体が凄いのである。あの巨大な装置は今日の夕刻には全部撤収され、ボンに送り返されてしまう(ほとんどの装置はボンで制作されていた)。跡形もなく消え去ってしまうあの世界が、まもなく虹のように感じられる。
アレホ・ペレスと東響の音楽は驚異的で、ペレスは演劇に寄り添った音楽を積極的に作り、ノットとの『サロメ』や『エレクトラ』が素晴らしかった東響も神業的なサウンドを聴かせた。歌手たちは全員エンジンを唸らせて、オーケストラと一心同体になっていた。
人間はショックなことが起こらないと眠ったままでいる、と言ったのはベジャールだった。眠ったままでいいはずがない。揺り起こそうとするコンヴィチュニーに「嫌だ!」とブーイングした観客まで、演出家が予測したアートの一部だったのかも知れない。黙示録的な上演だった。