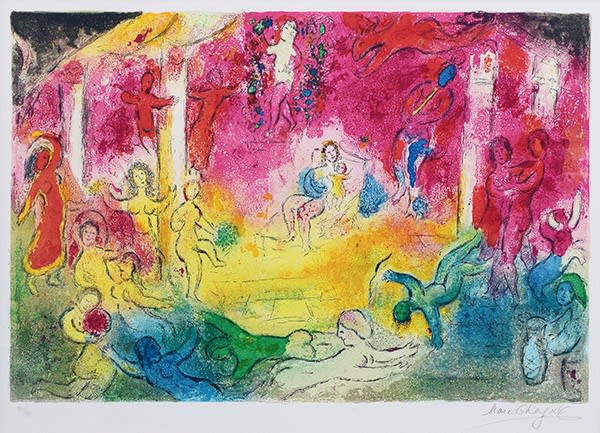来日できなかったインバルの「代役」を振った先週のプロムナードコンサートに続き、予定されていたブルックナー7番を2日間指揮した都響の首席客演指揮者アラン・ギルバート。2日目のサントリーホールでのコンサートを聴いた。コンサートマスターは矢部達哉さん。
日本初演となるソルヴァルドスドッティル『メタコスモス』(2017)は、14分ほどの曲。オーケストラ全体にディストーションがかかっているような印象の曲で、弦楽器からは日本の声明(しょうみょう)のような、西洋音楽の合唱ではみられない微妙なバラつきのある「声」の重なりを感じた。異様なほどの音の密度がホールに充填し、呪術的な気配が立ち込めた。管楽器の単一の響きもマンモスの産声(?)のように不気味で、フルートは石笛を連想させ、音楽全体が基音ではなく倍音のみの「影」から出来ているような印象。打楽器がワイルドに鳴り出す件は、神社太鼓なのではないかと思った。邪なるものを祓っているような、逆に降ろしているような、両方の意味が感じられた。作曲家の覚え書きには直接記されていないが、東洋的な器楽演奏にインスパイアされている部分が多いと思われた。
前半の短い曲のあとに20分の休憩があり、後半はブルックナー『交響曲第7番(ノヴァーク版)』が演奏された。ギルバートは指揮棒なし。譜面台も譜面もなく、宇宙遊泳するようにブルックナーを歌い始めた。指揮をしているというより、歌っているような感じなのだ。第1楽章の冒頭では、これはオーソドックスなブルックナーなのかなと一瞬思った。奇異なところがなく、大きなものに抱かれているような安心感がある。おおらかで透明感があり、弦の合奏は前半とは対を成すような流麗な「詠唱」だった。どのようなリハーサルだったのだろう。指揮者が安心してオケに「心を読ませている」ような様子を想像した。
大柄なギルバートがオケから温かい音を引き出す姿を見て、人が無心に何かを表現しているとき、顕在意識ではコントロールできない「素」が顕れるものだなと考えた。曖昧模糊とした言葉になるかも知れないが、その人が負った「魂」が見えるような気がする。指揮者がうっかり引き出してしまう音楽の邪悪さというものもあるが、ギルバートはイマジネーションを極限まで拡げても、どこまでも透明感があって善良なのだ。人は何によって善良となるか。先祖の魂によってだ。おかしなことを言っていると思われても構わない。人間はある意味受け身の存在で、膨大な先祖の魂が玉突きになって、今の自分が存在している。世俗を生きていくときに嘘をつくのも嘘がつけないのも、その行いは先祖の魂が支配している。
ブルックナーは信心深く、世事に疎いところがある人物だった。女性にもてなかった逸話も有名で、愛に傷ついていたマーラーや、愛に関しては放埓だったチャイコフスキーのことを考えながらブルックナーの7番の交響曲を聴くと、現実の女性を必要としない、根源的な女性性が既に作曲家の中に存在しているように思われる。平和さや慈愛、優しさが感じられ、それは太陽のような無条件の愛なのだ。子供が太陽の絵を描くと微笑のような目鼻をつけることが多いが、子供は直観的だから嘘を描かない。古来から人間が太陽に感じてきた「ありがたさ」で、それは一種の宗教感覚に通じると思う。
ブルックナーが背負ってきた宗教的な魂の蓄積は、彼が「今、生きて輝く」瞬間に、歌となって結実した。都響とギルバートの演奏を聴いて、ブルックナーの交響曲は歌の集積だと思った。宗教的な魂をもつ人間にとって、音楽は食べ物と同じくらい重要で、ベネディクト派の僧たちに「負担を減らすため」宗教曲を歌わせる日課を省かせたところ、みるみるうちに全員が元気をなくしていったという記録がある。オペラ歌手、声楽家の中にも宗教的な魂の履歴を持った人々がいて、その人たちがコロナ禍で歌えなくなっていることの苦しさは、命の危機に匹敵すると思う。
ギルバートのマーラーは素晴らしい。都響とも過去に名演を残したが、マーラーとはある種のフィーリング、情感を共有していて、相性がいい。ブルックナーはそれよりも宿命的な相性で、ギルバートはブルックナーの完全なる対岸にいて、鏡のように精緻に「魂のすべて」を読み取ることが出来る。譜面を読んだときに、下手にこねくり回したり深読みしたり曲解したりせず、ありのままの作曲家の精神を引き出せる相性だと思う。指揮者にも膨大な先祖がいて、その時代にそれぞれの振る舞いをして生き残ってきた。ギルバートが「今生きて、輝く」瞬間に、ブルックナーとの出会いがあったのは、ふたつの魂にとって宿命であった。
ブルックナー7番の特に1楽章と2楽章から感じられるのは、マントラ詠唱や六方拝のような習慣化された反復で、素朴であると同時に執拗な日々の行いだ。ブルックナーはキリスト者だったが、魂が覚えているのは無数の宗教で、仏教やユダヤ教やイスラム教、原始太陽崇拝も履歴としてあった。妄想といえばそうだが、音楽とはそもそも目に見えないもの、五感を超えた感覚を喚起するものではないか。客席にいる自分は、都響とギルバートが「今生きて輝いている」ことの意味が、理屈や恐れに満ちた現実だけでは消化しきれないのだった。
3楽章のスケルツォのはじまりは何度聞いても回教徒のトランスダンスを思い出す。その後に出現する雄大な光景には、巨大な太陽の光彩が感じられる。ブルックナーもまた、今生きている自分の魂がどちらの方向に玉突きされているか、不安を抱えていた。4楽章の重々しいユニゾンは、グレゴリオ聖歌を彷彿させる。カソックを着た修道士たちが唸るように合唱している。19世紀という「モダン」を生きていたブルックナーはそこに、自分の現世のリアリティを重ねてシンフォニーの曼陀羅を完成した。指揮者は、この曲のすべてをわかっている。こんこんと湧きだしてくる自然な歌には、崇高さしか感じられなかった。
先週のプロムナードコンサートでは、(恐らく)手書きのノートの譜面が置かれていて、バルトークもコダーイも、指揮者によって緻密に研究されていた痕跡があった。あちらは急な代役だったから、責任感も強かったと思う。2つのコンサートでは、ギルバートが都響に感じている故郷のような安息感、ハイレベルな友情が共通して伝わってきた。19日にはトロンボーンの小田桐寛之さん(1986年入団)が退団され、この日はチェロ奏者の松岡陽平さんとヴィオラ奏者の南山華央倫さんが退団という、立て続けのさよならコンサートだったが、全員にプレゼントを渡していたギルバートの姿も心に残った。都響の「日常」を支えていたプレイヤーを送り出す姿に、指揮者が長年オーケストラと日常をともにしていた印象さえ抱いたのである。

日本初演となるソルヴァルドスドッティル『メタコスモス』(2017)は、14分ほどの曲。オーケストラ全体にディストーションがかかっているような印象の曲で、弦楽器からは日本の声明(しょうみょう)のような、西洋音楽の合唱ではみられない微妙なバラつきのある「声」の重なりを感じた。異様なほどの音の密度がホールに充填し、呪術的な気配が立ち込めた。管楽器の単一の響きもマンモスの産声(?)のように不気味で、フルートは石笛を連想させ、音楽全体が基音ではなく倍音のみの「影」から出来ているような印象。打楽器がワイルドに鳴り出す件は、神社太鼓なのではないかと思った。邪なるものを祓っているような、逆に降ろしているような、両方の意味が感じられた。作曲家の覚え書きには直接記されていないが、東洋的な器楽演奏にインスパイアされている部分が多いと思われた。
前半の短い曲のあとに20分の休憩があり、後半はブルックナー『交響曲第7番(ノヴァーク版)』が演奏された。ギルバートは指揮棒なし。譜面台も譜面もなく、宇宙遊泳するようにブルックナーを歌い始めた。指揮をしているというより、歌っているような感じなのだ。第1楽章の冒頭では、これはオーソドックスなブルックナーなのかなと一瞬思った。奇異なところがなく、大きなものに抱かれているような安心感がある。おおらかで透明感があり、弦の合奏は前半とは対を成すような流麗な「詠唱」だった。どのようなリハーサルだったのだろう。指揮者が安心してオケに「心を読ませている」ような様子を想像した。
大柄なギルバートがオケから温かい音を引き出す姿を見て、人が無心に何かを表現しているとき、顕在意識ではコントロールできない「素」が顕れるものだなと考えた。曖昧模糊とした言葉になるかも知れないが、その人が負った「魂」が見えるような気がする。指揮者がうっかり引き出してしまう音楽の邪悪さというものもあるが、ギルバートはイマジネーションを極限まで拡げても、どこまでも透明感があって善良なのだ。人は何によって善良となるか。先祖の魂によってだ。おかしなことを言っていると思われても構わない。人間はある意味受け身の存在で、膨大な先祖の魂が玉突きになって、今の自分が存在している。世俗を生きていくときに嘘をつくのも嘘がつけないのも、その行いは先祖の魂が支配している。
ブルックナーは信心深く、世事に疎いところがある人物だった。女性にもてなかった逸話も有名で、愛に傷ついていたマーラーや、愛に関しては放埓だったチャイコフスキーのことを考えながらブルックナーの7番の交響曲を聴くと、現実の女性を必要としない、根源的な女性性が既に作曲家の中に存在しているように思われる。平和さや慈愛、優しさが感じられ、それは太陽のような無条件の愛なのだ。子供が太陽の絵を描くと微笑のような目鼻をつけることが多いが、子供は直観的だから嘘を描かない。古来から人間が太陽に感じてきた「ありがたさ」で、それは一種の宗教感覚に通じると思う。
ブルックナーが背負ってきた宗教的な魂の蓄積は、彼が「今、生きて輝く」瞬間に、歌となって結実した。都響とギルバートの演奏を聴いて、ブルックナーの交響曲は歌の集積だと思った。宗教的な魂をもつ人間にとって、音楽は食べ物と同じくらい重要で、ベネディクト派の僧たちに「負担を減らすため」宗教曲を歌わせる日課を省かせたところ、みるみるうちに全員が元気をなくしていったという記録がある。オペラ歌手、声楽家の中にも宗教的な魂の履歴を持った人々がいて、その人たちがコロナ禍で歌えなくなっていることの苦しさは、命の危機に匹敵すると思う。
ギルバートのマーラーは素晴らしい。都響とも過去に名演を残したが、マーラーとはある種のフィーリング、情感を共有していて、相性がいい。ブルックナーはそれよりも宿命的な相性で、ギルバートはブルックナーの完全なる対岸にいて、鏡のように精緻に「魂のすべて」を読み取ることが出来る。譜面を読んだときに、下手にこねくり回したり深読みしたり曲解したりせず、ありのままの作曲家の精神を引き出せる相性だと思う。指揮者にも膨大な先祖がいて、その時代にそれぞれの振る舞いをして生き残ってきた。ギルバートが「今生きて、輝く」瞬間に、ブルックナーとの出会いがあったのは、ふたつの魂にとって宿命であった。
ブルックナー7番の特に1楽章と2楽章から感じられるのは、マントラ詠唱や六方拝のような習慣化された反復で、素朴であると同時に執拗な日々の行いだ。ブルックナーはキリスト者だったが、魂が覚えているのは無数の宗教で、仏教やユダヤ教やイスラム教、原始太陽崇拝も履歴としてあった。妄想といえばそうだが、音楽とはそもそも目に見えないもの、五感を超えた感覚を喚起するものではないか。客席にいる自分は、都響とギルバートが「今生きて輝いている」ことの意味が、理屈や恐れに満ちた現実だけでは消化しきれないのだった。
3楽章のスケルツォのはじまりは何度聞いても回教徒のトランスダンスを思い出す。その後に出現する雄大な光景には、巨大な太陽の光彩が感じられる。ブルックナーもまた、今生きている自分の魂がどちらの方向に玉突きされているか、不安を抱えていた。4楽章の重々しいユニゾンは、グレゴリオ聖歌を彷彿させる。カソックを着た修道士たちが唸るように合唱している。19世紀という「モダン」を生きていたブルックナーはそこに、自分の現世のリアリティを重ねてシンフォニーの曼陀羅を完成した。指揮者は、この曲のすべてをわかっている。こんこんと湧きだしてくる自然な歌には、崇高さしか感じられなかった。
先週のプロムナードコンサートでは、(恐らく)手書きのノートの譜面が置かれていて、バルトークもコダーイも、指揮者によって緻密に研究されていた痕跡があった。あちらは急な代役だったから、責任感も強かったと思う。2つのコンサートでは、ギルバートが都響に感じている故郷のような安息感、ハイレベルな友情が共通して伝わってきた。19日にはトロンボーンの小田桐寛之さん(1986年入団)が退団され、この日はチェロ奏者の松岡陽平さんとヴィオラ奏者の南山華央倫さんが退団という、立て続けのさよならコンサートだったが、全員にプレゼントを渡していたギルバートの姿も心に残った。都響の「日常」を支えていたプレイヤーを送り出す姿に、指揮者が長年オーケストラと日常をともにしていた印象さえ抱いたのである。