
政府の発表で、2019年の自殺者数が2万人をきったという報道がありました。
「日本の自殺者が2万人を割った!」と話題になっているが、その代わりに「変死体」は増え続け、平成29年には変死体が2万体を超えた。一見自殺っぽく見えても、遺書がなければ変死体として処理することで、自殺者数を減らせる数字のトリック。 pic.twitter.com/9Rc5jIg5kn
— zapa (@zapa) January 19, 2020
これが嘘八百なのは周知の事実なのですが、子育てをする親として、他山の石として自殺に対して考えていかなくては、明日は我が身である問題の一つだと思います。
そして、中学生の自殺に対して、関与した中学生が書類送検されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(岐阜市でいじめが主な要因で中3男子生徒が自殺した問題で同級生3人を書類送検 2020年1月17日 23:26)
岐阜市で去年7月、いじめが主な要因で中学3年の男子生徒が自殺した問題で、同級生3人が強要などの疑いで書類送検されました。
男子生徒(当時14歳)は去年7月、岐阜市のマンションから転落死し、市の第三者委員会は先月、いじめが主な要因と認定しました。
捜査関係者によりますと、同級生3人は男子生徒が自殺する前日に、男子生徒に対して学校のトイレの和式便器の前で無理やり土下座をさせた強要の疑いがもたれています。
同級生3人のうち1人については現金を脅し取ったり平手打ちしたりしたとして恐喝と暴行の疑いでも書類送検されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
少年事件は通常、検察には送致されません。
つまり、起訴前提ではない事件として検察と少年警察は処理していきます。

一件書類をまとめると、捜査は家庭裁判所に送致します。
そして、家庭裁判所が、成人と同様に裁判する必要があると判断すると、逆送といって、検察庁に事件を送ることになります。
つまり、少年ゆえの未熟さで起こった犯行ではなく、計画性がり、悪質かつ更生するために成人と同様の罰が必要と判断するからです。
しかしながら、殺人罪ではなく、強要罪で送致しているため、かなりの情状酌量バイアスがかかっています。
少年たちは、気に食わなかったため、殺してやろうとイジメたわけです。
結果予見ができなかったのでなく、死ねばよいと思って犯行に至ったとしたら殺人罪となります。
「まさか死ぬかと思わなかった」
これは言い訳でしょう。
少年たちに「君たち、ここから飛び降りてみて」と取調官が質問したら、
「嫌です。死にたくない」と答えるでしょう。
それはなぜか?
「ここから飛び降りたら、死ぬと分かるから」
です。
つまり結果予見はできるのです。
捜査の過程はわかりませんが、日本の刑法や少年法はザル法であるため、私たちは自分の身、自分の身内は自分たちで守っていかなくてはなりません。
これだけ、上級国民と下級国民との格差が開いてきた現状において、下級国民のストレスは計り知れないものがあります。
そのストレスを下級国民同士でぶつけ合う形が「自殺」という結果に現れるのかもしれません。
「下級国民同士、助け合う」のではなく、「下級国民同士、争い合う社会」を上級国民は作ってきたのでしょう。
大人も子供も嘘まみれの世の中で、怒りやストレスのやり場に困り、弱いものを攻撃しているのかもしれません。
では、どのようにして親は子供を守ることができるのでしょうか?
上級国民のように、慶應幼稚舎に通わせればよいのでしょうか?
確かに、上級国民が通う、エレベーター式の幼稚園などは、教員の質も高く、治安が維持されているかもしれません。
しかし、そのようにお金をかけなくてもわが子を守る方法などあるのです。
それは、「親自身が成長すること」です。
思春期は「親の価値観から一度離れようとする時期」でもあります。それは家庭という集団から社会、学校という集団の価値観に染まっていくため、「どっちに所属したらいいのか?」という葛藤に陥ることがあるからです。
しかし、社会、学校が「必ずしも正しいわけではない」ことはこのブログの読者の方ならご存知だと思います。
むしろ、洗脳教育ばかり、嘘ばかり、役に立たない、生きていく力がみにつかないことばかりを教えています。
しかし、学校で、日本という社会でいきていく常識は学ぶ必要があります。
学校で学ぶことは真実ではありません。
しかし、日本で生活していく以上、「常識=所属する社会、集団での共通認識、慣習、ルール」は身に着けておく必要はあるのです。
そのうえで、自分の信念を持ち生きていかなければいけません。
ですから、「常識に従って生きること=正しいこと」ではないのです。
親はそこを吐け違いてしまうと、子供は板挟みになります。
学校でいじめてくるやつら、バカにしてくるやつらがいる。
彼らは言葉の暴力や無視したり、孤立させて心理的に追い込んでくる。
「こんな不正が罷り通るのはおかしい」と感じます。
本来、子供はこういった「悪と戦わなければならない」はずです。
そして、親自身が「悪と戦え!」と堂々と言わなくてはなりません。
しかし、実際のところはどうでしょうか?
親が、社会の渦や常識に流されて生きる、ただの奴隷のような生活をしていては、いざというとき、子供は親のいう事を聞くでしょうか?
そもそも、奴隷が奴隷に対して、「どうしたら奴隷から抜け出せるかな?」と質問するでしょうか?
しませんよね?
ホームレスに対して「どうすれば金持ちになれるかな?」と質問する人はいないと思います。
つまり、いじめられている子供が、相談する対象が、周囲にいなければ、当事者である子供は孤立無援であり、解決策が見いだせず、ただただ苦痛の日々、劣等感にさいなまれ続ける日々が続くのです。
「親が、大人が悪と戦って勝っていない」のです。
日本の一般家庭に目を向けてみましょう。↓
・父親が不倫したりギャンブルしたり、時間があればスマホばかりしている。
・母親が
「家にお金さえ入れてくれれば、子育て終わるまでは、多少の粗相は見逃す」
というスタンスで父親を見下している。
・「お父さんにみたになっちゃだめだよ」とほのめかす愚痴を子供にこぼす母親。
という愛が覚め切った、家族ではなく単なる「同居人」集団ではないでしょうか?
つまり、法に触れなてないからと、常識から外れていないからと、表面的に装っているだけで
「平然と悪を行っている人たちの集団」しか当事者の子供の周りには存在していません。
「全く、愛がない世界で生きている」のです。
学校にも、家庭にも愛がないのです。
戦う事が愛なら、戦争ばかりして人殺しするのが愛なのか?
と思うかもしれません。
別に、武器を使ったり殴ったりけったりして戦うのではありません。
「不正に対して、反論する、争うこと」が戦いなのです。
武力で対抗してきたら、証拠をとっておいて、警察に捜査してもらえばいいだけです。
そして、「悪と戦うこと」がなぜ「愛」なのでしょうか?
それは「悪」とは「不正を正当化するための武力行使の手段」だからです。
いじめた側の少年たちはストレスがたまっていて、遊び半分でイジメを開始します。
暴言や暴力を振るわなければストレスが解消できないのはイジメた側の論理です。
勉強でもスポーツでも何でも文化的なことに打ち込み、エネルギーを使えばいいのです。
しかし、そういったプラスのことをせず、たまった鬱憤を弱いものに向けて、抵抗してこないものにむけてぶつけていることで憂さ晴らしをしているのです。
つまり、「正しい、文化的な憂さ晴らしもせず、他人を害する方法で憂さ晴らしをしている」といった「不正」を行っているのです。
悪を行って、憂さ晴らしをしているのです。
それは、私たちの社会常識が「悪を行って憂さ晴らしすることを常識、黙認する社会だから」まかり通っているのです。
「善も悪もごちゃまぜにしている常識、文化に疑問を持つことが”愚か者、精神異常者”頭が固い」と批難されてきた背景があるからです。
泥水を真水と思い込まされて飲んでいる社会なのです。
「泥水は泥水だ」と堂々と言える大人がいないのです。
ですから、親が大人が、善と悪の区別をくっきりとつけて、実践する必要があります。
そして、いつも「悪と戦う」「悪がなくなるまで戦う」存在でなくてはならないのです。
しかし、この世の中には、「善と悪の判断基準が刑法くらいしかない」のではないでしょうか?
そして、私たちをとりまく社会常識が
「泥水」なのではないでしょうか?
そんな基準のない社会で生きているため、子供たちも基準を持てず、将来に絶望してしまうのかもしれません。
人間の基準、倫理に従っても、それはどこかに矛盾や欲望が混じってきます。
ですから、「聖書」「御言葉」という「神の発想、思考」から人生の指針、生き方を学んでいかなくことが必要となってくると思います。
興味のある方は以下のサイトからどうぞ。
RAPT有料記事150(2017年2月27日)あなたたちが聖書の預言を実現する人たちだ。善と悪をしっかりと裂きなさい。
RAPT有料記事317(2018年10月6日)聖書の中には個々人それぞれの答えが封印されている。その封印を解いてこそ自らの人生を成功に導くことができる。
RAPT有料記事316(2018年10月1日)聖書は神様の書いた書物だから、聖書を面白いと思って読める人が、神様の頭脳に近い頭脳を持った人だと言える。
現在は、「モノの時代から心の時代に変わってきている」のです。
物質や欲望が満たされても何も解決されないのです。
巷にあふれる、有名大学教授や医者が書いた子育て本がどれだけ当てになるのでしょうか?
大切なのは、周囲の大人たちが、子供に一番近い存在の親が悟り、絶対的な基準を順守するために、毎日大人自身が厳しく実践していく必要があるのではないでしょうか?










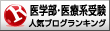

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます