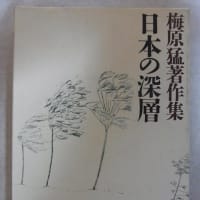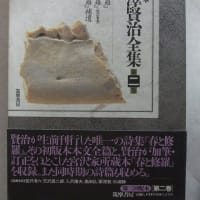嘗て『芸術劇場』というNHK教育テレビで放送されていた番組があったことを憶えていられる方もいらっしゃるだろうか。
古典から現代までの西洋音楽の演奏会,現代演劇,白黒のクラシック映画、これらが日曜の夜に毎週三時間、何の解説もなしに届けられ、私にとっては束の間の精神の自由を呼吸する時間であったのだと今は思う。この番組は演奏会や作品の選び方自体に無言の批評があり、相当な議論を経た上でそれが選定されていたことが滲み出ている、公共放送としての最上の仕事のひとつであった。
この同じ時間帯に時折歌舞伎が放映されることもあったけれど、それは『芸術劇場』とは別の歌舞伎独自の枠であり、そこで選ばれた舞台には、『芸術劇場』のスタッフが選んだそれではないからか、私にはあまりよく馴染めなかった。これが原因で、とは言い過ぎであるが、歌舞伎,そして文楽は私の中での空白地帯となっていた。旧歌舞伎座へはこの心の閾があり、足を踏み入れたことはない。
ところが『現代語訳,近松名作集』を読んでみて、是非文楽,歌舞伎を観てみたいとは思うけれど、そうそう生の舞台へ行くことはできない。そこで時を隔てた今、この歌舞伎,文楽の空白を埋める手段を考えたとき、「ユーチューブ」があることに気付いた。著作権的には問題があるが、「歌舞伎,文楽入門」として自分で選んで観ていくと、とてもおもしろい。
『文楽,曽根崎心中』
https://www.youtube.com/watch?v=nzm3Uov1qpk&ebc=ANyPxKrIqUbnj1LObIJItOSxq6-k4mA5zswJ0AkU_mpFvGVqAjulRP4Py73YOiKbSwJyYiEfoVrYaYDtiH8KWnDJNaaHDbe7JA
https://www.youtube.com/watch?v=wA-Q2cIHurU&ebc=ANyPxKrIqUbnj1LObIJItOSxq6-k4mA5zswJ0AkU_mpFvGVqAjulRP4Py73YOiKbSwJyYiEfoVrYaYDtiH8KWnDJNaaHDbe7JA#t=19.54601
https://www.youtube.com/watch?v=sohO1A0Sq38&ebc=ANyPxKrIqUbnj1LObIJItOSxq6-k4mA5zswJ0AkU_mpFvGVqAjulRP4Py73YOiKbSwJyYiEfoVrYaYDtiH8KWnDJNaaHDbe7JA#t=1542.896166
『歌舞伎,近松,油地獄』
https://www.youtube.com/watch?v=XkIp4YtRuJk
https://www.youtube.com/watch?v=Pr_3bXY8XCs
https://www.youtube.com/watch?v=GqWDAIT2LWI
https://www.youtube.com/watch?v=CXzTGIFoLjk
『歌舞伎,桜姫東文章』
https://www.youtube.com/watch?v=a2OIxQxTaGA
https://www.youtube.com/watch?v=7taANTlww18#t=1.114014
https://www.youtube.com/watch?v=vDOF27XrS5o#t=2.514014
『歌舞伎,東海道四谷怪談』
https://www.youtube.com/watch?v=AnI0b_nb6kA
いくつか観ていくうちに、関連動画として『影の名優,坂東八重之助,(1963)』という、これもおそらくNHKが製作したのであろうテレビ番組が出てきた。何気無しに観始めるとその鮮烈さに引き込まれた。
これは名題下筆頭の役者で立師の坂東八重之助を追ったドキュメンタリーで、もし今私が新しい歌舞伎座へ行き、黒衣や搦みの役者を観たら、とても平静ではいられなくなるであろう。視線の光を下から上の方向へ当てる傑出した双無き番組だ。表現は時代に制約されるが、確かな視点は時代を超える。NHKは1963年にこんな番組を作り、受容されていた。
この番組の後半に「市川団蔵」という名前が出る。耳に覚えがあったので落語家の八代目林家正蔵師のCD『淀五郎』を取り出して聴くと確かにあった。あわせて同じ正蔵師匠の『中村仲蔵』もこの『影の名優』を観てから聴き返すと、風景が鮮やかに細部まで立ち上がる。
ウィキペディアで「市川団蔵」の項目を見ると、三島由紀夫の『団蔵・芸道・再軍備』が紹介されていたので早速図書館で全集の当該巻を借りて読んだ。他のエッセーも拾い読みしていると「桜姫東文章」への言及もあった。
私は物事を体系的に学ぶことはしないが、このように自然に体系になってゆくのはまことに楽しいものである。
【2016年3月18日 追記】
先日書いた文章の後半を省筆しすぎて、少しわかりにくくなっているように思ったので、一点だけ補足しておく。三島由紀夫についてである。といっても私は三島の作品をいくつか読んだだけで、評伝,研究書の類いには一切目を通していないので、以下に述べることは既に指摘されているであろうが一応書いておく。
三島はエッセー『団蔵・芸道・再軍備』のなかで、歌舞伎役者八世団蔵の死に異常と思えるほど感応している。これが発表されたのは昭和41年(1966年)9月で、三島が市ヶ谷の自衛隊内で割腹したのは4年後の昭和45年(1970年)11月25日である。昭和41年以前から『葉隠』等を三島は研究していたけれど、直接自らの死に切腹をイメージしたのは、意識下で一瞬、団蔵の名前から『淀五郎』を想起したことにあるのではないか。突飛な思念ではあるが、『淀五郎』がどういう噺であったかを思い返してみよう。
名題早々の役者淀五郎は、座頭市川団蔵から『忠臣蔵四段目』判官の役に抜擢される。喜び勇んで淀五郎は演じるが、団蔵はそれをまったく評価しない。以下八代目林家正蔵師の口演を引いてみよう。
団蔵 「どういう訳ったって(お前の芝居は)悪すぎるもの」
淀五郎 「悪すぎますと…?」
団 「悪すぎますと…って、そうだなぁ、腹の切り方がいけねえのかなぁ」
淀 「腹の…、へえ、どういう風に切りましたら…」
団 「そうだよ、そこだよ。どういう風にって聞かれると困るんだが、役者はねえ、相手があるからな。俺も随分長生きをしたが、お前さんみたいにテコヘンな判官に出会ったのは初めてだよ。え、悪すぎるってぇのは、まあ、お前の判官だろうねえ。悪い所があるってのは、いい所があるから悪い所が目立つんだ。お前のはのこらず悪くって、いい所を探したってありゃあしねえ。腹を切るてえのはねえ、まともに切ってもらいたい」
淀 「まともと申しますと?」
団 「本当に切るんだよ」
淀 「本…、本当に切りますと、死んでしまいます」
団 「ん、まずい役者は死んでくれた方が相手は助かるね」
淀 「ハァ、ありがとうございます」
― ありがたくはないんですが……
CD『正蔵改め林家彦六名演集(五)』
三島由紀夫は決起の日、車で森田必勝たちと市ヶ谷の自衛隊へ向かう途中、時間調整のために神宮外苑を二周する間、全員で『唐獅子牡丹』を歌った、と伝えられている。
完全無欠の芸術家三島由紀夫がその最後に想起した作品は大衆仁侠映画であり、崇高な理念に殉じた壮絶な死の手段の発端が落語であったとしても、それは三島の死の意味を貶めるものではまるでなく、むしろそれは、残された者たちへの慰めと、三島自身に対しては、ひとつの優しい批評になるのではないだろうか。
『唐獅子牡丹』
古典から現代までの西洋音楽の演奏会,現代演劇,白黒のクラシック映画、これらが日曜の夜に毎週三時間、何の解説もなしに届けられ、私にとっては束の間の精神の自由を呼吸する時間であったのだと今は思う。この番組は演奏会や作品の選び方自体に無言の批評があり、相当な議論を経た上でそれが選定されていたことが滲み出ている、公共放送としての最上の仕事のひとつであった。
この同じ時間帯に時折歌舞伎が放映されることもあったけれど、それは『芸術劇場』とは別の歌舞伎独自の枠であり、そこで選ばれた舞台には、『芸術劇場』のスタッフが選んだそれではないからか、私にはあまりよく馴染めなかった。これが原因で、とは言い過ぎであるが、歌舞伎,そして文楽は私の中での空白地帯となっていた。旧歌舞伎座へはこの心の閾があり、足を踏み入れたことはない。
ところが『現代語訳,近松名作集』を読んでみて、是非文楽,歌舞伎を観てみたいとは思うけれど、そうそう生の舞台へ行くことはできない。そこで時を隔てた今、この歌舞伎,文楽の空白を埋める手段を考えたとき、「ユーチューブ」があることに気付いた。著作権的には問題があるが、「歌舞伎,文楽入門」として自分で選んで観ていくと、とてもおもしろい。
『文楽,曽根崎心中』
https://www.youtube.com/watch?v=nzm3Uov1qpk&ebc=ANyPxKrIqUbnj1LObIJItOSxq6-k4mA5zswJ0AkU_mpFvGVqAjulRP4Py73YOiKbSwJyYiEfoVrYaYDtiH8KWnDJNaaHDbe7JA
https://www.youtube.com/watch?v=wA-Q2cIHurU&ebc=ANyPxKrIqUbnj1LObIJItOSxq6-k4mA5zswJ0AkU_mpFvGVqAjulRP4Py73YOiKbSwJyYiEfoVrYaYDtiH8KWnDJNaaHDbe7JA#t=19.54601
https://www.youtube.com/watch?v=sohO1A0Sq38&ebc=ANyPxKrIqUbnj1LObIJItOSxq6-k4mA5zswJ0AkU_mpFvGVqAjulRP4Py73YOiKbSwJyYiEfoVrYaYDtiH8KWnDJNaaHDbe7JA#t=1542.896166
『歌舞伎,近松,油地獄』
https://www.youtube.com/watch?v=XkIp4YtRuJk
https://www.youtube.com/watch?v=Pr_3bXY8XCs
https://www.youtube.com/watch?v=GqWDAIT2LWI
https://www.youtube.com/watch?v=CXzTGIFoLjk
『歌舞伎,桜姫東文章』
https://www.youtube.com/watch?v=a2OIxQxTaGA
https://www.youtube.com/watch?v=7taANTlww18#t=1.114014
https://www.youtube.com/watch?v=vDOF27XrS5o#t=2.514014
『歌舞伎,東海道四谷怪談』
https://www.youtube.com/watch?v=AnI0b_nb6kA
いくつか観ていくうちに、関連動画として『影の名優,坂東八重之助,(1963)』という、これもおそらくNHKが製作したのであろうテレビ番組が出てきた。何気無しに観始めるとその鮮烈さに引き込まれた。
これは名題下筆頭の役者で立師の坂東八重之助を追ったドキュメンタリーで、もし今私が新しい歌舞伎座へ行き、黒衣や搦みの役者を観たら、とても平静ではいられなくなるであろう。視線の光を下から上の方向へ当てる傑出した双無き番組だ。表現は時代に制約されるが、確かな視点は時代を超える。NHKは1963年にこんな番組を作り、受容されていた。
この番組の後半に「市川団蔵」という名前が出る。耳に覚えがあったので落語家の八代目林家正蔵師のCD『淀五郎』を取り出して聴くと確かにあった。あわせて同じ正蔵師匠の『中村仲蔵』もこの『影の名優』を観てから聴き返すと、風景が鮮やかに細部まで立ち上がる。
ウィキペディアで「市川団蔵」の項目を見ると、三島由紀夫の『団蔵・芸道・再軍備』が紹介されていたので早速図書館で全集の当該巻を借りて読んだ。他のエッセーも拾い読みしていると「桜姫東文章」への言及もあった。
私は物事を体系的に学ぶことはしないが、このように自然に体系になってゆくのはまことに楽しいものである。
【2016年3月18日 追記】
先日書いた文章の後半を省筆しすぎて、少しわかりにくくなっているように思ったので、一点だけ補足しておく。三島由紀夫についてである。といっても私は三島の作品をいくつか読んだだけで、評伝,研究書の類いには一切目を通していないので、以下に述べることは既に指摘されているであろうが一応書いておく。
三島はエッセー『団蔵・芸道・再軍備』のなかで、歌舞伎役者八世団蔵の死に異常と思えるほど感応している。これが発表されたのは昭和41年(1966年)9月で、三島が市ヶ谷の自衛隊内で割腹したのは4年後の昭和45年(1970年)11月25日である。昭和41年以前から『葉隠』等を三島は研究していたけれど、直接自らの死に切腹をイメージしたのは、意識下で一瞬、団蔵の名前から『淀五郎』を想起したことにあるのではないか。突飛な思念ではあるが、『淀五郎』がどういう噺であったかを思い返してみよう。
名題早々の役者淀五郎は、座頭市川団蔵から『忠臣蔵四段目』判官の役に抜擢される。喜び勇んで淀五郎は演じるが、団蔵はそれをまったく評価しない。以下八代目林家正蔵師の口演を引いてみよう。
団蔵 「どういう訳ったって(お前の芝居は)悪すぎるもの」
淀五郎 「悪すぎますと…?」
団 「悪すぎますと…って、そうだなぁ、腹の切り方がいけねえのかなぁ」
淀 「腹の…、へえ、どういう風に切りましたら…」
団 「そうだよ、そこだよ。どういう風にって聞かれると困るんだが、役者はねえ、相手があるからな。俺も随分長生きをしたが、お前さんみたいにテコヘンな判官に出会ったのは初めてだよ。え、悪すぎるってぇのは、まあ、お前の判官だろうねえ。悪い所があるってのは、いい所があるから悪い所が目立つんだ。お前のはのこらず悪くって、いい所を探したってありゃあしねえ。腹を切るてえのはねえ、まともに切ってもらいたい」
淀 「まともと申しますと?」
団 「本当に切るんだよ」
淀 「本…、本当に切りますと、死んでしまいます」
団 「ん、まずい役者は死んでくれた方が相手は助かるね」
淀 「ハァ、ありがとうございます」
― ありがたくはないんですが……
CD『正蔵改め林家彦六名演集(五)』
三島由紀夫は決起の日、車で森田必勝たちと市ヶ谷の自衛隊へ向かう途中、時間調整のために神宮外苑を二周する間、全員で『唐獅子牡丹』を歌った、と伝えられている。
完全無欠の芸術家三島由紀夫がその最後に想起した作品は大衆仁侠映画であり、崇高な理念に殉じた壮絶な死の手段の発端が落語であったとしても、それは三島の死の意味を貶めるものではまるでなく、むしろそれは、残された者たちへの慰めと、三島自身に対しては、ひとつの優しい批評になるのではないだろうか。
『唐獅子牡丹』