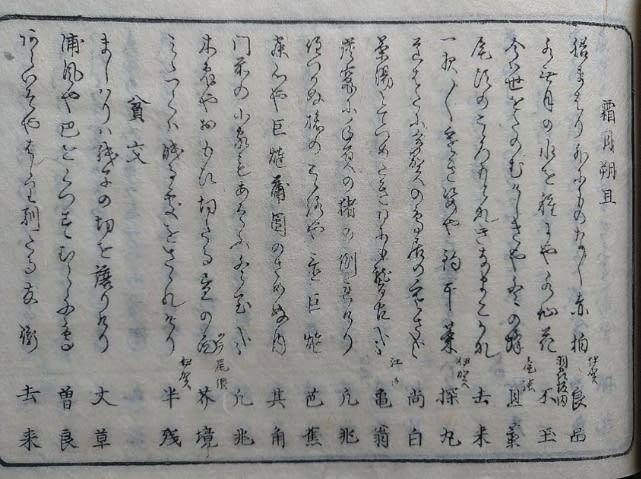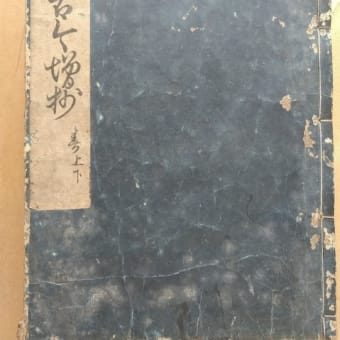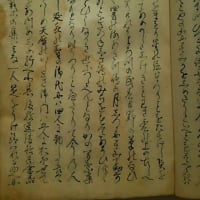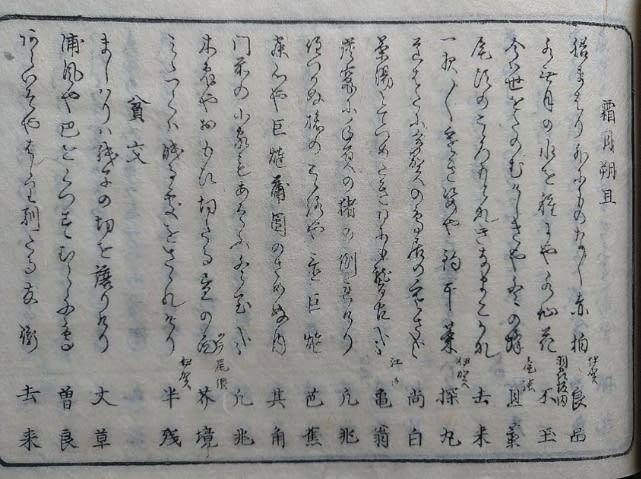
霜月朔旦
伊賀
膳まはり 外に物なし赤 柏 良品
羽州坂田
水無月の水を種にや 水仙花 不玉
尾張
今は世をたのむけしきや冬の蜂 旦藁
尾頭のこゝろもとなきなまこかな 去来
伊賀
一夜/\寒き姿や 釣 干菜 探丸
道はたに多賀の鳥居の寒さ哉 尚白
江戸
茶湯とてつめたき日にも稽古 哉 亀翁
炭竈に手負の猪 の 倒れけり 凡兆
住つかぬ旅のこゝろや置 巨 燵 芭蕉
寐心や巨燵蒲団のさめぬ内 其角
門前の小家もあそふ冬至哉 凡兆
尾張
木兎やおもひ切たる昼の面 芥境
伊賀
みゝつくは眠る處をさゝれけり 半残
貧 交
ましはりは紙子の切を譲りけり 丈草
浦風や巴をくつすむら千鳥 曽良
あらいそやはしり馴たる友 鵆 去来

狼のあと 蹈 消すや 濱千鳥 史邦
背戸口の 入江にのほる千鳥哉 丈草
いつ迄か雪にまふれて鳴千鳥 千邦
矢田の野や浦のなくれに 鳴鵆 凡兆
筏士の見かへる 跡や 鴛の中 木節
水底を見て来た㒵の 小鴨哉 丈草
鳥共も寝入て居るか余呉の海 路通
死まて操なるらん 鷹 の 顔 旦藁
襟巻に首引入て 冬 の月 杉風
この木戸や鎖のさゝれて冬の月 其角
長崎
からしりの蒲団はかりや冬の旅 暮年
大津尼
見ゆるさへ旅人寒し 石部 山 智月
翁行脚のふるき衾をあたへらる
記あり略之
みの
首出してはつ雪見ばや 此衾 竹戸
題竹戸之衾
畳めは我手の あとそ 紙衾 曽良
魚の かけ鵜のやるせなき氷哉 探丸
ぜんまはりほかにものなしあかがしは 良品(初時雨:冬)
みなづきのみづをたねにやすいせんくわ 不玉(時雨:冬)
いまはよをたのむけしきやふゆのはち 旦藁(冬の蜂:冬)
をかしらのこころもとなきなまこかな 去来(海鼠:冬)
ひとよひとよさむきすがたやつりほしな 探丸(寒き:冬)
みちばたにたがのとりゐのさむさかな 尚白(寒さ:冬)
※多賀の鳥井 彦根市高宮町の多賀大社一之鳥居
ちやのゆとてつめたきひにもけいこかな 亀翁(冷き:冬)
すみがまにておひのししのたおれけり 凡兆(炭窯:冬)
すみつかぬたびのこころやおきごたつ 芭蕉(置炬燵:冬)
ねごころやこたつぶとんのさめぬうち 其角(炬燵蒲団:冬)
もんぜんのこいへもあそぶとうじかな 凡兆(冬至:冬)
みみづくやおもひきつたるひるのつら 芥境(木兎:冬)
みみづくはねむるところをさされけり 半残(木兎:冬)
まじはりはかみこのきれをゆずりけり 丈草(紙子:冬)
うらかぜやともゑをくづすむらちどり 曽良(村鵆:冬)
あらいそやはしりなれたるともちどり 去来(友鵆:冬)
おほかみのあとふみけすやはまちどり 史邦(浜千鳥:冬)
せどぐちのいりえにのぼるちどりかな 丈草(千鳥:冬)
いつまでかゆきにまぶれてなくちどり 千邦(千鳥:冬)
やたののやうらのなぐれになくちどり 凡兆(千鳥:冬)
※矢田の野 福井県敦賀市南部
※なぐれ はぐれ
いかだしのみかへるあとやをしのなか 木節(鴛:冬)
みなそこをみてきたかほのこがもかな 丈草(小鴨:冬)
とりどももねいつてゐるかよごのうみ 路通(浮寝鳥:冬)
※余呉の海 滋賀県の余呉湖
しぬるまでみさをなるらんたかのかほ 旦藁(鷹:冬)
えりまきにくびひきいれてふゆのつき 杉風(冬の月:冬)
このきどやじやうのさされてふゆのつき 其角(冬の月:冬)
からじりのふとんばかりやふゆのたび 暮年(冬:冬)
1江戸時代、宿駅で旅人を乗せるのに使われた駄馬。人を乗せる場合は手荷物を5貫目(18.8キロ)まで、人を乗せない場合は本馬 (ほんま) の半分にあたる20貫目まで荷物を積むことができた。からしりうま。
2積み荷をもたない馬。荷物のない、からの馬。
みやるさえたびびとさむしいしべやま 智月(寒し:冬)
※石部山 滋賀県湖南市石部の丘陵。栗東市の境。
くびだしてはつゆきみばやこのふすま 竹戸(衾:冬)
※この衾 芭蕉が奥の細道の出羽最上で入手した紙衾。
たたみめはわがてのあとぞかみぶすま 曽良(紙衾:冬)
うをのかげうのやるせなきこほりかな 探丸(氷:冬)